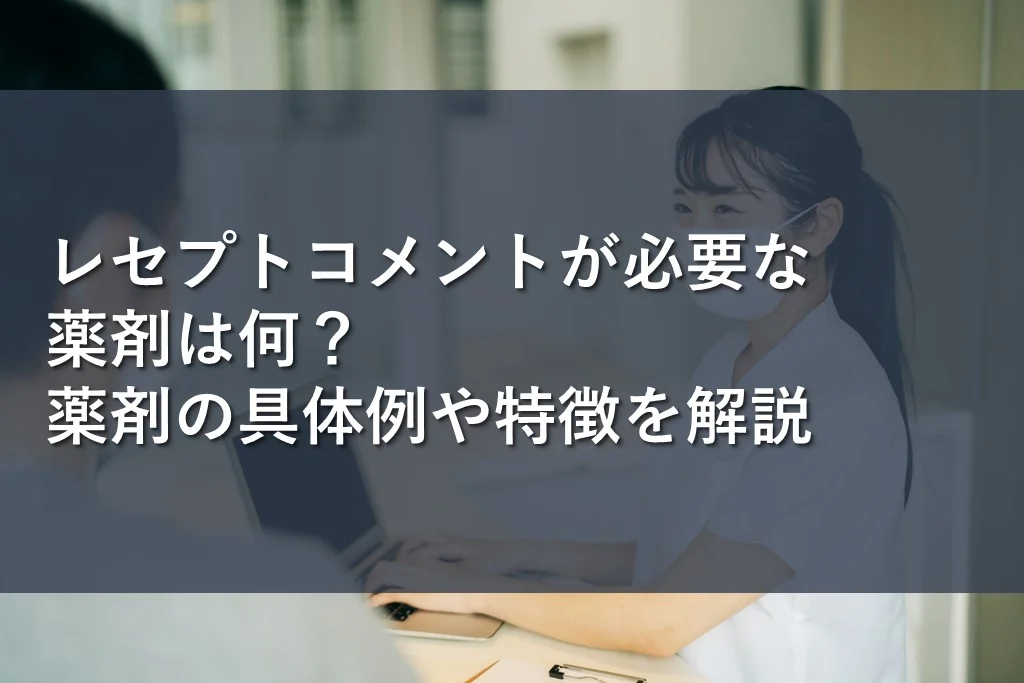
医療機関や調剤薬局でのレセプト業務において、適切なコメントの記載は非常に重要です。
特に、特定の薬剤を処方する際には、レセプトコメントが必要となる場合があります。
本記事では、レセプトコメントが必要な処方の具体例や特徴について詳しく解説します。
適切なコメント記載は査定を防ぎ、スムーズな保険請求につながります。
医療従事者にとって、この知識は日々の業務を円滑に進めるうえで欠かせません。
目次
レセプトコメントの入力方法

レセプトコメントの入力には、いくつかの方法があります。
状況に応じて適切な入力方法を選択することが重要です。
ここでは、主な4つの入力方法について詳しく解説していきます。
それぞれの特徴を理解し、正確なコメント入力を心がけましょう。
コード選択が決まっている場合
最も一般的なレセプトコメントの入力方法は、決められたコードを選択するものです。
この方法では、特定の診療行為に対して、あらかじめ設定されたコードを選択して入力します。
例えば、特定の検査や処置を行った場合、それに対応するコードを選んで入力することになります。
この方法では標準化されたコメントを簡単に入力できるため、効率的で誤入力のリスクも低くなりますが、選択できるコードが限られているため、詳細な情報を伝えたい場合は別の方法を併用する必要があるかもしれません。
条件に応じて選択するコードが変わる場合
患者さんの状況や診療内容によって、選択するコードが変わる場合があります。
これは、同じ診療行為でも、患者さんの状態や治療の経過によって、適用される保険点数や算定条件が異なるためです。
典型的な例として、初診料のコード選択が挙げられます。
初診料は、患者さんが初めて医療機関を受診した場合に算定されますが、状況に応じて異なるコード選択が求められる場合があります。
具体的に、初診料にコード選択が求められる状況は以下のとおりです。
- 初診のあと、当該初診に附随する一連の行為を後日行った場合であって当該初診日が前月である場合
○ 初診または再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来院
○ 往診等のあとに薬剤のみを取りに来院
いったん帰宅し、後刻または後日検査、画像診断、手術等を受けに来院
このような条件付きのコード選択では、患者さんの状況を正確に把握し、適切なコードを選ぶことが重要です。
誤ったコード選択は査定の対象となる可能性があるため、十分に注意しましょう。
コード選択ではなくフリーテキスト入力が必要な場合
患者さんの個々の状況や、特定の日付に関連する情報など、標準化されたコードでは表現しきれない場合があります。
このような場合、フリーテキストでの入力が必要です。
具体的には、検査や治療の実施日、退院日、検査の理由などが該当します。
これらの情報は患者さんごとに異なるため、あらかじめ設定されたコードでは対応できません。
フリーテキスト入力では、簡潔かつ明確な文言を用いることが重要です。
必要な情報を漏れなく記載しつつ、冗長な表現は避けるよう心がけましょう。
また、個人情報の取り扱いには十分注意し、必要最小限の情報のみを記載するようにしてください。
コード以外の追加情報をフリーテキストで入力する場合
一部の診療行為では、コード入力にくわえ、フリーテキストで追加情報を入力しなければなりません。
この場合、コードごとに設定されているテンプレートが表示されるのが一般的です。
テンプレート内の「******」の部分に、必要な追加情報をフリーテキストで入力しましょう。
例えば、特定の薬剤を処方した理由や、検査の詳細な結果などがこれに該当します。
このような入力方法には、標準化された情報と個別の詳細情報を組み合わせて記録できる利点があります。
フリーテキスト部分の入力では、簡潔性と正確性のバランスを取ることが重要です。
必要な情報を漏れなく記載しつつ、不要な内容は省略して簡潔にまとめるよう心がけましょう。
レセプト業務でコメントが必要な薬剤
レセプト業務において、特定の薬剤処方にあたってはコメントの記載が必要となる場合があります。
これは、薬剤の適正使用を確認し、保険請求の正確性を担保するために重要な手続きです。
ここでは、コメントが必要となる代表的な薬剤とその特徴について詳しく解説していきます。
正しいコメント記載が査定のリスクを減らし、スムーズな保険請求につながります。
コメントの記載を求められることが多い薬剤
特定の薬剤を処方する際、レセプトへのコメント記載が頻繁に求められます。
これらの薬剤は、使用条件が厳密に定められていたり、特殊な使用状況が想定されたりするものが多い傾向です。
適切なコメント記載は、処方の妥当性を示し、保険請求をスムーズに進めるために不可欠です。
以下では、コメント記載が特に重要な薬剤の例を挙げ、それぞれの特徴と記載すべき内容について詳しく説明します。
エンレスト
エンレストは、慢性心不全の治療や特定の条件下の高血圧症に対する治療薬として使用される比較的新しい薬剤です。
この薬剤を処方する際は、投与開始月にのみコメントの記載が必要です。
レセプトコード「830600024」を使用し、処方した理由を具体的に記載します。
例えば「従来の心不全治療薬で効果不十分のため」や「左室駆出率の低下が認められたため」などの処方理由を明記します。
エンレストは高額な薬剤であるため、適切な使用理由の記載は特に重要です。
患者さんの状態や既存の治療への反応性などを踏まえ、明確な処方理由を記載することが求められます。
PPI製剤
PPI(プロトンポンプ阻害薬)製剤は、胃酸の分泌を抑制する薬剤として広く使用されています。
この薬剤を処方する際は、投与開始日や再投与時にコメントの記載が必要です。
PPIには投与日数の制限があり、長期投与を行う場合は特に注意が求められます。
例えば、「再発再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法として処方」などの具体的な理由と期間を記載します。
適切なコメント記載は、PPIの使用が妥当であることを示し、査定のリスクを軽減します。
患者さんの症状や治療経過を踏まえ、明確な処方理由を記載することが重要なのです。
ビタミン剤
ビタミン剤の処方にあたっては、その必要性を明確に示すコメントが求められる場合があります。
薬事法承認の適応症である病名により、ビタミンの欠乏が明らかか推定される場合は、レセプトへの投与理由の記載は必要ありません。
しかし、消耗性疾患、妊娠時、授乳時などでビタミンの需要が増大したときや、下痢、嘔吐、脱水症状等によりビタミンの摂取・吸収が阻害されるときなど、病名のみでは投与理由が判断できない場合は、レセプトへ投与理由のコメントが必要です。
このような場合、レセプトコード「830100365」を使用し、具体的な投与理由を記載します。
例えば、「妊娠中のつわりによる経口摂取困難のため」や「長期の下痢によるビタミンB群の不足を補うため」などの理由を明記しましょう。
適切なコメント記載は、ビタミン剤処方の妥当性を示し、不要な査定を防ぐことにつながります。
投薬内容が医薬品の「用法・用量」に合致していない場合
医薬品の「用法・用量」は、安全性と有効性が確認された使用方法を示しています。
しかし、患者さんの状態や特殊な状況により、通常の用法・用量と異なる処方が必要となることもあるでしょう。
このような場合、レセプトにコメントを記載し、その理由を明確に示す必要があります。
以下では、用法・用量に合致しない処方でコメントが必要となる代表的な例を紹介します。
日数制限を越えて薬剤を処方した場合
新医薬品、麻薬、向精神薬等については、安全性の観点から投薬期間に上限が設けられています。
しかし、長期休暇や海外旅行など、特殊な事情により通常の投与日数を超えて処方する必要がある場合があります。
このような場合、備考欄に長期投与の理由を明記することが必要です。
コメントコード「830100366」を使用し、具体的な理由を記載します。
例えば、「3ヵ月の海外滞在のため90日分処方」や「年末年始の長期休診に備え60日分処方」などの理由を明確に記載しましょう。
また、抗生剤を2週間以上投与する場合も、その必要性を詳細に記載しなければなりません。
「難治性の肺炎のため4週間投与継続」といった具体的な理由を記載することで、処方の妥当性を示します。
適切なコメント記載は、特殊な状況下での長期処方の必要性を説明し、査定のリスクを軽減します。
湿布を63枚以上処方した場合
令和4年度の診療報酬改定により、湿布薬の処方は1回につき63枚までという制限が設けられました。
この制限を超えて処方する場合は、医師が必要と判断した理由を摘要欄に記載することが必要です。
コメントコード「830000052」を使用し、63枚を超えて処方する具体的な理由を記載します。
例えば、「広範囲の腰痛のため100枚処方」や「複数箇所の関節痛に対して90枚処方」などの理由を明記しましょう。
患者さんの症状の重症度や罹患部位の広さなど、63枚以上の処方が必要となる医学的根拠を明確に示すことが重要です。
検査薬剤や処置薬剤を使用した場合
検査や処置に薬剤を使用した場合、通常の投薬とは異なる扱いを受けます。
これらの薬剤については、調剤料や処方箋など投薬にかかる点数としての算定はできません。
検査薬剤を単独で使用した場合、投薬関連の手技がすべて査定されてしまう可能性があります。
このため、検査前薬や特定薬剤を用いて処置を行った場合は、適切な医薬品コードを入力することが必要です。
例えば、内視鏡検査前の前処置薬や、創傷処置に使用する外用薬などが該当します。
適切なコード記載により、これらの薬剤が検査や処置の一環として使用されたことを明確にし、査定を防ぐことができます。
医薬品コードの正確な記載は、適切な保険請求につながる重要な手続きです。
処方薬を調整した場合
多剤服用の入院患者に対して、退院時処方薬の調整を行った場合、薬剤調整加算が算定できます。
この薬剤調整加算を算定する際は、レセプトに特定のコメントを記載することが必要です。
具体的には、調整前後の内服薬の種類数を記載します。
この情報は、薬剤調整の結果を明確に示すものであり、適切な加算算定の根拠となります。
患者さんの安全性向上と医療費適正化の観点から、薬剤調整は重要な取り組みです。
正確なコメント記載により、その取り組みが適切に評価されることにつながります。
ジェネリック医薬品を調剤しなかった場合
医療費削減の観点から、ジェネリック医薬品の使用が推奨されていますが、調剤薬局では特定の理由により先発医薬品を調剤する場合があります。
このような場合、ジェネリック医薬品を調剤しなかった理由をレセプトに記載することが必要です。
記載する理由は、「患者の意向」「保険薬局の備蓄」「後発医薬品なし」「その他」のなかから最も当てはまるものを一つ選びます。
例えば、「患者がジェネリック医薬品の使用を希望しないため」や「該当する後発医薬品が存在しないため」などの具体的な理由を記載しましょう。
この記載により、先発医薬品処方の妥当性が示され、不要な査定を防ぐことができるのです。
ジェネリック医薬品の使用促進は重要ですが、患者さんの状態や薬剤の特性によっては先発医薬品の使用が適切な場合もあります。
そのような判断の根拠を明確に示すことが、このコメント記載の目的です。
公費負担医療の場合
公費負担医療制度を利用する患者さんの場合、レセプトへの特別なコメント記載が必要となることがあります。
例えば、公費負担は終了したものの、新型コロナウイルス感染症の治療薬で公費支援の対象となるものを処方する際には、処方を行った理由など、特別なコメントが必要でした。
これらの記載は、適切な公費負担の適用と正確な費用計算のために重要です。
公費負担制度は複雑で、地域や対象疾患によって異なる場合があるため、常に最新の情報を確認し、正確なコメント記載を心がける必要があります。
レセプトコメントが必要な薬剤の特徴を把握しておこう
レセプトコメントが必要なケースには、いくつかの共通した特徴があります。
まず、新薬や高額な薬剤では、その使用理由を明確にする必要があることが多い傾向です。
また、通常の用法・用量を超える使用や、特殊な状況下での処方には、詳細な説明が求められます。
さらに、ジェネリック医薬品への切り替えが困難な場合も、コメントが必要です。
これらの特徴を理解し、適切なコメントを記載することで、査定のリスクを減らし、スムーズな保険請求につながります。
医療従事者は、日々の業務のなかで、これらの特徴を念頭に置き、必要に応じて適切なコメントを記載する習慣をつけることが重要です。
正確でわかりやすいコメント記載は、医療の質の向上と適切な保険請求の両立に貢献します。







