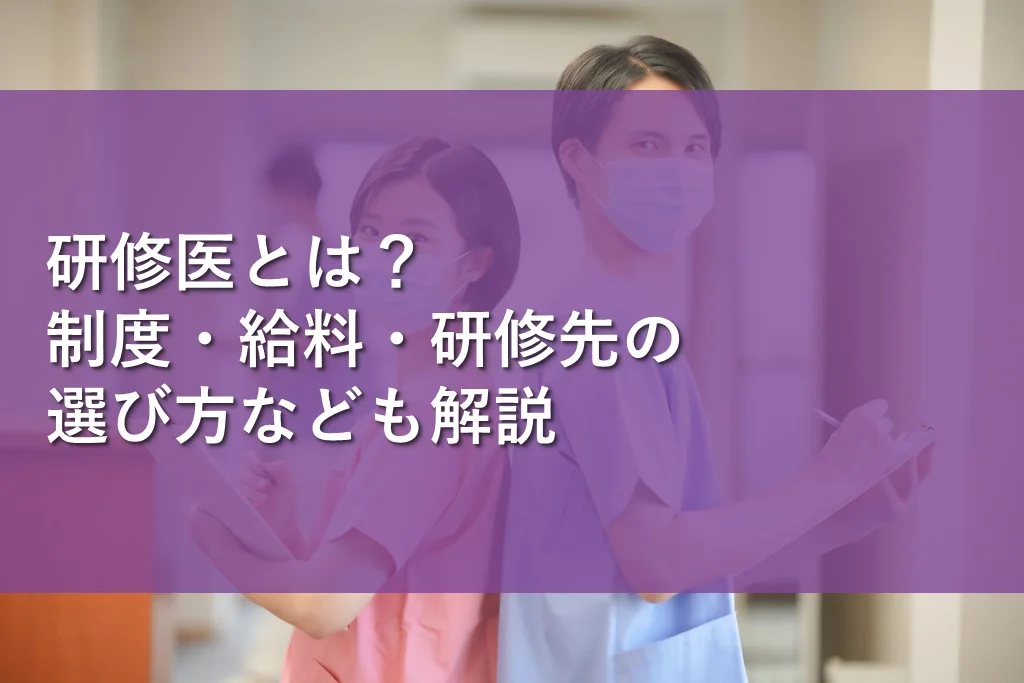
研修医とは、医師免許を取得したばかりで研修を受けている医師のことを指します。
医師法の一部改正により、2004年から医師の臨床研修制度が必修化されました。
この記事では、研修医の定義や研修内容、給与、研修先の選び方などについて詳しく解説していきます。
目次
研修医とは

研修医とは、医師免許取得後、臨床医になるための研修を受けている医師のことを指します。
医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令により、2004年より臨床研修制度が必修化されました。
医師国家試験合格後に、臨床スキル向上のため、国指定の基幹型臨床研修病院などにおいて研修を受けます。
制度はおおむね5年ごとに見直されており、2020年には「卒前卒後の一貫した医師養成」、「到達目標」「臨床研修病院の在り方」、「地域医療の安定的確保」などの観点から、研修内容が一部改定されています。
また、2018年4月からは、新専門医制度もスタートしました。
研修医と医師の違い
研修医は医師免許を取得しているので、資格上での差はありません。
唯一の例外は、開業して自分の病院を持つときに制限があるということくらいです。
法律上、研修医は「医師免許を持ち全国各地の医療機関で働く医師」という扱いになります。
しかし、すべての医療行為を一人で行うことはできないため、指導医にサポートしてもらわなければなりません。
研修医
初期研修医は原則2年以上の研修期間があり、「内科」24週以上、「救急」12週以上、「外科、小児科、産婦人科、精神科および地域医療」それぞれ4週以上の研修が義務付けられています。
なお、外科、小児科、産婦人科、精神科および地域医療においても、8週以上の研修を行うことが望ましいです。
初期研修の2年間はさまざまな診療科をローテートし、基幹型臨床研修病院、協力型臨床研修病院および臨床研修協力施設(診療所や保健所など)を巡回します。
医師としての「いろは」や、診療のための知識と技能を身につけるのです。
さらに、患者さんとそのご家族、ならびに一緒に働くコメディカルへの対応も学びます。
医師としての基本的価値観(プロフェッショナリズム)や、医師としての使命の遂行に必要な資質・能力を身につけているかどうかが重要視されます。
専攻医
専攻医の期間は、医療機関によって異なりますが、診療科ごとに3~5年が平均的です。
2018年から始まった新専門医制度に沿って、19ある基本領域から希望の領域を選択し、専攻医として専門研修プログラムを履修します。
研修医の呼称の違い
研修医は現場によっては、レジデント、フェロー、インターンなどと呼ばれることがあります。
レジデントとは研修医のことを指し、2年目までは「初期臨床研修医(ジュニアレジデント)」、3年目以降は「専攻医(シニアレジデント)」と呼ばれるのが一般的です。
フェローとは、3年目以降のまだ経験の浅い若手医師のことです。
一般的に医学部を卒業したあと、臨床研修医として2年間、いくつもの科を巡りながら経験を積み、その次の年には専攻する診療科を選択し、専門研修を修了して試験に合格すると専門医になれます。
この3年目以降がフェローと呼ばれます。
インターンという呼称については昭和23年に開始された、医学生が医師国家試験の受験資格を得るために制定された「インターン制度」から用いられています。
しかし実際には、ほぼ無休で働かされるという実態もあり、処遇が不明確で制度自体が見直されました。
近年では大学の医学部生が医師になる前に、病院等の医療の現場にとらわれず企業や行政などでの実務を体験しながら経験値を高めることを「インターン」と呼びます。
いずれにしてもインターンは「医師になる前の医学生」のことを指す言葉として用いられています。
医師免許を取得した研修医を指す言葉として、「レジデント、フェロー、インターン」などの言葉がありますが、実際の臨床現場では「〇〇先生」のように固有名詞と敬称で呼称されることがほとんどです。
また、厳密に意味を理解して使用している現場ばかりではなく、病院による伝統や組織による方向性で呼称が用いられていることもあります。
研修医は何年で修了するのか?
医師が研修に要する期間は、初期研修と後期研修(専攻医)を合わせると、最短でも5年はかかります。
専攻する診療科により異なりますが、医学生時代の留年や浪人がまったくない場合であれば、年齢的にはこの時点で29〜30歳ぐらいになっているのが一般的です。
研修医の仕事内容

研修医は医師免許を持っていますが、単独で行える医療行為には制限があります。
また、研修医が学ぶべきことは医療の知識と技術だけではありません。
研修医が単独でできることは限られている
研修医が単独で行える診療行為は限られており、患者さんの簡単な処置、診察、手術の補助、フォローアップなどが中心となります。
処置内容によっては指導医の許可の下で行えることもありますが、基本的には指導医のサポートが必要不可欠です。
研修医が学ぶべきことは医療のことだけではない
研修医が学ぶべきことは、医療に関することだけではありません。
医療チームの一員として協調性を発揮したり、患者さんとのコミュニケーション能力を高めたりするなど、チーム力や人間力も研修医として身につけるべき大切な要素です。
研修医の推定年収は?

参照:臨床病院における研修医の処遇|厚生労働省 第3回医師臨床研修制度の評価に関するワーキンググループ(平成23年11月)PDF資料
年収は、研修医と専攻医で大きく異なります。
一般に研修医ではそこまでの収入は望めず、専攻医になって初めて高収入になるのが特徴です。
厚生労働省の調査によると、研修医1年目の平均年収は500万円を割り込み、月収に換算すると平均36万2,718円となっています。
一方、専攻医になると平均年収は一般的に約650万円〜となり、多ければ1,000万円に到達する人もいます。
研修医の実際の金銭事情
研修医のアルバイト事情についても触れておきましょう。
専攻医はアルバイトができます。
専攻医は初期臨床研修を終えていると、アルバイトをすることが可能なのです。
なかでも、慢性期病棟での当直勤務は「寝当直」などといわれ人気のアルバイトです。
一方、研修医はアルバイトができません。
医師法第16条の5で「臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない」と規定されているためです。
研修医の待遇
研修医の待遇は病院によって異なりますが、住宅手当などの補助がある場合が多いです。
大学病院では全体の8割以上、臨床研修病院では9割以上で宿舎または住宅手当が用意されています。
また、賠償責任保険、賞与、社会保険の保証の有無なども確認しておくべきポイントです。
なかには学会参加費用などまで配慮した待遇がある病院もあります。
研修先の選び方
研修医にとって、研修先の選び方は非常に重要です。
ここでは、研修先を選ぶ際のポイントについて解説します。
医師臨床研修マッチングへ参加する
研修先を選ぶ際は、医師臨床研修マッチング協議会が提供する「医師臨床研修マッチング」に参加することを検討しましょう。
医師臨床研修マッチング協議会とは、研修希望者や研修医マッチング後の研修医のさまざまな相談等に応じる機関です。
参加者支援事業として、研修病院の研修プログラムや試験日程等の情報提供を行う他、説明会等を実施しています。
参加者と研修病院の組み合わせは、ゲール・シャープレーのマッチングアルゴリズムによって決まります。
このアルゴリズムは、デビッド・ゲイルとロイド・シャープレー(2012年ノーベル経済学賞受賞)という2名の学者によって提唱されたものであり、米国における研修医マッチング制度導入の際にも採用されました。
マッチングで内定した勤務先を変更することや、内定を辞退することはできないので注意が必要です。
研修先を選ぶときのチェックポイント
研修先を選ぶ際は、労働環境や教育体制、福利厚生、当直回数などについて確認することが大切です。
また、臨床研修は医師の基礎基本を学ぶ大事な期間なので、カリキュラムや将来のキャリアプランについても確認しておきましょう。
数多くの診療科を横断的に経験できる貴重な期間でもあり、選択期間の長さやカリキュラムの充実度を重視して選ぶことが大事です。
研修医としての立場を脅かさない環境かどうかもチェック
先に述べたように、研修医として一人で従事できる医療行為には限りがあります。しかしながら臨床現場の忙しさや医師同士の人間関係により、本来するべき確認事項が速やかに取れなかったり、そもそも越権行為である仕事内容を求められてしまうケースもあります。
2024年6月に起きた研修医の誤診事故については「研修医が未熟であった」という報道内容が見受けられましたが、この事件の背景として、病院の研修体制の問題や医師同士の風通しの良さなどについて疑問の声も上がりました。
必修研修である研修医時代の思わぬ事故を避け、キャリアプランにダメージが及ばないよう「研修医として守られる状況にあるかどうか」も、重要なチェックポイントの一つとなってくるでしょう。
研修医は「お金をもらいながら学べる期間」と心得て有意義な時間になるよう検討しよう
研修医の期間は、医師としてのスキルを磨きながらお金をもらえる貴重な期間です。
労働環境や教育体制、待遇面などをしっかりチェックしたうえで、自分に合った研修先を選ぶことが大切です。
研修医、専攻医を通して、医師としての基礎を固め、専門性を高めていってください。
研修医の期間を有意義なものにするためにも、研修先選びは慎重に行いましょう。
診療科選びに迷ったら医師転職サポートを活用してみるのもおすすめです。
ぜひ臨床研修を生かせる道を見出してください。






