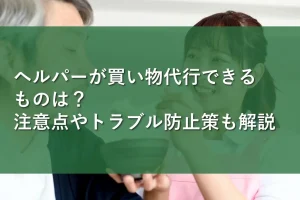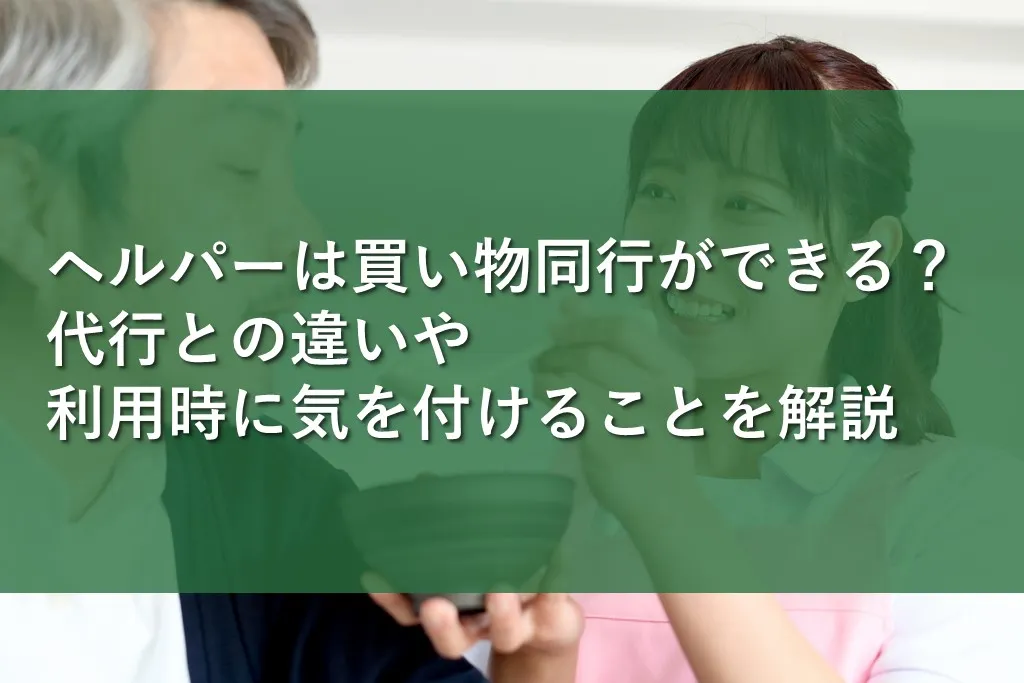
高齢者や障害を持つ人にとって、日常的な買い物は大きな課題となることがあります。
そんなときに頼りになるのがヘルパーによる買い物支援サービスです。
しかし、ヘルパーによる買い物支援にもさまざまなルールがあり、正しく理解して利用しなければなりません。
本記事では、ヘルパーによる買い物同行サービスについて詳しく解説します。
買い物代行との違いや、利用時に気を付けるべきポイントなども紹介しますので、適切なサービス利用の参考にしてください。
目次
ヘルパーは買い物同行ができる?

ヘルパーによる買い物支援には、同行と代行の2種類があります。
どちらのサービスも利用者の生活をサポートする目的で提供されますが、その内容や位置づけには違いがあります。
ここでは、ヘルパーによる買い物同行の可否や、代行との違いについて詳しく見ていきましょう。
ヘルパーは買い物同行できる
結論からいえば、ヘルパーによる買い物同行は可能です。
ただし、これは介護保険の枠内で、身体介助として行われるサービスであることに注意が必要です。
例えば、家族と同居していても食事が別の場合など、自力で食材を購入する必要がある利用者は買い物同行の利用が認められます。
しかし、購入した食材を家族と分けることが難しく、その食材を家族が調理するような場合には、適切な利用とはいえません。
介護保険を利用した場合の買い物同行の目的は、あくまで利用者本人の自立支援や生活維持にあります。
家族のための買い物や、生活に直接関係のない物の購入は対象外となりますので、注意しましょう。
なお、介護保険を利用せず、自費でヘルパーを依頼する場合はこの限りではないため、直接訪問介護事業所へ相談してみてください。
買い物同行は身体介助
買い物同行と買い物代行の大きな違いは、サービス導入の目的にあります。
買い物同行は、主に身体介助を目的としてサービスが検討されます。
つまり、利用者が自力で買い物に行くことが難しい場合に、ヘルパーが付き添って安全に買い物ができるようサポートするのが買い物同行の目的です。
歩行の補助や、商品を手に取る際の支援など、利用者の身体機能をサポートしながら買い物を行うことができます。
買い物代行は生活援助
一方、買い物代行は主に生活援助が目的となります。
利用者から買いたいものメモを受け取り、ヘルパーが一人で買い物を行い、利用者の自宅まで運ぶのが買い物代行です。
生活援助としての買い物代行では、利用者が最低限の生活を送るために必要な日用品や食材などを、ヘルパーが代わりに購入して届けます。
買い物同行とは目的が異なり、利用者本人が外出せずに必要なものを入手できるという点が特徴です。
買い物代行についてより詳しい情報が必要な場合は、以下のリンクをご参照ください。
ヘルパーの買い物同行のルール
ヘルパーによる買い物同行サービスを利用する際は、いくつかのルールを理解しておくことが必要です。
買い物代行とは目的が異なりますが、ルールには似ている点も多くあります。
ここでは、買い物同行時に守るべき主なルールについて解説していきます。
利用者以外(家族など)の分の買い物はできない
ヘルパーの買い物同行では、家族を含む利用者以外の買い物をすることはできません。
このサービスは、あくまで利用者本人の日常生活に必要な物の購入や、最低限必要な行為を支援する位置づけでの利用が求められます。
例えば、利用者の食事用の食材を購入するのは問題ありませんが、同居家族の分まで購入することはできません。
また、家族へのプレゼントや、利用者本人の生活に直接関係のない物の購入も対象外となります。
サービスの目的を理解し、適切な利用を心がけることが重要です。
不明な点がある場合は、事前にケアマネジャーや訪問介護事業所に確認しましょう。
たばこやお酒などの嗜好品を買うことはできない
ヘルパーの買い物同行では、たばこやお酒などの嗜好品は購入できません。
これらの商品は、日常生活上必要なものとしてカウントすることが難しいためです。
同様に、お歳暮や娯楽用品なども買うことができません。
買い物同行の目的は、あくまで利用者の日常生活に必要不可欠な物の購入です。
嗜好品や贈答品などの購入が必要な場合は、家族や友人に依頼するなど、別の方法を検討しましょう。
生活圏外のお店での買い物はできない
ヘルパーの買い物同行では、利用者の生活圏内での買い物が原則となります。
例えば、近くにスーパーがあるにも関わらず、遠くにある大きなスーパーや複合商業施設、デパートなどに行きたいという要望は通りません。
これは、買い物同行があくまで生活圏内での日常生活のサポートを行うことを目的としているためです。
利用者の要望だけで買い物先を変更することは難しく、あくまで日常的に利用している近隣の店舗が対象となります。
特別な理由で生活圏外の店舗での買い物が必要な場合は、ケアマネジャーや訪問介護事業所と相談し、対応を検討する必要があります。
大きすぎる荷物や重すぎる買い物はできない
買い物同行サービスを利用する際、重い荷物をヘルパーに持ってもらおうと考えることは適切ではありません。
このサービスは利用者の買い物時の身体介助が目的であり、ヘルパーの役割に大型のものや重量物を運搬することは含まれていないのです。
ヘルパーの役割は、利用者が安全に買い物を行えるようサポートすることです。
そのため、重い荷物を持ってもらおうという考えは避けるべきでしょう。
ただし、どうしても必要なものがある場合は、ケアマネジャーや家族などと相談する必要があります。
状況に応じて、別のサービスの利用や家族のサポートを検討することもあるでしょう。
ヘルパーの車に利用者が乗ることは原則できない
買い物に向かう際、利用者は原則としてヘルパーの車に乗って移動することはできません。
ヘルパーが利用者を乗せて運転する場合、道路運送法上の許可・登録が必要です。
さらに、自治体へ通院等乗降介助の届出が求められます。
これらの条件を満たしたうえで運転してもらうことは可能ですが、その場合は身体介護中心型ではなく通院等乗降介助(片道1回97単位)を算定する必要があります。
なるべく徒歩圏内ですませるか、公共交通機関の利用を検討しましょう。
ヘルパーの買い物同行時間は決まっている
ヘルパーの買い物同行時間は、利用者が満足するまでというわけではありません。
介護保険制度の単位数によって、あらかじめ時間が決められています。
例えば、以下のような時間区分と単位数が設定されています。
(例)
| サービス区分 | 所要時間 | 単位数 |
| 身体介護中心型 | 20分未満 | 163単位 |
| 20分以上30分未満 | 244単位 | |
| 30分以上1時間未満 | 387単位 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 567単位 | |
| 20分以上45分未満 | 179単位 | |
| 45分以上 | 220単位 |
この時間区分に基づいて、ケアプランで定められた時間内でサービスが提供されます。
そのため、買い物同行を利用する際は、限られた時間内で効率的に買い物を済ませることが必要です。
時間配分を考えて買い物リストを作成したり、優先順位をつけて購入する商品を決めたりするなど、事前の準備が重要となります。
ヘルパーと相談しながら、スムーズな買い物ができるよう心がけましょう。
複数のスーパーに行くことはできない
ヘルパーの買い物同行では、原則として一つの店舗で買い物を済ませる必要があります。
「肉はA店で、野菜はB店でそれぞれ安く買いたい」といった要望は認められません。
ただし、買わなければならないものがA店にない場合、B店に行くことは可能です。
また、同一施設(複合商業施設など)内に行きたい店が複数ある場合は、必要性を考慮したうえで行くことができる場合もあります。
複数の店舗を回ることは、時間的な制約や効率性の観点からも難しいでしょう。
事前に購入予定のものをリストアップし、1ヵ所で買い物を済ませられるよう計画を立てることが大切です。
ヘルパーの買い物同行を利用する際に気を付けること
ヘルパーの買い物同行サービスを利用する際は、いくつかの点に注意が必要です。
まず、このサービスをどのような目的で、なぜ必要としているのかをよく考えましょう。
そのうえで、ケアマネジャーや家族に相談し、適切なサービス利用を検討することが重要です。
また、ヘルパーを「家政婦」のように考えるのではなく、自立支援のためのサポート役としてとらえることも大切です。
できることは自分で行い、必要な部分でのみヘルパーの支援を受けるという姿勢が望ましいでしょう。
このような姿勢を心がけることで、自身のADL(日常生活動作)を維持し、できる限り自立した生活を送ることができます。
ヘルパーの買い物同行サービスを上手に活用し、生活の質を落とさないよう注意しましょう。
ヘルパーの買い物同行を利用して無理のない生活を送ろう
ヘルパーによる買い物同行サービスは、高齢者や障害を持つ人の日常生活をサポートする重要なサービスです。
このサービスを利用することで、自力での買い物が難しい方でも、必要な物を購入し、生活の質を維持することができます。
ヘルパーの買い物同行サービスを上手に活用することで、無理のない生活を送りながら、自立心を維持することができます。
サービスの利用に迷いがある場合は、ケアマネジャーや訪問介護事業所に相談し、自分に合った最適な利用方法を見つけていきましょう。