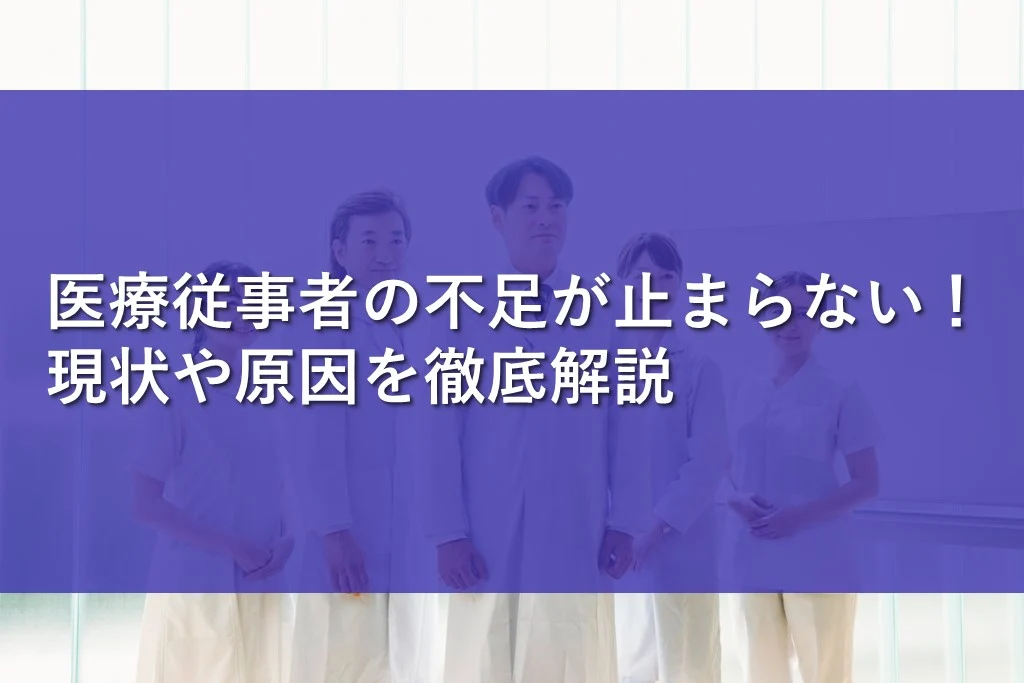
医療従事者は、業務量が多いことや医療事故への不安などの理由により、離職率が高く人手不足が深刻です。
一方で、日本国内では少子高齢化が進んでいるため、医療や福祉に従事する人材の需要は高まっていくと考えられます。
例えば日本看護協会の統計資料によると、看護職員の就労数は年々増加していることが明らかになっています。
一目見ただけでは人手不足と聞いても危機感を覚えにくいかもしれません。
しかし、医療業界の市場を全体的に見てみると、医師や看護師の人手不足が見受けられます。
なぜこのような問題が生じるのか、解消するにはどのような手段が考えられるのかをみていきましょう。
目次
医療従事者不足の現状について

早速、医療従事者の現状を見ていきましょう。
医療従事者の人手不足の現状や世界と日本の状況について解説いたします。
日本国内ではどれくらいの人手不足なのか
公益社団法人日本看護協会の「2018 年 病院看護実態調査」 によると、今後の看護職員について「今年度より増やす予定」と回答した病院が全体の約3割あり、人手が足りないと感じている病院が多く看護職員の需要が高いことがわかります。
しかし一方で、看護職員の毎年の離職率は正規雇用が11%前後、新卒が7.5%前後でほぼ横ばいになっており、改善の傾向がありません。
少子高齢化により15~64歳の生産年齢人口が今後も減り続けることを考えると、看護師の供給が大きく増えることは考えにくく、今後も人手不足は続くと予想されます。
また、厚生労働省は2025年までの看護職員の需要と供給のシミュレーションを発表しています。
現状の医療・介護サービス提供の問題点が解決されなかった場合や、医療資源を集中投入して急性期の入院日数が減った場合などさまざまなパターンでシミュレーションしていますが、いずれにしても2025年には185万~225万人の看護職員が必要になる見通しになっています。
一方で2025年の看護職員の供給はおよそ180万人にとどまるとされており、医療体制がどのように変化しても人手不足となることが予想されます。
人手不足を表す厚生労働省のデータ
医療従事者が不足している現状について、厚生労働省が発表している一般職業紹介状況(職業安定業務統計)から見てみましょう。
医療従事者の有効求人倍率は、以下の数値で推移しています。
| 医師(歯科医師、獣医師、薬剤師を含む) | 看護師(保健師、助産師を含む) | 医療技術者 | その他の保健医療の職業 | 職業計 | |
| 2020年2月 | 3.41 | 2.42 | 3.28 | 2.21 | 1.38 |
| 2021年2月 | 2.11 | 2.15 | 2.90 | 1.59 | 1.04 |
| 2022年2月 | 2.06 | 2.20 | 3.09 | 1.64 | 1.14 |
コロナウイルス感染症の流行でさらに深刻化
人手不足が続く医療従事者ですが、日本では2020年から爆発的に流行しているコロナウイルス感染症によって、労働環境はさらに深刻なものとなっています。
全日本自治団体労働組合(自治労)が医療従事者に対し「職場を辞めたいと思うかどうか」を調査した結果、「たまに思う」「しばしば思う」「常に思う」を合わせると7割程度の医療従事者が離職を検討していることが判明しました。
また、公益社団法人日本看護協会が2021年11月に発表した「コロナ禍における看護職員確保の現状と課題」によると、感染管理を担う看護職員を全国の病院に配置しようとすると約8,000人が必要とされています。
一方で、感染管理認定看護師は2021年3月時点で全国に3,006名、感染症看護専門看護師は90名しかおらず、感染症に関する高度な技術等を持つ看護職員が不足している原状があります。
世界の医療体制と比較
日本は諸外国に比べて、病床あたりの看護職員の配置数が少ないことが、厚生労働省より発表されています。
1床あたりの看護職員の配置数は、アメリカが4.1人、カナダが3.9人、イギリスが3.1人です。
これに比べて日本は0.9人と低い数値で、2017年度時点でOECD加盟国の35ヵ国のうち30位になっています。
集中治療室など、高度な技術を必要とされる看護補助者の配置も少なく、看護師が専門性が必要となる業務に集中するのが難しい状況です。
医療従事者が不足する2つの原因

さまざまな要因で人手不足が深刻化している医療従事者。
では、具体的にどのような原因で人手不足に陥っているのでしょうか。
こちらでは2つの原因を紹介します。
ハードな業務内容
新型コロナウイルス感染症の流行により、医療従事者のハードな業務内容をニュースなどで目にすることが多くなったという方もいるでしょう。
医療従事者は、勤務形態が不規則になるためプライベートとの両立が難しい仕事の一つです。
病院で勤務すると夜勤勤務が避けられない場合もあります。
夜勤においては、勤務している医療従事者の数は少なくなるので、緊急の対応が発生した場合には休息が取れないほど慌ただしくなる場合も考えられます。
さらに、人手不足が深刻なほど休暇も取りづらくなるでしょう。
不規則なうえ余裕もない勤務形態により、医療従事者に負担が重くのしかかっています。
高齢化による医療ニーズの高まり
高齢化がすすむ日本では、医療従事者の需要が高まっています。
前述したように、医療に関係する人材確保は大きな課題とされていますが、高齢化問題によって重要視されているのが、急増する要介護高齢者の介護サービスを支える人材の確保です。
介護サービスの場合、ベテラン介護職員でもいくつもの業務がこなせるわけではありません。
介護サービス量やニーズに応じた介護職員数が必要になります。
しかし、介護の仕事はハードなイメージを持つ方もいるため、介護福祉士を養成する大学や専門学校では入学者の定員割れが続いている状況です。
医療従事者の不足を食い止める方法は?

どうすれば医療従事者の人手不足を解決できるのでしょうか。
ここからは、解決にむけて考えられる方法を紹介いたします。
各種手当を充実させる
不規則な勤務形態である医療従事者に、夜勤手当や残業手当のような手当を充実させることで不満を軽減させることが可能です。
手当によって収入が上がれば、自身の業務が正当に評価されていると感じることができ、医療従事者の労働意欲向上が期待できます。
また、他の病院に比べて給与が高ければ、人手不足解消にもつながります。
そのため、手当を充実させることは雇用維持と採用の両方面から人手不足を解消できる施策だと考えることができます。
ライフスタイルに配慮した働き方
少子高齢化だけでなく、核家族化が進んでいる日本。
家庭では育児や家事に専念できる人が少なくなっているため、妊娠・出産において夜勤が難しくなる医療従事者の増加が考えられます。
このような事情から、やむを得ず離職を選択するケースも増えています。
このことから考えると、各々のライフスタイルに適したサポート体制が整えば、離職を防ぐことができるでしょう。
例として、勤務形態の見直しや時短勤務採用、夜勤の免除や有給休暇・看護休暇を取りやすくする環境づくりが考えられます。
デジタル機器の有効活用で負担を軽減
医療従事者の人手不足の原因として、患者さん個人と関わる予診や採血のような技術面以外の業務が多く、負担になっていることも挙げられます。
業務の負担を軽減するには、デジタル機器であるロボットやAIを有効活用することが効果的でしょう。
毎日の検温や検査をAIが実施し、医師がその結果をチェックするような流れを実現したとします。
これが成功した場合、医師や看護師一人あたりの負担が軽減され、限られた人手でも業務が滞ることが減ると考えられます。
しかし、デジタル機器の活用を実現するにはコストや技術の発展が不可欠になります。長期的な視点で考えることが必要になるでしょう。
医療従事者不足は止まらない!環境の整備が重要
今回紹介してきたように、医療従事者の人手不足は深刻化しているといえます。
人手不足の問題を解決するには、一人あたりの負担を軽減し評価を正しく与えられる環境が重要になるのです。
各種手当を充実させることや、ライフスタイルに合わせた働き方の実現が、人手不足を解消するための今後の課題といえるでしょう。
人の命を救うため力を尽くしている医療従事者に正しい評価がなされる環境づくりが待たれます。






