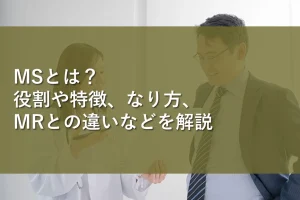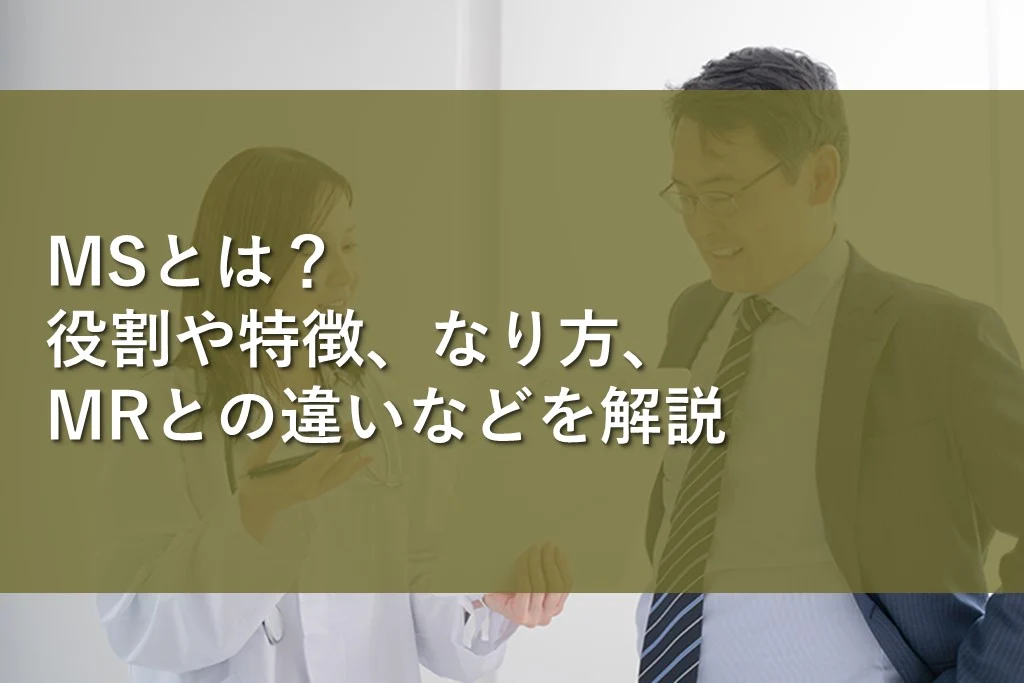
MS(医薬品卸販売担当者)は、医薬品や医療情報などを医療機関や調剤薬局に供給する仕事です。
今回の記事では、MSという仕事に興味がある方に向けて、MSの特徴やなる方法、MSと混同しやすいMRとの違いなどについて紹介します。
医療業界における営業の仕事に興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
医療に関わるMS(医薬品卸販売担当者)とは?

まずは、MS(医薬品卸販売担当者)の役割、なり方、やりがいなどについて紹介します。
MSは医薬品卸業の営業担当者
MSとはマーケティング・スペシャリストの略であり、医薬品卸会社の営業担当者のことです。
医薬品は主に、製薬会社から直接病院や調剤薬局などの医療機関に供給されるパターンと、製薬会社から医薬品卸会社を経由して医療機関に供給されるパターンがあります。
MSは、製薬会社と医療機関の仲介をしている医薬品卸会社に勤務し、医療機関に医薬品の営業を行います。
営業を通して、製薬会社から仕入れた医薬品を、病院や調剤薬局などの医療機関に安定的に供給することが、MSの主な役割です。
また、医薬品を販売するだけでなく、実際に納品したり、価格交渉をしたり、医療機関に医薬品の情報提供をしたりといった役割も担っています。
MSは、医療機関との営業を通して、医療機関の経営や最新の医療情報などさまざまな情報の収集ができます。
そのため、単なる営業だけでなく、医薬品の安全性や有効性、流行している疾患に対する薬の最新情報などを中立的な立場で提供し、適切な医薬品を選択できるよう提案するスキルが必要です。
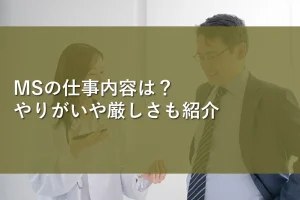
MSになるために資格は必要?
MSになるために必要な資格はありません。
そのため、医薬品卸売会社に就職することで誰でもMSとして活躍できます。
必須の資格ではありませんが、一般社団法人日本ジェネリック医薬品販社協会が認定しているMS認定資格制度を取得することで、次のようなスキルを身につけられます。
- 医薬品の情報提供に関するスキルの向上
- 医療経営のコンサルティング業務
- 効率改善に貢献できるような提案の実施
- コンプライアンスを守った業務を行うための知識や技術
MSは、医薬品や薬学の知識を中心に幅広い知識が必要になるため、MS認定資格制度を取得することでスキルのアピールになるでしょう。
MSのやりがいと大変さ
MSは、医薬品を通して医療を支えるという命に関わる仕事のため、大きなやりがいを感じる反面、大変さを感じることもあります。
MSのやりがい
MSは、医薬品の供給や医療に関する最新情報を提供することで、地域の医療現場をサポートできます。
そこに、やりがいを感じる方も多いでしょう。
医療現場をサポートできる
先述したとおり、MSの主な役割は、営業先である病院や診療所、調剤薬局などの医療機関に対して医薬品の販売活動や情報提供を行い、医薬品を安定的に供給することです。
医薬品の安定供給によって、医療現場を間接的にサポートすることができます。
また、さまざまな製薬会社の医薬品を取り扱ったり、訪問先に伺ったりすることで、多くの最新情報を得ることができます。
そうして得た最新の医療情報を、得意先である医療機関と共有し、医療機関に合った必要な医薬品を提案することで、結果的により良い医薬品を提供することにつながるでしょう。
地域の病院や調剤薬局の経営を支援できる
医薬品の購入は、医療機関の経営を左右するものです。
医療機関への医薬品の販売を通して、最適な医薬品の提案やコスト削減方法のアドバイスをすることで、医療機関の経営を支援できます。
単なる営業だけではなく、提案型の営業や、コンサルティング業務を通して経営をサポートするニーズもあり、MSの活躍の幅は広がっています。
MSの大変さ
MSの仕事は、職場によっては勤務形態が不規則であったり、ノルマがあったりと大変さを感じる場合もあります。
異動・転勤がある
MSの仕事では、転勤により引越しが必要になる可能性もあります。
医薬品卸会社は多くの支店を持っていることが多く、営業支店のなかで異動が発生したり、人事異動によって配属が変わったりするケースがあるためです。
一つの場所にとどまりたい方や、家庭の事情で引越しが難しい方は、就職する前に異動や転勤に関して融通がきくのかを確認しておくと安心でしょう。
ノルマに対するプレッシャーを感じる
MSは医薬品の営業職であるため、ノルマが存在します。
ノルマを達成できるかとプレッシャーを感じることもあるでしょう。
医薬品の価格決定権があることも、プレッシャーの要因の一つです。
価格を高く設定しすぎてしまうと契約に至らない反面、低く設定してしまうと会社の利益にならないため、価格設定の絶妙なバランスを取らなければなりません。
利益を確保できるように売上管理をすることが求められます。
MSに向いている人
MSは営業職のため、人とコミュニケーションを取ることが好きな人や、最新の医療知識を学ぶことが好きな人に向いている職業です。
人とコミュニケーションを取るのが好きな人
MSは、営業先である医療現場の方や、仕入れ先である製薬会社の方など、さまざまな立場の方と話す必要があります。
そのため、どのような立場の人とでも話せる人、相手の立場によって提案内容を臨機応変に変えられる人などに向いています。
また、取引先の方たちと会食をする場合もあるため、コミュニケーションが苦にならない人は向いているでしょう。
プレゼンテーション能力の高い人
プレゼンテーション能力も、MSに求められるスキルの一つです。
営業先である医療関係者は日々の業務で忙しいため、短い時間のなかで工夫しながら提案し、営業していく必要があります。
そのため、相手にとって必要な情報を端的に、かつ的確に伝えていくプレゼンテーション能力は重要です。
前職でプレゼンテーションをする機会が多かった人、得意だったと感じる人は向いているでしょう。
新しい知識を学ぶことが好きな人
医療業界では、日々新しい医薬品や医療機器などが開発・販売されています。
そのため、新しい知識を学び、情報をアップデートし続けなければなりません。
また、医薬品に関する最新情報以外にも、医薬品の営業経験を通して流通や販売、経営など、コンサルティング業務に関する知識も学ぶ必要があります。
最新情報をキャッチするのが得意な方、経営や医療業界などの知識を幅広く学ぶのが好きな人に向いている職業といえるでしょう。
MSとMRの違い

MSと混同してしまいがちな職業にMRがあります。
MSとMRの違いは、以下のとおりです。
働く場所が異なる
MSとMRは、働く場所が異なります。
MSは医薬品卸売会社の営業です。
複数企業の医薬品を取り扱い、医薬品の価格交渉や販売などを行うのが主な役割です。
一方、MRは製薬会社の営業担当者です。
自社で販売している医薬品のみを取り扱っており、他社の医薬品は取り扱いません。
MSとMRでは働く場所が異なりますが、MRは自社の製品の情報をMSに提供したり、MSは日々の営業活動のなかで得た情報をMRに提供したりと、お互いに必要なパートナー的存在となっています。
必要な知識が異なる
MSは、さまざまな医薬品を取り扱うため、医薬品の知識を中心に、物流や販売、経営など、幅広い知識が必要です。
一方でMRは、自社製品を提供するのが主な役割となるため、MSのような物流や経営などの知識までは求められない傾向にあります。
ただし、専門領域である臨床データや最新文献の知識など、専門的な知識が求められます。
価格決定権の有無
MSとMRにおける大きな違いの一つが、価格決定権の有無です。
卸売会社の営業であるMSは、価格決定権を持っています。
価格交渉も営業活動の一つのため、他社の動向を調査するなどマーケティングの知識や、売上・利益の管理といった経営の視点も求められます。
一方でMRは製薬会社の営業であり、決められた価格での医薬品販売となるため、価格決定権はありません。
医療用医薬品の流通実態に関する調査報告書のアンケート結果によると、全体の98.8%が価格交渉を行っていないと回答しています。
MRについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。
MSは医薬品を流通させるために必要な仕事
MSは、患者さんのもとへ安定して医薬品を届けるために、重要な役割を果たしています。
医薬品の供給を通して医療機関をサポートしたり、営業で得た知見を医療機関に情報提供したりすることで、経営のサポートやコンサルなどの提案まで行うことができます。
自身の営業スキルや経営の知見を活かして医療業界に貢献したいと考えている方は、めざしてみてはいかがでしょうか。