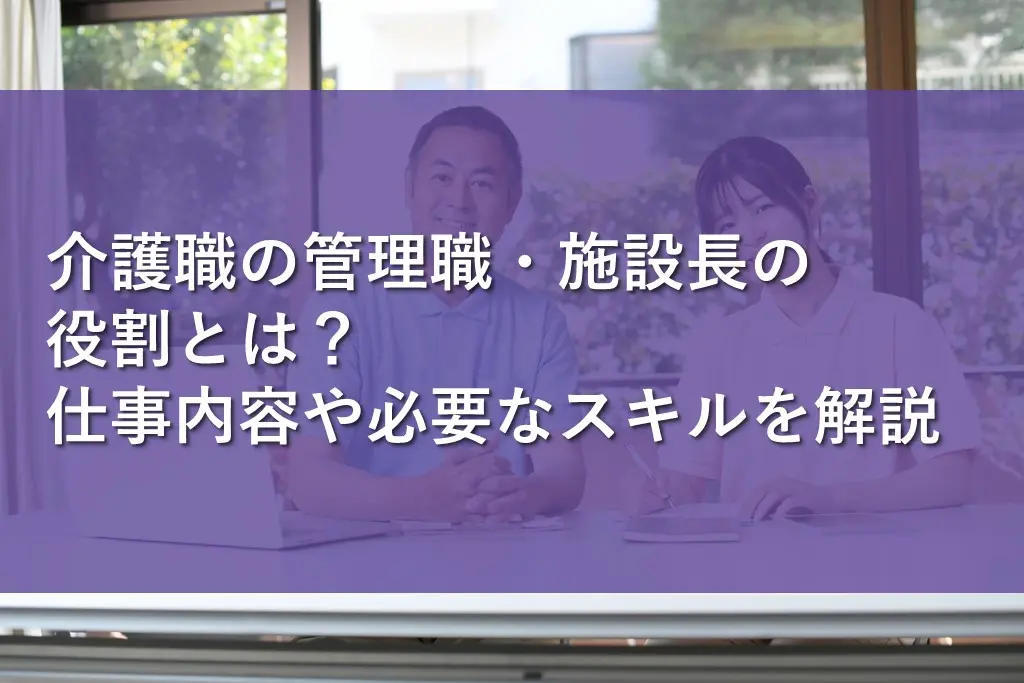
現在、介護士として働いている方のなかには、「いずれは管理職や施設長のポジションになりたい」と考える方もいるのではないでしょうか。
介護業界で収入アップをめざしたり多角的な視野を得たりするには、キャリアアップが有効な手段です。
管理職・施設長になる方法や業務範囲などが明確にわかれば、今後のキャリアパスを描きやすくなるでしょう。
今回は、介護職における管理職・施設長の役割や仕事内容、施設ごとの資格要件などを解説します。
目次
介護職における管理職・施設長とは

介護職の管理職・施設長とは、施設や事業所でのトップポジションを指します。
管理者やホーム長、所長と呼ばれることもあります。
職場によっていろいろな呼び方がある管理職ですが、どれも施設の顔となる存在には変わりありません。
利用者の方や職員のこと、営業活動や事務作業など、施設の運営に関わる全般的なことを管理するのが管理職や施設長です。
介護職の管理職・施設長の就職先
介護職における管理職の就職先は、主に以下のような事業所や施設です。
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護付有料老人ホーム
- 訪問介護事業所
- デイサービスセンター
介護職の管理職・施設長の役割
介護施設のトップポジションである管理職・施設長の業務内容は多種多様です。
現場の状況把握から施設の運営に関わる事務作業まで、すべてに意識を向けなければなりません。
良好な組織運営が求められる管理職・施設長の役割には、以下の3つが挙げられます。
- 人材の育成
- 理念や方針・ルールの周知・徹底
- 連絡・調整
ここで、それぞれの役割を具体的に解説します。
人材の育成
職場環境の改善に取り組み、職員のモチベーションを上げるのは施設長の役割です。
将来性のある職員をベテランに育て上げるのは、施設長の腕にかかっているといっても過言ではありません。
外部とのやり取りや事務作業にいくら長けていても、現場のことが理解できず職員に意識を向けられない施設長は、職員からの信頼を得られません。
組織のトップに立つ施設長は、介護士だけでなく看護師や生活相談員、ケアマネジャーなどあらゆる職種の人材がやりがいを持って職務に臨めるように、職員一人ひとりと向き合う必要があります。
理念や方針・ルールの周知・徹底
介護施設では職場によってさまざまな理念、方針、ルールなどがありますが、管理職・施設長には職員と一致団結してこれらを徹底し、サービスの質向上をめざす役割があります。
常に忙しく動き回り心身の負担が大きくなりがちな介護の仕事では、介護する側だけの効率を重視したサービスになってしまうことも少なくありません。
しかし、サービスの質向上とは、利用者の方にとって何が必要かを見極めたり、心地良く過ごしてもらったりするためのものです。
理念や方針、ルールなどが明確な職場では、職員が共通の意識を持ち、利用者目線で介護に従事できます。
したがって、管理職・施設長には、職員一人ひとりに理念や方針が浸透するよう意識的に伝え、遵守を徹底させる責任があります。
連絡・調整
管理職・施設長の役割は、施設内の管理だけではありません。
介護事業を存続するためには、施設のコンプライアンスを整備したうえで行政とやり取りをしたり新規契約の獲得のために営業を行ったりする必要もあります。
また、利用者の方の心身を維持するためには、医療機関とのスムーズな連携も欠かせません。
管理職・施設長はあらゆる職種と連絡・調整を行うことで、施設の運営を管理しなければならないのです。
介護職の管理職・施設長の仕事内容
介護職の管理職・施設長の役割は幅広いですが、具体的な仕事内容には以下に示す5つがあります。
- 利用者の管理
- 職場のマネジメント
- 施設の運営
- 経理
- 行政や外部業者との連携
それぞれの内容を以降で解説します。
これから管理職をめざす方はぜひ参考にしてみてください。
利用者の管理
利用者一人ひとりの経緯や家族関係、ADLや特性などを理解し、ケアプランが適切であるかを確認します。
また、これから入居・退去する方に対して、ご家族を交えて面談を行います。
職場のマネジメント
職員の採用面接や適切な人員配置、他施設へのヘルプ要請などを行い、施設の運営に必要な人員を確保します。
現場の声を汲み取るためにアンケートや面談を実施し、良好な職場環境の維持に努めるのも管理者の仕事です。
トラブルが生じた際には、担当職員の面談を行ったり人員配置を変更したりします。
施設の運営
管理職にとって重要な仕事は、施設の運営に関わるコンプライアンスに徹し、安心安全な介護施設をめざすことです。
そのためにも、施設の運営方針や目標、信条などを定めたり、広報・営業活動を行ったりします。
経理
利用者の契約に関する業務や介護保険の請求、諸々の経費の管理なども管理職の仕事の一つです。
施設の賃料や水道・光熱費、食費などの支出と介護報酬(収入)を算出し、収支のバランスを維持できるように各種コストの調整を行います。
なお、介護報酬請求業務や請求書作成、備品の発注、労務関連の事務といった経理業務は介護事務の方の仕事です。
外部業者や行政との連携
介護用品の販売会社など、外部業者とのやり取りもあります。
備品の在庫状況の管理や発注業務などは介護事務の仕事ですが、取引する会社を選んだり交渉したりするのは、管理職・施設長の役目であることも少なくありません。
また、介護事故報告書や職員の処遇改善・特定処遇改善に関する計画書、施設の運営に変更があった際の届出などを作成し、期日内に行政機関へ提出するのも管理職の仕事です。
提出期限を過ぎたり内容に過不足があったりする場合、申請の反映が延期され、施設の運営に負担がかかることがあります。
介護職の管理職・施設長になるには
介護職の管理職・施設長は、ただ経験を積めばなれるものではありません。
施設ごとに異なる要件をクリアした方が、組織のトップに立てるのです。
以下、施設別の要件を紹介します。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームで施設長になるには、以下条件のうちいずれかが必要となります。
- 社会福祉主事の要件を満たしている
- 社会福祉に関する事業に2年以上従事した経験がある
- 社会福祉施設長資格認定講習会を受講している
介護老人保健施設
介護老人保健施設の管理については、介護保険法の95条にて以下のように定められています。
介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。
出典:介護保険法 第九十五条
しかし、都道府県の知事から承認された方であれば、医師でなくても施設長になることができます。
前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。
認知症型グループホーム
認知症型グループホームで施設長になるには、以下に示す2つの要件をいずれもクリアする必要があります。
- 認知症介護経験が3年以上ある
- 認知症対応型サービス事業者管理研修を受講している
資格要件のない施設
以下のように、管理職・施設長になるための資格要件が特に設定されていない施設もあります。
- 有料老人ホーム
- デイサービス
- 訪問介護事業所
資格要件はないものの、介護現場での実務経験や、介護関連資格の保有者などが優遇されやすい傾向はあります。
なお、施設によっては資格取得、研修のサポートを行ってくれるところもあります。
介護職の管理職・施設長の給与
ハードな仕事の割には収入が低いとされる介護職ですが、キャリアアップによって収入は上がります。
ここで、現場の介護職員と管理職・施設長の給与を確認してみましょう。
公益財団法人「介護労働安定センター」による令和2年度の「介護労働実態調査」では、介護職の管理職と介護職員の所定内賃金と賞与が以下であるとわかりました。
| 分類 | 所定内賃金(月額) | 賞与 |
| 介護職員 | 243,135円 | 626,094円 |
| 介護職の管理職 | 382,036円 | 866,872円 |
また上記を踏まえて双方の大まかな年収を算出すると、下記の結果が得られます。
| 分類 | 年収(所定内賃金額×12+賞与額) |
| 介護職員 | 3,543,714円 |
| 介護職の管理職 | 5,451,304円 |
つまり、介護職の管理職と現場の職員の年収には190万円を超える差が認められます。
同じ介護職でもポジションが上がると大きく収入アップできることがわかります。
ただし、管理職・施設長はトラブル時には昼夜問わず時間外出勤を余儀なくされたり、ご家族への説明に長時間を費やしたりすることもあり、現場の職員よりも負担が大きくなりがちです。
現場職員の給与と比べると管理職・施設長は高給となりますが、その分仕事内容も精神力をともなうものとなることを考慮しておきましょう。
介護職の管理職・施設長に必要な能力
介護職の管理職・施設長に必要な能力には以下の3つが挙げられます。
- 組織をまとめる能力
- コミュニケーション力
- 介護に関する知識・経験
組織をまとめる能力
施設全体の取りまとめを行う施設長には、自らが率先して職員の手本となるような統率力が求められます。
施設長としての信念を職員全体にしっかりと伝え心をつかむことで、職員のモチベーションアップやサービスの質の向上、離職率の低下をめざせます。
コミュニケーション力
現場のヒヤリハットや事故を未然に防ぐには、施設長が積極的に職員や利用者、ご家族とコミュニケーションを取り、情報の連携がしやすい雰囲気を作ることが大切です。
特に、デスクワークも多い管理職と現場での仕事がメインの介護士とでは双方の職務への無理解から溝ができやすく、良好なコミュニケーションが困難になることがあります。
施設長には、職員一人ひとりと向き合い、些細な不安や疑問にも答えられる器の広さが必要といえるでしょう。
介護に関する知識・経験
施設長は現場のトラブルに柔軟かつ冷静な対応を求められますが、予測不能な事態で活きるのが、介護に関する知識と経験です。
また、利用者やご家族からの信頼を得るにはコミュニケーション力や統率力はもちろんのこと、介護技術に関する専門的な知識も求められます。
したがって、たとえ応募の条件が「介護未経験者歓迎」であっても、管理職・施設長になるには現場での実務経験があるほうが望ましいでしょう。
介護職の管理職・施設長に向いている人・向いていない人
介護職の管理職・施設長は責任の重い業務を担うため、やりがいを持って取り組める人と、業務に精神的な負担を抱えてしまう人とに分かれがちです。
以下では、介護職の管理職・施設長に向いている人と向いていない人、それぞれの特徴を紹介します。
向いている人の特徴
介護職の管理職・施設長に向いている人の特徴には以下の3つがあります。
- フットワークが軽い
- 協調性がある
- ポジティブである
管理職は施設でのあらゆる事象に対応しなければなりません。
また、施設の運営を職員と協力して進めたり、フレキシブルな動きができるよう時間と心にいつでも余裕を持っておいたりする必要があります。
上記3つを持ち合わせた人は、管理職・施設長の仕事にやりがいを感じられるでしょう。
向いていない人の特徴
介護職の管理職・施設長に向いていない人の特徴には以下の3つがあります。
- 現場での仕事が好き
- 周囲に作業を振るのが苦手
- ネガティブである
管理職の仕事は、「ただ人助けがしたい」という気持ちだけでは成立しません。
施設運営のための収入を意識した営業活動やコスト削減を実施したり、ときにはケアマネジャーや生活相談員、現場のリーダーに作業を振ったりすることもあるでしょう。
また、業務の忙しさから心の余裕がなくなり、目の前のことしか考えられなくなってしまうと、周囲のモチベーションを低下させる恐れがあります。
介護職に求められる管理職・施設長の役割を理解しておこう
介護職の管理職・施設長の仕事内容や役割、資格要件などを解説してきました。
高齢化社会を生きる私たちにとって、介護職は必要不可欠な存在です。
介護業界の要ともいえる管理職や施設長は、介護士がめざす価値のあるポジションといえるでしょう。
「現場の介護士を統率してより良いサービスを提供したい」という方は、管理職・施設長への道を選択肢の一つにしてみてはいかがでしょうか。






