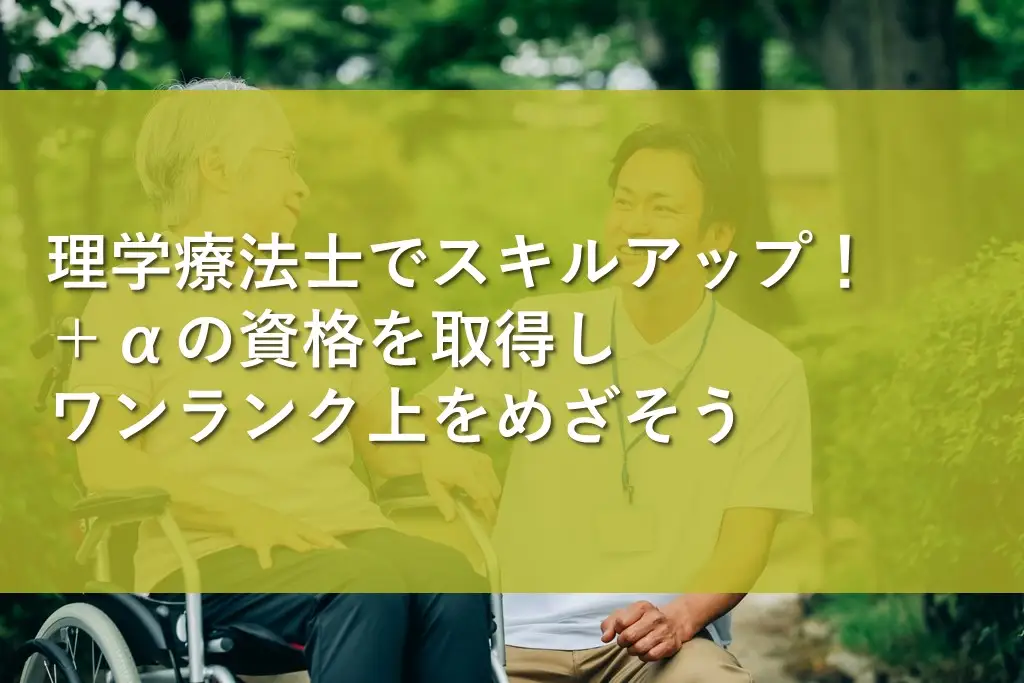
理学療法士がスキルアップして得られる+αの資格は数多くあります。
公的な資格から民間資格までさまざまで、取得の難易度もそれぞれです。
スキルアップできれば、給料の増額が見込めたり、有利な条件で転職できたりします。
この記事では、9つのスキルアップできる資格を紹介します。
自分にあった資格を探して、挑戦してみましょう。
目次
理学療法士がスキルアップできる+αの資格

理学療法士がスキルアップできる+αの資格のうち、以下の9つを紹介します。
- 認定理学療法士
- 専門理学療法士
- 心臓リハビリテーション指導士
- 呼吸療法認定士
- 認知症ケア専門士
- 日本糖尿病療養指導士
- 栄養サポートチーム専門療法士
- 福祉住環境コーディネーター
- スポーツ系資格
+αの資格を取得するスキルアップは、給料アップや転職時のセールスポイントにつながります。
気になる資格がある場合は、ぜひチャレンジしてみましょう。
上記の認定資格以外にも、別分野の国家資格を取得する方法でスキルアップする道もあります。
認定理学療法士
認定理学療法士は、公益社団法人日本理学療法士協会が実施する理学療法士の生涯学習制度の資格です。
臨床分野での専門性を修得することを目的として作られました。
2022年4月に制度がリニューアルされ、今後は5年ごとの更新制となります。
協会が発表したデータによると、2023年度の理学療法士国家試験合格者累計は213,735人でした。
認定理学療法士の取得者は14,567人(2023年3月31日時点)です。
理学療法士免許の取得者全体の割合に対し、認定理学療法士の取得者は約6.8%です。
資格を取得すると希少性が高い人材と見なされるでしょう。
資格を取得するには規定のカリキュラムを受講し、日本理学療法学術研修会へ参加したのち、認定試験に合格する必要があります。
認定資格を得ることは、豊富な知識を持っている証明になります。
そのため、所属施設への貢献度が上がり、給料の増加が見込めたり、転職時のアピールポイントとなったりするでしょう。
受験資格を得るまでに研修期間が最短で5年が必要です。
専門理学療法士
専門理学療法士も、公益社団法人日本理学療法士協会が実施する生涯学習制度の資格です。
学問的指向性の高い人材を育成する目的があります。
認定理学療法士と同様、2022年4月に制度がリニューアルされ、今後は5年ごとの更新制となりました。
専門理学療法士の取得者数は、認定理学療法士よりもさらに少なく、1,712人(2023年3月31日時点)となっています。
理学療法士免許の取得者全体のなかで、専門理学療法士取得者の割合は0.8%ほどです。
資格の取得には、規定のカリキュラムを受講するだけでなく、都道府県や全国規模の各学会への参加および発表、論文提出などもクリアする必要があります。
学会参加や研究活動の発表などで名前が広まると、勉強会や研修会で講師として活躍できるようになるかもしれません。
心臓リハビリテーション指導士
心臓リハビリテーション指導士は、特定非営利活動法人日本心臓リハビリテーション学会が2000年に定めた資格です。
理学療法士が心臓リハビリテーション指導士の資格を取得する条件は、以下のようになっています。
- 学会主催の講習会を当該年度に受講する
- 申請時に学会会員であり、直近2年以上継続した会員歴がある
- 心臓リハビリ指導の実務経験1年以上、または心臓リハビリ研修制度を受け、受験資格認定証を交付されている
- 10例の症例報告を含めた申請書類がすべて揃っている
心臓リハビリ指導士の役割は、循環器疾患の治療や再発予防とQOL(生活の質)の向上に貢献する活動を行うことです。
運動、食事療法や禁煙指導など包括的なリハビリを実施し、動脈硬化性疾患の発症予防から再発予防まで幅広く対応します。
心臓手術後のリハビリだけでなく、メタボリックシンドロームや脳血管疾患の患者さんに対して、動脈硬化の進展予防の教育を実施します。
運動による循環動態の変化を理解できる心臓リハビリテーション指導士は、安全で効果的な運動・生活指導が行えるでしょう。
心臓リハビリテーション指導士の資格を取得すれば、循環器系の診療科を持つ病院への就職活動で有利になることもあります。
呼吸療法認定士
呼吸療法認定士は「一般社団法人日本胸部外科学会」、「一般社団法人日本呼吸器学会」、「公益社団法人日本麻酔科学会」の3つの学会が合同で創設した認定資格です。
理学療法士が呼吸療法認定士の資格を取得するには、下記の条件を満たす必要があります。
- 2年以上の実務経験がある
- 学会が認める講習会や学会などに出席し、必要ポイントを取得する
- 認定講習会を受講する
呼吸療法認定士は、吸入療法、酸素療法、呼吸理学療法、人工呼吸などの呼吸療法の専門家です。
高齢化の進行と高度医療の適応拡大により、呼吸療法の普及が望まれています。
特に、人工呼吸サポートチーム(RST:Respiration Support Team)がある病院では、優先的にチーム医療へ配属されるケースもあり、重要な人材として重宝されるでしょう。
認知症ケア専門士
認知症ケア専門士は、一般社団法人日本認知症ケア学会が認定する更新制の資格です。
資格の取得には、第1次試験(WEB試験)、第2次試験(論述試験)に合格し、登録申請を行う必要があります。
受験には、認知症ケアに関する施設、団体などで過去10年以内に3年以上の実務経験が必要です。
認知症ケア専門士は、認知症介護従事者の自己研鑽と生涯学習の機会を提供するために設けられた資格です。
認知症の患者さんやそのご家族に対し、高水準の知識と技術を提供できます。
このまま高齢化が進展し、各年齢における認知症有病率が上昇した場合、2012年の推計462万人から2025年には730万人にのぼるという調査結果が出ています。
資格を持つ人を積極的に配置しようとする介護施設や病院などもあり、認知症ケアに特化した専門資格である認知症ケア専門士は、今後は需要がさらに高まっていくでしょう。
さらなるスキルアップをめざす場合、「認知症ケア上級専門士」という上級資格があります。
受験資格は、認知症ケア専門士としての3年以上の経験、指定期間内で認知症ケア専門士の単位を規定数以上取得、認知症ケア上級専門士研修会を修了、学術集会や研修会などでの演題発表または査読制度のある機関誌等での論文・事例発表が必要です。
取得後は、ケアチームのリーダーや地域のアドバイザーとしての活躍も見込まれます。
日本糖尿病療養指導士(CDEJ)と地域糖尿病療養指導士(CDEL)
糖尿病治療に関係する資格は2つあります。
日本糖尿病療養指導士(CDEJ)と地域糖尿病療養指導士(CDEL)です。
2つの資格について、それぞれ解説していきます。
日本糖尿病療養指導士(CDEJ)
日本糖尿病療養指導士は、日本糖尿病療養指導士認定機構が認定している資格です。
理学療法士が取得するには、以下の条件が必要になります。
- 糖尿病治療について一定の条件を満たしている医療施設で、過去10年以内に2年以上かつ通算1,000時間以上の糖尿病患者への療養指導業務に従事した実績がある
- 糖尿病療養指導の自験例が10例以上ある
- 認定機構が開催する講習(eラーニング)を受講する
業務内容は、患者さんの自己管理(療養)の指導です。
資格取得の際に身につけた幅広い専門知識は、生活指導のエキスパートとして患者さんの支援で発揮されます。
地域糖尿病療養指導士(CDEL)
地域糖尿病療養指導士(CDEL)は、都道府県や地区ごとの認定組織による資格です。
資格認定などに基準は設けられているものの、認定組織ごとのレベルの差が出ることがあります。
そのかわり、地域の特色に合わせた糖尿病の治療や予防ができる強みも持っています。
栄養サポートチーム専門療法士
栄養サポートチーム専門療法士は、日本臨床栄養代謝学会が認定する資格制度です。
理学療法士が取得するには、以下の条件が必要です。
- 医療・福祉施設に3年以上勤務し、栄養のサポートに関わる業務に従事した経験がある
- 日本臨床栄養代謝学会員であり、会費を完納している
- 学会や研修会へ規定回数参加する
- 認定施設において、40時間の実地修練を積む
- 1〜4の条件を満たしたあと、試験に合格している
栄養サポートチーム専門療法士を取得した場合、栄養サポートチーム(NST)の一員として活動できます。
現在すでにNSTは1,300以上の施設に設立され、多くの施設で稼働準備が進められています。
栄養管理実施加算、栄養サポートチーム加算の算定が認められるなど、栄養に対する治療は今後も需要があり、キャリアアップとして資格取得の視野に入れると良いでしょう。
福祉住環境コーディネーター
福祉住環境コーディネーターとは、東京商工会議所が認定する民間資格です。
受験資格はなく、学歴や年齢などの制限がありません。
1級〜3級まであり、段階を踏んでステップアップします。
| 3級 | 超高齢社会が到来する現在やこれからにおいて、生活者として知っておくべき福祉一般の基本的な知識を理解している |
| 2級 | 介護、医療、福祉、建築、福祉用部などの専門性ある知識を修得し専門の知識を身につけ、それらを実用適用できるよう深く理解している |
| 1級 | 地域社会でコーディネーターとしての能力があり、さらに福祉のまちづくりなどにも助言できる知識と調整力を有している |
2級では職場内で住環境における適切な知識を実務に生かし、1級では職場を飛び越え地域で活動できるようになります。
理学療法士が資格を取得すれば、臨床現場で培った知見を活かした活躍が期待されるでしょう。
スポーツ系資格
スポーツ好きには必見の、スポーツ現場で仕事ができる資格もあります。
- JSPO-AT(日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー)
- JATAC-ATC(ジャパン・アスレティック・トレーナー)
- NESTA-PFT(全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会のパーソナルフィットネストレーナー)
- NSCA-CPT(NSCA認定パーソナルトレーナー)
それぞれ解説します。
JSPO-AT
JSPO-ATは、日本スポーツ協会が定めるアスレティックトレーナーの略称です。
日本スポーツ協会公認の医師やコーチと協力し、以下の4つを目的に活動を実行します。
- スポーツ活動中の外傷・障害予防
- コンディショニングやリコンディショニング
- 安全と健康管理
- 医療資格者へ引き継ぐまでの救急対応
JSPO-ATは、以上の役割を担い、スポーツ中の安全と安心を確保するスポーツ指導者です。
日本スポーツ協会が実施する講習会を受講するなどして、資格を取得できます。
JATAC-ATC
JATAC-ATCは、ジャパン・アスレティック・トレーナーの略称です。
さまざまなスポーツ障害に対し、医療の視点だけではなく柔道整復接骨医学の視点も取り入れ、予防を重視した対応を行っています。
理学療法士が資格取得するには、協会の講習会と通信教育講座の受講が必要です。
NESTA-PFT
NESTA-PFTは、全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会が定めるパーソナルフィットネストレーナーです。
フィットネスジムなどで専属トレーナーとして活動できます。
資格取得には、NESTAが主催する認定試験に合格することが必要です。
受験資格はPFT(パーソナルトレーナー)テキストの購入、定期的なトレーニング、1年以上のパーソナルトレーナーやインストラクターとしての経験など複数あります。
NSCA-CPT
NSCA-CPTは、NSCA(National Strength and Conditioning Association)認定パーソナルトレーナーの略です。
アスリートだけでなく、年齢・性別・経験問わず幅広い層を対象にトレーニング指導を行います。
トレーニングの知識以外にも、医学、運動生理学の専門知識、コンディショニング指導も求められる資格です。
資格を取得するためには、NSCAジャパンの会員となり、認定試験に合格する必要があります。
理学療法士は+αのスキルアップでキャリアアップをめざそう
これまで理学療法士のキャリアアップにつながる資格を9種類紹介しました。
魅力的な資格は見つかったでしょうか。
今回紹介した資格には、取得までの難易度が高い資格も存在しますが、ぜひ挑戦してみてください。
+αのスキルアップで付加価値をつけた希少性の高い人材になれます。
理学療法士の人数は増加傾向にあるなか、専門性を高めることで、、転職市場でも有利に働くでしょう。







