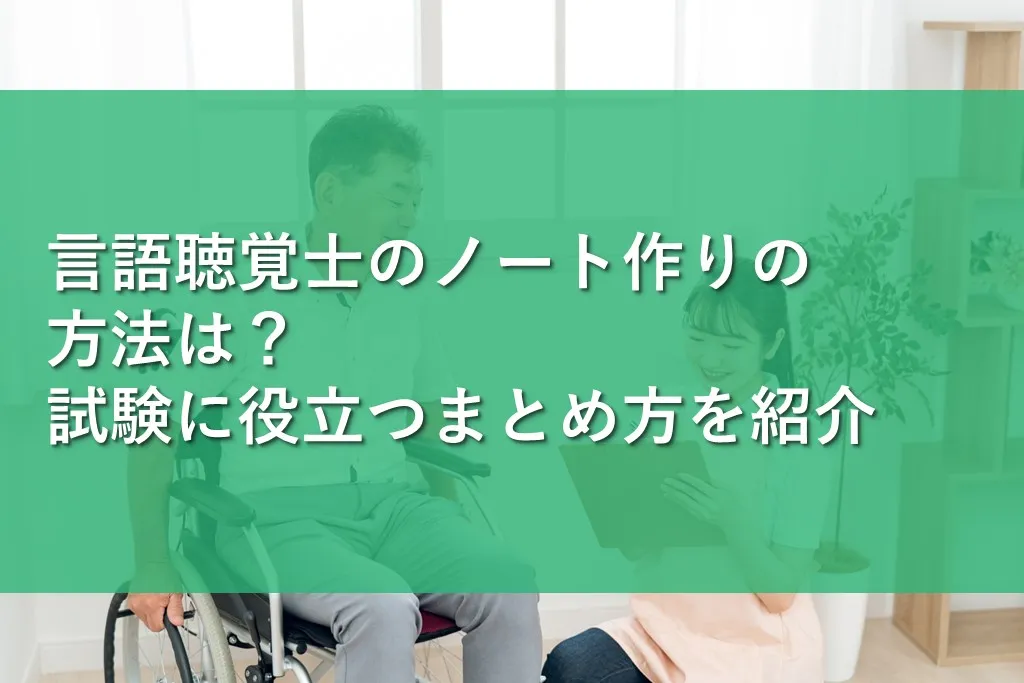
言語聴覚士の国家試験対策において、ノート作りは非常に重要な学習方法の一つです。
講義で学んだ内容を自分なりにまとめることで、知識の定着を図ることができます。
また、ノートを見返すことで、効率的に復習することも可能です。
しかし、ただ闇雲にノートを作るのではなく、戦略的に取り組むことが大切です。
本記事では、言語聴覚士のノート作りとその活用に関する4つのステップを紹介します。
これらのステップを踏まえて、国家試験合格に向けて有効なノート作りを行いましょう。
目次
言語聴覚士のノート作り4ステップ
言語聴覚士の国家試験対策では、ノート作りが欠かせません。
しかし、どのようにノートを作れば良いのか悩む人も多いのではないでしょうか。
ここでは、言語聴覚士のノート作りとその活用に関する4つのステップを、順を追って説明します。
分野ごとにノートをまとめて作成する
言語聴覚士の国家試験対策では、分野ごとにノートをまとめて作成するのがおすすめです。
言語聴覚士の学習範囲は広く、言語系、聴覚系、発声発語・嚥下系、その他の分野に分かれています。
すべての科目で一冊ずつノートを使用するのは効率が悪いので、これらの4つの分野に分けてノートを作成すると良いでしょう。
授業で学んだ内容を、自分なりにまとめてノートに記入していきます。
ノートを作る際は、図や表を活用して視覚的にわかりやすくまとめると、理解が深まります。
また、重要なポイントは色ペンを使って強調するのも効果的です。
ノートをもとに過去問を解く
ノート作成が完了したら、次はそのノートをもとにして過去問を解いていきましょう。
過去問を解くことで、自分の理解度を確認できます。
各分野で何問解けたかによって、分野ごとのノートの出来栄えを評価できます。
もし正答率が低いカテゴリがある場合は、そのカテゴリのノートに追記し、内容をさらに充実させる必要があるでしょう。
過去問を解く際は、単に答えを確認するだけでなく、解説をしっかりと読んで理解を深めることが大切です。
解説を読むことで、ノートに追記すべきポイントが見えてくるでしょう。
ノートの内容を実習に落とし込む
ノートの内容は単に丸暗記するのではなく、実習を通じて知識や経験に落とし込むことが重要です。
学習した内容を実習で向き合う患者さんに照らし合わせて、体験として記憶に定着させていきましょう。
例えば、言語系の分野で学んだ内容は、実際に失語症の患者さんを担当する際に活かすことができます。
患者さんとのコミュニケーションを通じて、失語症についての理解をさらに深めることができるでしょう。
また、患者さんの症状に関する過去問を解くなどして、自分の理解度を確認してみるのも大切です。
実習で得た経験をノートに書き加えることで、より実践的な知識を身につけることができます。
ノートをもとにさらに過去問を解く
実習などが終わり、国家試験が近づいてきたら、さらに過去問を解いていきましょう。
過去問を解くことで、国家試験の出題傾向をつかむことができます。
単に何点取れたかを気にするのではなく、間違えた問題について、なぜ間違えたのかを分析することが大切です。
分析結果をノートに書き込んで、さらにノートの内容をブラッシュアップすることも忘れてはいけません。
自分の弱点を把握し、それを克服するための学習方法を考えましょう。
過去問は、少なくとも5年分は解いておくことをおすすめします。
問題の傾向をつかむことで、本番の国家試験での得点アップにつながるでしょう。
言語聴覚士の勉強はノート作りが大切
言語聴覚士の国家試験対策において、ノート作りは非常に重要な学習方法です。
分野ごとにノートを作成し、過去問を解いて理解度を確認しながら、ノートの内容をブラッシュアップしていきましょう。
また、ノートの内容を実習で活かすことで、知識を体験として定着させることができます。国家試験が近づいてきたら、さらに過去問を解いて弱点を克服し、本番に備えましょう。






