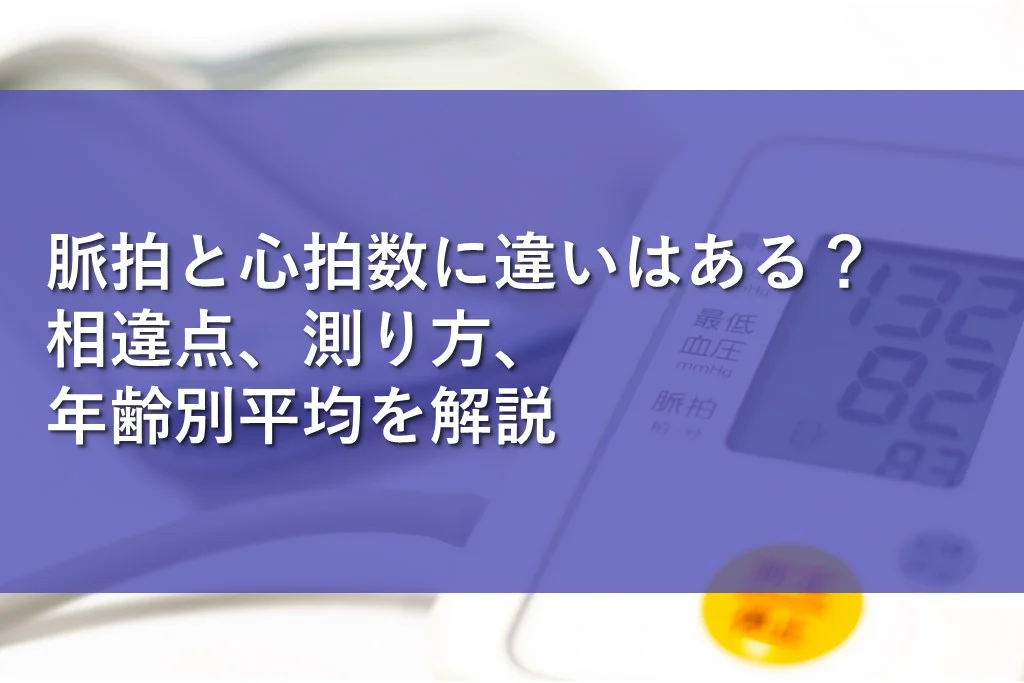
脈拍と心拍数はどちらもよく耳にする言葉ですが、違いがわからない方も多いでしょう。
脈拍は簡単に自分で測定でき、体調を把握するのに有用です。
この記事では、脈拍と心拍数の関係や測り方、平均値や異常になる原因を解説します。
自分の脈拍などを通して体調を把握し、健康管理に活かしましょう。
目次
脈拍と心拍数はどう違う?

脈拍と心拍数は、いずれもよく耳にする言葉です。
では、両者に違いがあるかどうか、あるとすればどのように違うかを知っていますか?
ここでは、脈拍と心拍数の違いや、どのようなときに差が生じるのかを解説します。
脈拍と心拍数の違いを理解して、自分の身体について知識を持ちましょう。
脈拍と心拍数の違い
脈拍は手首の橈骨動脈など、末梢で測定する脈のことです。
一方、心拍数は1分間に心臓が拍動する回数のことです。
心臓が拍動するとポンプのように血液が送られ、動脈に収縮運動が伝わり脈をうつので、通常であれば心拍数と脈拍数は一致します。
ところが、不整脈が発生したときには両者が一致しないことがあります。
不整脈が生じている場合、心臓の拍動が1対1で伝わらず、脈拍としては休んだり、大きく感じたり小さく感じたりするでしょう。
たとえずれがあったとしても、心拍数と脈拍数は連動して動いています。
心臓が拍動しないのに動脈に脈拍が生じることはありません。
脈拍、心拍数の測定法
自分の普段の調子を把握するために、心拍数や脈拍を知ることは有用です。
それぞれどのようにして把握するかを解説します。
脈拍を測るときにはリラックスし、できれば座った姿勢をとります。
利き手でないほうの手首の、固い腱より親指側にドクンドクンと触れるのが動脈です。
利き手の人差し指、中指、薬指の三本で軽く動脈をさわり、拍動の回数を数えます。
1分間測ると正確に数えられます。
心拍数は、先述したように心臓の拍動の回数です。
厳密には胸にセンサーをつけて心電図として記録したり、心臓の音を計測したりしなければ心臓の動きを測ることができないので、特別な機械がないと正確に測ることは難しいでしょう。
簡易的に、連動している脈拍で大まかな心拍数を把握できます。
しかし、心臓の拍動が正確に動脈に伝わらない場合には、脈拍だけでは心臓がどのように拍動しているかがわかりません。
したがって、脈が飛んでいる感じがする場合や、動悸を感じるときには病院を受診して心電図をとらなければ、正確な情報が得られないことがあります。
脈拍や心拍数は、通常1分間あたりの回数で表現します。
脈拍や心拍数を表す単位として医療従事者が用いるのが、bpmという単位です。
beat per minutesの頭文字で、「脈拍80bpm」のように使います。
レートとは?脈拍との違いは?
医療従事者が身近にいる場合や、病院を受診した場合に、「レート」という言葉を聞くことがあるかもしれません。
レートとは拍数の英訳です。
英語で脈拍数は「pulse rate」、心拍数は「heart rate(HR)」と表現されます。
日本の医療現場における「レート」は、どちらの略とも受け取れる通称のような言葉です。
「レートが速い」「レートは正常」などと言われることがありますが、文脈に応じて脈拍か心拍数のどちらのことかを判断する必要があります。
脈拍と心拍数が異なるのはどのようなとき?
脈拍と心拍数が異なるのは、心臓の拍動が1対1で伝わらない、不整脈のときです。
自分で気付くことの多い不整脈で、脈拍と心拍数が異なるものとして挙げられるのが、「心室性期外収縮」と「心房細動」です。
心臓が拍動して血液を送り出すとき、心臓の中にまず血液がたくさん入ってきて、心臓が収縮する力で押し出す運動を繰り返しています。
「心室性期外収縮」は、この規則正しいリズムが崩れ、十分に血液が心臓の中にたまらないうちに心臓の収縮が起こります。
すると、心臓は拍動しているのに血液が少ししか送り出されず、脈拍が触知できなかったり、弱くなったりしてしまうのです。
次の拍動のときには二回分近くの血液が送り出されるために、より強く脈拍を感じることもあります。
「心房細動」では、心臓がリズムを通常どおりとれず、心房という部分がふるえるだけで収縮できなくなってしまいます。
心臓の中の通常と違う部分がリズムをとるため、心臓の収縮のリズムが不規則になってしまったり、血液を送り出す強さがまちまちになってしまい、脈拍が不規則にふれるようになるのです。
脈拍を測ってみたときに数分間不規則なリズムだったとしても、ただちに病気とはなりません。
他に症状がなければ、急いで受診を勧めるものでもないです。
しかし、かかりつけの病院を受診して、一度検査をすることで、どのような不整脈が隠れているのかを診断できるかもしれません。
定期的に自分の脈拍をとることを習慣にすると、健康管理に役立つでしょう。
脈拍と脈波の違いは?

脈拍は末梢動脈を触知して拍動を数えた結果を、通常1分あたりの回数で表現するものです。
これに対して脈波は、自分の指だけでは診察できません。
脈波とは、心臓が血液を送り出すことで生まれる血管の容積変化を波形として表現したもので、これをモニタする検知器が「脈波センサ」です。
脈波は心臓から発生して、動脈を通じて手足など身体の先まで血液を送ります。
脈波センサで得られる波形は、さまざまなモニタや検査に応用されています。
動脈血中酸素飽和度(SpO2)のモニタも、脈波センサを用いた計測機です。
その他、動脈の状態を評価する検査にも使われています。
このように、脈拍と脈波は違うものです。
脈拍と心拍数の正常値は?
ここまで、脈拍と心拍数の意味や測定法について解説しました。
次に、自分の脈拍が正常かどうかを知るため、大まかな正常値を解説します。
ぜひ自分の脈拍と比べて参考にしてください。
【年齢別】脈拍数の正常値
脈拍数の正常値は、年齢によって異なります。
大人と子どもが異なるのはもちろんのこと、成人と高齢者の正常値にも差があります。
その原因の一つは、成人より高齢者のほうが活動量や代謝が低くなるからです。
活動量が低ければ、それほどエネルギーを消費しないため、心臓が身体の隅々まで酸素を送る必要量も少なくなるという機序が考えられています。
また、女性が男性よりわずかに脈拍が高いことが知られています。
以下に年齢別の脈拍数の正常値をまとめました。
| 新生児 | 120~140 |
| 乳児 | 110~130 |
| 幼児 | 100~110 |
| 学童 | 80~90 |
| 成人 | 60~90 |
| 高齢者 | 50~70 |
安静時心拍数
大まかに自分の年齢に応じた脈拍の正常値を把握したら、自分の安静時の脈拍数も知っておくと良いでしょう。
先述のように、脈拍数なら自分の指と時計があれば、移動中や寝る前などどこでも測ることができます。
病気でなくとも、心拍数、ひいては脈拍数が高めの人も低めの人もいます。
そのため、一般的な正常値との比較だけでなく、自分の普段との変化に気付くことが健康管理に役立ちます。
心拍数を調整しているのは、主に自律神経です。
自律神経には交感神経と副交感神経があり、互いにアクセルとブレーキのような関係でバランスを取り合って身体の状態を整えています。
例えば、身体の隅々に血流がいきわたっているか、精神的ストレスを受けているか、血液の酸塩基のバランスはどうかなど、さまざまな因子で交感神経と副交感神経が心拍数を調整します。
運動後や入浴後、感情が高ぶったあとなどは、自律神経の影響で脈拍が速いこともあるでしょう。
安静時の心拍数で比較することが重要です。
脈拍が正常より速い・遅い場合の問題点
脈拍が通常より速いときや遅いとき、ただちに病気となるわけではありません。
さまざまな原因で正常値から離れた値になる場合があります。
どのような場合に、脈拍が正常値より速くなったり遅くなったりするかを解説します。
脈拍が速い
脈拍が速くなる原因はさまざまです。
高血圧や糖尿病、甲状腺機能の異常、心因性、心臓自体に負担がかかっている状態(心不全)でも脈拍が速くなることがあります。
成人で、脈拍が1分間に約100回以上の場合は頻脈です。
そのなかで、リズムが規則的で整っているものを洞性頻脈といい、原因が多岐にわたるため、病気が隠れていないか検査が必要な場合があります。
脈拍が速くなることが多い不整脈には、先述した2つの不整脈、心房細動と期外収縮が含まれます。
心房細動は加齢で増加し、患者さんが増えているといわれている病気です。
また、心臓の病気や脳梗塞の原因になることがあるため、治療が必要になることが多いです。
動悸や疲れやすさがあり、脈拍が高かったりリズムが一定でない場合には心房細動が疑われることもあるので、病院受診を検討しましょう。
期外収縮は、症状や頻度が軽度ならば治療の必要のないこともある病気です。
心配しすぎず、症状が強く気になるときにはかかりつけ医に相談しましょう。
脈拍が遅い
極端に脈拍が遅い場合も問題です。
脈拍が1分間に50回以下の場合は徐脈といいます。
そのなかでも、洞性徐脈とは、リズムが整っていて、心臓の正常な部位から収縮を促す電気信号が発生している徐脈です。
飲んでいる薬の影響や、もともとスポーツを経験していて徐脈傾向にある場合の他、自律神経の調節やホルモンの問題などが原因となります。
気が遠くなったり失神を繰り返したりといった症状がなければ、治療が必要ない場合が多いです。
一方、詳しい検査や治療が必要になる病気もあります。
収縮を促す電気信号が正常に発生しなくなる洞不全症候群や、その先の伝導が障害される房室ブロックなどが徐脈性不整脈の代表です。
めまいや息切れ、失神などの症状があったり、不規則に脈拍が低くなっていることに気付いた場合には、病院を受診したほうが良いでしょう。
脈拍と心拍数の違いを理解して、健康増進に努めよう
脈拍と心拍数は、不整脈などのときを除いておおむね一致し、脈拍の測定は体調をおおまかに把握できるというメリットがあります。
不整脈にもさまざまな種類があり、心配ないものから病院を受診する必要があるものまで多様です。
自分の脈拍がどのくらいかを知り、体調管理することで健康の増進に役立てましょう。






