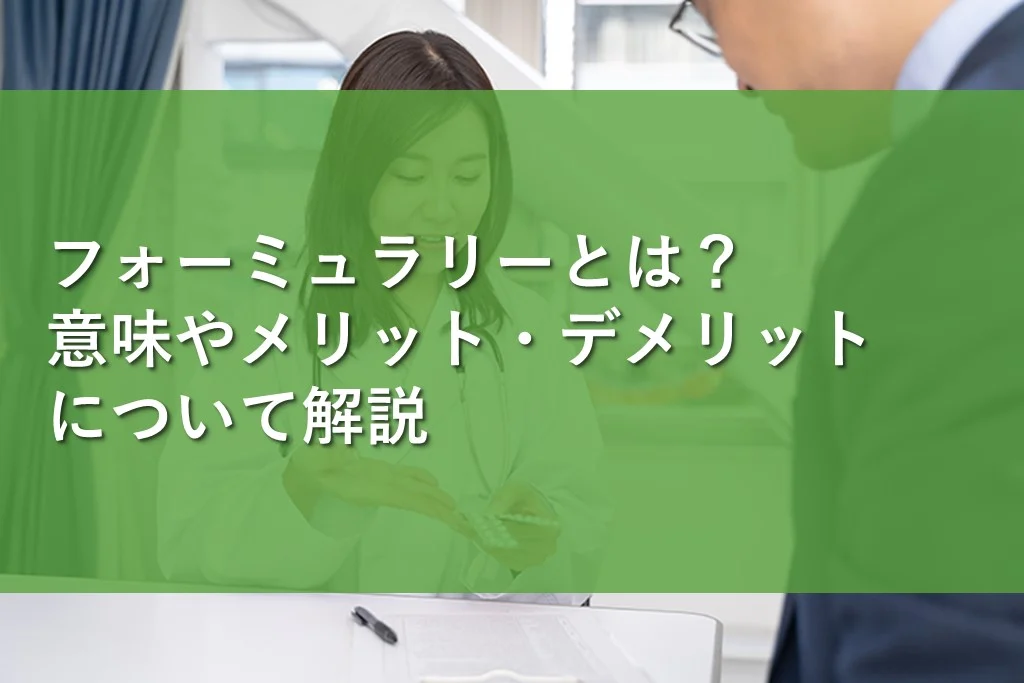
フォーミュラリーとは、医療機関や地域における医薬品の使用方針を示したものです。
院内フォーミュラリー・地域フォーミュラリーの大きく2種類に分けられ、医師や薬剤師が中心となって作成します。
フォーミュラリーの導入には、医療費削減をはじめとしたさまざまなメリットがありますが、作成のための手間がかかる点も念頭に置いておきましょう。
本記事では、フォーミュラリーの意味やメリット・デメリットを解説します。
フォーミュラリーの活用をご検討中の方は参考にしてみてください。
目次
フォーミュラリーとは?

フォーミュラリーとは、医薬品の処方(使用)をより効率的かつ経済的に導くための指針のようなものです。
医薬品の安全性や有効性、経済性の最適化に向け、医師・薬剤師が中心となって策定します。
英国では1980年頃から実用的なフォーミュラリーが活用され、欧米にも広がっていますが、日本で注目が高まったのは2021年頃です。
「経済財政運営と改革の基本方針2021」が策定されたことで、フォーミュラリーの運用方法や基本となる考え方が、国内でも知られることとなりました。
フォーミュラリーの種類
フォーミュラリーの種類は、病院や診療所単位で作成される院内フォーミュラリーと、地域単位で作成される地域フォーミュラリーの大きく2つです。
それぞれ、作成に関わる人や地域医療経済に与える影響の大きさが異なります。
院内フォーミュラリー
院内フォーミュラリーは、特定の医療機関内での医薬品の使用指針を示したものです。
作成した病院や診療所のなかでのみ効力を持つ指針であり、地域全体への影響力は少ないという特徴があります。
地域フォーミュラリーと比べると、運用のハードルもそこまで高くありません。
作成のための話し合いには、医師と薬剤師、理事長、オーナーなどが出席します。
地域フォーミュラリー
地域フォーミュラリーは、地域全体への影響を考慮した医薬品の使用指針です。
特定の医療機関だけでなく、その地域にあるさまざまな病院や診療所で活用されることから、影響度は院内フォーミュラリーと比較して大きくなります。
話し合いの席には、医師や薬剤師だけでなく地域の医師会・薬剤師会の関係者も出席するため、内容の決定が難しくなりやすい傾向にあります。
フォーミュラリーを導入するメリット
フォーミュラリーの導入には、次のようなメリットがあります。
- 専門外の医師が医薬品を選定する際の参考になる
- 患者さんが安心して病院に通える
- 医療費削減につながる
フォーミュラリーには経済的なメリットだけでなく、治療が標準化されることで医師が医薬品を選びやすくなる利点もあります。
また、患者さんの安心感にも寄与するでしょう。
専門外の医師が医薬品を選定する際の参考になる
フォーミュラリーによって医薬品の使用指針が定められると、医師は患者さんに処方すべき医薬品の選定に迷うことがなくなります。
ときとして医師は、専門外の疾患で来院した患者さんに対応しなければならないケースもあるでしょう。
その際、フォーミュラリーがあれば、病院や地域で決められた指針に則った医薬品をスムーズに処方できます。
選定時間が短縮されれば、業務効率の向上も可能です。
患者さんが安心して病院に通える
地域フォーミュラリーが導入されている地域では、どの病院に行っても同じ薬を処方してもらえるため、患者さんは安心して通院できます。
同じ疾患でも病院ごとに処方される薬が異なる場合、患者さんの不安や混乱を招くだけでなく、調剤薬局での取り違えといったトラブルを引き起こしかねません。
フォーミュラリーは、医薬品を安全に扱うためにも重要です。
医療費削減につながる
慢性疾患で長期間処方が多い医薬品や地域で使用頻度の高い領域の医薬品に対してフォーミュラリーを利用します。
すると、より価格の低い後発医薬品を第一選択薬とすることで、結果として医療費の削減につながります。
患者さんが安く医薬品を手に入れられるだけでなく、地域にとっても中長期的な目線で医療費の削減をめざすことが可能です。
先発薬と後発薬の価格差が大きいほど、経済的な面でのメリットは大きくなるでしょう。
フォーミュラリーを導入するデメリット
フォーミュラリーの導入には、メリットだけでなく次のようなデメリットもあります。
- 地域フォーミュラリーは影響の範囲が大きく、より慎重に運用する必要がある
- 実施にあたっては医師や薬剤師、医師会・薬剤師会の関係者などが話し合いに参加するため、作成に手間と時間がかかる
- 地域フォーミュラリーを実施する場合、自院の治療方針に沿った処方がしにくくなる可能性がある
- フォーミュラリーで指針を出した医薬品の供給が止まった場合、早急に代替薬を選定しなければならない
フォーミュラリーで決定された医薬品が適さない患者さんの場合、必ずしもフォーミュラリーに沿った内容で処方(使用)する必要はありません。
厚生労働省は、医学・薬学的な視点でより適した医薬品があると考えられるケースでは、別の医薬品を使用しても良いとしています。
上記のデメリットをふまえたうえで、フォーミュラリーのスムーズな運用のためには、他職種の連携が必要不可欠です。
話し合いの機会を利用して医師や薬剤師のあいだで密な情報共有を行い、地域一体となった組織体制を整えることで、フォーミュラリーを適切に管理できます。
フォーミュラリーの導入方法
フォーミュラリーの導入は、大まかに以下のような流れで進めます。
- 院内周知
- 薬剤選定
- 医師や薬剤師、薬事委員などと検討
- 薬事委員会での審議
- 医師への周知
まずは、フォーミュラリー作成に関係する医療機関に周知し、医師や薬剤師で医薬品を選定しましょう。
薬事委員会などフォーミュラリー作成に関する委員会などで、承認が得られるまで審議を重ねます。
最終承認に至ったら、再度関係する医療機関に周知するという流れです。
フォーミュラリーを取り入れ医薬品の適正使用に努めよう
フォーミュラリーは、医薬品にかかる費用を最適化しながら、より効率的に使用するための指針です。
院内フォーミュラリー・地域フォーミュラリーの大きく2つに分けられ、医師や薬剤師が中心となって話し合いを行い、作成を進めます。
フォーミュラリー運用のメリットには、医師が医薬品を処方する際の参考になるほか、患者さんが安心して通院できる点、医療費削減に貢献する点などが挙げられます。
一方、作成のために手間がかかるというデメリットもあり、他職種との連携や組織体制の整備は欠かせません。
医薬品の効率的で経済的な使用のために、各医療機関や地域に合わせたフォーミュラリーを検討してみてはいかがでしょうか。







