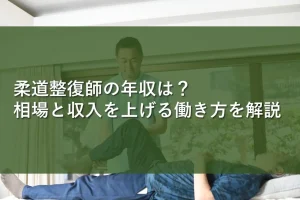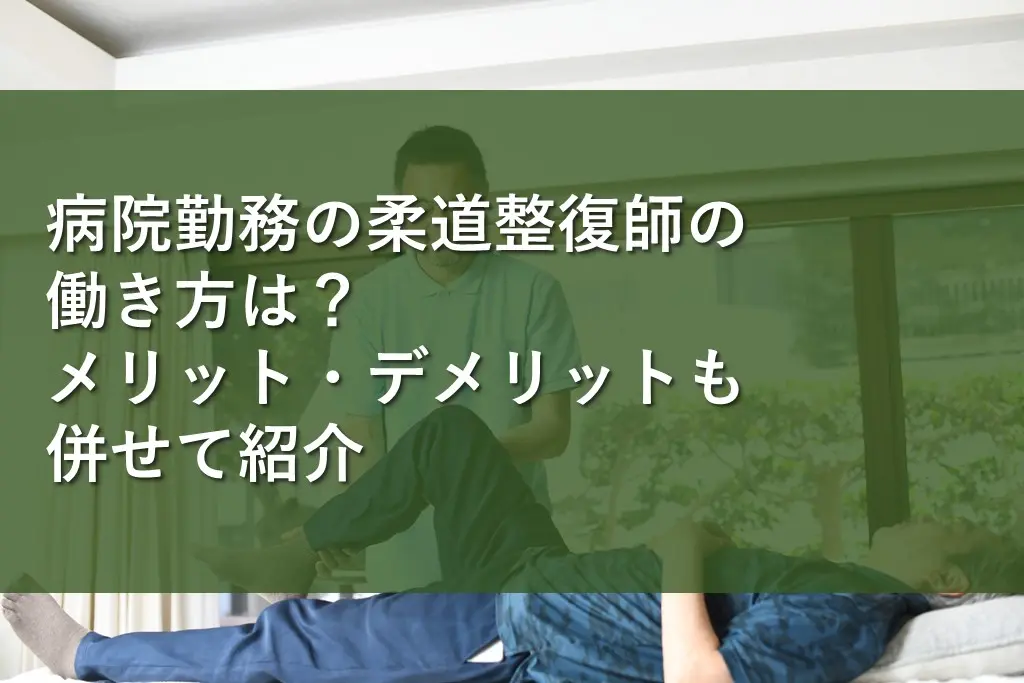
柔道整復師は、骨折や脱臼、捻挫などの外傷の手当を行う専門職として知られています。
多くの人は柔道整復師が接骨院や整骨院で働いているイメージを持っていますが、実は病院勤務の柔道整復師も増えてきています。
今回は、病院勤務の柔道整復師の働き方や、メリット・デメリットについて詳しく解説していきましょう。
目次
柔道整復師は病院勤務が可能?

柔道整復師は、接骨院や整骨院だけでなく、病院やクリニックにも活躍の場があります。
病院で働く場合は、主に整形外科やリハビリテーション科に所属し、外傷の処置やリハビリテーションが担当です。
柔道整復師の専門知識と技術は、病院での治療やリハビリテーションにも大いに役立ちます。
特に、骨折や脱臼、打撲などの外傷の処置には、柔道整復師の専門性が発揮されます。
柔道整復師が働ける場所(病院勤務編)
病院での柔道整復師の活躍の場は多岐にわたります。
ここでは、代表的な診療科や部門について紹介していきましょう。
整形外科
整形外科は、柔道整復師の専門性を活かせる診療科の一つです。
特に、骨折や脱臼、打撲の患者さんが多い病院では、柔道整復師の技術と知識が大いに役立ちます。
整形外科での柔道整復師の業務は多岐にわたります。
リハビリテーションはもちろん、骨折や脱臼、打撲などに対するギプスの作成・装着、テーピングなどもその一つです。
リハビリテーション科
リハビリテーション科は、怪我や病気の後遺症に対するリハビリテーションを行う部門です。
柔道整復師は、物理療法、手技療法、運動療法などを用いたリハビリテーションを実施できるため、リハビリテーション科での活躍も期待されます。
リハビリテーション科での柔道整復師の役割は、患者さんの日常動作の援助から、運動機能の維持・回復まで多岐にわたります。
最終的には、患者さんが日常生活へと無理なく復帰できるよう、サポートすることが目的です。
スポーツ整形外科
スポーツ整形外科は、サッカーや野球、バスケットボールなどのスポーツにともなって発症する障害やケガを専門に扱う診療科です。
柔道整復師は、スポーツ障害の予防とリハビリテーションの両面で活躍が期待されます。
スポーツ整形外科での柔道整復師の役割は、運動学と医学の両面から、選手が身体に負担をかけずにスポーツに復帰できたり、パフォーマンスを向上できたりするようサポートすることです。
的確なアドバイスと適切なリハビリテーションプログラムの提供が求められます。
柔道整復師が働ける場所(病院勤務以外)
柔道整復師の活躍の場は、病院だけにとどまりません。
ここでは、病院以外で柔道整復師が働ける代表的な場所を紹介します。
整骨院・接骨院
整骨院や接骨院は、柔道整復師の代表的な働き口です。
ここでは、整復、固定、運動療法などの技術を駆使して、骨折、脱臼、打撲、捻挫などの応急処置や治癒力を高めるための施術を行います。
近年は、施術だけでなくもみほぐしなどのサービスを提供する整骨院・接骨院もあります。
また、保険を使わない自由診療を導入することで、1回の施術に十分な時間をかけ、短期間で確実な施術効果を上げることをめざす施設も増加傾向です。
スポーツ現場
柔道整復師は、スポーツ現場でもその専門性を発揮可能です。
具体的には、スポーツトレーナーとしての活躍や、スポーツジムやフィットネスジムでの勤務などが挙げられます。
特にスポーツトレーナーは、プロのアスリートや実業団の選手を対象に、トレーニング指導、メンテナンス、健康管理などの役割を担います。
選手のコンディションを最適に保ち、ベストパフォーマンスを引き出すことが求められる重要な仕事です。
介護施設
介護施設も、柔道整復師の活躍が期待される場所の一つです。
高齢者施設やデイサービスなどで、機能訓練指導員として働くことができます。
介護施設での柔道整復師の主な役割は、要介護者に対する筋力低下予防のためのリハビリテーション、マッサージ、歩行訓練などです。
必要に応じて、自主トレーニングの指導や援助も行います。
高齢者の QOL(生活の質)の維持・向上に貢献することが期待されます。
開業
柔道整復師は、医師などと同様に、独立して開業することもできます。
開業には、施設管理者としての要件を満たす必要がありますが、自分のペースで仕事ができるのが大きな魅力です。
ただし、開業には事業計画の作成、店舗の内装や備品の管理、保険の取り扱いなど、柔道整復師としての業務以外の仕事も増えます。
独立開業には、専門知識とビジネススキルの両方が求められるといえるでしょう。
教員
一定のキャリアを積んだあと、柔道整復師専科の教員をめざすことも可能です。
後進の育成に携わることで、柔道整復師業界の発展に貢献できます。
病院勤務の柔道整復師の1日の流れ
病院勤務の柔道整復師の1日は、おおむね以下のような流れになります。
| 時間 | 仕事内容 |
| 8:30~ | 出勤。カルテを確認し情報収集をしたり医師や理学療法士など他のスタッフと情報共有を行う。 |
| 9:00~ | 診療開始 ・医師の指示のもと実際に患者さんに処置やリハビリテーションを提供する |
| 12:00〜 | 午前の受付終了、休憩 勉強会や新人の指導、施術の練習などもこの時間を利用して行う |
| 15:00〜 | 午後の診療開始 午前と同様、医師の支持のもと患者さんの処置やリハビリテーションを提供する |
| 19:00〜 | 診療終了 カルテの記入や雑務を行い退勤 |
1日の業務は、患者さんの状態に合わせた処置やリハビリテーションが中心です。
他の医療スタッフとの連携も重要で、カンファレンスなどを通じて情報共有と意見交換を行います。
柔道整復師には、医学的な知識だけでなく、コミュニケーション能力も求められます。
患者さんの訴えを的確に把握し、適切な処置やアドバイスを行うことが必要不可欠だからです。
柔道整復師が病院で働くメリット

病院勤務には、柔道整復師にとって大きなメリットがあります。
ここでは、その代表的なものを紹介していきましょう。
安定した収入と福利厚生
病院勤務の柔道整復師の給与は、整骨院や接骨院勤務の場合とそれほど差はありません。
ただ、病院では勤怠管理システムがしっかりしていることが多く、賞与や昇給、有給休暇などの福利厚生が充実しています。
安定した収入と手厚い福利厚生は、長く働き続けるためには欠かせない要素です。
より詳しい給与については、以下のリンクを参照してください。
幅広い症例を経験できる
病院には、介護状態の患者さんや、外傷、重度の障害を抱えた患者さんなど、さまざまな症例の患者さんが来院します。
これは、柔道整復師にとって非常に貴重な経験となります。
幅広い症例を経験することは、柔道整復師としてのスキルアップには欠かせません。
特に、将来の独立開業を考えている人や、さらなる成長をめざしている人にとっては、病院勤務はおすすめです。
院内研修や講習に参加することができる
多くの病院では、定期的に院内研修や講習会が開催されています。
これらに参加することで、柔道整復師は最新の医療知識や技術を学ぶことが可能です。
また、院内研修では、さまざまな職種のスタッフが集まり、多角的な視点からの意見交換が行われます。
このような機会は、外部の研修では得難い貴重な学びの場となるでしょう。
チーム医療の一員として活躍できる
病院では、医師、看護師、薬剤師、理学療法士など、多職種が連携してチーム医療を行っています。
柔道整復師もこのチームの一員として、患者さんの治療に携わることができます。
チーム医療に参加することで、柔道整復師は医療に関する知識と技術を深めることが可能です。
また、他職種との連携を通じて、コミュニケーション能力も磨かれます。
これらは、柔道整復師としてのキャリアアップに大いに役立つはずです。
プライベートと仕事を分けやすい
病院勤務の柔道整復師は、基本的にシフト制で働きます。
そのため、急な出勤や休日出勤を求められることは少ないでしょう。
また、看護師のような夜勤もありません。
このような勤務体制は、プライベートと仕事のバランスを取りやすいというメリットがあります。
家庭との両立を考えている人や、趣味の時間を大切にしたい人にとっては、病院勤務は魅力的な選択肢といえます。
柔道整復師が病院で働くうえで大変なこと
柔道整復師にとって病院勤務には、大変だと感じることもいくつかあります。
ここでは、その代表的なものを紹介していきましょう。
スキルの向上が必要
病院勤務に限らず、柔道整復師には解剖学や生理学の深い理解が求められます。
病院勤務の場合、これに加えてリハビリテーションの方法や処置の技術など、より高度な知識と技術が必要とされます。
つまり、病院勤務の柔道整復師には、常にスキルアップが求められるのです。
自己研鑽を怠ると、患者さんに十分な施術を提供できなくなるおそれがあります。
コミュニケーション能力が必要
病院には、患者さんだけでなく、医師や看護師など多職種のスタッフがいます。
柔道整復師には、これらのスタッフとのコミュニケーションが欠かせません。
また、患者さんに対しても、的確なコミュニケーションが求められます。
「肩が痛い」などの曖昧な訴えから、具体的な症状や痛みの状況を聞き出す能力が必要とされるのです。
体力が必要
先にも述べたように、病院には幅広い症例の患者さんが来院します。
そのなかには、重症の患者さんも少なくありません。
このような患者さんの施術には、柔道整復師の体力も求められます。
具体的には、強い力を要する処置や、長時間の立ち仕事などが挙げられます。
体力がないと、患者さんに適切な施術を提供することが難しくなるでしょう。
就職のための競争率が高い
近年、柔道整復師の数は増加傾向にあります。
令和4年時点で78,827人で、令和2年から3,041人増えています。
この傾向は今後も続くでしょう。
柔道整復師の増加は、病院への就職競争の激化を意味します。
病院勤務を希望しても、なかなか就職できないというケースも出てくるかもしれません。
ただし、どのような場所でどのような働き方をしたいのか、明確なビジョンを持っていれば、道は開けるはずです。
柔道整復師は成長できる病院勤務がおすすめ
柔道整復師にとって、病院勤務は大きな成長の機会です。
整形外科やリハビリテーション科など、さまざまな診療科で専門性を発揮できるチャンスがあります。
また、スポーツ整形外科では、選手の復帰をサポートする重要な役割を担うことができます。
病院勤務の大きなメリットは、幅広い症例を経験できることです。
これは、将来の独立開業や、さらなるスキルアップをめざす人にとって、非常に貴重な経験となります。
加えて、院内研修や多職種との連携を通じて、医療知識とコミュニケーション能力を磨くこともできるでしょう。
一方で、病院勤務にはデメリットもあります。
高度な知識と技術が求められるため、常にスキルアップが必要です。
また、コミュニケーション能力や体力も求められます。
就職競争も激化しているため、明確なビジョンを持つことが重要です。
それでも、柔道整復師としてのキャリアアップをめざすなら、病院勤務は非常におすすめです。
多くの学びの機会があり、チーム医療の一員として活躍できる病院勤務。
それは、柔道整復師にとって大きな成長の場となるはずです。