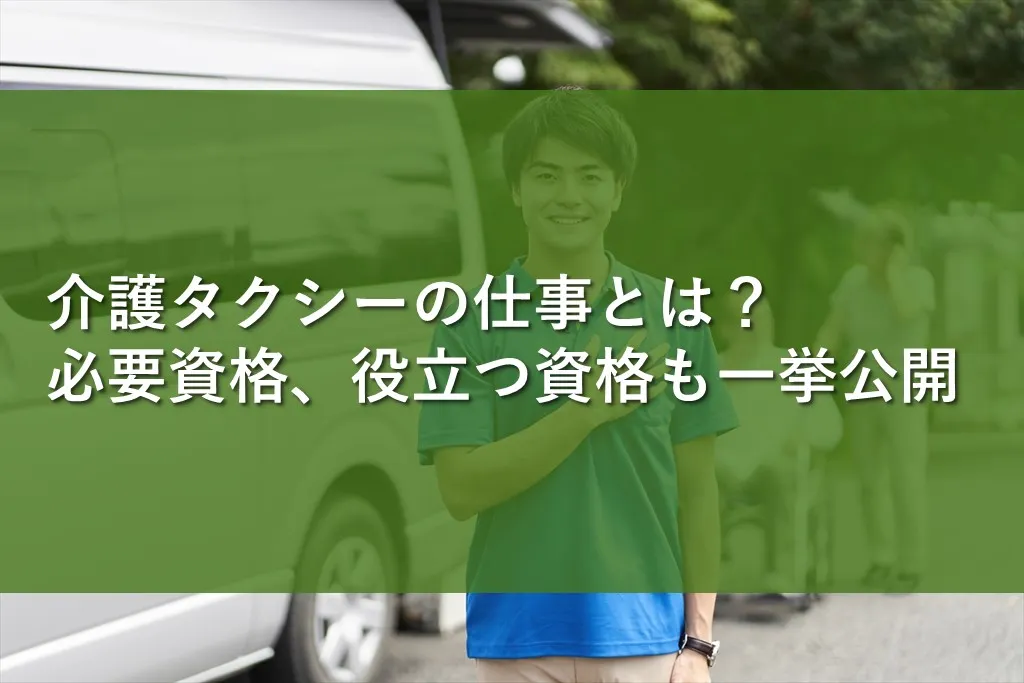
介護タクシーとは、介護を必要とする高齢者や障がい者が目的地に移動する際に利用するタクシーのことです。
タクシー運転手として働いている人や介護系の仕事をしたい人のなかには、近年見かけることが多くなった介護タクシーに興味がある人もいるでしょう。
この記事では、介護タクシーの仕事内容や必要な資格、役立つ資格、働き方などを紹介します。
また、介護タクシーと福祉タクシーの違いも解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
介護タクシーとは

ここではまず、介護タクシーの仕事内容を解説し、介護タクシーと福祉タクシーの違いを紹介します。
介護タクシーの仕事内容
介護タクシーの仕事は、介護を必要とする人が車椅子やストレッチャーで乗車できる特別仕様の自動車を使い、乗降介助を行いながらタクシーサービスを提供することです。
会社に勤める以外にも、個人事業主や法人として開業も可能です。
では、会社に勤める介護タクシー運転手の仕事の流れがどのようなものなのか、例を見ていきましょう。
- 出社して朝礼や業務の確認を行う
- 予約済みの利用者宅を訪問し、タクシーに乗せて目的地に移動する
- 利用者の予定が済み次第、利用者宅へ送り、事務所に戻る
- 予約業務の終了後、報告書の作成や事務処理を行う
置かれた立場によっても仕事内容は異なりますが、基本的には介護が必要な高齢者や障がい者を乗車させ、目的地へと送り届けます。
要望があれば、介護タクシーにご家族を同乗させることも可能です。
介護タクシーと福祉タクシーの違い
介護タクシーには、介護保険適用の介護保険タクシーと、介護保険が使えず全額自己負担になる介護タクシーの2種類があります。
介護保険タクシーを利用するには利用条件を満たす必要があり、運転手として就業するには特定の資格が必要です。
しかし、介護保険が使えない介護タクシーには、利用者や目的の制限がありません。
福祉タクシーも身障者の外出支援を目的としていますが、介護保険は利用できません。
ただし、身体障害者手帳を持っていて車椅子を常用している人などには、自治体による一部負担金の制度が利用できる場合もあります。
介護タクシーに必要な資格
介護保険が使える介護タクシーの運転手になるには、普通自動車二種免許と特定の介護関連資格が必要です。
以下で詳しく見ていきましょう。
普通自動車二種免許
介護保険適用の介護タクシーを運転するには、普通自動車一種免許ではなく、普通自動車二種免許が必須になります。
普通自動車二種免許とは、旅客を運送する目的で運転する場合に必要な免許です。
介護タクシーに限らず、普通のタクシーや運転代行などでも、二種免許は必要になります。
二種免許を取得するには、以下の2つの条件があります。
- 満21歳以上
- 普通免許などの保持期間が3年以上
特定の介護関連資格
普通自動車二種免許だけでは、乗車中の利用者への介助や乗降介助を行えません。
そのため、介護タクシーの運転手は、介護職員初任者研修(旧ホームペルパー2級)などの介護関連資格を取得する必要があります。
介護職員初任者研修は130時間の研修を受け、筆記試験に合格することで取得できる資格です。
介護タクシーで役立つ資格

介護タクシーの運転手として働くためには、普通自動車二種免許と特定の介護関連資格が必要ですが、その他にも役立つ資格があります。
ここでは、介護タクシーの運転手に役立つ資格として、以下を紹介します。
- 普通救命講習
- サービス介助士
- ユニバーサルドライバー研修
- ハートフルアドバイザー研修
普通救命講習
普通救命講習とは、各地の消防本部が行う応急処置技能講習です。
総務省による応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱をもとに、救命に関わる正しい知識と技術の普及を目的として作られました。
介護タクシーの利用者は身体の不自由な人が多く、その人たちが体調を崩したときに正しい知識と技能があれば、落ち着いた対応ができるでしょう。
また、緊急時の応対処置の知識があることは、利用者にとっても安心材料の一つになります。
サービス介助士
サービス介助士は、公益財団法人 日本ケアフィット共育機構が認定する資格です。
高齢者や障がい者をサポートする心と介助技術のスキルを習得することで得られる資格であり、ケアをフィットする人を指すためケアフィッターと呼ばれることもあります。
要介護者が求める介助は状況によって変わるため、正しい理解と支援が必要です。
介護タクシーでも同じことがいえるため、相手のニーズを読み取って満足度の高いケアを与えられる、サービス介助士の資格が役立ちます。
ユニバーサルドライバー研修
ユニバーサルドライバー研修とは、バリアフリー研修推進実行委員会が開発・推進している資格です。
研修期間は1日(7時間)で、内容は講義や映像、討論、実践などに分かれています。
車椅子の取り扱いや乗降介助、利用者とのコミュニケーションなどについても学びます。
短期間で取得できる手軽さが魅力です。
ハートフルアドバイザー研修
ハートフルアドバイザー研修は、公益財団法人 総合健康推進財団が運営しています。
接客業に従事する人が、高齢者や障がい者に適切なサービスを提供するための知識や技術を習得するために作られました。
介護タクシーというと介護に特化しているイメージを持つかもしれませんが、介護面以外での利用者とのやりとりも重要です。
適切なサービスで満足してもらうためにも、ハートフルアドバイザー研修は役立つ資格だといえるでしょう。
介護タクシー運転手としての働き方
介護タクシー運転手としての働き方には、就職する方法と、開業して自営業者として働く方法があります。
就職
タクシー会社に就職して勤務する場合は、一般のタクシーと介護タクシーの運転を並行して担当することが多い傾向です。
介護タクシーの予約があるときのみ、介護タクシー運転手として働き、それ以外の時間は一般のタクシー運転手として働きます。
自営(開業)
介護タクシー運転手は、開業して自営業者として働くことが可能です。
開業方法には、個人事業主や法人があります。
介護タクシー業で開業するには、一般常用旅客自動車運送事業の開業認可を受けなければなりません。
基本的な流れは以下のとおりです。
- 車両や事務所、開業資金を用意する
- 運輸支局へ事業登録申請を行う
- 審査後、地方運輸局で法令試験と事情聴取を受ける
- 事業認可後、車両の検査・登録、緑ナンバーへの変更を行う
また、認可を受けてから6ヵ月以内に開業する必要があります。
開業後に経営を安定させるためには、病院や医療機関、行政と提携し、事業者間で連携していくことが大切です。
資格を取って介護タクシーの運転手をめざそう
介護保険を利用する介護タクシーは、要介護1以上の人が受けられるサービスです。
そのため、普通自動車二種免許に加えて、介護関連の資格を取得しておく必要があります。
介護タクシーは値段が高い傾向にありますが、介護保険適用の場合、利用者は1割負担で利用できます。
また、最近では一般料金を支払ってでも介護タクシーを利用したいという人も増えており、今後も需要が見込まれる分野です。
ぜひ必要な資格を取って、介護タクシーの運転手をめざしてみましょう。






