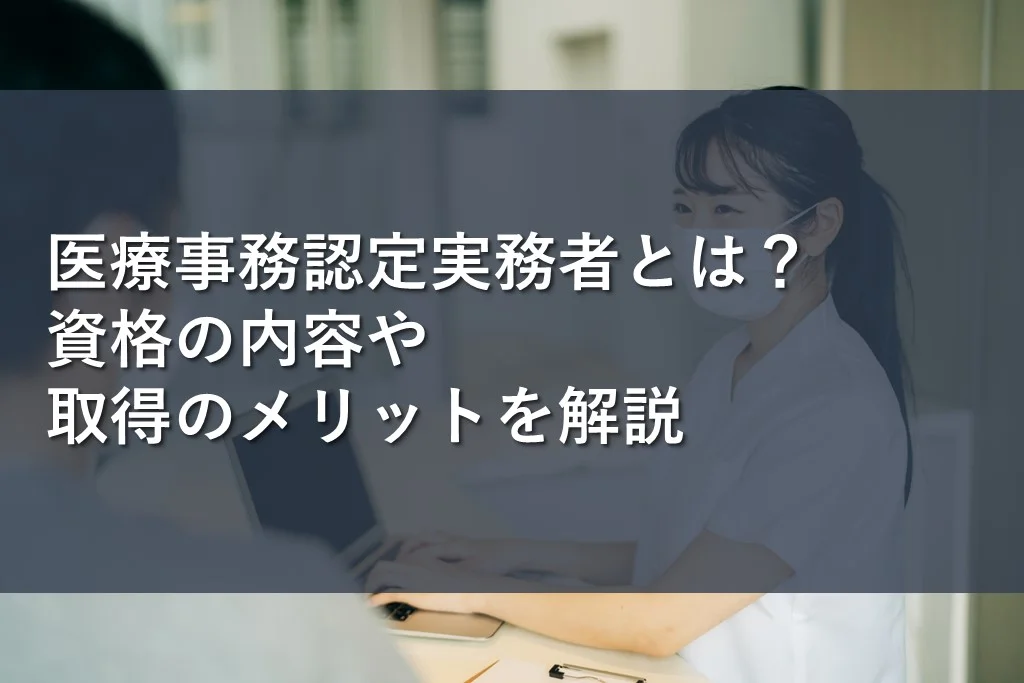
医療事務認定実務者は、医療事務の基礎知識やレセプト作成能力を証明する民間資格です。
取得することで職場での信頼を得られるほか、転職や就職、昇進などにおいて有利になる可能性もあります。
医療事務としてのスキルアップやキャリアアップをめざすのなら、取得する価値のある資格の一つでしょう。
本記事では、医療事務認定実務者の試験概要や取得のメリット、勉強方法などを詳しく解説します。
目次
医療事務認定実務者とは

医療事務認定実務者は、医療事務の基礎知識とレセプト作成のスキルを認定する資格です。
全国医療福祉教育協会により、2016年に創設されました。
受験資格の定めはなく、誰でも受験できます。
試験は学科と実技で構成され、回答はすべてマークシート方式です。
在宅での受験も可能で、参考書やノートの持ち込みもできます。
初めて医療事務にチャレンジする方や、医療事務への転職や就職を検討している方に最適な資格といえるでしょう。
医療事務認定実務者試験について
続いて、医療事務認定実務者の試験概要や、申し込み方法などについて詳しく見ていきましょう。
試験概要
医療事務認定実務者の試験の概要は、次のとおりです。
| 受験資格 | なし |
| 実施日程 | 年12回(1ヵ月に1回) |
| 受験料 | 一般受験:5,000円(税込) 団体受験:4,500円(税込) |
| 申し込み方法 | インターネット・郵送 |
| 受験方法 | 一般受験:自宅受験 団体受験:会場受験 (認定機関の通信・通学講座を受講した方) |
| 回答方法 | マークシート |
| 試験内容 | 学科:30問 実技:外来1症例 |
| 試験時間 | 90分 |
| 出題範囲 | 【学科試験】 ・接遇・マナーの知識 ・医療機関での各種制度に関わる知識 ・医療事務の業務についての知識 ・診療報酬請求に関わる知識 【実技試験】 レセプトの作成 |
| 合格率 | 約60~80% |
| 合格基準 | 学科・実技それぞれ6割以上の正答が必要 (ただし、問題の難易度によっては変動あり) |
| 主催団体 | 全国医療福祉教育協会 |
在宅受験と会場受験の申し込み方法
医療事務認定実務者試験の受験方法は、在宅受験と会場受験の2種類があります。
在宅受験は一般の受験生や、認定機関の講座を通信課程で受講している方が対象です。
一方、会場受験は講座を通学で受講している方が対象となります。
それぞれの申し込み方法は、次のとおりです。
【在宅受験の申し込み方法】
- インターネットまたは郵送で受験を申し込む
- 指定口座へ受験料を振り込む
- 試験の約1週間前に受験票が到着する
- 試験日の前々日までに、問題用紙・解答用紙が郵送される
【会場受験の申し込み方法】
- 通信講座受講生:教材に同封されている受験申込書にしたがって申し込む
- 通学講座受講生:スクールの案内に沿って申し込む
医療事務認定実務者を取得するメリット
医療事務認定実務者の資格を取得すると、以下のようなメリットがあります。
- スキルや知識の証明ができる
- 転職や就職の際に有利になる
- 仕事に必要な知識が身につく
医療事務認定実務者の資格を取得すると、医療事務の基本的な知識や、レセプト作成の能力を客観的に証明できます。
そのため、即戦力とみなされ、昇進や転職においても有利に働くでしょう。
また、仕事に役立つ知識を身につけると、自信をもって取り組めるようになり、モチベーション向上にもつながるでしょう。
医療事務認定実務者試験の勉強方法
医療事務認定実務者試験の勉強法には、次の3つがあります。
- 通信講座で学ぶ
- 独学で勉強する
- 通学講座に通う
自分に最適な学習スタイルを見つけましょう。
通信講座で学ぶ
通信講座を受講すれば、自分のライフスタイルに合わせて学習を進められます。
資格取得までの期間は約3〜4ヵ月で、受講費用は4〜5万円ほどが一般的です。
仕事や子育ての合間にも勉強できるため、自分のペースで無理なく資格取得をめざせます。
専用のテキストや添削指導により、不明点を解消しながら合格に向けて着実にステップアップできるでしょう。
ただし、独学よりも費用がかかり、講師が目の前にいる通学講座と比べると疑問点の解消に時間がかかります。
独学で勉強する
市販のテキストを入手して、独学で勉強する方法もあります。
独学のメリットは、費用を抑えながら、自分のペースで学習できる点です。
しかし、丁寧に教えてくれる講師も、ともに試験合格をめざす仲間もいないため、疑問の解決やモチベーションの維持に苦労する場合もあります。
自分でしっかり計画を立て、コツコツと学習を進めるのが得意な人に向いているでしょう。
独学で学習を進める場合は、自分に合ったテキストを見つけて読み込み、繰り返し問題を解いて苦手を克服することが重要です。
全国医療福祉教育協会のサイトには問題例が掲載されているので、参考にすると良いでしょう。
通学講座に通う
スクールや認定機関で開催されている通学講座に通うことも、選択肢の一つです。
通学講座のメリットとしては、講師に直接質問できるため疑問をすぐに解決できることや、ともに資格取得をめざす仲間がいるのでモチベーションを維持しやすいことなどが挙げられます。
ただし独学に比べて費用がかかる点や、通学の必要があるため時間の融通が効きにくい点などはデメリットといえるでしょう。
そのため、時間や費用に余裕がある人に適しています。
講座の割引キャンペーンや教育訓練給付金を利用して費用を抑える方法もあるので、事前に情報収集しておきましょう。
医療事務認定実務者に関するよくある質問・回答
ここからは、医療事務認定実務者に関する、よくある質問と、その回答を紹介していきます。
医療事務認定実務者とメディカルクラークの違いは?
代表的な医療事務の資格としては、医療事務認定実務者の他にメディカルクラークがあります。
下表は、医療事務認定実務者とメディカルクラークの違いをまとめたものです。
| 医療事務認定実務者 | メディカルクラーク | |
| 主催団体 | 全国医療福祉教育協会 | 一般財団法人日本医療教育財団 |
| 開設時期 | 2016年 | 1974年 |
| 合格率 | 約60~80% | 約50~60% |
| 出題形式 | 全問マークシート形式 | 実技I/記述式(2問) 学科/択一式(25問) 実技II/実技(4問) |
| 受験方法 | 在宅試験・会場試験 | 在宅試験 |
| 受験料 | 5,000円(税込) | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 学科・実技それぞれ 6割以上の正答 |
学科・実技Ⅰ・実技Ⅱともに 7割以上の正答 |
医療事務認定実務者の試験は全問マークシート方式で、合格率が60〜80%と比較的高めです。
一方メディカルクラークの合格基準は、学科・実技Ⅰ・実技Ⅱの3科目すべてにおいて7割以上正答することが条件です。
難易度としては、メディカルクラークのほうが高いといえるでしょう。
医療事務認定実務者試験の過去問やテキストは入手できる?
医療事務認定実務者の過去の問題集や専用のテキストは、市販されていません。
そのため、勉強する資料を入手する場合は、他の医療事務資格の過去問やテキストを探す必要があります。
医療事務関連の問題集やテキストは、書店やインターネットで購入できます。
また、全国医療福祉教育協会のサイトに掲載されている問題例を参考にするのもおすすめです。
医療事務認定実務者の資格は何ヵ月で取得できる?
医療事務認定実務者の資格を取得するのに必要な学習時間は、90~180時間程度といわれており、1日に60分ずつ勉強する場合、3~6ヵ月程度かかる計算です。
参考までに、通信講座のカリキュラムは、一般的に通信講座で3〜4ヵ月程度となっています。
ただし、個人によって学習ペースは異なるため、上記の期間はあくまで目安です。
独学の場合、医療事務認定実務者の専用テキストが存在しないため、通信講座より時間がかかる可能性があります。
医療事務認定実務者なら基礎知識やレセプト作成スキルを証明できる
医療事務認定実務者は、医療事務の基礎知識やレセプト作成の能力を証明できる資格です。
資格の取得はキャリアアップにつながり、昇進や転職にも有利に働く可能性があります。
通信や通学講座を活用すると、効率的な学習やモチベーションの維持に役立ちますが、独学に比べると費用がかかります。
独学は費用を抑えられて自分のペースで学習できる一方で、問題集の選定が難しく、わからない問題の対処に苦労する場合があるでしょう。
医療事務認定実務者試験の勉強方法のメリットとデメリットを考慮しつつ、自分に合った方法を見つけて資格取得をめざしましょう。






