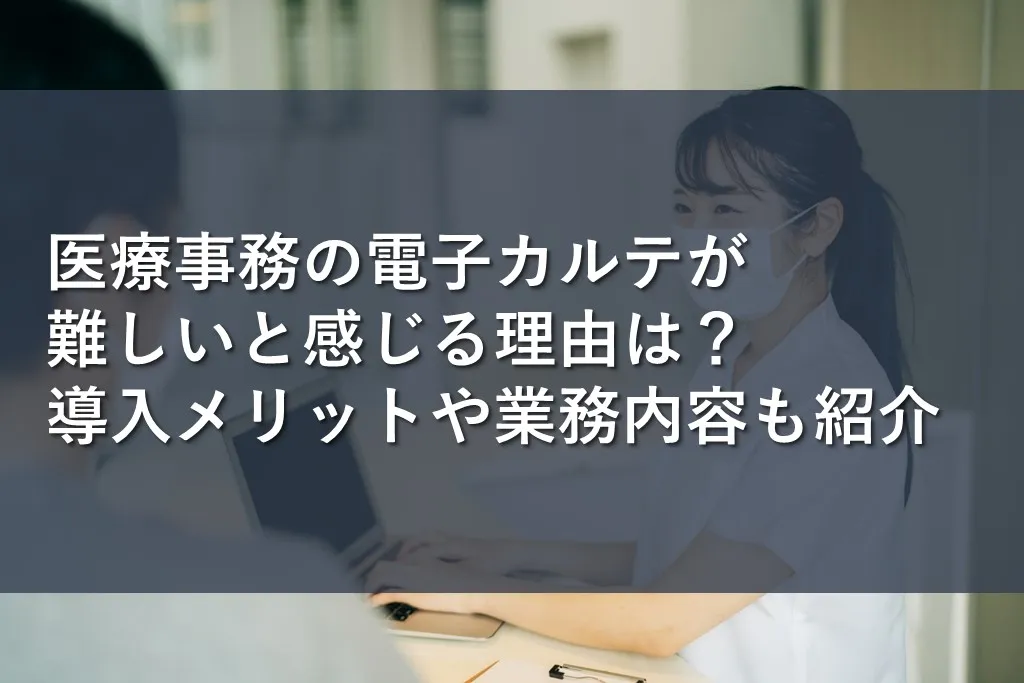
医療現場のデジタル化が進むなか、電子カルテを導入する病院・診療所も年々増加しています。
電子カルテとは、患者さんの診療記録や検査結果などの医療情報をデジタルで管理するシステムのことです。
紙カルテに比べて情報の管理が容易になるメリットがある反面、電子カルテは医療事務の業務の進め方にも大きな影響を与え、慣れるまではスタッフの負担となりかねません。
本記事では、医療事務が電子カルテの扱いを難しいと感じる理由、さらに導入のメリットや活用できる業務内容までを詳しく解説します。
効率的かつ質の高い医療サービスの提供に役立てるため、電子カルテの課題を理解したうえで、スムーズな導入をめざしましょう。
目次
医療事務にとって電子カルテが難しいと感じる理由

病院・診療所で電子カルテの導入が急速に広がるなか、医療事務に関わるスタッフは次のような背景から戸惑いを感じる場合があります。
- 紙カルテに慣れているため移行が難しい
- 操作方法を覚える必要がある
- 故障などのトラブル対応の負担がある
- 診療報酬のセットコードを作る必要がある
医療事務スタッフが電子カルテに対して扱いにくい、難しいと感じてしまう理由を具体的に見てみましょう。
紙カルテに慣れているため移行が難しい
紙カルテを長年使用してきた医療事務スタッフにとって、電子カルテへの移行は大きな変化です。
紙カルテでの業務フローに慣れていると、新しいシステムに適応するまでには時間がかかります。
特に、何年も紙カルテで業務をこなしてきたベテランスタッフほど、電子カルテへの移行に抵抗を感じる可能性があるでしょう。
紙カルテでは、手書きで情報を記入し、ファイリングするのが一般的です。
それに対して、電子カルテはキーボード入力やマウス操作が中心となるため、これまでの業務スタイルを大きく変更させなければなりません。
新たな業務フローに慣れるまでには、ある程度の練習や経験を積む必要があります。
操作方法を覚える必要がある
電子カルテは、多様な機能を備えた複雑なソフトウェアです。
使いこなすには操作方法を理解し、習得しなければならず、特に新しい技術に不慣れなスタッフにとっては大きな課題となります。
操作に慣れるまでにはある程度の時間がかかるため、導入初期は業務効率が一時的に低下する可能性もあるでしょう。
メニューの構成や情報の登録方法、データの検索、予約管理など、覚えるべき項目は多岐にわたります。
また、システムのアップデートがあるたび、新しい機能や変更点にも適応する必要があり、継続的な学習は欠かせません。
故障などのトラブル対応の負担がある
電子カルテは業務効率の向上に寄与する一方で、システムにトラブルや障害が発生したり、停電が起こったりした際は、現場へ与える影響も大きくなります。
紙カルテであれば、システムダウンの心配なくいつでも利用できますが、電子カルテの場合は機器の故障やネットワーク障害が起きる可能性もゼロではありません。
もし電子カルテが一時的に使えなくなれば、診療内容の入力や診療費計算を手作業で行う必要があります。
加えて、過去のカルテを参照できないため、診療に大幅な支障をきたすでしょう。
こうしたトラブル発生時は、医療事務スタッフに臨機応変な対応が求められるため、通常時以上に負担やストレスがかかる場合もあります。
診療報酬のセットコードを作る必要がある
電子カルテの導入後、避けては通れない作業の一つが、診療報酬計算を行うためのセットコードの作成です。
セットコードとは、頻繁に使用する診療行為や処方を電子カルテにまとめて登録する機能であり、作成には専門知識と操作スキルが求められます。
医療機関ごとに診療内容や処方パターンが異なるため、汎用的なセットコードだけでは不十分な場合も少なくありません。
自院の特性に合わせたカスタマイズが必要なとき、医療事務スタッフは複雑な作業に対応しなければならず、慣れるまでは負担を感じるでしょう。
医療事務の業務に電子カルテを導入するメリット
電子カルテの導入には難しい側面もありますが、適切に活用できれば、医療事務の業務をサポートしてくれる心強い味方となります。
医療事務の業務に電子カルテを導入するメリットは、大きく以下の5つです。
- 業務を効率化できる
- ヒューマンエラーを防止できる
- カルテを出し入れする必要がない
- すぐに情報共有できる
- 他の医療機関と連携できる
順に詳しく見てみましょう。
業務を効率化できる
電子カルテ導入による第一のメリットは、医療事務に関する業務効率の向上です。
患者さんのデータを一元管理できるため、各部門間での情報共有がスムーズになります。
従来は手作業で行っていた医療事務の業務も、電子カルテを利用することで自動化されるため、負担を削減できるでしょう。
また、電子カルテにはさまざまなテンプレートが用意されており、文書作成の時間も短縮できます。
例えば診断書や紹介状などの作成時に、必要な情報を自動で引用したり、定型文を簡単に挿入したりといった設定が可能です。
医療事務の業務が効率化された結果、スタッフはより付加価値の高い仕事に時間を割けるようになります。
ヒューマンエラーを防止できる
電子カルテを導入すると、手書きで作成された紙カルテの判読ミスや転記ミスが減り、ヒューマンエラーを防止しやすくなります。
紙カルテの場合、書き手によって文字の読みやすさに差がありますが、デジタル化された情報はつねに明瞭です。
さらに、複数のスタッフが同時に確認できるため、ミスの早期発見にもつながるでしょう。
なかには、入力内容のチェック機能や警告機能を搭載した電子カルテも存在します。
薬の処方量が通常の範囲を超えている場合や、禁忌薬の組み合わせがある場合などに警告を出し、ヒューマンエラーを防ぐためのサポートをしてくれるシステムです。
医療事故のリスクを低減し、患者さんの安全性を高めるうえでも、電子カルテは有効といえます。
カルテを出し入れする必要がない
電子カルテの導入により、紙カルテの物理的な管理から解放されます。
カルテは診療完結から5年間の保管が義務付けられており、医療機関によっては、膨大な紙カルテを保管するための広いスペースを設けなければなりません。
一方で、電子カルテはサーバー上でデータを管理するため、カルテを出し入れする手間が省けるだけでなく、紙資料の紛失や破損のリスクも軽減できます。
紙カルテの保管に使用していたスペースは、別の用途で使えるようになるでしょう。
患者さんの待合室を広げるほか、新たな診療室を設けるのも一つの選択肢です。
また、データのバックアップが容易になるため、災害など万が一の事態に見舞われても、重要な医療情報を守りやすくなります。
すぐに情報共有できる
電子カルテの大きな利点は、リアルタイムで情報共有ができることです。
医師が診察や治療を終えて電子カルテに診療情報を入力すると、医療事務スタッフはすぐにその内容を確認できます。
医療費が自動計算されるものもあるため、会計業務がスムーズになるでしょう。
情報伝達のリアルタイム性は、医療チーム全体の連携強化につながります。
医師、看護師、薬剤師、検査技師など、あらゆるスタッフ間で最新の情報を瞬時に共有し、認識のすれ違いを回避することで、より質の高い医療サービスを提供できるためです。
患者さんの待ち時間も短縮しやすくなり、満足度の向上にも寄与する可能性があります。
他の医療機関と連携できる
電子カルテは、自院以外の医療機関との連携を図るうえでも有益な存在です。
診療記録などがサーバーに保存されるため、電子カルテのメーカーによっては分院をはじめとした他の医療機関と情報を共有できます。
これにより、包括的かつ一貫性のある医療サービスの提供をめざせるでしょう。
また、電子カルテによっては、外注先と連携できるものもあります。
電子カルテに入力した検査項目情報を外注検査会社に送信したり、検査結果を電子カルテに自動で取り込んだりできる場合もあるため、より迅速な診断と治療方針の決定に役立ちます。
医療事務で電子カルテを使う業務
電子カルテは、医療事務のさまざまな業務と深く関係しています。
医療事務の担当業務を大きく受付業務・会計業務・レセプト業務の3つに分け、それぞれで電子カルテがどのように活用されているのか見てみましょう。
受付業務
医療機関に訪れた患者さんの窓口対応を行う受付業務は、医療事務にとって代表的な仕事です。
医療事務スタッフは、来院した患者さんから診察券や保険証を預かり、本人で間違いがないかを確認したうえで、電子カルテに情報を入力します。
このような窓口業務の効率化や正確性の向上に貢献しているのが、電子カルテです。
システムに登録された過去の診療履歴や基本情報などを瞬時に把握できるため、患者さんを窓口で待たせることなく、適切な対応をとれるでしょう。
電子カルテシステムと連動して、待ち時間の表示や診察順の管理などまで行える場合、受付業務はよりスムーズになり、患者さんの満足度にもプラスの影響を与えます。
会計業務
医療事務の会計業務は、診療後の患者さんから医療費を受け取るための工程であり、スピーディさとともに正確性も重視しなければなりません。
電子カルテのなかには、カルテの内容や診療報酬の点数表、患者さんが加入している医療保険をもとに、システムが自動的に医療費を計算してくれるものもあります。
自動計算機能があると、スタッフの熟練度に関わらず、複雑な医療費の計算も瞬時に行うことが可能です。
電子カルテに診療内容を入力すると、会計情報も同時に更新されるため、伝達ミスを防ぎやすくなるとともに、正確な医療費をリアルタイムで把握できます。
患者さんから会計に関する疑問や質問を受けたときも、電子カルテを参照すれば不安なく対応できるでしょう。
レセプト業務
レセプト業務は、被保険者である患者さんが自己負担した診療費の残りを、健康保険組合や共済組合、市町村などに請求する仕事です。
電子カルテでは、診療内容や処方薬、検査結果などのあらゆる情報が電子化されています。
電子カルテによっては、これらの情報からレセプト作成の自動化が可能です。
昨今のレセプト業務は、主に自動で作成されたレセプトの内容に間違いがないかを点検する作業になります。
レセプト点検は、請求漏れや過剰請求を防ぎ、医療機関が適切な報酬を受け取るための重要な工程です。
手書きでのレセプト作成や点数計算といった負担が減少したため、医療事務スタッフは点検作業に重きを置けるようになりました。
また、完成した電子レセプトは、オンラインで請求手続きが可能です。
医療事務の電子カルテを難しく感じる理由とあわせて導入メリットも知ろう
電子カルテの導入は、医療事務の業務に多くのメリットをもたらす反面、いくつかの課題があることも事実です。
紙カルテからの移行に抵抗があったり、操作方法の習得やトラブル発生時の対応が負担になったりするなど、医療事務スタッフのなかには電子カルテを難しいと感じる方もいます。
ただし、電子カルテの難しさは、現場での慣れとともに乗り越えることが可能です。
業務の効率化はもちろん、ヒューマンエラーの防止、カルテの一元管理、迅速な情報共有、院内外の連携強化など、電子カルテの導入にはさまざまなメリットがあります。
医療事務スタッフが主に担当する受付業務、会計業務、レセプト業務にも、今や電子カルテは欠かせない存在です。
電子カルテの基本的な操作スキルを学ぶことはもちろん、日々の業務のなかで理解を深めながら、医療事務の業務品質の向上をめざしましょう。







