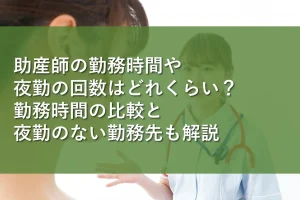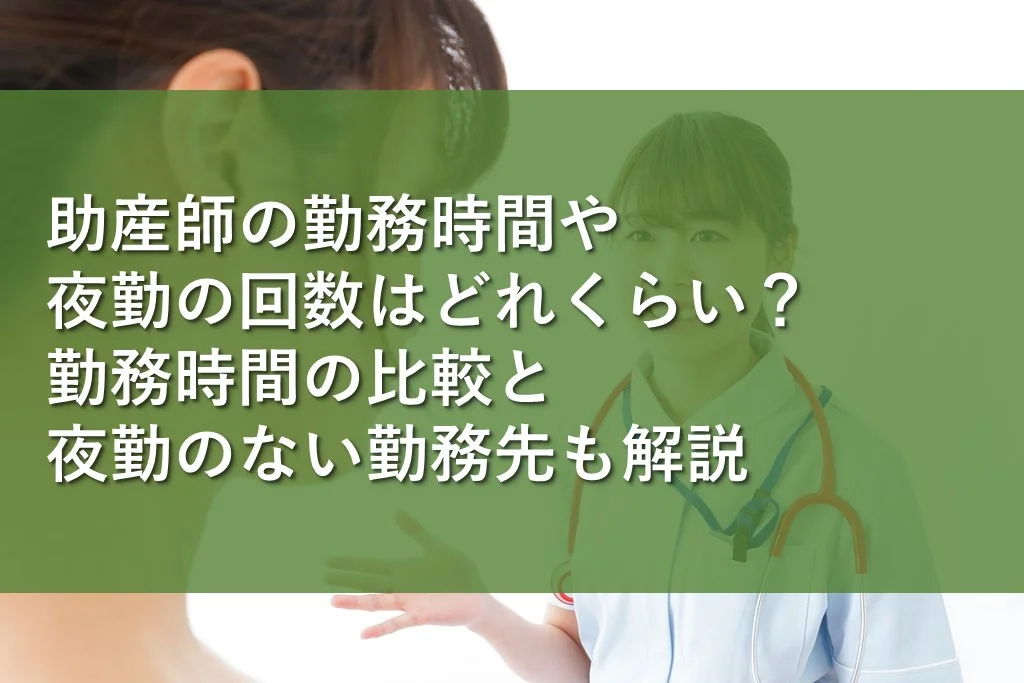
助産師が働く場所の多くは、二交替制か三交替制のシフトでローテーション勤務をしています。
そのため夜勤に出ることが前提になるのですが、日勤と夜勤を繰り返すシフトでは勤務時間がどのように設定されているのか気になる方もいるでしょう。
これから助産師をめざす方からすれば、本当に働けるのか不安になるのも不思議ではありません。
そこで今回は、助産師の勤務時間や、二交替制・三交替制のメリットとデメリットについて解説します。
目次
助産師の勤務時間は?

助産師には、さまざまな勤務先があります。
働く場所によって勤務時間は異なりますが、多くの助産師が働く病院は24時間体制で稼働しているため、会社員のように午前中に出勤して夕方に退勤するリズムを続けられるわけではない場合が多い、ということだけ理解しておきましょう。
また、お産は予定どおりに来るものではないため、変則的な勤務となる場合や突然の呼び出しを受けることもあります。
ここでは、助産師の勤務時間について詳しく解説します。
助産師の勤務時間:三交替制
三交替制とは、日勤・準夜勤・深夜勤の3つの勤務時間がローテーションする仕組みです。
助産師の勤務先で三交替制を採用している場所は多く、病棟で不測の事態が起きたときでもすぐに対応できる体制が敷かれています。
三交替制ではそれぞれ、日勤は昼間、準夜勤は夕方から真夜中、深夜勤は真夜中から早朝の8時間勤務になります。
どれか一つの時間帯に固定で入るわけではなく、日勤をこなしながら、準夜勤や深夜勤をローテーションで回していきます。
三交替制は日によって生活時間が異なるため生活リズムが乱れやすく、心身への負担も大きくなります。
そのため、病院によってはシフトの調整を行い、働きやすい環境が整えられています。
日勤の労働時間
勤務先によって出勤・退勤時間は変動しますが、基本的には朝出勤して夕方に退勤する一般的な社会人の働き方と同じです。
日勤の助産師は、深夜勤に出ていた助産師から患者さんに関する申し送りを受け、昨晩の様子を把握したうえで業務にあたります。
休憩は交替で取得し、夕方に出勤してきた準夜勤に申し送りをしてから、夕方16~17時頃に退勤します。
準夜勤の労働時間
準夜勤の場合、日勤の助産師と入れ替わりで情報を引き継ぎ、業務を開始します。
開始時間は、日勤の方が退勤する16~17時頃です。
準夜勤は日勤よりも人数を減らして運営するので、日勤とは業務内容が異なります。
分娩担当・ベビーキャッチ・その他業務というように担当者を分ける病院もあります。
休憩は20時頃に交替で取得し、24~25時頃に退勤 します。
深夜勤の労働時間
深夜勤の出勤時間は、日付が変わる24時頃です。
準夜勤から申し送りを受けて、業務を開始します。
深夜勤は真夜中から朝までを病院で過ごし、緊急対応が必要な場合は適宜処置を行います。
また、夜は赤ちゃんが産まれやすい時間でもあるため、救急車の対応が多くなります。
地域によってはそもそも夜中に開いている病院が少なく、大型病院に救急車が集中するケースもあります。
休憩は朝方4時頃に交替で取得し、日勤の看護師へ申し送りをして8~9時頃に退勤します。
助産師の勤務時間:二交替制
二交替制とは、日勤と夜勤の2つをローテーションして業務をこなす仕組みです。
三交替制を採用している病院が多いですが、一部では二交替制での勤務が採用されています。
二交替制では、日勤は昼間の8時間勤務、夜勤は夕方から翌朝までの16時間勤務となります。
夜勤は長時間の勤務になるため、途中で仮眠を認めている場所がほとんどです。
それでも心身の負担が大きいことに変わりなく、一般的に夜勤の翌日は休みになります。
また、勤務先によっては二交替制のみ採用している場所と、三交替制と組み合わせることで状況に応じて夜間のスタッフ数を増減させるところがあります。
日勤の労働時間
日勤の出勤時間は、朝8~9時頃です。
勤務先によって出勤・退勤時間は変動しますが、基本的に昼間の勤務になります。
夜勤の助産師から引き継ぎを受け、受け持つ患者さんの様子を確認したり外来診療の手伝いをしたりして、日中の業務を行います。
日勤では、産後のお母さんへ授乳指導や沐浴指導も行っています。
休憩は11~12時頃に交替で取得。
夕方出勤してくる夜勤の助産師に申し送りをして、16~17時頃に退勤になります。
夜勤の労働時間
夜勤の出勤時間は、夕方16~17時頃です。
三交替制で準夜勤と深夜勤に分かれている勤務を、二交替制ではすべて夜勤が行うことになります。
体力勝負の仕事になるため、夜22時頃から交替で2~3時間の仮眠を取ります。
頭が働かずに誤った判断をしてしまうと取り返しがつかないため、助産師は休養が取れるときにきちんと取ることが大切です。
また、休憩は20時と2時頃に分けて取得している病院もあります。
長時間勤務を乗りきったら、日勤の助産師に引き継ぎをして8時30分に退勤です。
翌日は休みのところが多いので、しっかりと身体を休めて次の勤務のリズムに戻していきます。
三交替制と二交替制のメリット・デメリット
三交替制と二交替制には、それぞれメリットとデメリットがあります。
勤務時間だけ見ると大変そうな二交替制にもメリットはあります。
三交替制のメリット・デメリット
三交替制のメリットは、どの勤務時間帯であっても勤務時間の長さが同じである点です。
すべての勤務時間が8時間で統一されているため、二交替制よりも疲労を感じにくいでしょう。
また、三交替制を取れる勤務先はスタッフの人数が確保できていることが多いため、一人あたりの業務の負担も少なくなります。
一方で、3つの時間帯のシフトをこなすため、体調を崩しやすくなるデメリットもあります。
三交替制はシフトの回転も早いため夜勤が回ってくる回数も多く、連休が取りにくいのも気になるところです。
三交替制のメリット
三交代制のメリットをまとめると、主に挙げられるのは以下の3点です。
- 一シフトの勤務時間が短い
- 一人あたりの負担が少ない
- 集中して業務に取り組める
三交替制のデメリット
三交代制のデメリットは以下の3点になります。
- 3つのシフトに対応するため、体調を崩しやすい
- 準夜勤、深夜勤の回数が多い
- まとまった休みが取りにくい
二交替制のメリット・デメリット
二交替制のメリットは、1回の出勤で2日分の勤務をするため、毎月の出勤数が少なくなることです。
まとまった休みが取りやすく、ゆっくりと休養することができます。
また、勤務時間が長い夜勤には深夜手当が付くため、収入が増えることもメリットです。
一方で、心身の疲労が大きくなるデメリットもあります。
助産師の仕事は集中を切らせない瞬間が連続することもあるため、二交替制では長時間集中力を維持する必要があります。
夜間対応や分娩で仮眠がとれないこともあるため、体力も必要です。
二交替制のメリット
二交代制のメリットをまとめると、主に挙げられるのは以下の3点になります。
- 連休が取りやすく休日の予定を立てやすい
- 次の勤務に備えてゆっくり休める
- 深夜手当で収入が増える
二交替制のデメリット
二交代制のデメリットは以下の2点になります。
- 夜勤が16時間勤務になるため、心身の負担が大きい
- 仮眠が取れない場合がある
助産師の大変な部分について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
働く場所によって勤務時間は異なる?
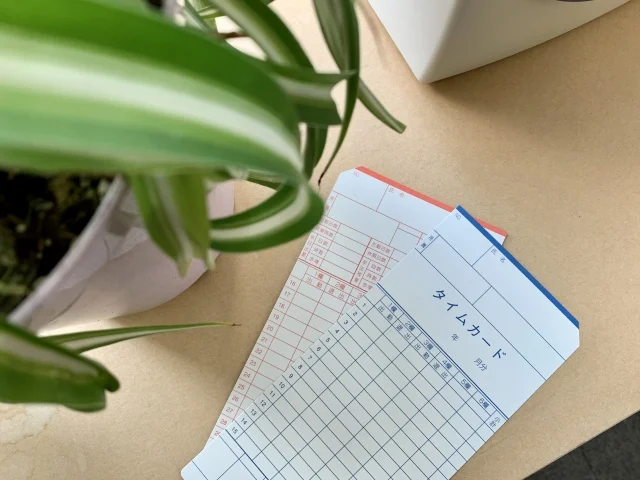
助産師に多い勤務体制として三交替制・二交替制を紹介してきましたが、働く場所によって勤務時間は変化します。
ここでは、職場ごとに採用されているシフトや気になる残業についても解説します。
大学病院や総合病院
大学病院や総合病院では、主に三交替制が採用されています。
大規模な病院は病床数が多く、産婦人科病棟にも入院患者が常にいるため、どの時間でも万全の体制を整えておく必要があります。
そのため、三交替制で一人あたりの負担を減らし、集中を絶やさない環境を作っています。
しかし、毎日のように分娩介助があるような職場なので、お産が重なることで勤務時間をまたいだ介助が必要になり残業をするケースもしばしばあります。
産婦人科(産科クリニック)
産科クリニックなどの助産師の数が少ない中小規模の病院の場合は、二交替制のケースもあります。
助産師として正社員で働くには、夜勤に入ることが前提となる可能性が高いです。
明け方にお産が始まる可能性もあり、夜勤の勤務時間を超えて分娩介助を行うことも珍しくありません。
大型病院同様に残業になることもあります。
助産院
助産院の勤務時間は、開院時間に合わせて指定されることが一般的です。
しかし、お産が始まったときには勤務時間外でも呼び出しがあり、状況に応じて残業や泊まりこみが発生することもあります。
一方で、お産がないときはまったく残業が発生しない場合もあるので、忙しいときとそうでないときの差が激しいのが助産院の特徴です。
助産院は医師がいない施設で、病床が9床以下と小規模 であるため、助産師の一人ひとりの働きにかかる責任が重く、病院や産科クリニック以上に臨機応変な勤務が求められる職場ともいえるでしょう。
残業ゼロで働ける場所はある?助産師の働ける場所を解説
日勤や夜勤など不規則な勤務が前提になっている助産師には、常に忙しく残業が多いイメージを持っている方も多いでしょう。
しかし、働く場所によっては残業が発生しないこともあります。
ここでは残業になりにくい職場について解説していきます。
市町村の保健センター
市町村の保健センターに勤務する助産師は、地方自治体の公務員という扱いになります。
そのため勤務時間も朝から夕方までに限定され、土日祝日も休みがあります。
保健センターでの助産師の仕事は、主に妊産婦の支援です。
出産や育児に関する相談に乗り、助産師としての知識や経験を活かして解決していくことになります。
勤務時間や休日の体制がしっかりとしているため、家庭と仕事を両立しやすい人気の職場です。
養成学校
養成学校とは、助産師をめざす学生が通う学校のことをさします。
助産師は教員として勤務し、実際の経験に基づいた講義や指導を行います。
勤務時間は8時30分頃に出勤して17時頃に退勤するケースが多く、土日祝日も休みのところがほとんどです。
土曜日も開講している学校の場合は、土曜日出勤があります。
不妊治療クリニック
不妊治療クリニックでの助産師の主な仕事は、治療内容や検査内容の説明や患者さんのケアです。
また、妊娠した患者さんに出産のアドバイスをすることもあります。
勤務時間は職場によってさまざまで、仕事終わりに受診できるように21時頃まで開いている場所も少なくありません。
しかし、不妊治療クリニックには入院施設はないため夜勤がなく、勤務時間や休みも安定しています。
助産師として働く際にチェックすべき労働条件
助産師としてこの先継続して働いていこうと考えている方にとって、勤務時間や労働時間は就職先を決める重要な要素になります。
助産師として働く前にチェックしておくべき労働条件のポイントを解説します。
休憩時間が設定されているか
まずチェックすべきポイントは、休憩時間です。
労働基準法では8時間以上の勤務を行う場合、休憩を1時間以上取ることが定められています。
助産師は二交替制の夜勤で16時間勤務があるだけでなく、休憩時間に休憩が取れない場合があります。
忙しい時でも臨機応変に休憩が取れる仕組みがあるのか、確認しましょう。
勤務スケジュールのバランスはとれているか
次にチェックしておくべきポイントは、勤務スケジュールのバランスです。
助産師は三交替制や二交替制を前提として働くことになるので、勤務スケジュールのバランスが取れていないと体調を崩す原因にもなってしまいます。
三交替制の場合は日勤、準夜勤、深夜勤のバランスが取れているか、無理なシフトになっていないかを確認してください。
二交替制の場合は、日勤、夜勤のバランスと、夜勤翌日の休日が確保されているか確認することが重要です。
残業の管理は行き届いているか
助産師は、妊産婦と赤ちゃんの命を預かる責任重大な仕事です。
そのため、どうしても患者さん優先の働き方になりがちで、残業が発生しやすい環境になっています。
残業が起こる職場の場合は、その管理がきちんと行われているか確認することが重要です。
労働基準法では1日に8時間、週に40時間しか働いてはいけない ことになっています。
これを超える場合は残業になりますが、残業も36協定の締結と届け出が必要です。
また、36協定があっても月に45時間、年間360時間までの労働しか認められない ため、一人あたりの勤務時間がこれを超えていないか、確認しておきましょう。
生活タイプやスタイルに合わせて勤務時間を選ぶ
助産師は妊産婦と赤ちゃんの安全のために、24時間体制のシフトが必要な職業です。
二交替制や三交替制でサポートしている職場が多いですが、日勤のみという職場や残業がほとんどない職場もあります。
ライフスタイルや体力と相談をして、自分に合った職場と勤務時間を探してみてください。