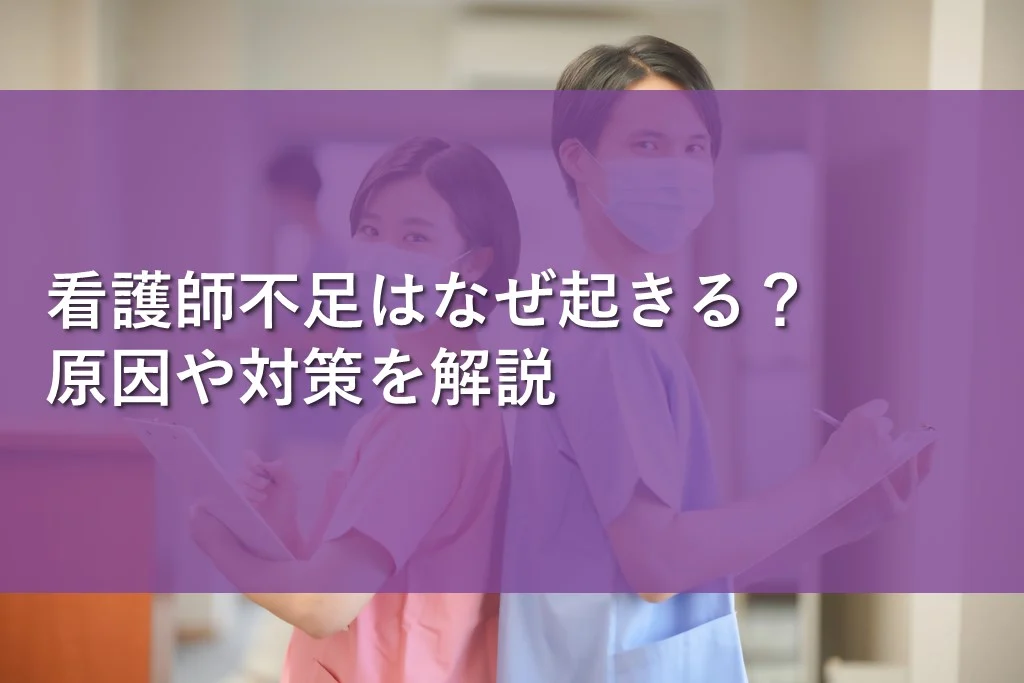
高齢化により医療のニーズが増加するなか、看護師の人手不足が深刻な社会問題となっています。
そこで今回は、看護師不足の現状や原因、今後の見通しや国の対策を解説します。
看護師になりたいが将来に不安を感じている人や、現在看護師として働いている人は、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。
目次
看護師の人手不足の現状

まず、看護師の人手不足の現状を確認してみましょう。
データを見ると、日本の看護師数は平成20年以降、年々増加しています。
厚生労働省の「令和2年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」によると、令和2年に国内で就業している看護師数は1,280,911人であり、前回調査と比較し5.1%増加していることがわかります。
しかし、離職率の高さや、ニーズの高まりを受けて、現場では看護師不足が発生しているのです。
また、厚生労働省の「医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分科会中間とりまとめ案」によると、令和7年における看護師の需要推計は188~202万人であるとされています。
看護師数が現在のペースで増加を続けても、令和7年までにその推計数に到達するのは難しいでしょう。
さらに、令和元年の看護師の求人倍率は、全都道府県において1.0倍を下回る県が一つもなく、需要に対して供給が追いついていない現状も明らかとなりました。
今後、団塊の世代が後期高齢者となっていくことを考えても、看護師不足の状況が続くことが予想されるでしょう。
また、世界と比較しても日本の看護師不足は深刻です。
厚生労働省の調査によると、アメリカやイギリスなどの諸外国と比べると、日本の100病床あたりの看護師数はわずか4分の1程度であることがわかっています。
看護師が不足している原因
日本が慢性的な看護師不足に陥っている原因は以下のとおりです。
- 業務過多・責任の重さ
- 不規則な勤務形態
- 女性看護師の離職
- 病床・看護ニーズの増加
- 看護師数に地域格差がある
順に解説します。
業務過多・責任の重さ
看護師の主な業務は、医師による診療の補助と患者さんの療養上の世話です。
患者さんの身の回りのお世話はもちろんのこと、点滴・注射による投薬や各種検査、処置の介助、ご家族への対応など日々さまざまな業務に追われます。
そのため、多重業務やマルチタスクに陥り、心身ともに疲弊しやすいでしょう。
また、人の命を預かっているというプレッシャーや責任感の重さも、精神的な負担となることがあり、離職してしまう看護師もいます。
不規則な勤務形態
不規則な勤務形態も、看護師不足の一つの原因だといえるでしょう。
勤務スケジュールや夜勤の有無などは病院や施設によって異なりますが、看護師の職場では2・3交代勤務を求められることが多くあります。
本来、人間には朝に起きて夜に寝るというリズムが刻み込まれていますが、夜勤でそのリズムが崩れることで、心身の不調を訴える看護師もいます。
また、不規則勤務ではプライベートと仕事との両立が難しく、ワークライフバランスが崩れてしまうことも。
これらの不規則な勤務体系を理由に、離職してしまう看護師もめずらしくありません。
女性看護師の離職
最近では産休や育休を取得したあとに現場復帰する女性看護師も増えていますが、まだまだ結婚や出産を機に退職してしまう看護師が多いのも事実です。
家事や育児はもちろんのこと、休暇によりブランクができてしまったことによる不安も、現場復帰を困難にしている可能性があります。
病床・看護ニーズの増加
病床数や看護ニーズの増加も、看護師不足の一因となっています。
病床数を世界の諸外国と比較すると、日本は急性期・リハビリ・長期ケア・精神いずれの分野においても突出して多い結果となっています。
病床数が増加すればするほど、看護師数もたくさん必要になることはいうまでもありません。
また、高齢化にともない、地域や在宅を医療の現場とするなど医療や看護へのニーズも増加しています。
すべてに対応しうるだけの看護師数が確保できず、どうしても看護師一人ひとりの負担が増えてしまう現状があります。
看護師数に地域格差がある
全国的なデータで見れば看護師数は年々増加していますが、地域ごとの内訳にはばらつきがあります。
平成24年度の「衛生行政報告例(就業医療関係者)」によると、人口10万人あたりの看護師数は、四国や九州などにおいては1,000~1,200人であるのに対し、関東地方や近畿地方などの都心部では1,000人に満たないところが多いことが明らかになっています。
都市部に病床数が集中しているため、看護師数が追いつかない状態となっているのです。
看護師の人手不足が続くとどうなる?

看護師が人手不足である現状が続くと、以下のような問題が発生します。
- 安全性に影響が出てしまう
- スキルアップ・キャリアアップしにくくなってしまう
- 現場の負担がますます大きくなる
順に解説します。
安全性に影響が出てしまう
看護師不足によって最も心配されるのが、医療の安全性への影響です。
人員不足により看護師一人ひとりの業務量が増加すると、身体的にも精神的にも負担が大きくなり、集中力の低下によるミスにつながってしまうおそれがあります。
また、常に余裕がない状態が続くことで看護師の不安感が増加し、モチベーションの低下を招くかもしれません。
スキルアップ・キャリアアップしにくくなってしまう
看護師が不足すると、現場全体が日々の業務をこなすのに精いっぱいになりがちになり、新たなことに取り組んだり勉強したりといった機会が奪われてしまうことがあります。
その結果、スキルアップやキャリアアップがしにくくなり、看護師の質の向上に影響がおよびやすくなるでしょう。
現場の負担がますます大きくなる
看護師不足により、現場の負担がますます大きくなることはいうまでもありません。
一人あたりの業務量の増加はもちろんのこと、夜勤の回数が増える可能性もあります。
業務やシフトによる負担を理由に離職してしまう看護師もいるでしょう。
看護師の人手不足への対策
これまで、日本における看護師の人手不足の深刻さを解説してきました。
厚生労働省は、この現状を突破することを目的に、看護職員確保対策を実施しています。
看護職員確保対策では、以下のような取り組みを行っています。
- 復職支援対策(新型コロナウイルスワクチン接種業務人材確保、看護師等免許保持者の届け出制度、ナースセンターとハローワークの連携強化など)
- 離職防止・定着促進対策(医療勤務環境改善など)
- 養成促進対策(大卒社会人経験者の養成、教育訓練給付金の拡充など)
- 財政支援(地域医療介護総合確保基金など)
- 看護職員の多様なキャリアパス周知事業(看護職のキャリアと働き方支援など)
看護師不足の状況を踏まえ就職・転職を検討しよう

今回は、看護師不足の現状と原因、今後起こりうる問題や国による対策を解説しました。
看護師不足には、不規則勤務や心身の負担による離職率の高さなどが影響しています。
看護師の需要は高まる一方であり、人手は慢性的に不足しているため、就職や転職には有利な状況であるともいえます。
自分が働きやすい環境を見つけて、就職や転職を検討してみましょう。






