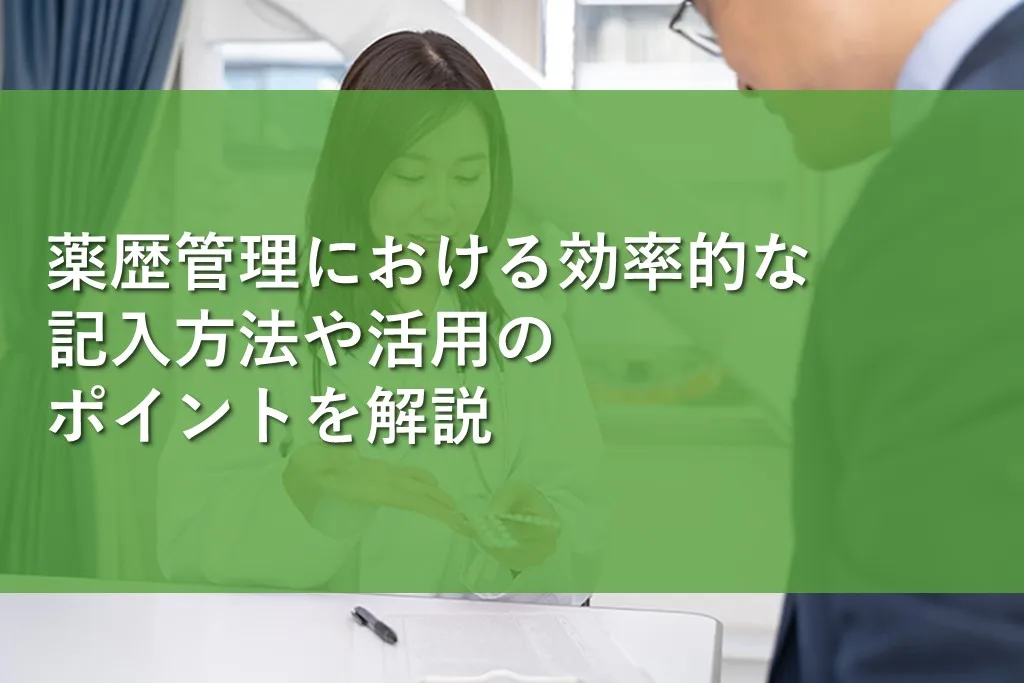
薬歴管理は、薬剤師の重要な業務の一つで、患者さんの安全で適切な薬物療法を支援し、医療の質を向上させるうえで欠かせない役割を果たしています。
本記事では、薬歴管理の基本的な概念から、効率的な記入方法、活用のポイントまでを詳しく解説します。
薬剤師はもちろん、医療に関心のある方々にとっても、薬歴管理の重要性と実践的なアプローチを理解する一助となるでしょう。
目次
薬歴管理とは?

薬歴管理は、患者さんの薬物療法を安全かつ効果的に行うために必要な業務です。
具体的には患者さんの服薬状況や副作用の有無、薬の効果などを継続的に記録しておき、適切な薬物療法を提供するために活用します。
薬歴は医療の質を向上させ患者さんの安全を守るために欠かせない記録であり、適切な医療を提供するために欠かせません。
以下では、薬歴の定義や管理の目的について詳しく説明します。
薬歴とは
薬歴とは、「薬剤服用歴」の略で、患者さんの薬物療法に関する包括的な記録のことを指します。
薬歴に含まれる内容は、調剤内容、服薬指導の内容、患者さんの基礎情報や体質、疾患などです。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則のなかで、保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師は、調剤を行う際に患者さんの服薬状況と薬剤服用歴の確認が義務付けられています。
薬歴は、単なる薬の履歴ではなく、患者さんの健康状態や生活習慣、薬に対する反応など、多岐にわたる情報を含む重要な医療記録です。
これらの情報を適切に管理し活用してはじめて、安全で効果的な薬物療法を提供が可能です。
また、薬歴は医療機関や他の調剤薬局との情報共有にも活用されます。
切れ目のない医療サービスの提供にも、薬歴は貢献しています。
薬歴管理の目的
医療の質向上に貢献する薬歴管理の目的を、もっと詳しく紹介します。
患者さんに合った適切な薬を提供するため
薬歴管理の主な目的の一つは、患者さん一人ひとりに合わせた適切な薬の提供です。
アレルギー情報や家族歴、過去の薬の服用歴などを薬歴で管理していれば、より患者さんに合った薬物療法を提供できます。
例えば、特定の薬に対してアレルギー反応を示したと薬歴に記載されていれば、将来的にアレルギーを起こす可能性のある薬物を推察可能になります。
処方監査の際にアレルギーが発生するリスクを予見して、医師に処方変更を提案することも可能です。
つまり、患者さんが同様の薬でアレルギーを起こすリスクを避けられるのです。
また薬歴の内容によっては、患者さんの体質や生活習慣を考慮し、服用方法を選択したり用量を調整したりして服用しやすく工夫することもできます。
このように、薬歴に情報が蓄積されていれば、より安全で効果的な薬物療法が実現可能になります。
患者さんが納得できるより良い医療を提供するため
薬歴管理のもう一つの重要な目的は、患者さんが納得できる医療の提供です。
薬剤師が患者さんにどのような説明をしたか、どのような質問や懸念があったかを薬歴に記録しておけば、継続的な医療サービスが提供できます。
例えば、前回の来局時に「副作用が心配だ」と話していた患者さんに、次の来局時にその後の経過について確認できます。
副作用の状況によっては、処方の見直しの提案も必要になるかもしれません。
このように、薬歴に会話の内容を記載しておけば、多くの患者さんに対応しなければならない薬剤師でも丁寧なフォローアップが可能になります。
患者さんの気持ちに寄り添った対応ができれば、医療に対する信頼が高まり、今後の薬物療法にも積極的に参加する気持ちになりやすいでしょう。
これは服薬アドヒアランスの向上にもつながります。
調剤報酬請求の根拠とするため
薬歴管理は、調剤報酬請求の根拠としても重要な役割を果たしています。
令和6年度診療報酬改定により、薬剤師が調剤時に薬剤服用歴や医薬品リスク管理計画などの情報に基づき薬学的分析および評価を行うことが、調剤報酬の算定要件に追加されました。
このうち服薬管理指導の根拠としても薬歴が使用されます。
薬剤服用歴の記録に服薬指導の内容を記載していない場合、不当請求として調剤報酬が支払われない可能性もあります。
極端な場合には保険薬局の取り消し処分も考えられるので、薬局経営の観点からも薬歴は非常に重要です。
このように、薬歴は単なる記録ではなく、適切な医療サービスの提供と、その対価としての調剤報酬請求を結びつける重要な役割を果たしています。
薬歴管理の記載事項
薬歴に記載する内容は、法令で義務付けられている内容から、患者さんとのコミュニケーションで得た情報・薬学的な分析結果まで、さまざまな情報が必要です。
以下では、薬歴管理における主要な記載事項について詳しく解説します。
義務付けられている内容
薬歴の記載内容については、薬剤服用歴管理指導料の算定要件に規定されています。
これらの記載は、薬歴管理の質を担保し、患者さんの安全を確保するものです。
また、同一患者についてのすべての記録が必要に応じてただちに参照できるよう、薬歴は患者さんごとに保存および管理することが求められます。
具体的な記載事項は、以下の項目です。
- 患者さんの基本情報(氏名、生年月日、性別、住所など)
- 処方内容(処方箋の記載内容、調剤日、薬剤名、用法・用量など)
- 患者さんの体質(アレルギー歴、副作用歴など)
- 疾患に関する情報
- 現在服用中の薬剤情報(他院での処方薬、市販薬、サプリメントなど)
- 患者の服薬中の体調の変化
- 服薬指導の要点
- 手帳活用の有無
- 今後の継続的な薬学的管理及び指導の注意点
- 指導を担当した保険薬剤師の氏名
薬歴には、これらの情報が適切に記録されていなければなりません。
患者さんから収集した情報
患者さんから直接収集した情報は、薬物療法の際に大きな意味を持つことがあります。
患者さんが相談した事項や、それに対する答えなど、定型文を用いて画一的に記載するだけでなく、今後必要と考えられる内容については、きちんと記載しておかなければなりません。
例えば、患者さんとの会話のなかで薬の副作用かもしれない症状が出てきた場合には、その具体的な症状や発現時期、程度など詳細に確かめて、記録しておきます。
また、質問の内容や転職や進学、出産などライフステージの変化、スポーツを始めたなどという話なども、薬物療法に影響を与えますから、記録すべきでしょう。
これらは、次回の来局時の服薬指導や、処方内容の見直しの際に役に立つこともある情報です。
より患者さんが納得できる薬物療法を提供するために、薬剤師は常に患者さんの声に耳を傾け、その内容を適切に記録する必要があります。
薬学的分析および評価の実績
薬学管理料やその加算を算定する場合は、その根拠と内容などを簡潔に記載する必要があります。
その際には、薬剤師が情報に基づいて処方内容について薬学的分析評価を実施したことを示し、なぜそう考えたのかという経緯を含めて記載します。
例えば、処方薬の相互作用をチェックし問題がないと判断した場合であっても、その判断理由や参考にした資料などを記載しておきましょう。
薬物療法の効果を、患者さんの症状や検査値の推移から分析評価した結果なども、具体的な記録が必要です。
これらの記録は、薬剤師の業務の証明となるだけでなく、継続的な薬物療法にも役に立ちます。
また、他の医療従事者と情報共有するときにも、医療チームに情報を提供する根拠ともなります。
処方医へ情報提供した内容
薬剤師が処方医へ情報提供を行った場合には、その内容を薬歴に記録することが必要です。
分割調剤や疑義照会において処方医に提供した内容は、その経緯や処方変更の有無を含めて詳細に記載します。
例えば、患者さんの副作用について報告した内容や報告した日時、処方医の指示などです。
また、疑義照会を行った場合には、その理由や処方医との協議内容、最終的に処方内容が変更されたのかどうかについても記載すべき内容でしょう。
これらの記録は、医師に情報提供をした証明となるだけでなく、治療経過を把握する情報源にもなります。
また、将来同様のケースが発生した場合には、参考資料としても使用できるでしょう。
薬歴管理の方式は?

薬歴管理の方式に決まりはありません。
SOAP方式が多く使われていますが、それ以外にも、箇条書きやテンプレート化など、さまざまな方式があります。
それぞれの特徴を理解し、自分の調剤薬局に最適な方式を選択しましょう。
SOAP方式
SOAP方式は、従来から看護の場面で使われてきた、最適な治療計画を立案する際に役立つ記載方式です。
主観的データ(Subjective)、客観的データ(Objective)、アセスメント(Assessment)、計画(Plan)の4つの要素を順に記載し、明確にします。
SOAPの各要素の内容は以下のとおりです。
- S(Subjective):患者さんの主観的な訴えや症状
- O(Objective):薬剤師が観察した客観的なデータや検査結果
- A(Assessment):SとOの情報をもとに行った薬学的評価
- P(Plan):評価に基づいて立てた計画や介入方法
SOAP方式には、患者さんの情報を一貫性を持って記録できる利点があります。
患者さんの声に耳を傾け(S)、客観的なデータ(O)と照らし合わせて評価を行い(A)、その結果に基づいて計画を立てる(P)という流れが明確になり、誰にでも理解しやすくなります。
SOAP方式では、薬剤師の思考過程が明確になるため、他の医療従事者と情報共有も容易です。
箇条書き
箇条書き方式は、その名のとおり内容を簡潔に箇条書きで記録します。
この方式の最大の利点は、記載時間の短縮です。
また、個人による記載の差が出にくいというメリットもあります。
箇条書き方式のメリットを以下にまとめました。
- 情報が簡潔で見やすい
- 大切なポイントが一目でわかる
- 記録時間が短縮できる
- 個人差が出にくい
- あとから情報を追加しやすい
箇条書きならば、患者さんとの会話の要点や、服薬指導の内容などを簡潔に記録できます。あとから情報を確認する際にも便利です。
ただし、箇条書きだけの記載は、詳細な情報や思考過程を記録する際には不向きな場合もあります。
必要に応じて他の方式と組み合わせましょう。
テンプレート化
薬歴管理をテンプレート化すれば、記録の効率化と標準化が可能に
なります。
テンプレートとは、定型的な文章を作成する元となるひな形のことです。
テンプレートを使用すれば、記載すべき内容の漏れを防ぎ、あとから見やすく使いやすい薬歴になります。
テンプレート化のメリットは以下のとおりです。
- 記録が標準化できる
- 必要な情報の漏れを防げる
- 記録時間を短縮できる
- 情報の検索や抽出が容易になる
- 電子化への移行がスムーズになる
日本病院薬剤師会では薬歴の標準のテンプレートを提供しています。
これを参考にすれば、効率的に薬歴の管理ができるでしょう。
また、薬歴の電子化にはテンプレート化が必要不可欠です。
電子薬歴システムを導入するステップで、自局の業務フローに合わせたテンプレートにカスタマイズしておけば、より効率的な薬歴管理が実現できます。
薬歴は電子化することが可能

近年、医療のデジタル化が進むなか、薬歴管理においても電子化の動きが加速しています。
マイナ保険証の導入に向けて、薬歴のシステム化も進んでおり、お薬手帳の電子化も進行中です。
患者さんの医療情報をより効率的に管理できれば、医療機関の間で情報共有が容易になると考えられます。
薬歴を電子化する際には「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に従って進めます。
このガイドラインは、患者さんの個人情報保護やシステムのセキュリティ確保など、電子化にともなうリスクを最小限に抑えるための指針です。
医療業界全体として薬歴のDX(デジタルトランスフォーメーション)化が進行中ですが、システムの導入にあたっては調剤薬局の状況や患者さんのニーズを考慮する必要があるでしょう。
電子薬歴管理と紙薬歴管理のメリット・デメリット
薬歴管理は、現状では電子薬歴と紙での記録の両方が使用されています。
どちらにもメリットとデメリットがあるので、調剤薬局の規模や業務の特性、患者さんの特性などによって、どちらが適しているのかを見極めましょう。
自局に最適な方法で薬歴管理がきちんと実施されていれば、どちらの方法を選択しても問題ありません。
電子薬歴管理のメリット
電子薬歴管理には、業務効率化や情報管理の観点から多くのメリットがあります。
主なメリットは以下のとおりです。
- 時間短縮:情報の入力や検索が迅速に行え、業務効率が大幅に向上する。
- クラウド保管:データをクラウドに保管するので、紛失のリスクが低減する。
- 在宅訪問で使用可能:タブレットなどを使用すれば、在宅訪問時など出先でも薬歴にアクセスし、データを参照・更新が可能。
- 記録方式の統一:テンプレートへの記載を実施するので記録が標準化し、情報が見やすくなる。
- 保管スペースの節約:物理的な保管スペースが不要。
一般に電子薬歴管理では、薬剤師の業務効率が向上し、より多くの時間を患者さんとのコミュニケーションなどに割くことが可能です。
また、データの分析や統計処理も容易なので、調剤薬局全体の業務改善にもつながるでしょう。
電子薬歴管理のデメリット
一方で、電子薬歴管理にはデメリットもあります。
- 導入コストが必要:システムの導入には初期投資が必要で、特に小規模薬局では負担となる。
- 故障した場合に使えない:いったんシステムが故障してしまうと、業務に大きな支障が出る可能性がある。
- 習熟が必要:スタッフがシステムの使用方法を習得する必要があり、導入初期は業務効率の低下が予想される。
- セキュリティ対策が必要:患者さんの情報は機密情報なので、漏洩を防ぐため高度なセキュリティ対策が必要。
- 記録の多様性低下:テンプレート化によって、記載の自由度が下がり、個々の患者さんの状況を反映しにくくなる可能性がある。
これらのデメリットを補うために、電子薬歴の導入前には十分な検討と準備が必要になります。
特に、スタッフの教育やセキュリティ対策には十分な注意を払わなければならないでしょう。
紙薬歴管理のメリット
従来から使用されている紙薬歴管理にも、メリットがあります。
- 操作の簡便さ:特別なマニュアルがなくても扱えるため、新人スタッフでもすぐに活用できる。
- 視認性の高さ:紙面上で情報を俯瞰しやすく、全体像を把握しやすい。
- カスタマイズの容易さ:個々の患者さんの特性に応じて、柔軟に記録方法を選択できる。
- 停電でも使える:電力に依存しないため、停電していても問題なく使用できる。
- 導入コストの低さ:特別なシステム導入が不要なため、初期コストが低く抑えられる。
特に小規模な調剤薬局や、高齢の患者さんが多い調剤薬局では、紙薬歴管理が引き続き使われています。
紙薬歴管理のデメリット
一方で、紙薬歴管理には以下のようなデメリットもあります。
- 保管スペースが必要:物理的な保管場所が必要で、調剤薬局のスペースを圧迫する可能性がある。
- 破損・紛失リスク:火災や水害、単純な紛失などにより、貴重な情報が失われるリスクがある。
- 持ち運びの困難さ:在宅訪問時に、必要な薬歴をすべて持参するのは困難。
- 検索の手間:情報を探す場合に、時間がかかる場合がある。
- 記録者による違い:記入者によって記載内容や様式に違いが出やすく、情報が標準化しにくい。
紙薬歴管理では、特に患者数が多い調剤薬局や、複数の薬剤師が関わる大規模な調剤薬局では、業務効率低下につながるかもしれません。
薬歴管理を行う際の注意点

薬歴管理は、患者さんの安全と適切な薬物療法を支える業務です。
患者さんとのコミュニケーション、情報の記録と管理などについて、具体的に解説します。
患者さんの話をしっかり聞いて記録する
薬歴管理には、患者さんとの良好なコミュニケーションが欠かせません。
患者さんの話をしっかりと聞いた適切な記録があるからこそ、より質の高い薬学的管理が可能です。
記録する際に気をつけたいポイントをまとめましたので、参考にしてください。
- 質問を使い分ける:自由に答えられるオープンクエスチョンと二者択一で答えられるYES/NO質問を使い分けると、相手が話しやすくなり、より多くの情報を引き出しやすくなります。
- 得た情報はすべて記録する:一見重要でないと思える情報でも、後々役に立つ可能性があります。
会話の内容はできるだけ記録しましょう。
「最近疲れやすい」という世間話は、薬の副作用の可能性や生活習慣の変化を示唆する重要な情報かもしれません。 - なぜ聞くのかについても説明し信頼関係を構築する:患者さんに質問の意図を説明すれば、信頼関係を構築するとともにより正確で詳細な情報を得やすくなります。
薬剤師の質問について、プライベートに立ち入られたように感じる患者さんもいます。
「お薬の効果を正確に評価するために伺っています」といった説明があれば、患者さんの理解と協力を得やすくなるでしょう。
患者さんの話を聞き記録する際には、これらのポイントを意識しておきましょう。
患者さんとの信頼関係を築いていけば、より充実した薬歴管理を行うことが可能になります。
必要なときに情報が見つかるように書く・保管する
薬歴は、あとから参照して活用するためのものです。
そのため、必要な情報がすぐに見つかるように記録し、保管しましょう。
効率的に記録し、わかりやすく保管するためには、以下のようなポイントがあります。
- 連番をつける
- 記載項目をフォーマット化する
- 患者さんごとにファイルを分ける
電子化する
なぜそう考えたか思考の過程を残す
薬歴には、薬剤師の専門的な判断や思考過程を記録しましょう。
あとから振り返った際に判断の根拠が明確になり、継続的な薬学的管理の質の向上につながります。
思考過程を記録するポイントをまとめます。
- SOAP形式を活用する:Subjective(主観的情報)、Objective(客観的情報)、Assessment(評価)、Plan(計画)の順で記録することで、思考の流れが明確になる。
- 判断の根拠を明記する:なぜそのような判断に至ったのか、参考にした情報源なども含めて記録する。
- 複数の可能性を考慮する:一つの結論だけでなく、他の可能性についても記録しておく。
- 疑問点や不明点も記録する:すべてが明確でない場合でも、疑問点や不明点を記録し、次回の来局時に確認できるようにする
- 患者さんとの対話内容も含める:患者さんの反応や理解度、懸念事項なども記録する。
「患者さんは□□について不安を感じている様子。次回、確認する必要がある」といった記録があるとわかりやすいでしょう。
なぜそう考えたか思考の過程を残しておけば、薬剤師の専門性を医療に役立てることが可能になります。
また、他の薬剤師に情報を共有するのにも必要です。
薬歴管理は薬剤師の職能が必要な大切な仕事
薬歴管理は、単なる記録ではなく、薬剤師の専門知識と経験を活かした重要な業務です。
適切に薬歴管理が実施されていれば、より効果的な薬物療法を提供できますし、患者さんの安全も確保できるでしょう。
近年、薬歴管理の電子化が進められていますが、紙ベースの薬歴管理にもメリットがあります。
重要なのは、どの方法を選択するにせよ、患者さんの声に耳を傾け、適切に情報を記録・管理し、薬学的な思考過程を残すことです。
患者さん一人ひとりに最適な薬物療法を提供するために、日々薬歴を作成し管理することは、薬剤師としての責務といえるでしょう。







