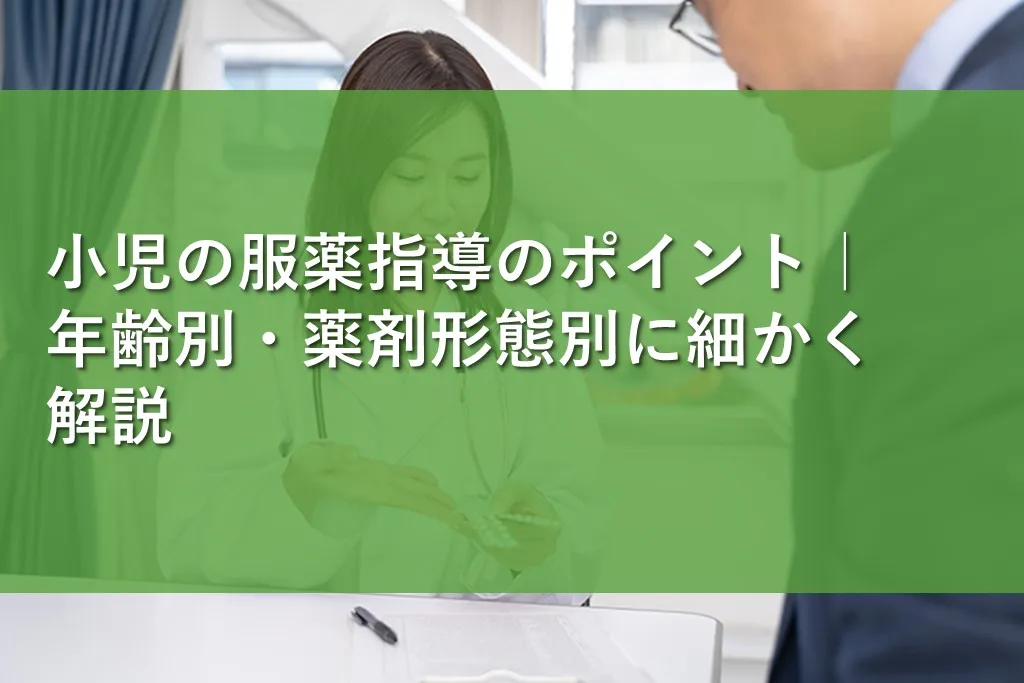
小児の服薬指導は、対象小児の年齢や成長、状況に合わせて行う必要があります。
小児は大人よりも薬の味や形状に敏感であり、服薬拒否が起こりやすい傾向にあります。
そのため、小児の服薬指導では、事前の確認事項や年齢別・薬剤形態別のポイントを押さえたアドバイスが重要です。
この記事では、小児の服薬指導のポイントを詳しく解説します。
目次
小児の服薬指導で事前に確認すること

小児の服薬指導を行う前には、いくつかの確認が必要です。
これらの確認は、服薬指導をスムーズに進めるうえで重要な情報となります。
今まで服薬で困ったことはなかったか
小児の服薬指導をする前には、おくすり手帳なども参照しながら、服薬歴を確認しましょう。
今まで薬を飲んだことがあるのか、飲んだことがあればその際の手順や困ったことがなかったかなどを確認することが大切です。
この確認により、今回の服薬にあたって起きやすい問題を予測でき、対応策を事前に伝えることが可能になります。
例えば、過去に薬の味が苦手で飲むのを嫌がったことがあれば、今回の服薬ではできるだけ味を感じさせない飲み方の工夫を伝えることが有効です。
また、錠剤が飲みづらかったという情報があって今回も錠剤が処方された場合には、オブラートや服薬ゼリーの使用を提案できます。
薬をきちんと保管していたか
今までに薬の誤飲をしたことがあるか、勝手に子どもが薬を飲んでしまったことがあるかなどを確認しておくことが大切です。
そういったことがあれば、薬の保管方法についても指導が必要であるため、服薬指導の際にどこに重きをおけば良いかがわかります。
例えば、過去に子どもが自分で薬を飲んでしまったことがあれば、薬は子どもの手の届かない場所に保管するよう説明します。
誤飲防止のために保管場所へチャイルドロックを使用することや、薬の数の確認方法についても伝えておくと良いでしょう。
介助者は誰か
実際に飲ませる人が誰かを確認しておくことで、服薬指導をする対象を定めることができます。
介助者に直接指導をすることで、実際に服薬介助をするときのイメージがつきやすく、指導の効果が期待できます。
例えば、母親が主に服薬介助を行う場合、母親に直接指導をすることが効果的です。
一方、祖父母が服薬介助を行う場合は、高齢の祖父母も理解しやすいよう、ゆっくりと丁寧に説明したり、ポイントをメモに書いたりしておくことも良いでしょう。
保育園や幼稚園に服薬介助を依頼する必要がある場合は、文書での指導や電話での説明が必要になることもあります。
アレルギーの有無
アレルギーや併用できない医薬品があるかどうかは、事前に確認しておく必要があります。
小児だと今までに医薬品の服用経験がなく、そもそもアレルギーがあるかどうかがわからないことも少なくありません。
事前に確認できる事柄に関しては、情報を集めておくのが良いでしょう。
例えば、卵アレルギーがある場合、卵の成分を含む薬剤は避ける必要があります。
また、過去に特定の薬剤でアレルギー反応が出たことがある場合は、その薬剤と同系統の薬は避けるよう医師に相談する必要があります。
適切な薬剤選択につなげるため、今後はこれらの情報を処方時に医師に伝えるようすすめることも大切です。
小児の服薬指導ポイント【年齢別】
小児の服薬指導は、年齢によって大きく異なります。
乳児期、幼児期、学童期では、服薬方法や指導内容に違いがあるため、それぞれの年齢に合わせた指導が必要となります。
乳児期(1歳未満)
乳児期は、粉末やシロップを白湯や水などに溶かして服薬させることが一般的です。
このとき、普段飲んでいるミルクに混ぜてしまうと、「ミルク=苦い」と思ってしまい、ミルクを嫌がって栄養不足になってしまう可能性があるため、ミルクとは混ぜないように指導します。
また、服薬時にはむせ込まないよう、上体を立て(または抱っこをし)て飲ませるよう伝えましょう。
乳児期の服薬では、介助者に不安があると伝わってしまい、服薬の失敗につながるケースもよくあります。
自信をもって介助しやすくするため、介助者の疑問や不安を解消しながら指導することが重要です。
幼児期(1~5歳)
幼児期は個性が出始めるため、服薬する理由をごっこ遊びやわかりやすい資料などを用いながら説明し、本人の理解を促してから服薬を進めるよう指導します。
水やぬるま湯で飲むよう勧めながらも、嫌がる場合は飲みやすい味がついたゼリーなどを用いても構わないことを伝えましょう。
学童期(6歳~12歳)
親(介助者)だけではなく、子どもとの対話を通しても、服薬の必要性や論理的な説明を行う必要があります。
子どもがどの程度理解できているか、「先生からどんな風に聞いているかな」や「この薬の作用は知ってるかな」など、理解度を確認する問いかけを行いましょう。
理解度を確認しながら服薬指導を行うことで、服薬拒否を避けることにつながります。
そもそも服薬指導とはどういったものかを知りたい人は、下記の記事をご覧ください。
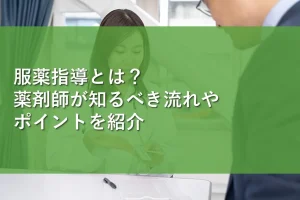
小児の服薬指導ポイント【薬の種類別】
小児の服薬指導では、薬の種類によっても指導内容が異なります。
シロップ薬、粉薬、錠剤、坐薬、点眼薬など、それぞれの薬剤形態に合わせた指導が必要です。
シロップ薬
シロップ・水薬の場合、カップやスポイト、スプーンなどを用いて、適切な量をすべて飲ませる必要があります。
服薬後にぬるま湯などを追加で飲ませることで、適切な量をもれなく投与できます。
ミルクを飲んでいる場合は哺乳瓶などを用いて飲ませ、最後にぬるま湯をいれて飲み切らせるよう指導しましょう。
粉薬
歯の生えていない乳児期の子どもであれば、粉薬を水で練り、味を感じにくい頬の内側やあごの奥に塗布して飲ませます。
苦みを感じることも多いため、すぐに水やぬるま湯を飲ませると良いでしょう。
成長したら粉薬を水やぬるま湯、必要に応じてジュースやスポーツドリンクなどで溶き、飲ませるようにします。
ただし、薬剤の種類によっては溶かす飲み物によって苦みを増強させてしまう可能性もあるため、その都度薬剤師に確認してもらうよう説明します。
適宜オブラートや服薬ゼリーを用いてもかまいません。
錠剤
錠剤は飲みづらく喉に引っかかりやすいため、身体を起こし口の中を湿らせてから内服させるよう指導します。
水やぬるま湯とともに服用しますが、うまく飲み込めないと苦みが出てきてしまう場合もあります。
そうした際には、オブラートや服薬ゼリーを使ったり、プリンやヨーグルトとともに口に入れたりする方法も有効です。
自己判断で錠剤を崩してしまうと、薬効が変わってしまう危険性がある場合もあります。
砕いて服薬させたい場合には、一度薬剤師へ相談してもらうよう説明しましょう。
坐薬
清潔な指で薬剤を手に取り、おむつを変える際のように仰向けに横にした姿勢で肛門に挿入します。
挿入後すぐに薬剤が出てくるのを防ぐため、数秒間ティッシュペーパーなどで押さえるよう伝えましょう。
すぐに排便感を催す可能性があるため、排便後が好ましいです。
坐薬が入りづらい場合には、薬剤の先端に水やオリーブ油をつけることで、無理なく挿入できることも合わせて伝えると良いでしょう。
点眼薬
子どもを仰向けに寝かせて、介助者の両ももで頭を固定します。
目を閉じたままで目頭に1滴垂らしたあとに、目を開けさせてぱちぱちと瞬きを促します。
冷所保存などで冷たいままだと、目に当たったときに驚いてしまうこともあるため、室温に戻しておくように勧めると良いでしょう。
小児の服薬指導の注意点
小児の服薬指導は、上記でも説明したとおり、年齢や成長状況によって大きく変わります。
本人の前向きな姿勢も重要となるため、苦い薬を飲めたあとは褒めてあげたり、飲むたびに「頑張ったねシール」などを貼ったりなどして、成功体験につなげていくことが大切です。
薬を飲むなかでアレルギーのような症状が出た場合や、症状が改善しない場合は、すぐに医師や薬剤師に相談してもらうよう伝えておくことも重要です。
小児の発達段階を考慮し、適切に服薬指導を行おう
小児の服薬指導では、年齢や成長、状況に合わせた指導が重要です。
乳児期、幼児期、学童期では、服薬方法や気をつけるべきポイントに違いがあり、それぞれの発達段階に適した指導を行う必要があります。
また、薬の種類によっても注意点が異なるため、シロップ薬、粉薬、錠剤、坐薬、点眼薬など、それぞれの薬剤形態に合わせた指導が求められます。
小児の服薬指導では、本人の前向きな姿勢を引き出すために、内服できたことを褒めてあげたり、飲むたびに「頑張ったねシール」などを貼ったりして、成功体験につなげていくことが大切です。
また、アレルギーのような症状が出た場合や症状が改善しない場合は、すぐに医師や薬剤師に相談してもらうよう伝えておくことも欠かせません。
小児の服薬ではさまざまな問題や疑問が起こりやすいことを念頭に、事前の確認事項や年齢別・薬剤形態別のポイントを押さえ、適切な指導を行いましょう。







