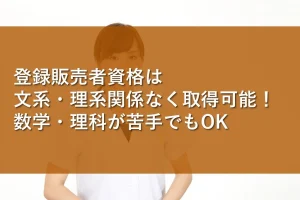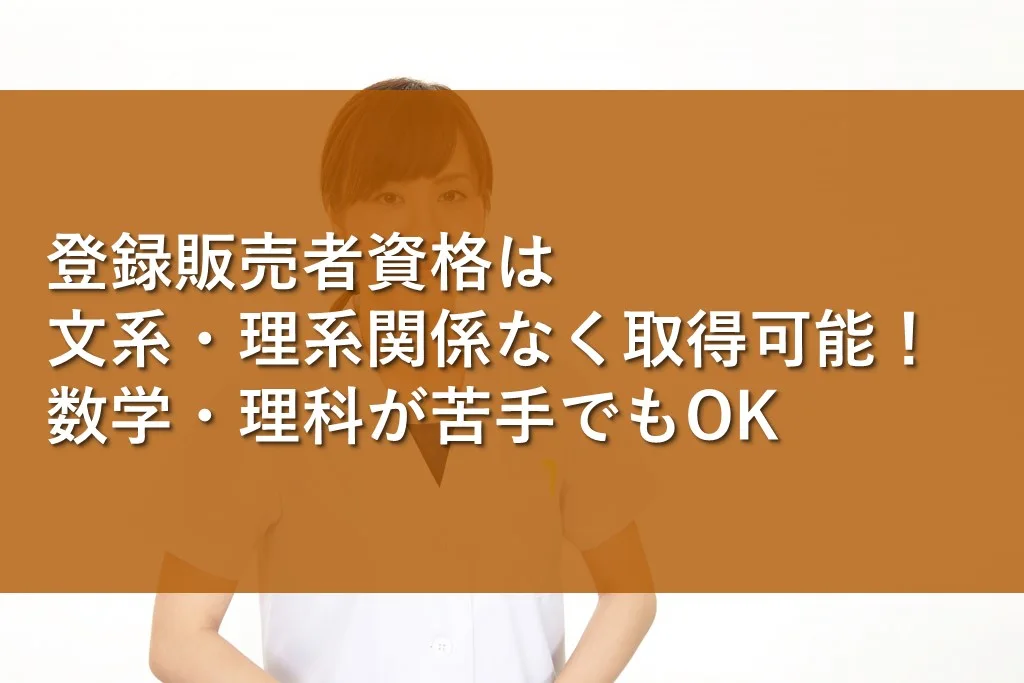
ドラッグストアや調剤薬局で働く登録販売者は、市販の医薬品を扱える専門家として人々の健康をサポートしています。
私たちにとって身近な存在でもある登録販売者ですが、文系でもめざせるかどうか気になっている人も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、文系でも登録販売者はめざせます。
本記事では、文系でも登録販売者をめざせる理由や、具体的な勉強方法についてわかりやすく解説します。
目次
登録販売者は数学や理科が苦手な文系の方でも取得可能
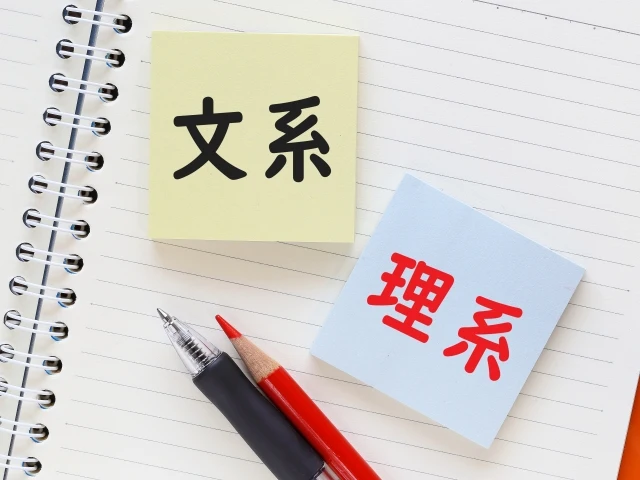
登録販売者とは、一般医薬品の販売を扱う仕事に必要な専門資格です。
どのような症状があらわれているのかヒアリングし、患者さんの症状に適した薬をおすすめする役割を担っています。
医薬品に関する資格だからといって、かならずしも理系出身の必要はありません。
文系でもめざせる資格であるため、意欲がある人はぜひ資格取得にチャレンジしてみてください。
ここでは、文系でも登録販売者をめざせる理由を説明します。
試験に難解な数式が必要ない
登録販売者の試験項目と問題数は以下のとおりです。
- 医薬品に共通する特性と基本的な知識(20問)
- 人体の働きと医薬品(20問)
- 主な医薬品とその作用(40問)
- 薬事関係法規・制度(20問)
- 医薬品の適正使用・安全対策(20問)
登録販売者の試験は、文系でも受けられる内容になっています。
難解な数式や化学式などが含まれた問題は出題されないため、理系科目を学んでいない人でも問題ありません。
暗記系の内容が多い
試験内容は暗記要素が多い傾向にあり、合格するためには出題される範囲をおぼえて自分の知識にすることが重要です。
理系で専門的なことを学んでいなくても合格は十分めざせます。
登録販売者の試験に求められるのは、医薬品に関する知識です。
医薬品の名称や成分といった基礎内容や安全に使うための方法などを学びましょう。
また、薬事関係の法規や医療制度に関する問題も出題されます。
法規や制度は変更が多いので注意が必要です。
受験資格に学歴は関係ない
平成26年度以前の登録販売者試験では、受験資格として特定の教育課程修了や実務経験が必要でしたが、平成27年度以降の試験では、それらの要件が撤廃されました。
そのため、学歴に関係なく受験することができます。
文系出身者におすすめの登録販売者試験の勉強方法

登録販売者は、文系であってもめざせることがわかりました。
では、実際にどのような試験対策をすれば良いのでしょうか。
ここでは、文系出身者におすすめの勉強方法についてご紹介します。
参考書を使って独学で学ぶ
自分のペースで勉強したい人や、早めの合格をめざしたい人には独学がおすすめです。
参考書を購入する際には、直近の法規や制度の改定に対応しているかを忘れずに確認しましょう。
また、用語集などのテキストが付属されていたり、問題集が多く掲載されていたりする参考書を選ぶのもおすすめです。
通信・通学講座で学ぶ
時間はかかっても確実に合格をめざしたいのならば、通信・通学講座を受けるのがおすすめです。
独学より費用はかかりますが、わからない部分があれば講師に質問できるのは大きなメリットです。
ただし、講座を受けるためにまとまった時間を確保しなければいけないため、時間に余裕がある人でなければ計画的に進めるのは難しいかもしれません。
通信・通学講座を選ぶ際は、サポート体制や試験日までのスケジュールを確認しておきましょう。
文系でも登録販売者取得は可能
医薬品を扱う登録販売者は、理系でなければ資格を取得するのは難しいと思われがちですが、実際には学歴・実務経験を問わないため、意欲さえあれば誰でも取得をめざせます。
文系でも理系でも、登録販売者の仕事に興味がある人は、ぜひチャレンジしてみてください。
資格を取得したあとの気になる給料や仕事内容などについて知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。