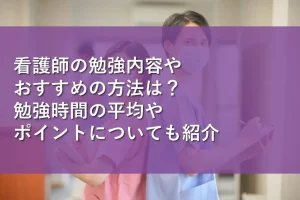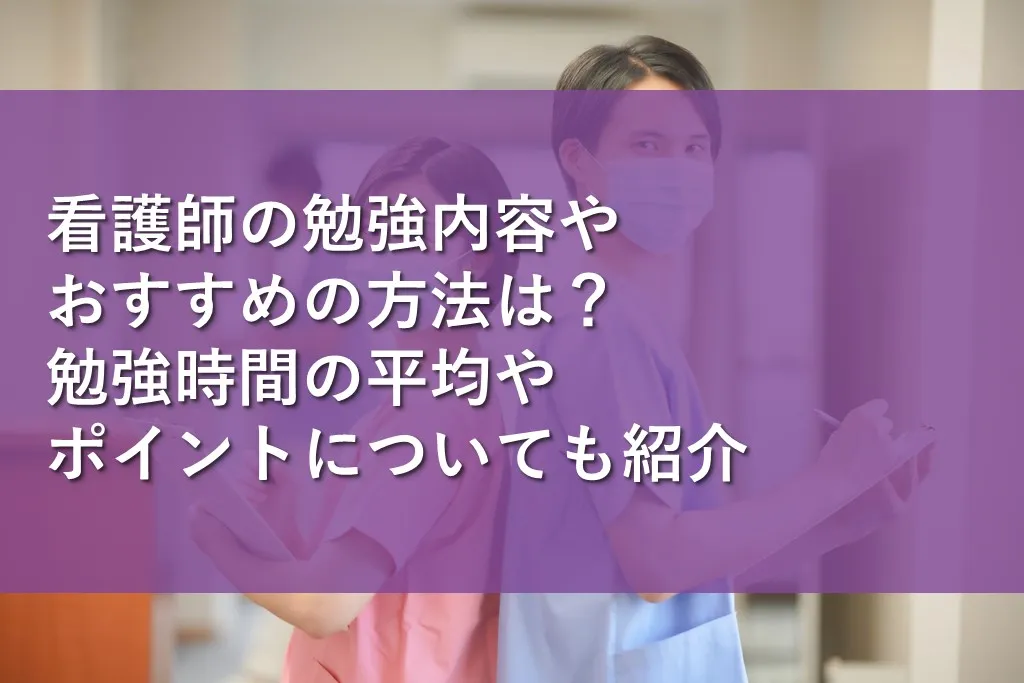
看護師として働くには、スキルアップのために勉強は欠かせません。
新人だけでなく、ベテラン看護師にも勉強が必要です。
この記事では、現役看護師におすすめの勉強方法や勉強時間、勉強の注意点などを解説します。
看護師として勤務して間もない方やベテラン看護師の方はもちろん、看護師をめざしている学生の方にも役立つ内容なので、ぜひ参考にしてください。
目次
現役看護師におすすめの勉強方法

現役看護師におすすめの勉強方法は次のとおりです。
- 関連図にまとめて思考を整理する
- 症例や対処法の根拠を理解しながら勉強する
- マイ辞書やノートを作成して覚える
それぞれの内容を解説します。
関連図を作成しながら勉強する
看護師は、関連図を作成しながら勉強するのがおすすめです。
関連図とは、患者さんの看護問題を明確にするために、病状や治療歴などの疾患情報から家族歴や生活習慣、心理・社会的な背景まで関連性がわかるようにまとめた図です。
看護問題は、さまざまな情報が複雑に絡み合って発生しています。
患者情報を頭のなかだけで整理することは難しいでしょう。
そのようなときに関連図を用いることで、視覚的にも情報を整理でき、患者さんが抱えている問題やその原因を把握しやすくなります。
また、関連図には疾患や症状、治療法、副作用などの情報をまとめる「病態関連図」があります。
「病態関連図」を用いることで、患者さんの病態を論理的に理解でき、看護に必要な医療知識を効率的に覚えられます。
特に、新しく入院する患者さんの病態の予習に関連図を利用するのがおすすめです。
経験年数を重ねていくと、関連図を使わなくても自然に頭のなかでまとめられるようになるかもしれませんが、慣れるまでは関連図を使って情報を整理して覚えるようにしましょう。
症例や対処法を根拠とセットで勉強する
勉強をする際は、病態の概要だけでなく症例や対処法などを根拠とセットで勉強するようにしてください。
断片的な知識だと覚えにくいうえに体系的な知識が身につかないため、現場で役立つ知識になりません。
なぜ症状が起きるのか、対処法はなぜ行うのか、ほかにどのような症状が起きるのかなどと、根拠を考える癖をつけて勉強するようにしましょう。
マイ辞書・ノートを作成して覚える
自分だけの辞書やノートを作成する勉強方法もおすすめです。
参考書の疑問点や補足の内容、大事な点を科目や分野ごとにノートにまとめて、すぐに見返せるようにしておきます。
付箋やインデックスを活用して、すぐに目的のページを開けるようにしておくのも良いでしょう。
自作したノートは自分にとって必要な情報がまとめられているので、復習しやすく知識が定着しやすいのがメリットです。
業務中にまとめたノートを確認したい方は、コンパクトなノートにまとめておくのがおすすめです。
特に血液検査の結果は、看護師として患者さんを受け持つ際に事前に確認しなければいけないデータです。
血液検査項目の意味や基準値は、事前にまとめておき、業務中もすぐに確認できるようにしましょう。
自宅でゆっくり確認したい場合は、パソコンで作成するのもおすすめです。
看護師におすすめの持ち歩きノートの詳細は、こちらの記事に記載しています。
看護師になってからやるべき基本の勉強内容とは
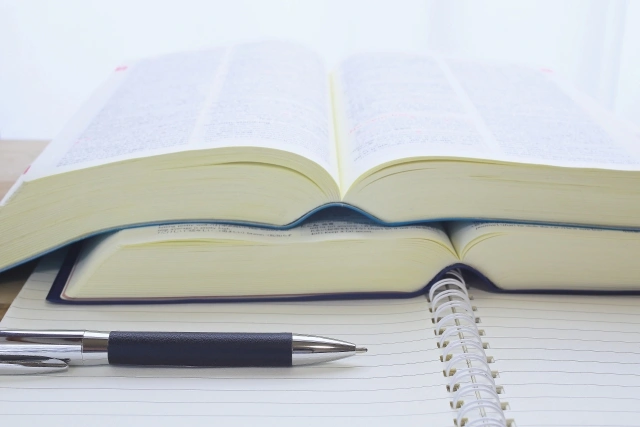
新人看護師は、何から勉強すれば良いのだろうと思う方もいるかもしれません。
看護師になってからやるべき基本の勉強内容は、その日の業務の復習と、新たに受け持つ患者さんの病態の予習です。
新人看護師は具体的にどのような勉強をする必要があるのか、解説します。
毎日の業務復習が勉強の基本
看護師の基本の勉強は、毎日の業務の復習です。
業務で経験したことや、実際に受け持った患者さんの病状はイメージができるため、定着しやすいでしょう。
業務で新しく教わったことや覚えたいこと、大事なことは、忘れずにメモしてください。
業務中は忙しく、殴り書きになってしまうことも多いかもしれませんが、メモした内容を忘れないように、なるべく当日中に復習を済ませるようにしましょう。
新たに受け持つ患者さんの予習
患者さんの病態を理解していれば、業務中にスムーズに対応できるため、新しく受け持つ患者さんの病態を予習しておきましょう。
新人看護師の頃は、次の日に受け持つ患者さんを把握しておき、事前に疾患や治療方法を勉強しておくと、学んだ知識を活用して業務を実施できます。
病状は学生時代に勉強したから予習は必要ない、という考えは危険です。
知識が抜けている場合もあり、最新の医療の情報を得ておく必要もあります。
新しく受け持つ患者さんがいるときは、事前にしっかりと患者さんの病態の知識を頭に入れておきましょう。
勤続年・キャリア別|看護師の勉強ポイントを紹介
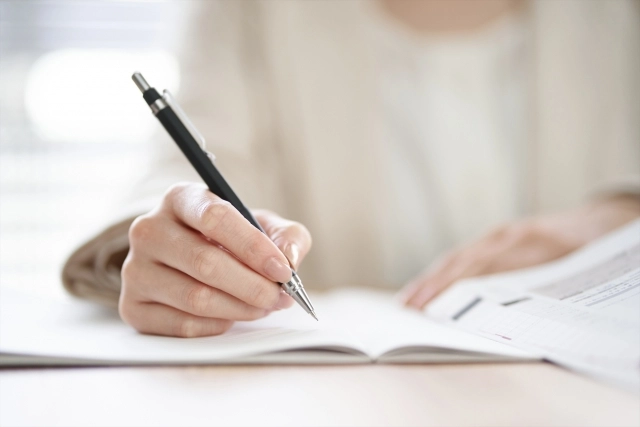
看護師の勉強ポイントは、次の3つの立場によって異なります。
- 新人看護師
- 5年目以降のベテラン看護師
- 休職明けでブランクのある看護師
勉強するうえで大事なポイントを、項目ごとに解説します。
1年目|新人看護師の勉強ポイント
1年目の新人看護師の勉強は、復習がメインになってくるでしょう。
疑問点を自分で解消できない場合は、先輩看護師に質問して解消する姿勢も大事です。
新人看護師の勉強で大切なポイントを解説します。
臨床の現場で日々新しく学んだことを復習する
1年目の新人看護師の勉強で特に大事なポイントは、現場で学んだ知識を覚えることです。
1年目の看護師は、業務の流れや先輩から教わった内容、患者さんの病態の知識など、多くのことを覚える必要があります。
一度経験したことや教わったことは確実に覚える心持ちで、メモを取ったり復習したりすることが大切です。
メモした内容は、忘れないうちに当日中にノートにまとめておきましょう。
理解できないことは先輩看護師に聞く
看護師として働いていると、「患者さんの薬剤の変更理由は?」「患者さんにとって適したケアの方法は?」など疑問点も多く出てきます。
疑問に感じた部分はメモをしておき、そのままにせずにインターネットや本で調べてみたり、わからなければ先輩看護師に聞いて解消していきましょう。
実施する医療行為や看護には、すべて根拠があります。
わからないまま仕事を進めてしまうと、重大なミスにつながる恐れもあります。
調べてもわからなかったため教えてほしいと素直に聞けば、親切に教えてくれる先輩もいるでしょう。
積極的に質問すれば、ほかの新人看護師への刺激になったり、先輩に意欲を認められたりするなどのメリットもあるかもしれません。
5年目以降|ベテラン看護師の勉強ポイント
5年以上経験を積むと「ベテラン看護師」と呼ばれる領域になってくるため、キャリアアップを見据えた勉強が必要です。
また、新人教育やリーダー業務を任される方も多いため、マネジメントの勉強も大事です。
ベテラン看護師の勉強ポイントを解説します。
キャリアアップを視野に入れた勉強
5年目以降のベテラン看護師は、キャリアアップを視野に入れて勉強していくことが大事です。
急性期病院や療養型病院、訪問看護など、看護師が働く領域は多岐に亘ります。
ご自身の看護師としてのキャリアの方向性を見つめ直し、関わりたい分野の資格を取得したり、転職して経験を積んだりするのも良いでしょう。
また、主任や師長などの管理職をめざしている方は、マネジメントの勉強もする必要があります。
マネジメントに興味がある方は、研修や勉強会に参加してみるのも良い方法の一つです。
リーダーシップスキルを磨く
ベテラン看護師は、リーダーシップスキルが求められることが多くあるでしょう。
看護部は組織が細分化していることが多いため、業務を円滑に進めるために現場をまとめるリーダーが必要です。
ある程度経験を積んだ看護師は、新人教育やリーダーを任されることも少なくないでしょう。
現場をまとめるには、看護師としての経験や知識だけでなく、コミュニケーション能力や判断力、問題解決スキルなどが求められます。
リーダーシップスキルを学べるセミナーや勉強会を受講できる機会があれば、参加してみるとスキルアップにつながるかもしれません。
休職明け|ブランクありの看護師の勉強ポイント
出産や子育てのために、看護師の職場を長期間離れる方もいるでしょう。
産休や育休明けに職場に復帰するときは、基本の復習が大切です。
ブランクがある看護師に必要な勉強のポイントを解説します。
一度基本からすべて復習する
ブランクのある看護師が職場に復帰する際は、一度基礎からすべて復習しておくのがおすすめです。
復習しておけば、職場に復帰してもスムーズに業務をこなせる可能性が高まります。
看護師としての基礎知識には、以下のようなものがあります。
- 基礎看護技術(採血、静脈注射、清潔ケアの技術など)
- 基本的な医療知識(検査データの見方、解剖生理の知識など)
- 勤務する診療科の疾患や治療、薬剤の知識
- 看護記録の作成方法
基本の知識はすべて復習し、場合によっては最新の医学の知識を勉強する必要があります。
書籍やインターネットで調べて、新しい知識を頭に入れておくことも大事です。
独学が難しいと感じる方は、ブランクがある方に向けた勉強会やセミナーに参加するのも良いでしょう。
例えば、都道府県ナースセンターでは、最新の医療知識や看護技術の研修を実施しています。
適宜情報を確認しておきましょう。
自分の不安要素を探る
基本を復習したら、不安に思っていることや知識があいまいな点を明確にして復習すると効率的です。
申し送りの流れやカルテの記録方法、点滴や採血の仕方、体位交換のやり方などの業務内容だけでなく、臨床の基本的な知識も忘れている内容があるでしょう。
疑問点や不安点を洗い出し、参考書で解決できることは自分で補います。
業務内容で不明点がある場合は、ほかの現役看護師に聞くのも良いかもしれません。
看護師の勉強時間の平均はどれくらい?

看護師は精神的にも体力的にもハードな仕事で、仕事が終わってから勉強したくてもなかなか難しい場合もあるかもしれません。
体力的に難しかったり、忙しくて勉強する暇がなかったりする場合は、隙間時間を見つけて効率的に勉強する姿勢が大切です。
無理なく取り入れられる勉強時間の目安としては、1日平均15~30分程度がおすすめです。
体力や時間に余裕のある方は、1~2時間程度まとめて勉強するのも良いでしょう。
勉強時間は、無理のない範囲で決めるのが大切です。
勉強する際の注意点
看護師の業務は忙しいため、勉強時間を確保するためには勉強の時間やタイミングをあらかじめ決めておいたり、休息時間を確保したりするなどの工夫が必要です。
勉強する際の注意点を解説します。
勉強する時間とタイミングを決めておく
帰宅後についダラダラしてしまい、なかなか勉強できない方は、勉強する時間とタイミングを決めておくのがおすすめです。
勉強を習慣化してしまえば、無理なく取り組める可能性が高くなるからです。
例えば、朝30分早く起きて勉強する、昼休憩の半分を勉強時間にする、歯磨きのあと15分は復習の時間にするなど、無理なくできる時間やタイミングを決めておきます。
習慣になれば、勉強時間を自然と確保できるでしょう。
睡眠や休息はきちんと取る
仕事や勉強が忙しくても、睡眠や休息はしっかりと取るようにしてください。
疲労が溜まっている状態で仕事をすると業務に集中できず、インシデントやアクシデントにつながってしまう恐れがあるからです。
また、疲れた状態で勉強しても知識が頭に定着しにくいでしょう。
睡眠や休息は、仕事や勉強をするうえで大切なものです。
休む時間を確保しながら勉強のスケジュールを立ててください。
看護師の勉強は隙間時間を活用した毎日の積み重ねが大切
新人看護師は覚えることがたくさんあり、心身ともに疲れ切ってしまうことも多々あるかもしれません。
退勤後に勉強時間を確保するのが難しい場合もあるでしょう。
しかし、疲れていても隙間時間を見つけて、その日の業務内容の復習を中心に勉強すれば、着実に勉強できます。
また、ベテラン看護師になるとキャリアアップも見据えて勉強していく必要があります。
自分に必要な勉強は何かを把握して、効率的に勉強を進めましょう。