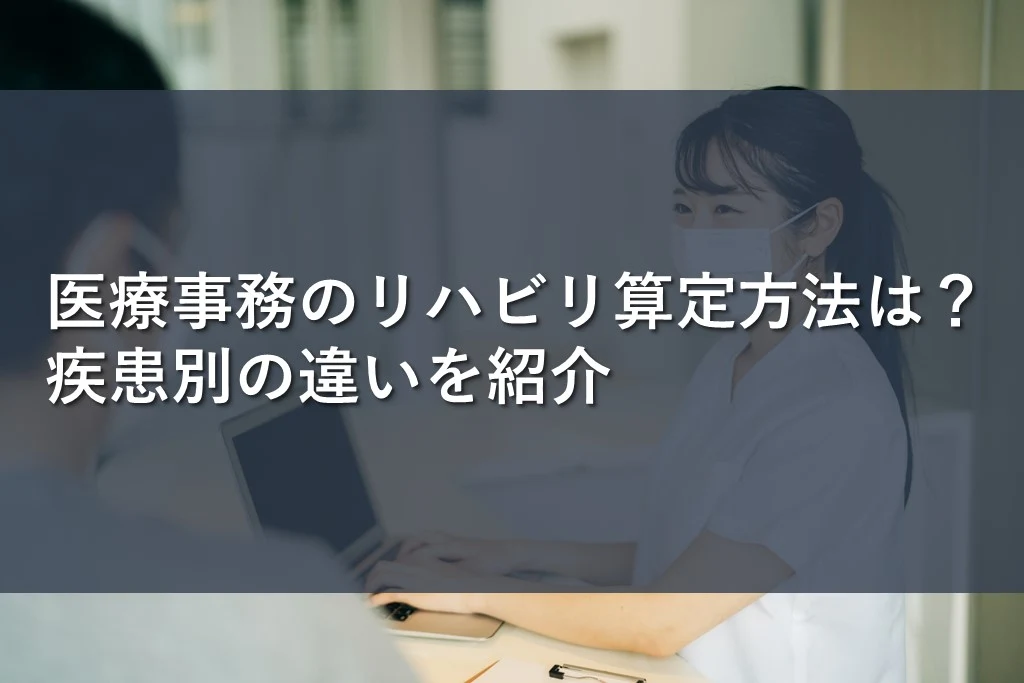
医療事務の仕事において、リハビリテーションの算定は重要な業務の一つです。
患者さんの健康回復を支援するリハビリテーションは、適切な算定によって初めて、その価値が正当に評価されます。
しかし、リハビリの算定方法は疾患によって異なり、さらに医療機関の規模や設備によっても変わってくるため、複雑で難しいものとなっています。
医療事務の会計担当者に向けて、リハビリテーションの算定方法について詳しく解説します。
目次
医療事務におけるリハビリ算定の基本

医療事務の現場で、リハビリテーションの算定は重要な業務の一つです。
患者さんの治療に直結するリハビリの正確な算定は、適切な医療サービスの提供と、医療機関の健全な運営に欠かせません。
リハビリ算定の基本を理解することで、スムーズな事務処理が可能になり、患者さんへのサービス向上にもつながります。
ここでは、リハビリ算定の基本となる単位と保険点数について解説していきます。
リハビリの単位
リハビリテーションの算定において、「単位」は非常に重要な概念です。
リハビリの単位は1単位20分と定められており、実際に実施した時間に基づいて単位数を算定します。
例えば、60分のリハビリを行った場合、算定するリハビリテーション料は3単位分です。
単位制度には、患者さんの状態や治療の必要性に応じて柔軟にリハビリ時間を設定できるメリットがあります。
また、リハビリは無制限に実施できるわけではなく、リハビリの種類ごとに1日や週で算定できる単位の上限が定められています。
医療事務の会計担当者は、単位制度を正確に理解し、適切な算定を行うことが必要です。
保険点数の計算方法
リハビリテーションの保険点数は、リハビリの種類ごとに定められています。
例えば、がんやその治療によって生じた疼痛や障害に対して、運動器や生活機能の低下予防・改善を目的に行う「がん患者リハビリテーション」は、1単位205点です。
つまり、3単位のリハビリを実施した場合、615点となります。
医療費は保険点数1点ごとに10円と設定されているため、60分(3単位)のリハビリを実施した場合、医療費の計算は以下のとおりです。
205点 × 3単位 × 10円 =6,150円
ただし、実際に患者さんが請求される自己負担額は年齢や収入によって異なります。
基本的には、6歳までと70~74歳までは2割負担、7〜69歳までは3割負担、75歳以上は1割負担です。
患者さんごとの支払金額は、この自己負担割合をかけて計算されます。
医療事務の会計担当者は、患者さんの年齢や保険の種類を確認し、正確な自己負担額を算出する必要があります。
医療費の計算を適切に行うことで、患者さんへの説明もスムーズになり、医療機関の信頼性向上につながるでしょう。
医療事務における疾患別のリハビリ算定
リハビリテーションの算定は、疾患の種類によって大きく異なります。
医療機関の規模や設備によっても算定方法が変わるため、会計担当者は幅広い知識が必要です。
ここでは、疾患別リハビリテーションの算定方法について解説します。
疾患別リハビリテーション料は施設基準によってⅠ~Ⅲに分類され、これによって保険点数が変わるので注意が必要です。
高度な設備や専門的なスタッフを有している「Ⅰ」が最も充実したリハビリテーションを提供できるため、点数も高く設定されています。
脳血管疾患等リハビリテーション料
脳血管疾患等リハビリテーション料は、脳卒中や脊髄損傷などの患者さんに対するリハビリテーションの算定に用いられます。
点数は施設基準によってⅠ~Ⅲに分けられており、それぞれ以下のように保険点数が異なります。
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 245点
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 200点
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 100点
例えば、リハビリを1時間受けた場合の総医療費(10割)は以下のとおりです。
- (Ⅰ)対象施設の場合:245点 × 3単位 × 10円 = 7,350円
- (Ⅱ)対象施設の場合:200点 × 3単位 × 10円 = 6,000円
- (Ⅲ)対象施設の場合:100点 × 3単位 × 10円 = 3,000円
このように、同じ3単位のリハビリを行っても、施設基準によって医療費に大きな差が生じます。
心大血管疾患等リハビリテーション料
心大血管疾患等リハビリテーションは、急性心筋梗塞や慢性心不全などの患者さんに対するリハビリテーションです。
心大血管疾患等リハビリテーションの施設基準は2種あり、以下の保険点数が定められています。
- 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 205点
- 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 125点
3単位のリハビリを受けた場合の総医療費(10割)を計算すると、以下のようになります。
- (Ⅰ)対象施設の場合:205点 × 3単位 × 10円 = 6,150円
- (Ⅱ)対象施設の場合:125点 × 3単位 × 10円 = 3,750円
運動器リハビリテーション料
運動器リハビリテーションは、骨折や関節疾患などの患者さんに対するリハビリテーションです。
運動器リハビリテーションの施設基準は3種あり、以下の保険点数が定められています。
- 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 185点
- 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 170点
- 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 85点
3単位のリハビリを受けた場合の総医療費(10割)を計算すると、以下のようになります。
- (Ⅰ)対象施設の場合:185点 × 3単位 × 10円 = 5,550円
- (Ⅱ)対象施設の場合:170点 × 3単位 × 10円 = 5,100円
- (Ⅲ)対象施設の場合:85点 × 3単位 × 10円 = 2,550円
呼吸器リハビリテーション料
呼吸器リハビリテーションは、肺炎や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患の患者さんに対するリハビリテーションです。
呼吸器リハビリテーションの施設基準は2種あり、以下の保険点数が定められています。
- 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 175点
- 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 85点
3単位のリハビリを受けた場合の総医療費(10割)を計算すると、以下のようになります。
- (Ⅰ)対象施設の場合:175点 × 3単位 × 10円 = 5,250円
- (Ⅱ)対象施設の場合:85点 × 3単位 × 10円 = 2,550円
廃用症候群リハビリテーション料
廃用症候群リハビリテーションは、長期の安静や入院によって身体機能が低下した患者さんに対するリハビリテーションです。
廃用症候群リハビリテーションの施設基準は3種類あり、以下の保険点数が定められています。
- 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 180点
- 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 146点
- 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 77点
3単位のリハビリを受けた場合の総医療費(10割)を計算すると、以下のようになります。
- (Ⅰ)の場合:180点 × 3単位 × 10円 = 5,400円
- (Ⅱ)の場合:146点 × 3単位 × 10円 = 4,380円
- (Ⅲ)の場合:77点 × 3単位 × 10円 = 2,310円
リハビリ上限を超えて算定することは可能か
疾患別リハビリテーションでは、種類ごとに算定できる日数(標準算定日数)が定められています。各疾患別リハビリテーションの標準算定日数は以下のとおりです。
- 脳血管疾患等リハビリテーション:180日
- 心大血管疾患等リハビリテーション:150日
- 運動器リハビリテーション:150日
- 呼吸器リハビリテーション:90日
- 廃用症候群リハビリテーション:120日
ただし、厚生労働省が定める患者で、治療を継続することで状態の改善が期待できると医学的に判断された場合は、標準算定日数を超えても月に13単位に限り算定可能です。
また、入院中の要介護被保険者が標準算定日数を超えた場合は、脳血管疾患リハビリテーション、運動器リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーションは月に13単位まで追加で算定できます。
ただし、その場合は通常時とは保険点数が異なるため注意が必要です。
で
このような制度は、患者さんの状況に応じた医療サービスの提供を可能にする一方で、医療費の適正化を図る目的もあります。
医療事務の会計担当者にはこれらの規定を十分に理解し、適切な算定が求められます。
医療事務のリハビリ算定は施設規模や種類で変わる
医療事務におけるリハビリテーションの算定は、単純ではありません。
施設基準や患者さんの状態、リハビリの種類などによって算定方法が異なります。
さらに、リハビリの単位数や1日の上限、週の上限なども考慮しなければなりません。
患者さんの年齢や保険の種類によって自己負担割合も変わるため、最終的な請求額の計算には細心の注意が必要です。
医療事務の会計担当者は、これらの複雑な規定を正確に理解し、適切な算定が求められます。
正確な算定は、患者さんへの適切な医療サービスの提供と、医療機関の健全な運営の両立につながります。
常に最新の制度を把握し、正確な事務処理を心がけることが、医療事務の専門家として強く求められているのです。







