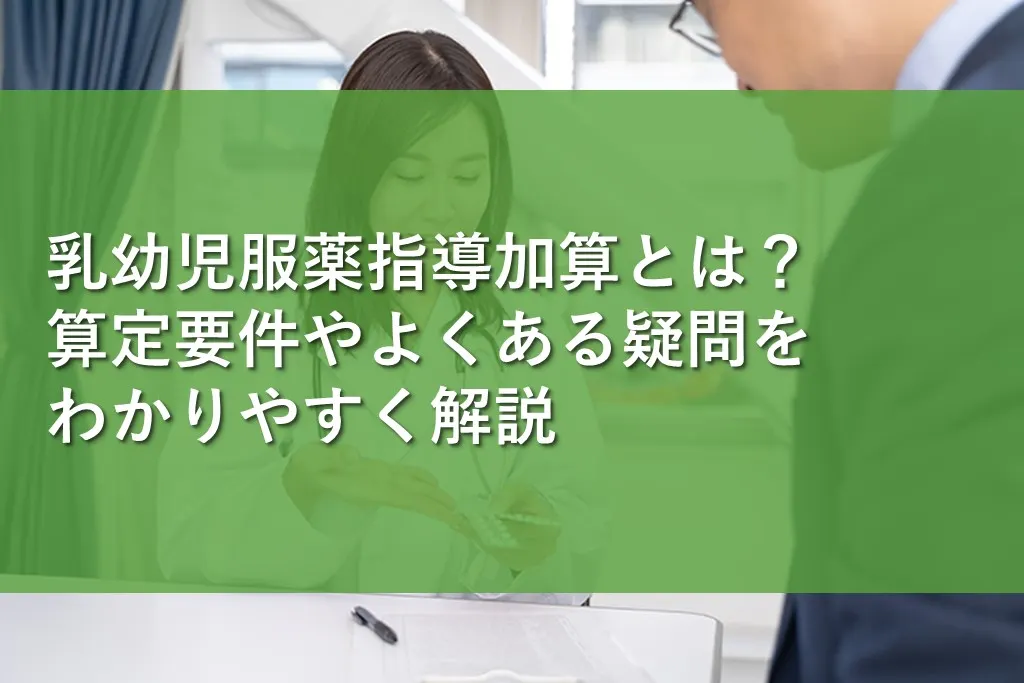
調剤薬局で働いている薬剤師が、6歳未満の患者さんに対して調剤し、要件を満たした服薬指導を行うと、乳幼児服薬指導加算を算定することが可能です。
内服薬の飲み方や保管方法の注意点、薬を飲ませやすくするためのアドバイスなどが服薬指導にあたりますが、実際に薬を出すとき「これは服薬指導加算される?」「内服薬以外は該当しない?」など、判断がつきにくく悩む薬剤師もいるでしょう。
今回は、調剤薬局で乳幼児に対応するとき、服薬指導加算の対象となるケースの具体例や、実際に服薬指導する際に役立つ例文を詳しく解説します。
目次
乳幼児服薬指導加算とは?

調剤薬局の薬剤師が、患者さんへ薬を渡すときに行う服薬指導には服薬管理指導料が発生し、点数が加算されます。
患者さんが6歳未満の乳幼児だった場合、患者さん本人の服薬管理は難しいため、付き添いのご家族や保護者に対し、服薬管理指導を行わなければなりません。
6歳未満の乳幼児に代わり、服薬管理を行う方へ服薬指導する行為を乳幼児服薬指導といい、乳幼児服薬指導加算として12点を追加で算定できます。
厚生労働省の資料では、以下のとおり明示されています。
6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する。
出典:厚生労働省 別表第三調剤報酬点数表
つまり、6歳未満の乳幼児が安全に服用できるよう、ご家族や保護者に必要な情報を伝えて指導し、詳細をお薬手帳や薬歴に記載することが、乳幼児服薬指導加算の対象です。
服薬指導に関する情報は、以下のページで詳しく解説しています。
ぜひご参照ください。
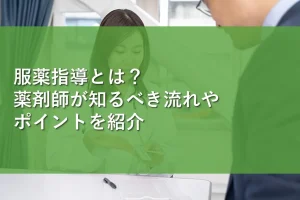
乳幼児服薬指導加算の算定要件
乳幼児服薬指導加算は、以下の要件を満たした場合に算定可能です。
- 6歳未満の乳幼児や家族等に必要事項の確認や服薬指導を行う
- 問い合わせがあった場合に指導など対応し、記録する
- 要点を薬歴や手帳に記載する
詳細を以下で解説します。
6歳未満の乳幼児や家族等に必要事項の確認や服薬指導を行う
厚生労働省は、乳幼児服薬指導加算の算定要件として、患者さんのご家族や保護者に確認・指導するべき内容を、次のように提示しています。
(1) 乳幼児服薬指導加算は、乳幼児に係る処方箋の受付の際に、年齢、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、
誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。
出典:厚生労働省 別添3調剤報酬点数表に関する事項
乳幼児の年齢・体重は、薬の用量を間違えないために欠かせない情報です。
年齢・体重を事前に尋ねておくと、患者さんに適した薬が処方されているか確認できます。
また、初めて飲む薬か、使用する薬の剤形(錠剤・シロップ・粉薬など)に慣れているかを知っておけば、より的確な服薬指導が可能です。
特に、初めて服用する薬や今まで出されたことがない剤形の薬は、乳幼児が嫌がったり誤飲させたりする可能性があるので、指導漏れがないよう事前によく確認して指導しましょう。
問い合わせがあった場合に指導など対応し、記録する
薬の服用期間中に、乳幼児のご家族や保護者から問い合わせがあったとき、疑問や悩みに合わせて指導を行うケースも算定要件の一つです。
ただし、ただ指導したりアドバイスしたりするだけでは、乳幼児服薬指導加算の算定要件を満たせません。
厚生労働省の資料では、以下のとおり明示されています。
(2) 乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から 電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応および指導等を行うとともに、その要点について、薬剤服用歴等に記載すること。
出典:厚生労働省 別添3調剤報酬点数表に関する事項
つまり、乳幼児のご家族や保護者から問い合わせを受けて指導した場合、要点を薬歴に記載しなければ、要件を満たせません。
また、問い合わせはあくまでご家族・保護者から任意で寄せられた場合のみで、調剤薬局側からの能動的な連絡は該当しないため注意しましょう。
要点を薬歴や手帳に記載する
調剤薬局で薬を渡す際に丁寧に指導したり、電話・メールによる問い合わせに対応したりしても、指導内容の要点を薬歴やお薬手帳に記載しなければ、乳幼児服薬指導加算の要件を満たしません。
厚生労働省も、下記のとおり要点の記載を指示しています。
(3)(1)における確認内容および指導の要点について、薬剤服用歴等及び手帳に記載する。
出典:厚生労働省 別添3調剤報酬点数表に関する事項
実際に、乳幼児の身長・体重を確認したにも関わらず記載しなかったり、服薬指導の要点を記録していないケースもありました。
乳幼児服薬指導加算は、情報の確認・服薬指導(問い合わせ対応も含む)・要点記載の3点を満たすと12点加算されます。
漏れがないよう、注意しながら業務を行いましょう。
乳幼児服薬指導加算のコメント・アドバイス例文
乳幼児の服薬指導で伝えるべき内容は、服薬方法や保管の仕方、飲ませやすくするためのアドバイスなどです。
乳幼児服薬指導のコメントやアドバイスは、例文を頭に入れておくとスムーズに伝えられます。
乳幼児服薬指導で使える、コメント・アドバイスの例文を以下でご紹介します。
服薬方法
服薬方法では、乳幼児が嫌がらずに薬を飲む方法や、具体的な飲ませ方を伝えると良いでしょう。
例文は以下のとおりです。
タイミングが多少ずれても良いので、お子さんのご機嫌を伺いながら飲ませてください。
組み合わせる食べ物・飲み物によっては、薬の効果が強くなったり、弱くなったりする可能性があります。
組み合わせを避けるべき食品名と一緒に、スムーズに薬を飲ませるためにおすすめの食品名も伝えると良いでしょう。
保管の仕方
処方された薬の保管の仕方も、薬剤師が伝えるべき項目です。
詳しい保管方法を伝えておけば、誤飲やいたずらも防ぎやすくなります。
下記の例文を参考に、上手な保管方法のアドバイスをしてみましょう。
ご兄弟の薬と間違えないよう、名前を書いた袋に入れて、お子さんが触れない場所に保管してください。
お子さんの手が届かない場所に保管して、薬を飲みすぎないよう注意してください。
乳幼児服薬指導加算に関するよくある疑問

乳幼児服薬指導加算の要件を理解していても、実際に業務を行っていると、次の疑問を持つケースが良くみられます。
- お薬手帳を忘れた患者さんも算定できる?
- 内服薬以外には算定できない?
それぞれの疑問に対する回答を、以下で解説します。
お薬手帳を忘れた患者さんも算定できる?
患者さんがお薬手帳を忘れていても、必要な情報を聞き取り服薬指導したあと、処方された薬を記載したシール等を交付すれば算定可能です。
交付されたシールは、持ち帰った患者さんに自分でお薬手帳に貼ってもらいます。
交付したシールがきちんと貼られているかどうか、次に来局したときに確認しましょう。
もともとお薬手帳を持っていない患者さんの場合、手帳を交付すれば算定可能です。
処方された薬の内容や注意点を繰り返し確認できるという、お薬手帳のメリットを患者さんに伝え、発行を勧めると良いでしょう。
内服薬以外には算定できない?
服薬と明示されているため、外用薬のみの処方箋では乳幼児服薬指導加算を算定できないこともあります。
しかし、社会保険や国民健康保険、各都道府県の支払基金によっても判断が分かれることは否定できません。
ただし、乳幼児服薬指導は、薬剤師が薬の正しい使用方法を伝え、誤飲を防止する目的があるため、必要な指導を行った場合は内用薬・外用薬を問わず薬歴やお薬手帳に記録しておきましょう。
大切なのは、必要な情報を伝え正しい使用方法を指導することです。
たとえ、丁寧な言葉遣いで長々と説明しても、伝えるべき内容からそれてしまうと適切な服薬指導とはなりません。
何を伝え何をアドバイスするべきか見極め、患者さんにとって必要な事柄をわかりやすく伝えましょう。
乳幼児服薬指導加算を算定できる条件を把握しよう
乳幼児服薬指導加算は、6歳未満の乳幼児に薬が処方されたとき、乳幼児本人やご家族・保護者に対し、薬の正しい使い方を指導した場合に加算されます。
算定するためには、次の3点の要件を満たさなければなりません。
- 患者さんの情報確認と服薬指導
- 問い合わせへの対応や記録
- 指導内容の要点をお薬手帳や薬剤服用歴へ記載する
服用中に患者さんのご家族から問い合わせがあった場合も、指導を行い要点をお薬手帳や薬剤服用歴に記載すれば、算定条件を満たします。
乳幼児服薬指導加算の算定条件を確認し、やるべき内容に見落としがないよう、注意して業務に従事しましょう。







