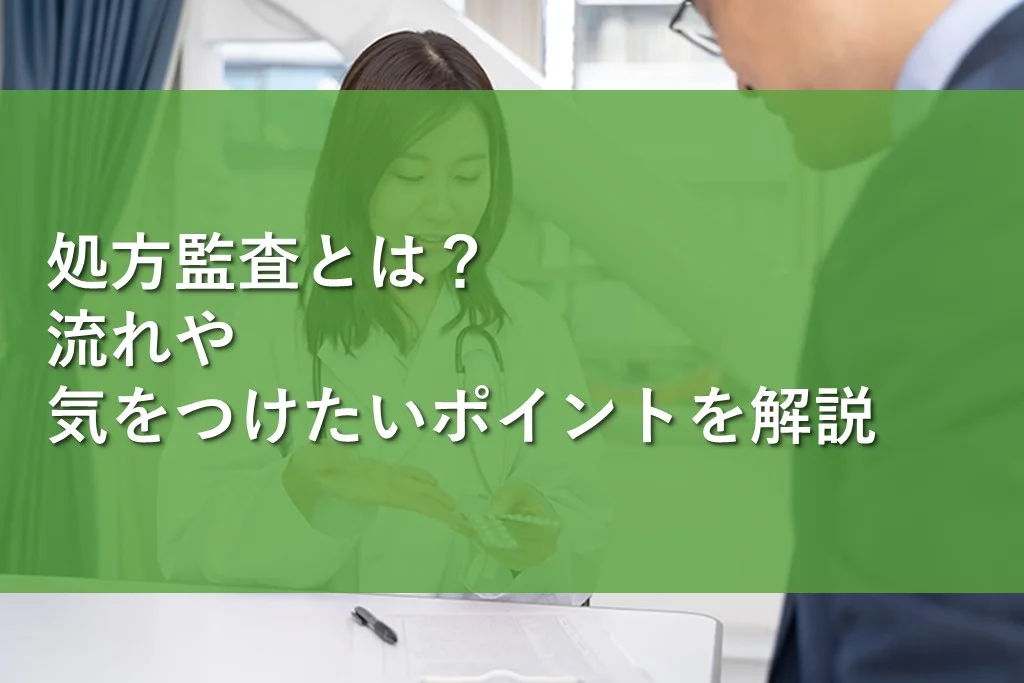
処方監査は、薬剤師の重要な業務の一つです。
患者さんの安全を守り、適切な薬物療法を提供するために欠かせない役割を果たしています。
本記事では、処方監査の定義や流れ、注意すべきポイントについて詳しく解説します。
薬剤師の方はもちろん、医療関係者の方や患者さんにとっても参考になる情報となるので、ぜひ最後までお読みください。
目次
処方監査とは

処方監査は、薬剤師法第24条の「薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師または獣医師に問い合わせて、その疑わしい点
を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない」という義務を果たすために必要な行為です。
具体的には、処方せんに記載された薬やその投与量を確認し、薬物療法に問題がないかどうかを薬剤師が確認する作業を指します。
この作業は、患者さんの安全を守るための最初の砦です。
薬剤師は専門的な知識と経験を活かし、処方内容が適切かどうかを慎重に確認する必要があります。
処方監査の流れ
処方監査は、医師から発行された処方せんを、調剤薬局で受け付けた時点から始まります。
処方監査の具体的な流れについて、順を追って見ていきましょう。
情報収集する
処方監査の最初のステップは、患者さんに関する情報の収集です。
主な情報源としては、お薬手帳、初回質問票、薬歴などです。
情報源から、患者さんの基本情報、既往歴、現在服用中の薬剤、アレルギー歴などだけでなく、過去の処方内容や副作用の有無などについても総合的な患者情報として収集します。
この情報に基づいて、処方内容の確認や疑義照会の判断が行われるため情報収集は慎重かつ丁寧に行う必要があります。
記載事項を確認する(形式的疑義照会確認事項)
情報収集の次のステップは、処方せんに記載された内容の確認です。
これは形式的疑義照会確認事項と呼ばれ、処方せんの体裁や必要事項が正しく記載されているかどうかをチェックします。
具体的なチェック項目は以下のとおりです。
- 処方年月日、患者氏名、性別、年齢などの基本情報
- 薬剤の規格や用法・用量の記載漏れの確認
- 処方せんの正規性(正規の処方せんかどうか)
- 販売中止品目や名称変更品目の有無
- 投与制限や処方制限の超過がないか
これらの記載によって、処方せんの形式的な正確性が担保されます。
内容に問題がある場合には、薬剤師は医療機関に確認を取る必要があります。
記載事項を確認する(薬学的疑義照会確認事項)
形式的な確認に続いて、薬学的な観点から処方内容を精査します。
これは薬学的疑義照会確認事項と呼ばれ、より専門的な知識を要する重要な過程です。
主なチェックポイントは以下のとおりです。
- 用量・用法が患者さんの体質に適しているか
- 副作用や薬物アレルギーのリスクはないか
- 必要な薬剤がすべて処方されているか
- 用法・用量、剤型、規格は適切か
- 休薬期間や定期的検査が必要な医薬品ではないか
- 重複投与、相互作用、配合変化のリスクはないか
これらの項目を確認し、処方内容が安全で適切な薬物療法が実施されているかどうかを検証します。
疑問点がある場合は、次のステップである疑義照会が必要になります。
疑義照会を行う
処方内容に疑問や不明点がある場合、薬剤師は医師に疑義照会を行います。
これは患者さんの安全を守るために非常に重要な手続きです。
疑義照会は、わずかな疑問でも行うべきとされます。
「たぶん大丈夫だろう」という予測的な判断は避け、確実な情報を得ることが必要です。
令和5年5月26日付の日本薬剤師会の調査によると、保険薬局では応需処方せんのうち2.1%で疑義照会を行っています。
そのうち95.0%が薬学的な疑義照会です。
また、薬学的疑義照会を実施したうちの83.8%は薬剤師の提案等により処方変更が行われています。
この数字をみても、疑義照会が患者さんの安全と適切な薬物療法に大きく貢献していることがわかります。
処方監査の主な課題とヒヤリ・ハット事例
処方監査は非常に重要な業務ですが、同時にいくつかの課題も抱えています。
実際に医療現場ではさまざまなヒヤリ・ハットが発生しているとの報告もあります。
これらを知れば、日々の処方監査実施に役に立つでしょう。
処方監査の主な課題
処方監査には以下のような課題があると言われています。
- 新人薬剤師のリスク:経験不足から事故を起こしやすい
- 医療現場の複雑性:さまざまな要因がヒューマンエラーを誘発する
- 時間的制約:丁寧な確認には時間がかかり患者さんを長時間待たせる場合が発生する
- 集中力の維持:長時間の作業で集中力が低下する
- 薬剤師の多忙:薬剤師の役割が多様化し業務量が増して時間がとりにくい
これらの課題には、システムの改善や継続的な教育などの対策が必要です。
そして薬剤師同士が互いにサポートできる体制の構築も課題となっています。
処方監査のヒヤリ・ハット事例
処方監査に関するヒヤリ・ハット事例は、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業によって収集されています。
これらの事例は、同事業のホームページの「事例検索」で公表され、誰でも閲覧が可能です。
2024年に収集されたヒヤリ・ハット事例の一部を紹介します。
・新型コロナウイルス感染症の20歳代の女性患者にゾコーバ錠125mgが処方された。 患者に妊娠または妊娠している可能性について確認したところ、月経が予定日より 遅れており、妊娠の可能性があることを聴取した。処方医に疑義照会を行った結果、 薬剤が削除になった。
・患者にゾコーバ錠125mgが処方された。患者はゾコーバ錠125mgと併用禁忌のラツーダ錠40mgを服用しているため、薬剤師は処方医に疑義照会を行った。処方医によると、患者から併用薬はないと診察時に聞いた、とのことであった。疑義照会の結果、ゾコーバ錠125mgがラゲブリオカプセル200mgへ変更となった。
・施設に入所中の患者にラゲブリオカプセル200mgが処方された。薬剤師は、施設職員から患者に他の医療機関からパキロビッドパックが処方されていることを聴取した。薬剤師がラゲブリオカプセル200mgを処方した医師に疑義照会を行い、削除となった。
・患者にパキロビッドパック300が処方された。薬剤師は患者から腎機能障害がないことを聴取した。パキロビッドパック300は中程度の腎機能障害患者に投与するため、処方医
に疑義照会を行った結果、パキロビッドパック600に変更となった。・90歳代の患者にラゲブリオカプセル200mgが処方された。患者は今まで嚥下困難はなかったが、交付の翌日、カプセルが大きくて飲み込めないと薬局に相談があった。製薬
企業が提供しているデータを見て、脱カプセル後に懸濁して服用させても薬剤の吸収に問題はないと判断した薬剤師は、処方医に情報提供を行った。協議の結果、カプセルを外し水に懸濁した直後に服用することとなった。薬剤師は、懸濁後2時間以降のデータはないこと、懸濁せずに粉末を服用した場合のデータはないこと、妊婦への曝露に注意する必要があることについて患者に説明した。・18歳未満の患者にラゲブリオカプセル200mgが処方された。ラゲブリオカプセル200mgは18歳以上が対象であるため、薬剤師は処方医に疑義照会を行った。ラゲブリオカプセル200mgからゾコーバ錠125mgに変更となった。
引用:経口新型コロナウイルス感染症治療薬に関する事例 <疑義照会や処方医への情報提供に関する
また、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のWebサイトでもヒヤリ・ハット事例が共有されています。
薬剤師は常に発信されるヒヤリ・ハット事例を確認し、日々の処方監査業務を実施しなければなりません。
処方監査を行うときのポイント

処方監査は、患者さんの命に関わる重要な業務です。
見逃しや誤りは重大な結果を招く可能性があります。ここでは、処方監査を行う際に押さえておくべき重要なポイントをいくつか紹介します。
知識をアップデートしておく
医薬品に関する情報は日々更新されています。
知識をアップデートするために、日常的に最新の情報を把握しておきましょう。
具体的には以下のような情報源が活用できます。
- PMDAが発信する副作用情報
- 薬の飲み合わせチェックサイト
- 医薬品メーカーの新製品情報
また、学会や研修会への参加も、知識のアップデートに役に立ちます。
ヒヤリ・ハット事例を参考にする
前述のとおり、公表されているヒヤリ・ハット事例は、貴重な学びの材料となります。
これらの事例を詳しく分析し、どのような状況でミスが起こりやすいのか、どうすれば防げたのかを考察しておきましょう。
また、自分の職場で発生したヒヤリ・ハットについても、オープンに話し合い、再発防止策を検討する必要があります。
スピードを意識しすぎない
ヒヤリ・ハット事例のなかには、「焦っていた」というケースが多くあります。
患者さんを長時間待たせたくないという気持ちのあまり、重大なミスを犯してしまっては本末転倒です。
「待たせている」と焦る気持ちがわいてくるときは「患者さんの安全のために間違いない仕事をしよう」と考え、自分の仕事に向き合うことが大切です。
薬剤師の処方監査に必要なのはスピードではありません。
職責を果たすには、何が大切なのかを忘れないでください。
あいまいな点は自己判断せず確認する
処方監査中に疑問点や不明点が生じた場合「大丈夫だろう」とあいまいなまま自己判断してはいけません。
必ず、きちんと確認するようにしましょう。
「ミスがあるかもしれない」という意識を常に持って、慎重に対応してください。
自分で確信をもって判断できないときは、先輩薬剤師や処方した医師に確認を取ります。小さな行動が、大きな医療事故を防ぐことにつながるのです。
コミュニケーションを大切にする
患者さんやそのご家族とのコミュニケーションも、処方監査の質を高めます。
患者さん自身の気付きやご家族からの情報提供から、処方の問題点が明らかになることも多いものです。
薬剤師は話しやすい雰囲気を作り、患者さんの声に耳を傾けましょう。
より安全で効果的な薬物療法を提供するため、医師や他の医療スタッフとのコミュニケーションも大切にし、チーム医療の一員としての役割を果たしましょう。
処方監査と調剤鑑査の違いは?
処方監査について理解を深める中で、似た用語との違いも把握しておきましょう
特に「調剤鑑査」は、処方監査と混同されやすいので、注意が必要です。
処方監査は、調剤を行う前に処方せんの内容が正しいかどうかを確認します。
主に処方せんの記載について適切かどうかを監査します。
一方、調剤鑑査は調剤後に行う作業です。
薬剤が処方せんどおりに正しく調剤されているか、数量や薬剤の種類に間違いがないかを確認します。
処方監査は「調剤前」、調剤鑑査は「調剤後」と理解するとわかりやすいでしょう。
ともに、患者さんの安全を守るために欠かせないことに変わりはありません。
処方監査のポイントを理解して患者さんに安全な薬物療法を提供しよう
処方監査は、薬剤師の専門性を最大限に発揮する必要のある業務であり、患者さんの安全を守り、適切な薬物療法を提供するために欠かせません。
処方監査にはさまざまな手順とチェックポイントがあります。
場合によっては処方監査には時間がかかります。
プレッシャーを感じることもあるかもしれませんが、患者さんの命と健康を守る重要な役割を果たしていることを忘れずに、落ち着いて確実に実施しましょう。
本記事で紹介したポイントを意識し、より安全で効果的な薬物療法が実施できるよう薬剤師の職責を果たしましょう。







