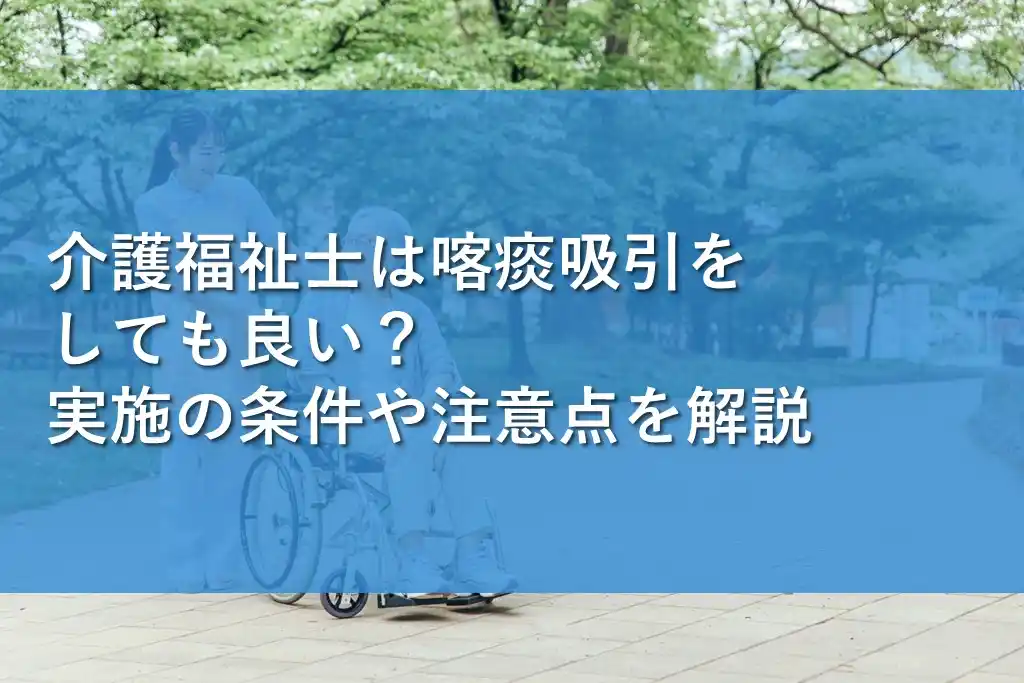
医療行為の一つである喀痰吸引。
高齢者や障がい者など、自力で出すことが難しい人の痰を吸い出す行為です。
従来は看護師や医師のみが実施できる行為でしたが、現在では一定の条件をクリアした介護福祉士にも実施が認められています。
今回は、介護福祉士および介護職員等の喀痰吸引の実施について、その条件や研修内容、注意点を解説します。
これから介護福祉士をめざす人や、現在介護福祉士として勤務している人は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
目次
介護福祉士が喀痰吸引できる「喀痰吸引等制度」

喀痰吸引は医療行為であり、平成23年度までは介護福祉士による実施は許可されていませんでした。
しかし、現場でのニーズを踏まえ、平成24年度に「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部が改正され、「喀痰吸引等制度」が設けられました。
以下に、制度の詳細を解説します。
実施可能な行為
喀痰吸引等制度により許可された行為は、喀痰吸引と経管栄養です。
介護対象者が日常生活を送るのに必要な行為であって、医師の指示の下であれば、介護職員等による実施が許可されています。
喀痰吸引については、口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部の吸引が実施可能な行為として定められました。
介護職員等の範囲
喀痰吸引等制度における「介護職員等」は、介護福祉士の資格を持つ者、あるいは一定の研修を修了し、都道府県知事に認定された介護職員などをさします。
なお、介護福祉士有資格者は、カリキュラムのなかで喀痰吸引・経管栄養の研修を受けた、平成27年度以降に資格を取得した方に限られます。
介護福祉士が喀痰吸引を行うための条件
介護福祉士が喀痰吸引を行うには、二つの条件をクリアする必要があります。
医療的ケア実地研修を受けた介護職員であること
一つ目の条件は、喀痰吸引等研修を受けることです。
研修を受け、喀痰吸引等の業務の登録認定を受けた介護職員等は、認定特定行為業務従事者とよばれます。
平成27年以降に国家試験に合格した介護福祉士の場合は、カリキュラムに研修が組み込まれているため、国家試験の合格をもって喀痰吸引の実施が許可されることになります。
しかし、平成27年以前に国家試験に合格した介護福祉士の場合は、あらためて喀痰吸引等研修を受けなければなりません。
事業者が「登録喀痰吸引等事業者」であること
二つ目の条件は、介護福祉士や介護職員等が所属する事業者が登録喀痰吸引等事業者であることです。
都道府県知事へ届け出をし、許可された施設のみが登録喀痰吸引等事業者として認定されます。
認定には、医師、看護職員らの医療関係者との連携確保のほか、安全かつ適正に実施するための措置がなされていることが必要です。
喀痰吸引等研修とは

ここからは、喀痰吸引等研修を詳しく解説します。
基本研修と実地研修がある
喀痰吸引等研修は、基本研修と実地研修に分かれます。
基本研修では50時間にわたる講義のあと、喀痰吸引および経管栄養の演習を行います。
喀痰吸引の演習では、口腔・鼻腔・気管カニューレ内部それぞれに対し5回以上の演習が義務付けられており、演習終了後には筆記試験とプロセス評価が実施されます。
また、実地研修は、実際の施設や在宅などにおける利用者へのケアを通して行われ、口腔吸引は10回以上、鼻腔および気管カニューレ内部の吸引は20回以上の実施が必要です。
その後、基本研修と同様にプロセス評価が実施され、認定特定行為業務従事者の認定が行われます。
実施行為・対象者により第1~3号研修に分かれている
喀痰吸引等研修は、実施行為と対象者により、第1~3号研修に分けられています。
それぞれに許可された実施行為、対象者は次のとおりです。
- 第1号研修:不特定多数の利用者に対し、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の吸引が実施できる
- 第2号研修:不特定多数の利用者に対し、口腔内・鼻腔内のみの吸引が実施できる
- 第3号研修:在宅療養中の重度障がい者など、特定の利用者を対象とし、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の吸引が実施できる
介護福祉士が喀痰吸引を行う際の注意点
認定特定行為業務従事者に認定されたあとは、実際に現場で喀痰吸引を実施していくことになります。
安全に医療行為を行うためには、次のような注意点を守ることが求められるでしょう。
観察を念入りに行う
喀痰吸引の実施前・中・後には、利用者の状態を注意深く観察することが重要です。
喀痰吸引は、医師や看護師とともに事前に作成した基準に従ったタイミングで行います。
実施前後に気管カニューレ内部に出血が見られる場合や、呼吸困難感を認める場合、顔色が悪い場合など、異常時には速やかに医師あるいは看護師に報告しましょう。
また、食後すぐに吸引を実施すると刺激により嘔吐が誘発されることがあるため、そのような場合は避けるなどタイミングの考慮も大切です。
カテーテルを無理に押し込まない
利用者の鼻腔の構造によっては、吸引カテーテルを挿入しにくいこともあります。
その際、無理やりカテーテルを押し込んでしまうと、粘膜を傷つけ出血を起こしてしまうことがあるため注意しましょう。
挿入が難しいと感じる場合には、看護職員などへの相談をおすすめします。
口腔内吸引の場合、刺激を避ける
口腔内吸引を実施する際、口蓋垂や咽頭など奥のほうを刺激すると、嘔吐反射が起こってしまうおそれがあります。
嘔吐による誤嚥を防ぐためにも、カテーテルの挿入は痰が貯留しやすい部位に留めましょう。
一般的に口腔内で痰が貯留しやすい部位は、奥歯と頬の内側の間や舌の上下、前歯と口唇の間です。
気管カニューレの吸引に、口鼻腔吸引で使用したカテーテルを使ってはいけない
気管カニューレ内は無菌状態であるため、気管カニューレ内部の吸引する際に、口鼻腔吸引に使用したカテーテルを使ってはなりません。
カテーテルは、気管と口鼻腔で分けて使用しましょう。
条件をクリアした介護福祉士であれば喀痰吸引を行える

今回は、介護福祉士および介護職員等による喀痰吸引の実施に関して、制度や研修などを解説しました。
介護福祉士および介護職員等は、決められた研修を受け、認定特定行為業務従事者として認められた場合にのみ喀痰吸引の実施が許可されます。
喀痰吸引はリスクをともなう医療行為ですので、正しい知識に基づいて安全に実施していきましょう。






