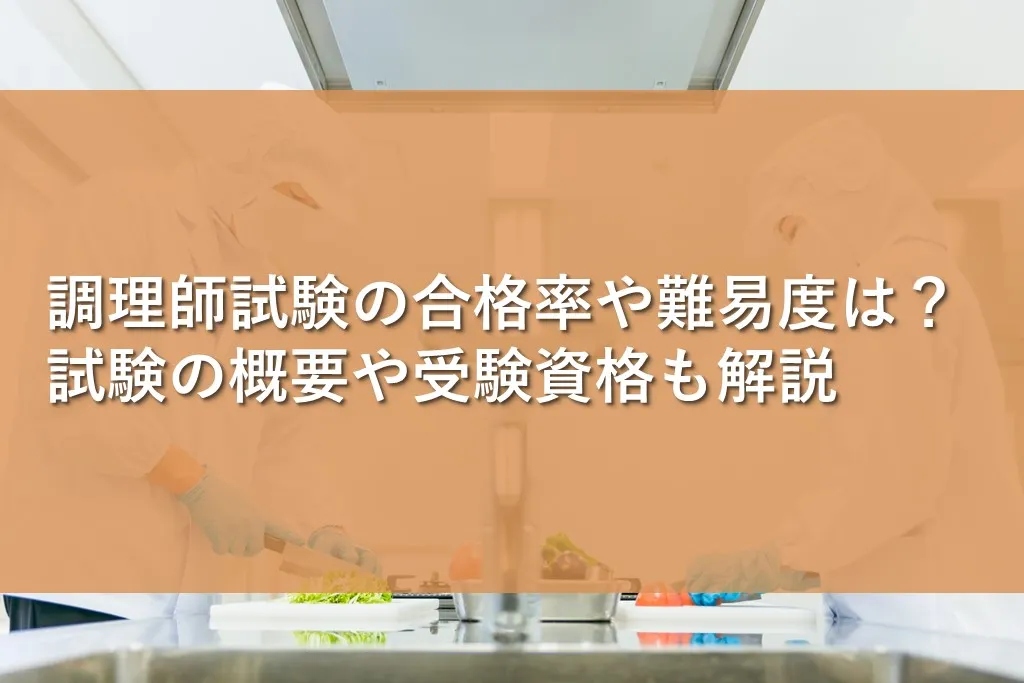
調理師試験の受験を検討している方は、調理師試験の合格率はどれくらいなのか、気になるのではないでしょうか。
また、試験の概要や流れ、勉強方法についても把握しておきたいと考える方も多いでしょう。
そこで、この記事では、調理師試験の都道府県ごとの合格率や合格点、試験の概要・流れ、受験資格、調理師の仕事内容、勉強方法などを解説します。
調理師という職業が気になっている学生や社会人は、参考にしてください。
目次
調理師試験の合格率や難易度
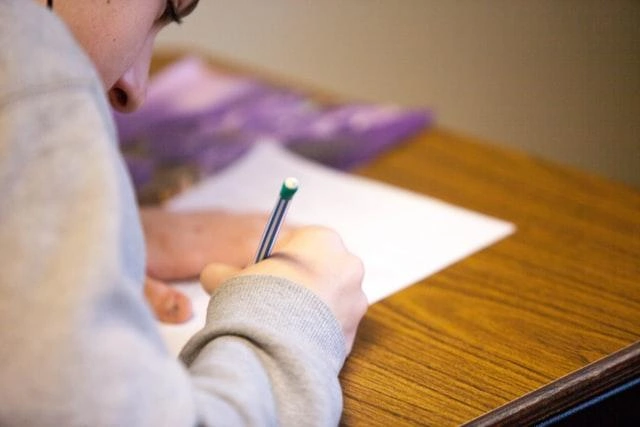
調理師試験は、都道府県ごとに試験問題が異なるので、合格率も都道府県によって差があります。
まずは、調理師試験の都道府県ごとの合格率や、合格の目安となるボーダーライン、試験の難易度について見ていきましょう。
東京や神奈川、千葉など都道府県別の合格率
調理師試験は、都道府県ごとに実施され、合格率は都道府県によって異なります。
令和3年を見ると、合格率の全国平均は約65%です。
また、過去3年間の合格率は、全国平均で65~70%程度でした。
実際に、各都道府県の合格率を確認してみましょう。
令和3年の都道府県別の調理師試験合格率
| 都道府県 | 合格率(%) |
| 北海道 | 60.7 |
| 青森 | 60.4 |
| 岩手 | 53.5 |
| 宮城 | 66.4 |
| 秋田 | 58.0 |
| 山形 | 64.8 |
| 福島 | 55.0 |
| 茨城 | 65.1 |
| 栃木 | 71.7 |
| 群馬 | 86.8 |
| 埼玉 | 71.6 |
| 千葉 | 63.7 |
| 東京 | 70.5 |
| 神奈川 | 83.0 |
| 新潟 | 69.6 |
| 富山 | 70.0 |
| 石川 | 69.4 |
| 福井 | 53.6 |
| 山梨 | 60.3 |
| 長野 | 82.7 |
| 岐阜 | 68.8 |
| 静岡 | 66.3 |
| 愛知 | 69.3 |
| 三重 | 61.4 |
| 奈良 | 64.0 |
| 関西広域連合 | 63.9 |
| 鳥取 | 63.8 |
| 島根 | 63.1 |
| 岡山 | 64.4 |
| 広島 | 67.6 |
| 山口 | 68.4 |
| 香川 | 65.3 |
| 愛媛 | 57.5 |
| 高知 | 65.2 |
| 福岡 | 65 |
| 佐賀 | 58 |
| 長崎 | 51.3 |
| 熊本 | 52.4 |
| 大分 | 63.1 |
| 宮崎 | 63.3 |
| 鹿児島 | 57.1 |
| 沖縄 | 35.4 |
| 平均 | 65.6 |
都道府県によって、合格率に大きな差があることがわかります。
なお、滋賀・京都・大阪・兵庫・和歌山・徳島の6府県は、関西広域連合として合同で調理師試験を実施しているため、合格率もまとめて表示しています。
次に、過去3年間の調理師試験における、平均合格率の推移を確認しましょう。
過去3年間の調理師国家試験合格率(全国平均)の推移
| 年度 | 合格率の平均(%) |
| 令和3年度 | 65.6 |
| 令和2年度 | 70.2 |
| 令和元年度 | 66.4 |
過去3年間の合格率は、65~70%程度で推移していることがわかります。
合格点の目安は6割程度
調理師試験の合格の目安となるボーダーラインは、全科目で満点の合計点数に対して6割以上です。
なお、1科目でも、平均点を著しく下回る点数の場合は不合格となります。
そのため、苦手な科目を「捨て科目」として、ほかの得意な科目に専念して勉強するというような勉強方法だと、調理師試験の場合は不合格になる可能性が高いでしょう。
すべての科目で6割以上の正解を取れるように、まんべんなく勉強することが大事です。
難易度はそこまで高くない
調理師試験の合格率は、過去3年間で65〜70%程度であることと、合格のボーダーラインが6割以上ということから、難易度はそこまで高くないと考えられます。
ただし、試験内容は都道府県によって異なるので、都道府県によって難易度に若干の差があることに注意が必要です。
調理師試験の概要
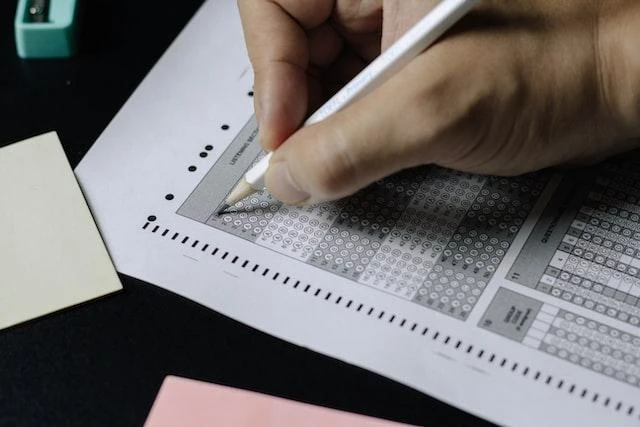
令和4年の調理師試験の概要を確認しましょう。
公益財団法人調理技術技能センターが実施する試験では、受験申請用書類配布と受験申請受付期間は、5月9日~6月3日です。試験日程は10月29日で、合格発表は12月16日となっています。
都道府県によっては日程が異なることがあるので、受験地のスケジュールを確認しておきましょう。
試験科目は、次のとおりです。
- 公衆衛生学
- 食品学
- 栄養学
- 食品衛生学
- 調理理論
- 食文化概論
試験の出題数は60問。
出題形式は、マークシートによる四肢択一方式です。
学科試験のみで、実技試験はありません。
試験会場や日程、受験手数料、受験申請用書類の配布場所、試験問題といった詳細は、都道府県によって異なります。
調理師試験を受ける場合は、受験地の都道府県の試験概要を確認しましょう。
調理師免許の取得方法
調理師免許の取得方法は2種類あります。
調理師養成学校に通う方法と、2年間の実務経験を経て調理師試験の受験資格を得てから、調理師試験を受験して合格する方法です。
それぞれの方法を、詳しく解説します。
調理師養成学校に通う
都道府県知事の指定を受けた調理師養成学校に通えば、調理師試験を受験せずに、卒業と同時に調理師免許を取れます。
学校に通えば最短1年で調理師免許を取得できるので、早く調理師免許を取得したい方は調理師養成学校に通うのがおすすめです。
学校では同じ志を持った仲間と出会え、勉強に対してのモチベーションを高く持つことにも役立つでしょう。
また、学校で学べば体系的な知識が得られます。
独学での知識の偏りが気になる場合は、あらためて調理師養成学校に通うのも良いかもしれません。
2年の実務経験を積んで調理師試験を受験する
調理師養成学校に通わず調理師免許を取得する場合は、2年の実務経験を経て、調理師試験の受験資格を得る必要があります。
そして、調理師試験を受験して合格しなければいけません。
実務経験は、1日6時間以上、かつ週4日以上勤務した場合にカウントされます。
複数の施設に勤務していた場合でも、上記の条件を満たす場合は合算して計算できます。
実務経験として認められる施設は、次のとおりです。
- 飲食店
- 魚介類販売業
- 総菜製造業
- 学校・病院・寮などに設置された給食施設
ただし、上記の勤務先でも、業務内容によっては実務経験と認められない場合もあるので、注意が必要です。
なお、正職員だけでなく、パート・アルバイトでも実務経験として認められます。
実務経験を2年間積んだら、施設の店長や責任者に、実務経験を経たことを証明する調理業務従事証明書を記入してもらいましょう。
調理師の仕事内容や勤務先
調理師の仕事は、勤務先によっても異なりますが、ここでは一般的な調理師の仕事内容を紹介します。
調理師は、まず食材の仕入れから始まり、納品した食材のチェックも欠かせません。
続いて仕込みでは、野菜を切ったり、米を研いだり、まな板をセットしたり、調理の前に用意できることを済ませておきます。
準備が完了したら、オーダーにしたがって調理を開始し、料理の提供が終われば、洗い物、清掃、後片付け作業も必要です。
単純な作業の繰り返しもありますが、知識や経験に基づく専門性を求められる作業もあります。
調理師資格のための学びが、役立つ場面も多いでしょう。
調理師の勤務先は、レストランやカフェなどの飲食店、ホテルなど、多岐にわたります。
また、病院や介護施設、学校給食などで、大量調理に従事する調理師もいます。
調理師試験の勉強方法

働きながら調理師試験を受験する場合は、勉強時間を確保するのが大変かもしれません。
そのため、効率的に勉強する必要があります。
調理師試験の参考書と問題集を用意し、問題集を解きながら必要に応じて参考書を確認する勉強方法がおすすめです。
調理師試験は試験範囲が広いので、参考書を最初から最後まで目を通すというような勉強方法では効率が悪いでしょう。
参考書は、全体の流れを把握する程度に留めておいて、問題集を中心にして勉強するというような工夫が、時間を有効活用するためには大切です。
調理師試験の申し込みから受験までの流れ
調理師試験の申し込みから受験の流れを、令和4年の東京都を例に解説します。
まずは、5月9日~6月3日の間に、受験申請用書類を指定の場所に取りに行きましょう。
受験申請用書類は、保健所や保健センター、地域庁舎、調理師関連団体など、多くの場所で受け取れます。
東京都外に居住している方は郵送で取り寄せることも可能です。
郵送での請求期間は、5月9日~5月27日と、直接取りに行くよりも期間が短くなるので、気をつけましょう。
書類に必要事項を記入したら、公益社団法人調理技術技能センターに送付します。
受験手数料は6,400円で、申請書類に同封されている払込取扱票を使用して、受験申請受付期間内に金融機関で支払うことが必要です。
試験は、10月29日に東京大学駒場キャンパスにて実施されます。
試験会場への交通手段は、公共交通機関の利用が推奨されています。
合格発表は12月16日の10時以降に、東京都庁第一本庁舎30階北側にある健康安全課で閲覧できます。
調理師試験の難易度はそこまで高くない
調理師試験の合格率は過去3年間、65〜70%で推移しています。
また、合格点のボーダーラインは6割です。
合格率と合格のボーダーラインから、調理師試験の難易度はそこまで高くないと考えられます。
ただし、受験した1科目でも平均点を著しく下回っている場合は不合格になる可能性が高いので、全科目をまんべんなく勉強することが大切です。
また、調理師試験を受験する際は、都道府県によってスケジュールが異なる場合があるので、受験地の試験の詳細を必ず確認しておきましょう。






