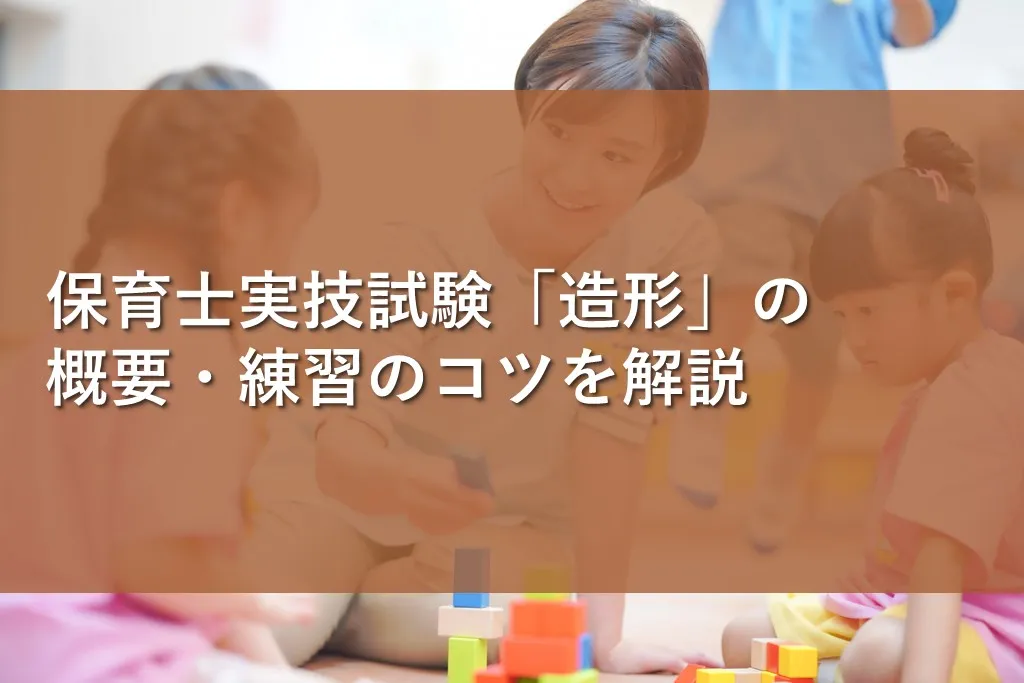
保育士実技試験の「造形」とは、保育士と子どもたちが遊んでいる場面など、指定された保育のワンシーンを絵に描く試験です。
実技試験「造形」の内容について知っておかないと、十分な対策ができなくなるかもしれません。
「造形」の実技試験を突破して、保育士の資格を取得したいのではないでしょうか。
ここでは、保育士実技試験「造形」の内容を解説します。
合わせて、試験対策を行うにあたり、押さえておくべきポイントも紹介します。
目次
保育士実技試験「造形」とは

実技試験の造形とは、指定された保育のワンシーンの絵を書く試験です。
優れた画力が求められるものではなく、指定された情景や人物の描写、色使いができているかどうかが問われます。
保育士実技試験の造形について、詳しく見ていきましょう。
試験の概要
試験内容は次のとおりです。
| 試験の内容 | 当日提示される問題文と、テーマ・背景・人物・彩色といった4つの条件に沿って色鉛筆を用いて描く |
| 求められる力 | 指定された保育の場面をイメージした造形表現ができるか |
| 描く絵の大きさ | A4版の解答用紙に設けられた、縦横19cmの枠内 |
| 制限時間 | 45分 |
| 合格基準 | 50点満点中30点以上 |
| 採点基準 | 未発表 |
| 当日の持ち物 (試験中に机上に置けるもの) |
●鉛筆またはシャープペンシル(HB~2B) ●色鉛筆(12~24色程度) ●消しゴム ●腕時計 |
| 注意点 | ●クレヨン、パス、マーカーペン等は不可 ●水溶性色鉛筆の使用は可能だが、水分の塗布は不可 ●摩擦熱で消せる色鉛筆は不可摩擦熱で消せる色鉛筆は不可 ●受験者間での用具の貸し借りは認められない ●鉛筆削りの持ち込みは可能だが、使用する場合は試験監督員の了承が必要 |
保育士実技試験「造形」の採点基準は、公表されていません。
とはいえ、人物の描写、色使いなど、保育園での保育の状況をイメージできる絵を描くことができれば合格となるでしょう。
造形の実技試験は絵画の試験ではありますが、特別に絵がうまいとか、高い描写技術を持っているかといった点はさほど重要ではありません。
文章で指定された出題の内容を理解し、すべての条件を網羅して絵を完成させることが大切なポイントです。
問題例
造形の試験では、テーマとなる絵の場面(事例)と、その絵で満たすべき4つの条件が提示されます。
過去に出題された問題を見てみましょう。
| 事例 | 保育所で子ども用プールを使い、3歳児と保育士が楽しく水遊びを行っていました。 |
| 条件 | ●子ども用プールでおもちゃを使って遊んでいる様子が描かれていること ●夏の季節や園庭の様子が描かれていること ●子ども3名以上、保育士1名以上を描くこと ●枠内全体を色鉛筆で着彩すること |
つまり、水遊びなどの「テーマ」、季節や園庭などの「背景」、子どもと保育士など複数の「人物」が正しく描かれ、全体を丁寧に「着彩」されているかどうかが問われるのです。
その他、過去には以下のような場面(事例)が出題されました。
条件を満たすことを意識しながら、表現できるようにしましょう。
絵が苦手でも保育士試験で造形を選んで大丈夫?
保育士実技試験は、音楽・言語・造形の3科目中2科目を選択します。
造形では高い画力が求められるわけではなく、時間内に提示された条件を満たし、保育にふさわしい絵を描くことができるかが問われます。
そのため、絵に対して苦手意識があったとしても、音楽や言語よりも、造形のほうが合格する可能性があると感じるのなら造形を選ぶべきでしょう。
実技試験で受ける科目にお悩みの方は、以下の記事を参考にしてください。実技科目の選び方を解説しています。
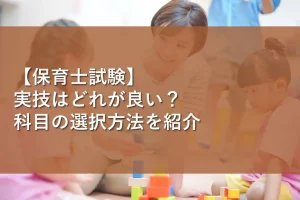
保育士実技試験「造形」の練習のコツ
造形の試験対策を行うにあたり、押さえておくべきポイントがあります。
ここからは、効率よく造形の試験対策を行うためのコツを解説します。
- きれいな発色で塗りやすい色鉛筆を選ぶ
- うまく見せるコツをつかむ
- 当日と同じシミュレーションで練習する
- 絵本などを参考に模写をする
きれいな発色で塗りやすい色鉛筆を選ぶ
造形の試験は、45分という限られた時間のなかで絵を描きあげなければなりません。
効率よく美しい絵を描く必要があり、紙への色のりがよく、発色もきれいな色鉛筆を使うことをおすすめします。
自宅に色鉛筆がある場合は、新しく購入する必要はありません。
ただし、練習で何度も使ってみて「色のりや発色は良いか」を確認しておきましょう。
摩擦熱で消える色鉛筆やクレヨン、クレパス、マーカーペンなどは使用できないので注意してください。
うまく見せるコツをつかむ
造形の試験対策では、闇雲にテーマを想定して絵を描くより、絵のクオリティを上げるポイントを押さえて練習を進めることをおすすめします。
造形のテーマは「粘土遊び」「折り紙」「給食の時間」など毎年テーマが変わり、練習した内容が出題されるとは限らないためです。
特定のテーマに絞って練習するよりも、絵のクオリティを上げるポイントを押さえてどのようなテーマにも対応できる準備をしておいたほうが、試験対策として効率が良いでしょう。
絵をうまく見せるコツは次のとおりです。
- 「笑う」「困る」「泣く」「怒る」といった表情を、それぞれ3パターン描けるようにする
- 性別や髪型・服装なども何パターンか描けるようにする
- 園内や季節などの背景パターンも決めておく
- 人物の「走る」「歩く」「しゃがむ」「手をつなぐ」「手を上げる」などの動作を描けるようにする
- 人物を大きく描き、顔の表情ははっきり描く
- 暗い印象になるため黒は多用せず、カラフルに描く
多彩な表情や動作表現などを確実に描けるようにして、どのようなテーマが提示されても応用できるようにしておきましょう。
当日と同じシミュレーションで練習する
試験当日は緊張感があるなかで、45分間の時間内に条件を満たした絵を描かなければなりません。
そのため、本番の状況を想定したシミュレーションを行いましょう。
シミュレーション方法は次のとおりです。
- 45分でタイマーをセットする
- A4用紙を用意し縦横19cmの枠内に絵を描く
- 構図・下絵・色塗り・見直し・仕上げのそれぞれにかかる時間を測定する
以上のように、試験と同じ状況にして、時間配分の感覚を身につけておきましょう。
また、人物の髪型や服装、園内の背景など、パターン化できるものはあらかじめ決めて練習しておけば、効率よく描くことができます。
絵本などを参考に模写をする
絵に自信がない人は、絵本やイラスト集を参考にして、模写から始めるのも一つの方法です。
人物と背景のバランスや、表情の表現などの勉強になるためです。
ただし、造形の実技試験は画力が問われるわけではないので、あまりにもレベルの高い絵本やイラスト集の模写はおすすめしません。
描きやすそうで表現力のある絵本などを参考にしましょう。
保育士実技試験「造形」はしっかり対策すれば合格をめざせる
保育士国家試験の実技試験「造形」は、しっかりと対策を行えば絵が苦手でも合格をめざせます。
画力ではなく、条件を満たして背景や人物が描かれているかどうかを問われるためです。
造形の実技試験対策では、どのようなテーマや条件が提示されても対応できる応用力を身につけることが大切です。
表情・髪型・服装・背景・人物の動作などを、複数のパターンで描けるように、事前に準備しておきましょう。






