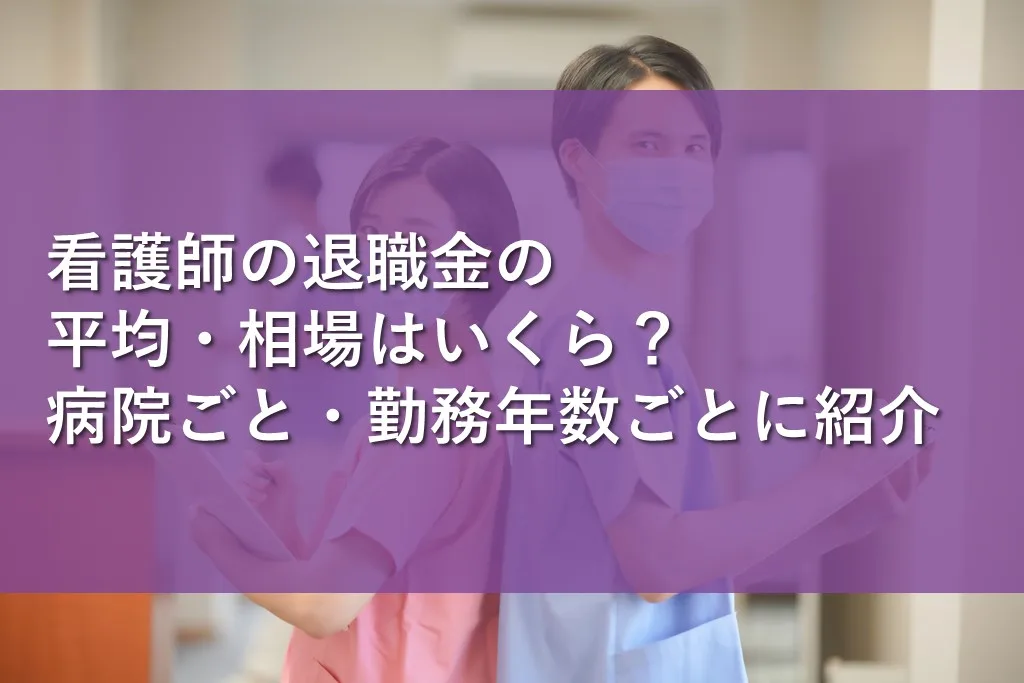
「看護師の退職金の相場はどれくらい?」と気になっている方もいるでしょう。
退職金制度は、法律で義務付けられているものではないため、すべての勤務先が退職金制度を導入しているわけではありません。
実際に、平成30年度に退職金制度を設けている企業の割合は80.5%で、従業員の多い企業ほど退職金制度を設けている割合が高い傾向にあります。
ご自身が勤めている病院やクリニックに、退職金制度があるのかどうか気になった場合には、就業規則を確認してみるとわかることが多いでしょう。
それらを踏まえたうえで、看護師の退職金の平均や相場を解説します。
大まかな目安として参考にしてみてください。
目次
【勤務年数別】看護師の退職金の相場

看護師の退職金は、多くの場合勤続年数によって異なります。
ここでは、勤続年数別の看護師の退職金を紹介していきます。
勤続年数が3年の看護師の退職金
勤続年数が3年程度の看護師の退職金は、一般的に30万円程度が相場であり、給料の約1ヵ月分程度もらえることとなります。
退職金は、「退職慰労金」と呼ばれることもあり、今まで働いてきた功績へのねぎらいという意味もありますので、病院への貢献度が金額に反映されることが多いです。
そのため、勤続年数が3年程度の場合、会社への貢献度が低いことから、あまり大きな金額を受け取ることができない場合が多いでしょう。
また、勤続年数が3年未満の場合は、退職金をなしとしている病院やクリニックもあります。
勤続年数が5年の看護師の退職金
勤続年数が5年の看護師の場合、退職金は30〜50万円が相場といわれています。
勤続5年目となると、リーダー業務を行ったり、委員会で積極的に活動を行ったりなど、普段の看護業務に加えて、病棟をまとめる役割を担うことが多くなります。
そのため、勤続年数3年の場合と比較して、会社への貢献度も大きくなるため、退職金も増えていくことが見込まれます。
勤続年数が10年の看護師の退職金
勤続年数が10年の看護師の場合、退職金は250〜300万円が相場といわれています。
勤続年数が10年程度となると、看護主任など役職についている場合もあり、そのような場合は貢献度がさらに大きくなっていきますので、退職金が相場よりも高くなることもあります。
まとまった金額がもらえることで、次のステップをゆっくりと見つめ直すこともできるでしょう。
【病院の種類別】看護師の退職金の相場
看護師の退職金は、前述した勤続年数の他に、病院の種類によっても異なってきます。
詳しい金額はそれぞれの就業規則を確認する必要がありますが、ここでは一例を紹介していきます。
国立病院機構の看護師の場合
国立病院の場合は、独立行政法人国立病院機構 職員退職手当規定によって退職金が細かく決められており、6ヵ月以上の勤務で退職金が支給されることとなっています。
自己都合の退職か勤務に関係する傷病による退職なのかなど、退職理由によって退職金の支給金額は異なります。
自己都合の場合、1年目で月給の半月分、3年目で1.5ヵ月分、5年目で2.5ヵ月分、20年目の場合では19ヵ月分が退職手当として支払われることとなっています。
公立病院の看護師の場合
公立病院の看護師は地方公務員になるため、各地方公共団体の条例によって定められており、国家公務員退職手当法に準じたものとなっています。
定年退職時の退職金は、都道府県立病院で約1,400万円となっており、政令指定都市の公立病院ではさらに高い傾向にあります。
私立病院・クリニックの看護師の場合
それぞれの就業規則を確認しなければわかりませんが、クリニックや小規模私立病院の看護師では、退職金制度がない場合もあります。
退職金が欲しいと思っている方は、入職する前に必ず退職金制度があることを確認しておきましょう。
【具体例あり】看護師の退職金の計算方法
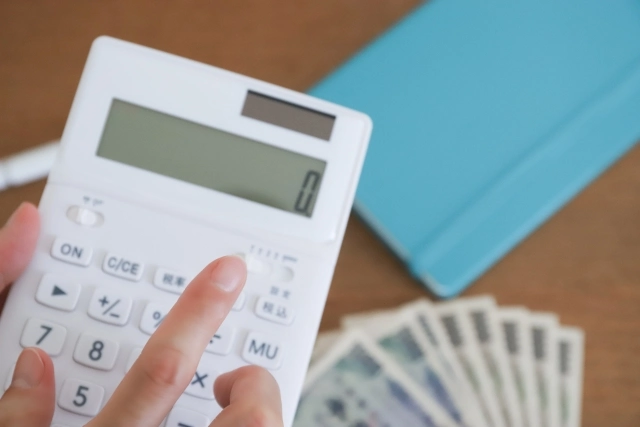
国立病院や公立病院には、退職金計算の具体的な方法があります。
また、一般的な退職金の計算方法が3種類ありますので、ここでは具体例を挙げながら、退職金の計算方法を紹介していきます。
国立病院機構看護師の退職金の計算方法
国立病院機構に勤めている看護師の退職金の計算方法は、以下のようになっています。
退職手当額=月給×退職理由別・勤続年数支給率
自己都合の退職か、定年による退職か、業務による傷害による退職かなど、退職理由によって支給率が少しずつ異なってきます。
また、勤続年数によっても支給率が異なります。
この計算式に当てはめると、例えば、月給25万の方が3年で自己都合により退職をする場合、支給率は1.5066になりますので、25×1.5066=37万円と計算することができます。
地方公務員看護師の退職金の計算方法
地方公務員看護師の退職金の計算方法は以下のようになります。
退職金=基本額+調整額
基本額とは、月給×退職理由別・勤続年数支給率です。
調整額とは、職務内容や勤続年数などによって変動するものとなっています。
公務員の退職理由別・勤続年数支給率は、以下の表のとおりです。
| 勤続年数 | 退職理由 | ||
| 自己都合 | 定年・勧奨 | 整理退職 | |
| 1年 | 0.6 | 1.0 | 1.5 |
| 5年 | 3.0 | 5.0 | 7.5 |
| 10年 | 6.0 | 10.0 | 15.0 |
| 15年 | 12.4 | 19.375 | 23.25 |
例えば、勤続年数5年で月給25万の方が自己都合で退職する場合、おおよその退職金は、25×3=75万円ほどと考えられます。
その他看護師の一般的な退職金計算方法
私立病院やクリニックに勤めている看護師の場合、退職金の計算方法や支給率は決まっておらず、支給額はそれぞれの病院によって異なります。
一般的な退職金の計算方法としては、以下の3パターンがあります。
- 基本給をもとにした場合
- 固定金をもとにした場合
- 功績倍率をもとにした場合
それぞれの計算方法を解説します。
基本給をもとにした場合
基本給に勤続年数や支給係数をかけて退職金を決定する方法です。
具体的な計算方法は以下のようになります。
例えば、
- 基本給が25万、勤続年数が3年の看護師の退職金は25×3=75万円
- 基本給が30万円、勤続年数が10年の看護師の退職金は30×10=300万円
となります。
固定金をもとにした場合
勤務先があらかじめ設定した、固定金に勤続年数をかけて退職金を計算する方法です。
固定金が少ないと、勤続年数が長くても退職金に反映されにくいというデメリットがあります。
具体的な計算方法は以下のようになります。
例えば、
- 固定金が15万、勤続年数が3年の看護師の退職金は15×3=45万円
- 固定金が20万円、勤続年数が10年の看護師の退職金は20×10=200万円
となります。
功績倍率をもとにした場合
功績倍率をもとにした場合は、基本給に勤続年数と功績倍率をかけて退職金を決定します。
具体的な計算方法は以下のようになります。
この功績倍率は会社からの評価によって変化していきます。
基本は1とされていますが、評価や貢献度が高い場合には1よりも大きくなり、反対に評価が低くなってしまった場合は1よりも小さくなることがあります。
例えば、
- 基本給が25万、勤続年数が3年、功績倍率が1の場合の看護師の退職金は25×3×1=75万円
- 基本給が30万円、勤続年数が10年、功績倍率が2の場合の看護師の退職金は30×10×2=600万円
となります。
看護師の退職金を増やす方法
看護師の退職金額を上げるには、以下のような方法があります。
- 役職につくことで会社への貢献度を上げる
- 資格を取得する
- 准看護師の方の場合は正看護師になることで基本給を上げる
役職につく
先述したように、退職金は基本給や功績倍率が関係する場合があります。
そのため、役職につくことで退職金が上がることが期待できます。
基本給が上がったり、勤務先への貢献度が上がったりすることで功績倍率が上がる可能性があるからです。
資格を取得する
看護師が認定看護師や専門看護師の資格を取得することで、取れる医療加算やコストが増え、病院への貢献度が上がる場合があります。
その場合は、功績倍率が上がる可能性があるため、功績倍率をもとに退職金を計算しているケースでは、退職金額が増える可能性があります。
また、助産師や保健師の資格を取得し、看護師よりも基本給が高い助産師や保健師として働くことで退職金が上がることも考えられます。
正看護師になる
一般に、准看護師よりも正看護師の方が基本給が高いケースが多いです。
そのため、基本給が退職金に関係する場合は、正看護師になることで退職金を上げることができます。
また、准看護師は自らの判断で業務を行うことができません。
より活躍の幅が広がる正看護師になることで、さらに医療に貢献することができるともいえるでしょう。
看護師の退職金はいつもらえる?
退職金の支給時期には、規定がありません。
そのため、支給時期は勤務先によって異なってきます。
一般的には、退職後1ヵ月〜半年の間に支給されることが多いですが、支給時期について詳細に知りたい場合には、勤務先の担当者に確認したほうが良いでしょう。
看護師の退職金にも税金はかかる
看護師の退職金にも所得税と住民税がかかります。
しかし、退職金のすべての金額に税金がかかるわけではありません。
「退職所得控除額」が設定されており、その分の税金はかからない仕組みになっています。
この退職所得控除額は勤続20年を超えると控除額が大きくなり、納税額が大きくなりすぎないようになっています。
退職金を増やしたい場合は、転職時期や病院を考えよう
退職金制度は、どの勤務先にも必ずあるとは限りません。
そのため、退職金を貰いたいと思っている方は、転職する際に退職金制度の有無を確認することが重要です。
また、退職金は基本給を増やしたり、勤続年数を長くしたり、スキルアップをして勤務先への貢献を大きくすることで増やせる可能性があります。
退職金をしっかり貰うことで、退職後も少しゆとりのある生活を送れたり、自分自身の将来を考え直したりする時間をつくることができます。
退職金の有無とその額は、離職前に必ず確認しておきましょう。






