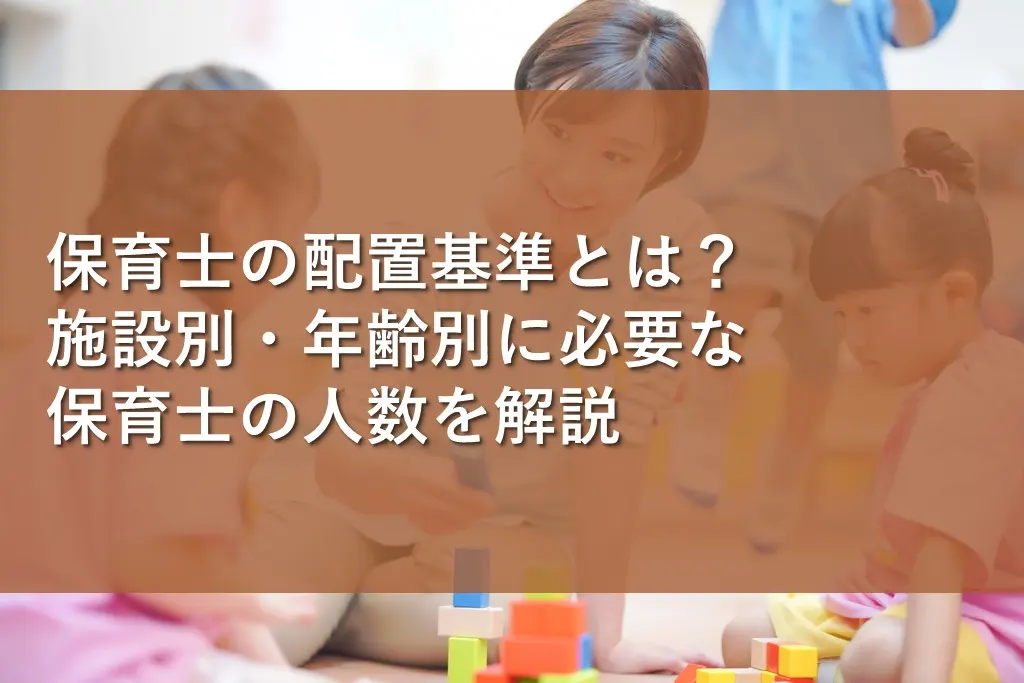
保育士の配置基準が気になっていて、基準を詳しく知りたいと考えていませんか。
保育士をめざすのであれば、業務に関する知識はすべて身につけておいたほうが良いでしょう。
ここでは、保育士の配置基準を解説します。
勤務する施設や、保育する子どもの年齢によって基準が異なるため、それぞれの人数についてもお教えします。
保育士をめざしている方は必見です。
目次
保育士の配置基準

配置基準とは、一人の保育士が担当できる子どもの人数のことです。
配置基準は、児童福祉法と呼ばれる法律にのっとって決められています。
未満児は大人の目が必要なため、一人の保育士が対応できる人数が少なく設定されています。
4歳児以上からは多くの人数を一人で担当できるため、30人に対して一人の保育士で対応可能です。
配置基準は厚生労働省のホームページから確認でき、認可保育園や認可保育所、認定こども園はルールにしたがわなければなりません。
しかし、施設によっては地方自治体の定めにしたがったもの、施設独自のルールを定めているものもあります。
地方自治体や施設独自のルールは、国の決まりよりも厳しい内容になっています。
次から、国・自治体・施設別の配置基準の詳細を解説しましょう。
国・自治体別の保育士配置基準は?

国が定めている配置基準とは別に、自治体・施設別に配置基準を定めている場合もあります。
では、国はどのように決まりを定めているのか、ここでご紹介しましょう。
国の保育士配置基準は2020~2021年まで変わっていない
| 保育する年齢 | 保育士の人数 |
| 0歳児 | 3人につき一人 |
| 1~2歳児 | 6人につき一人 |
| 3歳児 | 20人につき一人 |
| 4歳児以上 | 30人につき一人 |
配置基準は1948年から定められており、時代の推移とともに法令改正が繰り返されてきました。
しかし、2020年以降は特に変わりありません。
0歳児は3人の子どもに対して一人と少ないものの、年齢が上がるにつれて対応できる人数が増えます。
4歳児以上になれば30人の児童を一人で担当可能です。
自治体独自の配置基準が設定されているケースもある
自治体別に配置基準が定められているケースもあります。
地域によって内容は異なりますが、国の基準よりも厳しくなっており、より多くの人員が求められます。
例えば福岡市では、小規模保育園の場合は0歳児3人につき2人、1~2歳児6人につき2人の人員が必要 です。
参考:小規模保育事業等 職員配置基準
人材確保が難しくなるものの、大人の目が増えるため、子どもの安全性を確保できるでしょう。
保育士の配置人数の計算方法

基準内容がわかっても、実際何人置くべきかはわかりにくいものです。
しかし、適切な人数を置かなければルールに違反してしまいます。
ルールにのっとって運営するためには、施設側で必要な人数を把握しておかなければなりません。
自治体によっては、公式にエクセルなどで配置人数を自動計算できるソフトを提供しているところもあります。
しかし、すべての自治体で提供されているわけではないので、以下で月齢別の配置基準の計算について、例を使ってご紹介します。
0歳児の保育士配置基準の人数
0歳児クラスに9人いる場合、3人でクラスを担当します。
国の基準は3:1で、3人の児童に対し一人が対応します。
9÷3=3で、3人が必要な計算です。
1歳児の保育士の配置基準計算方法
1歳児クラスに18人の児童がいる場合は、3人でクラスを担当します。
国の基準は6:1、つまり6人に対し、一人が対応することになります。
18÷6=3なので、3人が必要な計算です。
2歳児の保育士の配置基準計算方法
2歳児クラスに21人の児童がいる場合は、4人でクラスを担当します。
国の基準では、1歳児同様6:1です。
21÷6=3.5なので、小数点以下を四捨五入して4となります。
整数で割り切れないと困惑するかもしれませんが、小数点が出た場合は四捨五入で計算すると覚えておきましょう。
3歳児の保育士の配置基準計算方法
3歳児クラスに15人の児童がいる場合、2人でクラスを担当します。
国の基準では、3歳児は20:1です。
20人を一人で担当できるため、ここで迷う方も多いかもしれません。
1つのクラスに2人以上人員を置く必要があるため、児童の人数に関係なく1クラスに2人の人員がいます。
たとえ一人の保育士が担当できる人数を下回っていても2人で対応する必要があると覚えておきましょう。
4歳児以上の保育士の配置基準計算方法
4歳児以上クラスに32人の児童がいる場合、2人が必要です。
国の決まりでは4歳児以上は30:1、つまり30人につき一人で対応できます。
1クラスは30人前後の人数になることが多いものの、人数に関係なく2人以上の人員を置かなければなりません。
そのため、各クラスに2人以上在籍する必要があります。
施設別の保育士配置基準について

2022年現在、子どもを預けられる施設は数多くあります。
しかし、以前は子どもを預けられる施設が少なく、待機児童が問題になることもありました。
それでは、いつから施設が多くなったのでしょうか。
保育施設の幅が広がったのは平成27年4月に「子ども・子育て支援新制度」という新制度が施行されてからです。
保育を希望する人が多いのにも関わらず、保育できる施設が少ないことからこの制度が施行されました。
その結果、小規模保育園や自宅で保育を行う家庭的保育事業が可能となりました。
以下では、さまざまな施設別の保育士配置基準をご紹介します。
地域型保育事業
| 保育施設 | 配置基準 |
| 小規模保育園 | 国の配置基準+一人 |
| 事業内保育事業 | 19人以下の場合は国の配置基準+一人 20人以上の場合は国の配置基準 |
| 居宅訪問型事業 | 一人 |
| 家庭的保育事業 | 3人につき一人 |
小規模保育園は国や自治体から公費を受け取って運営する、認可型保育園と同様の施設です。
定員数は6~10人のところ、6~19人と定めているところがあります。
定員数に応じて決まりが変わり、国の基準同様か、または基準+一人に分かれます。
事業内保育事業とは企業内の保育施設にて、児童の保育を行なうことです。
企業に勤める人の子どもを預かるだけでなく、企業がある地域で保育が必要な子どもを受け入れることもあります。
事業内保育事業は保育する人数によって配置基準が異なります。
保育する人数が19人以下であれば国の配置基準+一人、20人以上の場合は国のルールと同様です。
居宅訪問型事業は保育士などが子どもの自宅に伺って保育を行うことです。
こちらは一人の児童に一人の保育者がつくため、訪問する家庭に応じて向かう人数が変わります。
最後に家庭的保育事業とは、自宅などで5人以下の児童を保育することです。
0~2歳児の児童3人につき一人が対応します。
延長保育時は保育士の配置基準を増加する必要も
認可保育施設では、早い時間にお迎えに行けない保護者のために延長保育を実施しています。
延長保育時は日中の決まりに加え、最低2人以上の人員を追加しなければなりません。
保育園には園長が在籍していますが、園長は自身の業務があることから、保育に携われません。
そのため、基準を満たす人員に加えられないので注意が必要です。
保育士の配置基準緩和の内容

平成27年に新制度が施行されたものの、地域によっては待機児童が解消されず、増加傾向にあります。
そのため、国は平成28年に保育士の配置基準を緩和させ、少しでも多くの子どもが保育施設に入所できるよう配慮 しています。
ここでは、内容の緩和によってどのようなことが可能になったのかを解説します。
幼稚園教諭や小学校教諭も保育士の配置基準を満たせる
配置基準を満たす人は保育士のみと定められていましたが、緩和により、幼稚園教諭や小学校教諭も認められるようになりました。
保育士は全年齢への保育が可能ですが、幼稚園教諭などは対象が異なります。
幼稚園教諭は3歳児、小学校教諭は5歳児の保育が望ましいとされているため、保育できる児童が限定されるかもしれません。
また、保育に必要な研修の受講も求められるので、事前に受けておくと良いでしょう。
早朝・延長保育時の人員幅を拡大
保育施設では早朝・延長保育を行っており、保育資格を持つ2名以上の人材を置かなければなりませんでした。
決まりの緩和によって資格を持つものでなくても基準を満たせるようになったため、必ずしも保育士が対応する必要はありません。
保育士の代替が可能なのは、子育て支援員研修を修了した者です。
研修は自治体が行っているため、保育資格を所有していないけれど保育施設で働きたい方は、研修に申し込みましょう。
子育て支援員も保育士の配置基準を満たせる
保育施設としての認可に必要な人材数を確保していても、8時間以上開所していれば人材が足りなくなることもあります。
人材が足りない場合は、子育て支援員研修を修了した子育て支援員を追加することで、基準を満たせます。
子育て支援員の参加によって、人材不足の解消を狙えます。
しかし、在籍する人材の3分の2以上は保育資格を持っている人でなければなりません。
子育て支援員を多く在籍させるとルールに違反してしまうため、注意しましょう。
保育士の配置基準を満たしていない・違反した場合について
配置基準に違反していた場合の対応は、認可と認可外によって変わります。
認可の場合は改善勧告・命令といった処分を受けます。
場合によっては指導が入るため、指導にしたがって人員の配置を検討しなければなりません。
指導されたにも関わらず違反したままだと、認可が取り消される恐れもあります。
認可外の場合も、改善勧告・命令といった処分を受けます。
認可との違いは、違反したままだと施設の閉所命令や業務停止命令などの重い処罰を受ける恐れがあることです。
処分を避けるためにも、施設の配置基準が適切かをしっかりチェックしておかなければなりません。
配置基準を理解して保育士への知識を高めよう
保育士の配置基準は施設や保育する子どもの年齢によって異なります。
国の基準を採用しているところもあれば、自治体の基準や施設独自の基準を採用しているところもあるため、希望する施設のルールを確認しておくと良いでしょう。
配置基準は子どもを安全に保育するために守るべきことです。
保育士を志すのであれば知っておきたい知識なので、この記事で得た知識を、就職後にも活かしてください。






