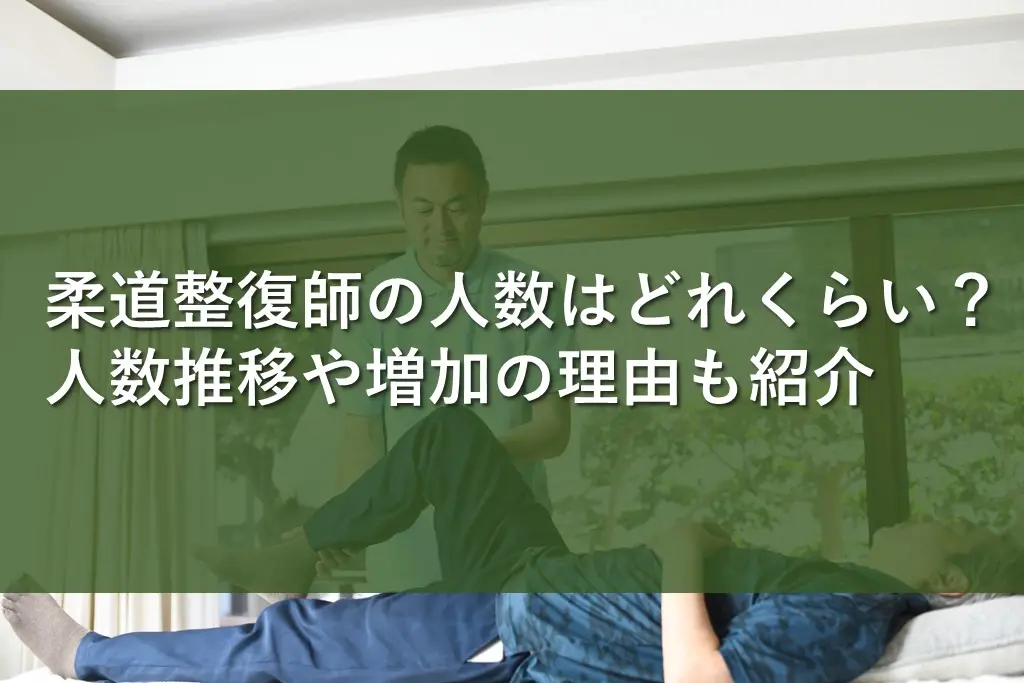
柔道整復師は、手技療法によって骨折や脱臼、捻挫などへの施術を行う医療技術職です。
接骨院・整骨院をはじめ活躍の場は幅広く、スキルアップやキャリアアップを見据えて柔道整復師の資格を取得する方も少なくありません。
また、高齢化という社会課題を抱える日本において、柔道整復師の需要は今後ますます高まっていくでしょう。
本記事では、柔道整復師の総数や近年の人数推移をデータで確認するとともに、人数が増加している理由もあわせて解説します。
柔道整復師の将来性を含めた業界の現状について理解を深め、自分自身のキャリアプランを考える際の参考にしてみてください。
目次
柔道整復師の人数は?

まずは、柔道整復師として働く方の総数と男女比・年齢層を見てみましょう。
「どれだけの人数の方がこの資格で働いているのか」という情報は、柔道整復師の現状を把握するための重要な材料となります。
柔道整復師の総数
厚生労働省の「令和4年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」によると、柔道整復師として働く方の総数は2022年末時点で78,827人でした。
この調査は2年ごとに実施されており、前回調査の2020年の総数75,786人と比較すると、2年間で3,041人増加しています。
柔道整復師の男女比
柔道整復師の男女比に関する公的なデータはありませんが、柔道整復師養成施設の入学者の男女比はおおむね7:3となっており、男性が多い傾向です。
しかし、整体施術は女性のニーズもあり、女性専用の整体院の利用意向や「女性に施術してもらいたい」と希望する方も珍しくありません。
このことから、今後の柔道整復師業界では、女性の活躍の場が広がる可能性もあるでしょう。
柔道整復師の年齢層
厚生労働省が公表した「令和5年度賃金構造基本統計調査の結果」によると、柔道整復師の平均年齢は40.1歳となっています。
国家資格である柔道整復師は、独立開業すれば定年を気にせず働ける仕事であり、30~40代からの転職も可能です。
柔道整復師の資格取得には最短でも3年かかりますが、年齢制限がないぶん、セカンドキャリアを考える世代にとっても魅力的な選択肢になります。
柔道整復師の人数推移
柔道整復師の資格で働く方の人数は、ここ数年で大きく増加しています。
人数推移を追うことで、業界の成長や需要の変化を読み取り、柔道整復師の将来性を判断するために役立てましょう。
近年の柔道整復師の人数推移
上記でも触れた厚生労働省の「令和4年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」によると、柔道整復師の就業人数は2012~2022年の10年間で次のように推移しています。
【就業柔道整復師の人数推移(2年ごと)】
| 年代 | 2012年 | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | 2022年 |
| 人数 | 58,573人 | 63,873人 | 68,120人 | 73,017人 | 75,786人 | 78,827人 |
2022年までの10年間で、柔道整復師の人数は約2万人増えていることがわかりました。
特に2012年から2018年にかけては、2年ごとに約5,000人ずつ増加しており、市場規模の成長がうかがえるでしょう。
2018年以降は増加のペースがやや緩やかになっていますが、人数は着実に増え続けています。
柔道整復師の人数増加の要因
柔道整復師の人数増加には、いくつかの要因が考えられます。
- 独立開業が可能な国家資格であり、収入アップをめざせるため
- 活躍できる分野が幅広く、就業先の選択肢が豊富にあるため
- 高齢化社会の進展により、利用者数の増加が見込めるため
柔道整復師は、自分のスキルと経験を活かして独立開業できるため、キャリアアップや収入アップをめざす方にとっても有益な資格です。
また、整骨院や接骨院はもちろんのこと、医療機関や介護施設、リハビリ施設、スポーツチームのトレーナーなど、柔道整復師はさまざまな場所で働けます。
高齢化が進む日本において、医療・介護の需要は高まっており、柔道整復師の就業先である医療機関や介護施設などの利用者は増加する見込みです。
患者さんの健康維持やケガの予防・改善のため、柔道整復師の果たす役割は今後さらに大きくなるでしょう。
さらに、国家資格である柔道整復師は、高い専門性を証明できることから、ブランクを経てからの再就職や産休・育休を取得した女性の職場復帰もしやすいといえます。
柔道整復師の人数は増加傾向にあり需要も高い
柔道整復師の人数は年々増加傾向にあり、2022年の調査時点で78,827人に達しました。
柔道整復師養成施設の入学者は男女比およそ7:3と男性が多いものの、女性柔道整復師の需要も高まっています。
全体の平均年齢は40.1歳で、中高年の方のセカンドキャリアとしても選ばれているのが特徴です。
柔道整復師の人数が増加している背景には、独立開業が認められていること、就業先の選択肢が多いこと、高齢化社会による需要増加など、将来性の高さが関係しています。
今後も資格保持者の増加傾向が続けば、競争も激化する可能性があり、ほかの柔道整復師と差別化を図るためのスキルアップが重要になるでしょう。
業界の現状や社会のニーズを把握したうえで、自分自身のキャリアプランに合わせて知識・技術を磨き、長く活躍できる柔道整復師をめざしてみてください。







