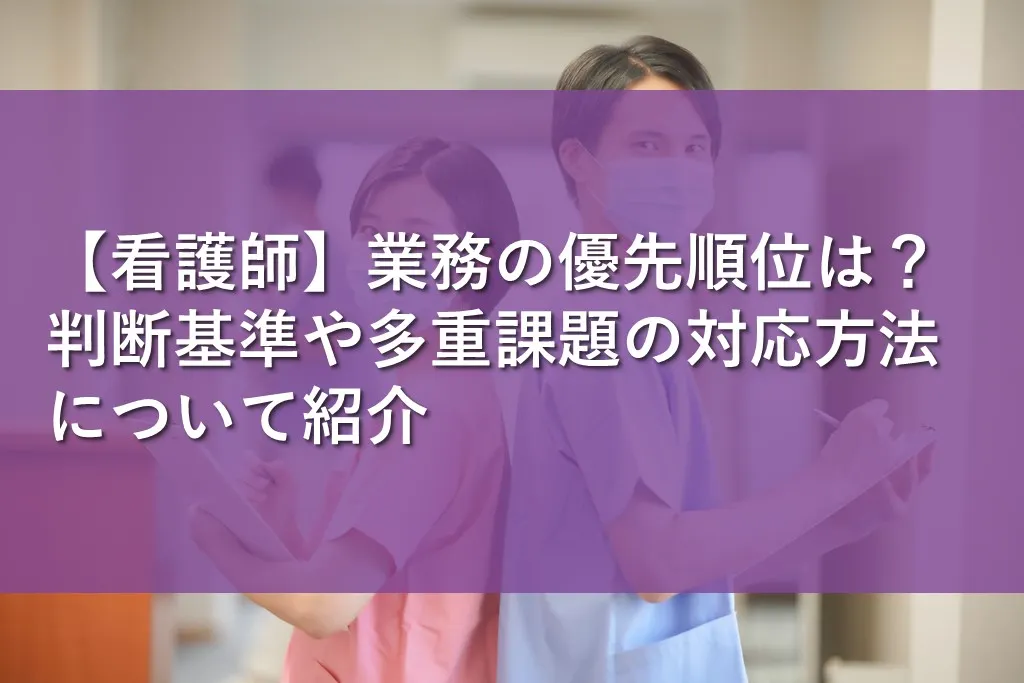
看護の現場は常に多くのタスクが積み重なっており、どの課題から取り組むべきか迷う場面もあるかもしれません。
こうした状況を多重課題といい、看護師は日々限られた時間のなかで多くの業務をこなす必要があります。
それと同時に、患者さんの安全を守り適切なケアを提供するためには、業務の優先順位を考えることが非常に重要です。
本記事では、看護師が業務に優先順位をつける際の判断基準や、判断のタイミングを解説します。
多重課題に陥ったときでも冷静に対処するためのポイントも解説しているため、看護業務の進め方に悩んでいる方は参考にしてみてください。
目次
看護業務は優先順位をつけることが大切

看護師の業務範囲は幅広く、受け持ち患者さんのケアや治療、検査の時間が重なってしまったりなど多重課題に陥りやすい傾向にあります。
そうしたなかで、限られた時間を有効に使い患者さんの安全を守るためには、業務の優先順位をつけることが大切です。
看護師が優先順位を考える際の判断基準
看護師の業務が重なったときには、主に以下3つの判断基準をもとに優先順位を考えます。
- 患者さんの生命に直結する事象かどうか
- 患者さんの状態が安定しているか
- 実施時間が決まっているかどうか
それぞれのポイントを詳しく見てみましょう。
患者さんの生命に直結する事象かどうか
看護師が業務の優先順位を考える際、特に重要視すべきは、患者さんの生命に直結する事象かどうかを判断することです。
具体的には、急変時の救命処置や安全確保、苦痛緩和などは優先順位が高い業務といえます。
なかでも、最も優先順位が高い業務は「救命処置」であり、患者さんの心肺停止が発生した場合、他のどの業務よりも優先して対応しなければいけません。
また、転倒リスクの高い患者さんのトイレ介助なども、「安全確保」の面で優先して対応すべき業務となるでしょう。
次いで、病状が悪化している患者さんなどに対する医療行為の補助も、優先順位が高い業務の一つです。
一方で、清潔ケアや精神的なケアなどは、相対的に優先順位が低くなる傾向にあります。
ただし、これらのケアも患者さんにとっては重要なものとなるため、状況に応じた柔軟な対応が必要です。
患者さんの状態が安定しているか
業務の優先順位を決める際には、患者さんの状態も重要な指標となります。
治療状況や年齢、病識などの要素を総合的にアセスメントし、状態が不安定な患者さんのケアを優先するようにしましょう。
例えば、術後の患者さんや高齢の患者さんは状態が変化しやすいため、より注意深く観察しなければなりません。
状態が不安定な受け持ち患者さんの場合は、バイタルサイン測定などのラウンドの時間も考える必要があるでしょう。
一方で、状態が安定している患者さんのケアは、ある程度時間に余裕を持ったうえでの対応もできます。
実施時間が決まっているかどうか
看護業務は、実施時間が固定されているもの、ある程度の時間が決められているもの、いつ行っても良いものの大きく3つに分類が可能です。
- 実施時間が決まっている業務:オペ出し・検査出し・点滴投与・医師の処置介助・カンファレンス
- ある程度時間が決まっている業務:バイタルサイン測定・血糖測定・術後の処置
- いつ行っても良い業務:清潔ケア・看護記録・環境整備
優先順位を考える際には、これらの時間的制約も考慮してみてください。
オペ出しや点滴投与など、実施時間が固定されている業務は最初にスケジュールに組み込むようにします。
次に、ある程度の時間が決められている業務を組み込み、最後に時間的制約のない業務をスキマ時間に実施するようにすると良いでしょう。
看護師が優先順位を考えるタイミング
看護師が業務の優先順位を考えるタイミングは、主に2つあります。
- 朝の情報収集時
- 受け持ち患者さんに急変が起こった場合
業務効率化のためには、毎朝の情報収集時にその日のスケジュールを立てておくのが効果的です。
ただし、緊急対応が発生するケースも考慮して、スケジュールにはある程度の余裕を持たせておきましょう。
朝の情報収集時
看護師は、出勤後の朝の情報収集時に、1日の業務スケジュールを立てる必要があります。
特に、自分自身が多くの仕事を抱えていることがわかっている場合は、優先順位を決めつつ、他の看護師とスケジュールを調整しておきましょう。
この際、時間にある程度のゆとりを持ってスケジュールを組むことがポイントです。
分刻みでスケジュールを詰め込んでしまうと、焦りから患者さんが発する重要なサインを見逃しかねません。
急な対応が必要になったり、時間に遅れが生じたりした場合に備えて、業務の進め方に柔軟性を持たせておくようにします。
受け持ち患者さんに急変が起こった場合
受け持ち患者さんに急変が起こった場合は、他のスケジュールよりも対応を優先します。
特に、心肺停止やショック、呼吸困難などの症状が現れたときには、速やかに適切な処置を行わなければなりません。
また、こうした状況下では、チームで強力して対応にあたることが求められます。
患者さんの様子を見たときの第一印象や一時評価による結果をふまえ、医師や他の看護師へ応援を要請しましょう。
急変対応に直面したときこそ冷静になり、スタッフに的確な指示を出すことが重要です。
多重課題でも優先順位をつけられる看護師になるには?

多重課題に陥ったときでも焦らず、より最適な優先順位をつけられる看護師になるには、次の3つの方法を試してみましょう。
- 先輩看護師に報告・相談する
- ワークシートを作成して1日のスケジュールを記載する
- 業務にかかる時間を把握する
順に詳しく解説します。
先輩看護師に報告・相談する
多重課題となり業務の進め方に迷ったときは、先輩看護師に報告・相談してみましょう。
受け持ち患者さんに関する業務は、必ずしも自分一人だけで進める必要はありません。
ナースステーションへ戻るのが遅れて心配をかけてしまう前に、自分が手一杯なことを先輩看護師などへ伝えることで、応援を受けられる可能性があります。
また、朝の情報収集時にあらかじめ業務スケジュールを先輩看護師に確認してもらい、アドバイスをもらうのも一つの手段です。
経験豊富な先輩看護師の意見を聞くことで、適切な優先順位をつけやすくなるでしょう。
なお、スケジュールを相談するときは、自分自身の行動計画に対する考えを述べられるようにしておくのがベターです。
ワークシートを作成して1日のスケジュールを記載する
朝の情報収集時にワークシートを作成し、1日の業務を整理しておくことで、視覚的にスケジュールを把握できます。
ワークシートは、日々のルーティン業務や時間が決まっているイベントなどを時系列順に書き込んでいくことで、簡単に作成が可能です。
【ワークシートの作成方法】
- 1日の時間軸を縦に記載する
- 各業務を時系列に沿って記入する
- 時間をずらせない重要な業務には色をつけて目立たせる
- 実施した業務にはチェックをつける
一度ワークシートを作成した後も、追加の業務が発生した際には、随時ワークシートに書き込んでいきましょう。
業務の優先順位は、前述した判断基準で決定します。
ワークシートを活用すると、忙しいときでも次に何をすべきか一目でわかるようになり、実施するべき業務を漏れなく実行することができるでしょう。
業務にかかる時間を把握する
各業務を実施するのにどれくらい時間がかかるのかを把握しておくと、優先順位を考慮したスケジュール調整がしやすくなります。
まずは1日1日の行動を振り返って、業務にかかった時間を記録するようにしましょう。
業務にかかる時間がわかれば、スケジュールの時間配分がより適切になります。
患者さんの状態によっては、同じ業務でも想定より時間がかかる可能性もあるため、余裕を持った時間配分を心がけてみてください。
看護師として業務の優先順位を意識しよう
多重課題に陥りやすい看護の現場では、業務の優先順位を適切に判断できるスキルが求められます。
優先順位を考える際は、患者さんの生命に直結する事象かどうか、状態が安定しているかどうか、実施時間が決まっているかどうかを基準に判断しましょう。
また、業務にかかる時間を把握してスケジュール管理をしたり、朝の情報収集時にワークシートを作成したりといった工夫で、業務はさらに進めやすくなります。
困ったときには、先輩看護師に相談して力を借りるのも一つの手段です。
緊急時でも患者さんの安全を守り、質の高いケアを提供するために、普段から業務の優先順位を意識しながら業務を進めてみてください。







