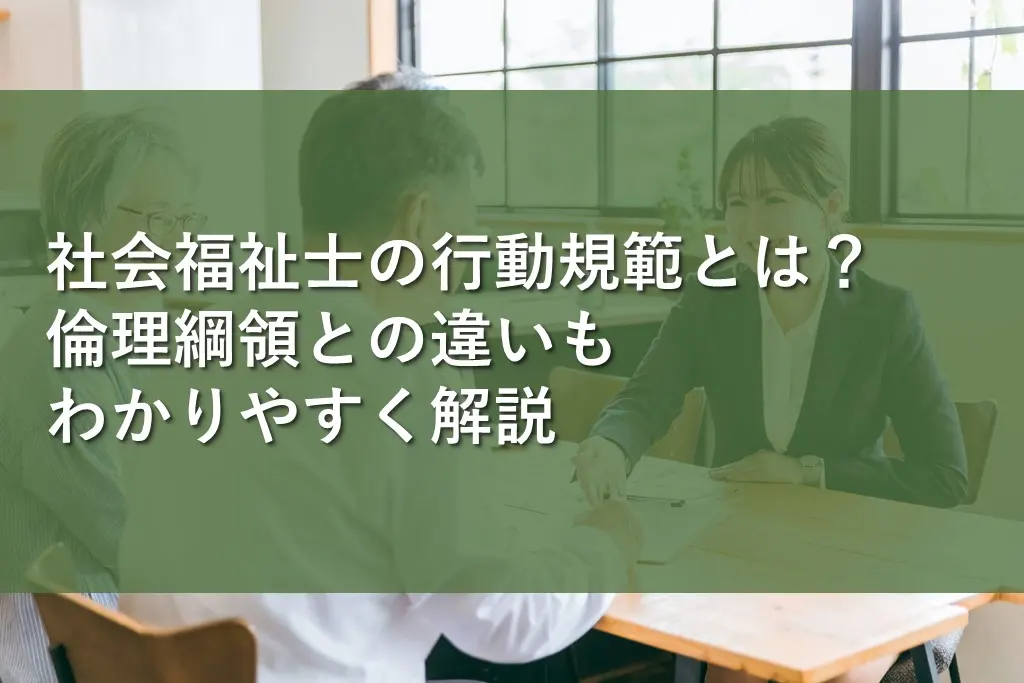
社会福祉士は、国家資格の必要なソーシャルワーク専門職として、行動規範に基づいた行動・考え方を実践しなければなりません。
理由として、社会福祉士は支援を必要とする方々に対して適切な援助を行うため、専門的な知識や技術に加えて、倫理観を持って業務にあたることが求められるからです。
行動規範とは、業務を遂行するうえでどのように行動すべきか、あるいは何をしてはならないのかを示した基準です。
本記事では、社会福祉士の行動規範の概要と具体的な内容、倫理綱領との違いをわかりやすく解説します。
目次
社会福祉士の行動規範とは?

社会福祉士の行動規範とは、公益社団法人日本社会福祉士会により定められた、社会福祉士がソーシャルワークの実践において従うべき行動の指針です。
社会福祉士の倫理綱領の内容を具体化し、日々の業務においてどのような行動が求められるのかを明確にしています。
社会福祉士の行動規範の概要
「行動規範」とは、特定の仕事において求められる行動や、してはならないことなどを明確にしたルールを指します。
社会福祉士の行動規範とは、同職の倫理綱領に基づき、社会福祉士がソーシャルワークを実践するにあたって従うべき規準です。
社会福祉士の行動規範は、倫理綱領の総体的な内容を行動に落とし込んだものと、個別の項目を具体化したもので構成されています。
社会福祉士の倫理綱領とは?
社会福祉士の倫理綱領は、ソーシャルワークの専門職として大切にすべき価値観や考え方をまとめた指針です。
1995年に制定されて以来、時代の変化に応じた内容に改定され、現在の倫理綱領は2020年6月に採択されました。
社会福祉士は、身体的または精神的、または経済的に困難な立場にいる方などに対して専門知識を活かして助言・指導を行う、高いモラルが求められる仕事です。
このことから、社会福祉士の倫理綱領では以下の6つの原理を定めています。
- 人間の尊厳:すべての人間をかけがえのない存在として尊重する
- 人権:すべての人が生まれながらの権利を持ち、どのような理由があってもその権利を抑圧・侵害・略奪する行為は認められない
- 社会正義:自由・平等・共生に基づく社会正義を実現させる
- 集団的責任:人と環境に働きかけて、互いに利益が得られる社会を実現させる
- 多様性の尊重:多様性を尊重する社会を実現させる
- 全人的存在:すべての人をさまざまな側面から見る
社会福祉士の倫理綱領について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
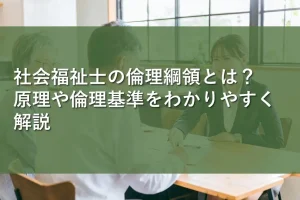
社会福祉士の行動規範の内容
社会福祉士の行動規範は、倫理綱領に基づき、以下4つの領域で構成されています。
- クライエントに対する倫理責任
- 組織・職場に対する倫理責任
- 社会に対する倫理責任
- 専門職としての倫理責任
各領域で社会福祉士が意識すべき行動規範を、具体的に見てみましょう。
クライエントに対する倫理責任
クライエント(支援対象者)に対する倫理責任では、クライエントとの関係の築き方や説明責任について定められています。
社会福祉士の仕事は、クライエントとの関係によって成り立つものです。
常にクライエントの利益を優先し、最善の支援を行うため、以下12の行動規範に基づいた実践が求められます。
| 行動規範 | 概要 |
| 1.クライエントとの関係 | 社会福祉士はクライエントとの援助関係を大切にし、その関係性を私利私欲のために利用してはならない |
| 2.クライエントの利益の最優先 | 社会福祉士はクライエントの利益を最優先させなければならない |
| 3.受容 | 社会福祉士はクライエントをあるがままに受容しなければならない |
| 4.説明責任 | 社会福祉士はクライエントが欲する情報をわかりやすく説明しなければならない |
| 5.クライエントの自己決定の尊重 | 社会福祉士はクライエントが自分で決めたことを尊重し、支援をしなければならない |
| 6.参加の促進 | 社会福祉士はクライエントの人生に影響を及ぼす決定や行動に関わり、社会への参加を促さなければならない |
| 7.クライエントの意思決定への対応 | 社会福祉士はクライエントの意思決定を支援しなければならない |
| 8.プライバシーの尊重と秘密の保持 | 社会福祉士はクライエントのプライバシーを尊重し、秘密を守らなければならない |
| 9.記録の開示 | 社会福祉士は原則として、クライエントから記録の開示請求があった場合は、開示しなければならない |
| 10.差別や虐待の禁止 | 社会福祉士はクライエントに対して差別や虐待を行ってはならない |
| 11.権利擁護 | 社会福祉士はクライエントの権利を擁護し、適切に行使できるよう支援しなければならない |
| 12.情報処理技術の適切な使用 | 社会福祉士は情報処理技術(デジタル化された情報を含む)を適切に使用しなければならない |
説明責任とは、クライエントから説明を求められた際に、相手が納得できるよう十分な情報を提供する責任のことです。
また、支援にあたって必要な情報をクライエントから提供されたとき、その情報の管理・開示には十分注意する必要があります。
組織・職場に対する倫理責任
組織・職場に対する倫理責任では、各自が所属する組織・職場の理念を理解し、最良のソーシャルワーク実践を行うよう求めています。
また、実践にあたっては所属機関の上司や同僚、部下に対し敬意を払い、それぞれの立場や専門性をふまえて協働しなければなりません。
こうした倫理責任を果たすための行動規範として、以下6項目が定められています。
| 行動規範 | 概要 |
| 1.最良の実践を行う責務 | 社会福祉士は所属する機関・職場の使命や理念を理解し、最良のソーシャルワーク実践を行わなければならない |
| 2.同僚などへの敬意 | 社会福祉士は上司や同僚の立場や専門性の違いを尊重し、敬意を払って接さなければならない |
| 3.倫理綱領の理解の促進 | 社会福祉士は自分が所属している機関・職場において、倫理綱領や行動規範が正しく理解されるように働きかけなければならない |
| 4.倫理的実践の推進 | 社会福祉士は所属する機関・職場にて、倫理綱領に基づいた実践を行わなければならない |
| 5.組織内アドボカシーの促進 | 社会福祉士は組織・職場内における虐待や差別、ハラスメントを認めてはならない |
| 6.組織改革 | 社会福祉士は人々のニーズや社会状況をアセスメントし、それらに基づいて組織改革を行わなければならない |
社会福祉士の仕事では、クライエントの利益と所属機関の方針のあいだで板挟みになり、ジレンマを感じる場面も多くあります。
このとき、所属機関の使命や理念を十分に理解したうえで、行動規範と照らし合わせ、クライエントの利益のために是正すべき点があれば提言することが大切です。
社会に対する倫理責任
社会に対する倫理責任では、社会福祉士が社会に対して行う働きかけや、ソーシャル・インクルージョンに関する行動規範が定められています。
| 行動規範 | 概要 |
| 1.ソーシャル・インクルージョン | 社会福祉士は、あらゆる差別や貧困、抑圧、排除、無関心、暴力、環境破壊を認識し、専門性を持って解決に努めなければならない |
| 2.社会への働きかけ | 社会福祉士は人権と社会正義を守るために社会に働きかけなければならない |
| 3.グローバル社会への働きかけ | 社会福祉士は人権と社会正義に関する問題について、グローバル社会へ働きかけなければならない |
ソーシャル・インクルージョンとは、日本語で「社会的包摂」といい、社会から誰一人として排除されず、すべての人が社会に参加できる状態を意味しています。
より良い社会を実現するための働きかけは、社会福祉士が担う重要な役割の一つです。
専門職としての倫理責任
専門職としての倫理責任では、ソーシャルワーク専門職としての社会的信用と専門性を高めるよう、8つの行動規範を定めています。
| 行動規範 | 概要 |
| 1. 専門性の向上 | 社会福祉士は最善の実践を行うために必要な資格を獲得し、専門性を向上させなければならない |
| 2. 専門職の啓発 | 社会福祉士は倫理綱領を守り、専門職としての社会的信用を高めなければならない |
| 3. 信用失墜行為の禁止 | 社会福祉士は信用を失墜させるような行為をしてはならない |
| 4. 社会的信用の保持 | 社会福祉士は社会的信用を保持するための働きかけを行わなければならない |
| 5. 専門職の擁護 | 社会福祉士が不当な批判を受けた場合、専門職としての立場を擁護しなければならない |
| 6. 教育・訓練・管理における責務 | 社会福祉士が教育・訓練・管理を行う場合、それらを受ける人の専門職を向上させるように努めなければならない |
| 7. 調査・研究 | 社会福祉士が調査・研究を行う場合、その目的や内容、方法を明らかにし、研究対象が不利益を被らないようにしなければならない |
| 8. 自己管理 | 社会福祉士はみずからが困難に直面する可能性があることを自覚し、心身の健康に気を配らなければならない |
社会福祉士は、より高い実践能力を発揮するために、必要な資格を所持し、専門性の向上に努めなければなりません。
研修や事例検討、自己学習などの機会を積極的に作り、身につけた専門性を実践に活かす必要があります。
社会福祉士の行動規範を守って仕事をしよう
社会福祉士の行動規範は、倫理綱領の内容に基づいた4つの領域で構成されています。
社会福祉士は、クライエントの利益を最優先に考えたうえで、組織・職場、社会に対する倫理責任も果たさなければなりません。
ジレンマを抱えやすい業務のなかでも、支援を必要とする方々に対して適切な援助を行うために、行動規範は大切な指針となるでしょう。
また、ソーシャルワークの専門職であることを自覚したうえで、専門性の向上を図る自己研鑽も必要不可欠です。
社会福祉士の行動規範を守りながら、自分に求められる役割や振る舞いを見極め、より質の高い実践に取り組んでみてください。







