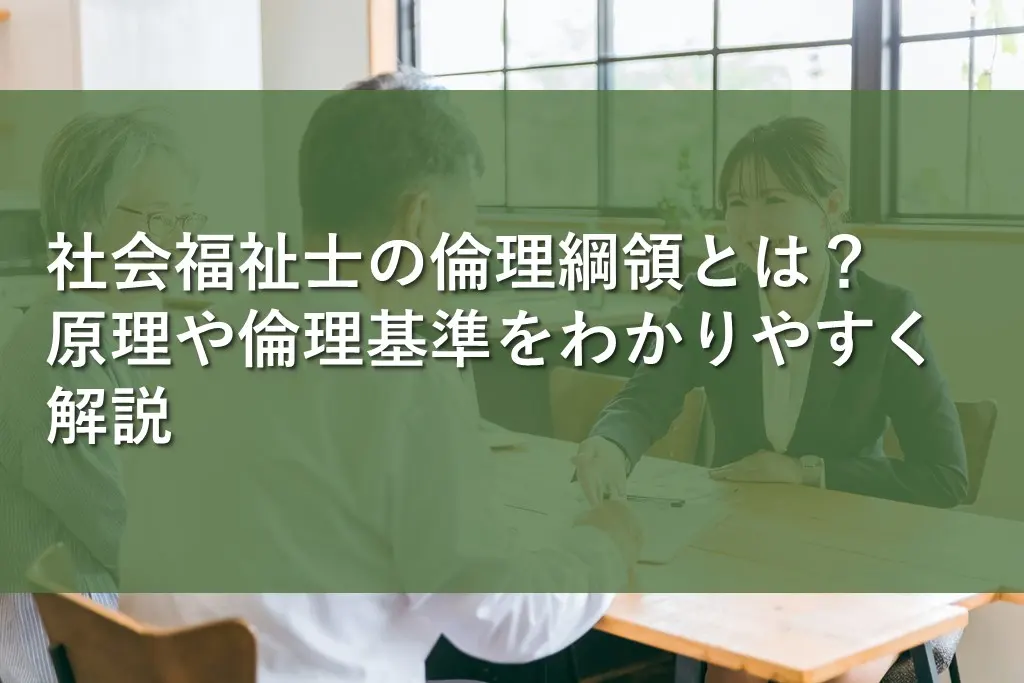
社会福祉士はソーシャルワーカーとも呼ばれ、社会福祉に深く関係する専門職の一つです。
生活課題を抱える方に対して相談・援助を行ううえで、人間の尊厳や人権、社会正義などの価値観を重要視しなければなりません。
そこで指針となるのが、社会福祉士の倫理綱領です。
本記事では、社会福祉士の倫理綱領で定められている原理と倫理基準をわかりやすく解説します。
倫理綱領がなぜ必要なのかを知り、社会福祉士が専門職として大切にすべき価値観、社会に対して果たすべき責任について理解を深めましょう。
目次
社会福祉士の倫理綱領とは
社会福祉士の倫理綱領とは、社会福祉士という専門職に従事するうえでの価値観や行動指針を明確にしたものです。
ソーシャルワーカーである社会福祉士にとって欠かせないものであり、クライエントと接するなかで忘れてはならない基本的な考え方がまとめられています。
1995年に採択されて以来、社会情勢の変化に合わせて改定が行われ、2020年6月に現在の倫理綱領となりました。
社会福祉士の倫理綱領は、前文と原理、倫理基準の3つから構成されています。
そして前文で、社会福祉士はすべての人間が尊厳を持っており、それぞれに価値がある平等な存在であることを深く認識するよう掲げているのが特徴です。
また、人と人のつながりを実感できる社会に向けて、社会福祉士はさまざまな組織と協働すると記述があります。
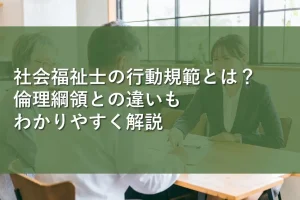
社会福祉士の倫理綱領の「原理」
従来の倫理綱領にあった「価値と原則」は、改定とともに「原理」へと変更されました。
ここでは、社会福祉士が専門職として大切にすべき価値観として以下6つを挙げています。
- 人間の尊厳
- 人権
- 社会正義
- 集団的責任
- 多様性の尊重
- 全人的存在
順に詳しい内容を見てみましょう。
人間の尊厳
人間の尊厳とは、すべての人をかけがえのない存在として尊重するということです。
倫理綱領の原理では、社会福祉士は人種や民族、国籍、宗教、性別などに関わらず、すべての人の尊厳を重んじるよう定められています。
2020年6月の改定で、これらの事項に加えて性自認や性的思考も追加されました。
社会福祉士は、クライエントにとっての自分らしい生き方や考え方を尊重し、尊厳を侵すことなく支援を行うことが大切です。
人権
人権とは、すべての人間が生まれながらにして持つ、侵してはならない権利のことです。
倫理綱領の原理において、社会福祉士は、すべての人々が生まれながらにして侵害されない権利を持つ存在であることを認識するよう定めています。
どのような理由があったとしても、社会福祉士は人の権利の抑圧・侵害・略奪を容認してはいけません。
社会正義
社会正義とは、どのようにすれば人々の尊厳が守られ、平等に扱えるのかを判断する基準であり、社会的に正しい道理のことです。
倫理綱領の原理には、社会福祉士は差別や貧困、抑圧、排除などがなく、人々が自由かつ平等に共生できる社会正義の実現をめざすよう定められています。
2020年の改定では、社会正義を果たせなくなる要因の一つとして「無関心」が追加されました。
集団的責任
集団的責任とは、人間関係におけるや相互扶助、環境への配慮など、人が集団となったときに発生する責任のことです。
倫理綱領の原理では、社会福祉士は集団の持つ力とそこに発生する責任を理解し、集団に属する人と環境の双方に働きかけて、協力関係を築ける社会をめざすよう定めています。
この際、社会福祉士は集団のなかにいる一人ひとりに目を向けて、個人を放っておかず、助け合える状態をめざさなければなりません。
集団的責任の原理は、2020年の改定で新たに追加されました。
多様性の尊重
多様性の尊重とは、自分の偏った価値観で人を判断するのではなく、個々の存在や考え方を大切にするということです。
倫理綱領の原理では、社会福祉士は個人や家族、集団、地域社会に存在する多様性に関する理解を深めたうえで、それらを尊重できる社会の実現をめざすよう定めています。
社会福祉士は、社会的弱者にあたる方や実際に差別を受けている方など、さまざまな境遇のクライエントを相手にするでしょう。
あらゆるケースに対応するためにも、多様性を尊重できる柔軟な考え方と豊かな感性が求められます。
全人的存在
全人的存在とは、人を一方的な側面だけで判断するのではなく、生物的・心理的・社会的・文化的・スピリチュアルな視点など、さまざまな側面から見ることです。
倫理綱領の原理では、社会福祉士は多角的な視点を持ち、人々を全人的な存在として認識するように定められています。
人間の痛みは必ずしも身体的なものとは限らず、精神的な痛み、生活問題などに関する社会的な痛み、存在意義を見失うなどのスピリチュアル的な痛みも考えられるでしょう。
社会福祉士は、クライエントのさまざまな痛みを和らげるため、最適なケアを実践しなければなりません。
社会福祉士の倫理綱領の「倫理基準」
倫理綱領では、社会福祉士が果たすべき責任として以下4つの倫理基準を挙げています。
- クライエントに対する倫理責任
- 組織・職場に対する倫理責任
- 社会に対する倫理責任
- 専門職としての倫理責任
それぞれ詳しく見てみましょう。
クライエントに対する倫理責任
クライエントに対する倫理責任とは、相談者やそのご家族と信頼関係を築き、相手の利益を最優先しなければならない責任のことです。
社会福祉士が活動するうえで、クライエントとの関係性は非常に重要なものであり、12項目の行動規範が設けられています。
社会福祉士は、クライエントとの専門的援助関係を何よりも大切にしなければならず、自分の利益のために相手との関係性を利用してはいけません。
また、適切な情報を提供したうえでクライエントの意思を優先し、プライバシーも尊重する必要があります。
組織・職場に対する倫理責任
社会福祉士は、持っている専門的な知識・スキルを業務へ最大限活かすとともに、他職種と連携を取りながらサービス提供を行うことが求められます。
自分が所属する組織・職場における理念や使命を理解し、最善を尽くして業務をまっとうしなければなりません。
社会福祉士は、クライエントの利益と自分の所属する組織・職場の理念との間で板挟みになり、ジレンマを感じることもあるでしょう。
このジレンマに対処する必要があることから、倫理綱領では組織・職場に対する倫理責任として6項目を設けています。
社会に対する倫理責任
社会に対する倫理責任では、社会的弱者にあたる方を含めた共生をめざすソーシャル・インクルージョンや、より良い社会を実現するための働きかけについて定めています。
差別や貧困、抑圧や排除などに立ち向かい、すべての人々が調和した社会をめざすことは、社会福祉士が担う大切な役割の一つです。
社会福祉士の倫理綱領において、社会に対する倫理責任には3項目が設けられています。
専門職としての倫理責任
社会福祉士は、クライエントに対して最良のサービスを提供するために、必要な資格を取得し、スキルアップに努めることが求められます。
社会福祉士の資格を取得したあとも、自己研鑽し専門性を磨く努力が必要です。
また、社会福祉士は、ソーシャルワークの専門職として社会的信用を失いかねない行為を避けなければなりません。
これらのことをふまえ、倫理綱領では専門職としての倫理責任を8項目設けています。
社会福祉士の倫理綱領の原理・倫理基準の内容を知って参考にしよう
社会福祉士の倫理綱領は、1995年に採択されたのち2020年の改定を経て、社会福祉士という専門職の指針として大切にされてきました。
倫理綱領の原理には、人間の尊厳・人権・社会正義集団的責任・多様性の尊重・全人的存在の6項目があり、ソーシャルワーカーの基本となる価値観が定められています。
一方の倫理基準では、クライエントや組織・職場、社会に対する倫理責任のほか、専門職としての責任にも触れており、社会福祉士が果たすべき使命がわかるでしょう。
これらの原理・倫理基準は、社会福祉士の仕事をするなかでジレンマや問題にぶつかったときに、行動規範となります。
判断や行動に迷った際は倫理綱領の内容を思い出し、実践に活かしてください。


-e1717472318883-150x150.webp)




