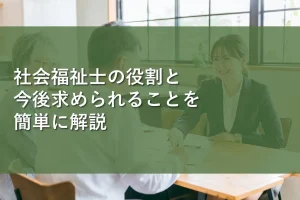社会福祉士と聞くと、福祉事業を行う施設で働くイメージを持つ人も多いことでしょう。
しかし、病院で働くことも決して珍しいケースではなく、問題を抱える患者さんやご家族の相談を受け、問題解決のために社会的支援へとつなげています。
では、病院で働く社会福祉士は具体的にどのような役割を担っているのでしょうか。
今回は、病院で働く社会福祉士の仕事内容を詳しく解説します。
目次
社会福祉士の病院での働き方

病院で働く社会福祉士は、医療ソーシャルワーカーとも呼ばれ、患者さんやご家族を支えています。
医療ソーシャルワーカーが取り組むのは、医師や看護師による医療行為では解決できない、患者さんの問題解決に向けた相談援助です。
病院の医師や看護師が担うのは、診断や治療、ケアといった医療に関わる役割が中心であり、それ以外の問題にまで対応するのは難しい状況があります。
しかし、患者さんやご家族が医療に関わらない問題を抱えており、問題解決に向けて支援を必要としているケースも少なくありません。
しかし、問題を解決せずそのままにしてしまうと、経済面で困窮し治療が続けられなくなったり、退院後に社会復帰できなくなる可能性もあります。
病院で働く社会福祉士は、患者さんやご家族の不安を丁寧に聞き取ってアドバイスを行い、必要に応じて社会的支援へとつなげるという、医師や看護師とは違う視点から支える役割を担っています。
社会福祉士の病院での仕事内容
病院で働く社会福祉士は、直接的な医療行為以外の問題を解決するエキスパートです。
患者さんやご家族の心理面から、退院後の自立へ向けた相談・支援まで、幅広い仕事を行います。
病院で働く社会福祉士の、具体的な仕事内容を以下で解説します。
心理的・社会的問題への援助
患者さんやご家族が抱えるさまざまな不安・問題を受け止め、心身の負担を軽減するための援助を行うのは、病院で活躍する社会福祉士の大切な仕事です。
思いもよらない病気を患ったり、突然大怪我を負って長期入院になった場合、心理的にも経済的にも不安を感じる人は少なくありません。
穏やかな日常生活からかけ離れた状況は、患者さん本人はもちろん、ご家族にも大きなストレスとなります。
病院の社会福祉士は、患者さんやご家族の心配ごとや不安を聞き取り、状況に合わせてアドバイスを行ったり、具体的な問題解決方法を提示して行政などの援助につなげることで、患者さんやご家族をサポートします。
退院や受診の相談支援
病院で働く社会福祉士は、患者さんの退院援助や、退院後の受診・通院に関する相談支援にも対応します。
例えば、入院している病院が自宅から遠く退院しても通院が難しい場合、社会福祉士に相談することで、転院や訪問医療サービスの利用などさまざまなアドバイスを受けられるでしょう。
母子家庭や介護が必要になった状況などで退院後の生活に不安を感じている場合は、支援機関と連携をとり、安心して療養を続けられる環境づくりに尽力します。
つまり、患者さんやご家族の状況を把握し、退院後の不安を解消するための支援を行うのも、病院で働く社会福祉士の大切な仕事です。
社会復帰支援
社会復帰支援とは、病院を退院した患者さんが、職場や学校で円滑に過ごせるよう、各方面へ事前説明を行ったり、調整を働きかける業務です。
例えば、難病を患っている患者さんが病院を退院したとします。
復職・復学にあたり、服薬や通院を継続しながら仕事や通学を続けるには、周囲の理解や協力が不可欠です。
病院で働いている社会福祉士は、患者さんが通う学校や勤務先と事前に話し合い、患者さんが問題なく社会復帰できるよう調整を行います。
地域活動
病院に所属する社会福祉士は、医療ソーシャルワーカーの立場から地域の関連施設とつながりを持ち、地域に密着した医療福祉システムを作る役割を担います。
具体的な活動内容を挙げると、地域にある患者さんとご家族を支える組織を支援したり、ボランティアの育成に貢献したりといった活動です。
社会福祉士の活動によって地域福祉活動の認知が広がれば、住民が安心して暮らせるまちづくりに貢献できるでしょう。
社会福祉士は病院で重要な役割を担う
病院で活躍する社会福祉士は、患者さんやご家族の状況・気持ちに寄り添い、的確なアドバイスや問題解決へ向けた支援を行います。
直接的な医療行為を行うことはありませんが、患者さんやご家族の心身の負担を軽減する役割を担う、責任とやりがいのある仕事です。
また、勤務先の病院と近隣の福祉関連施設をつなぎ、住民が安心して暮らせるまちづくりにも貢献します。
病院で求められる社会福祉士の役割を理解し、医療ソーシャルワーカーの立場から福祉に貢献する選択肢も検討してみると良いでしょう。
社会福祉士の役割に関する情報は、以下の記事でも詳しく解説しています。
ぜひご参照ください。