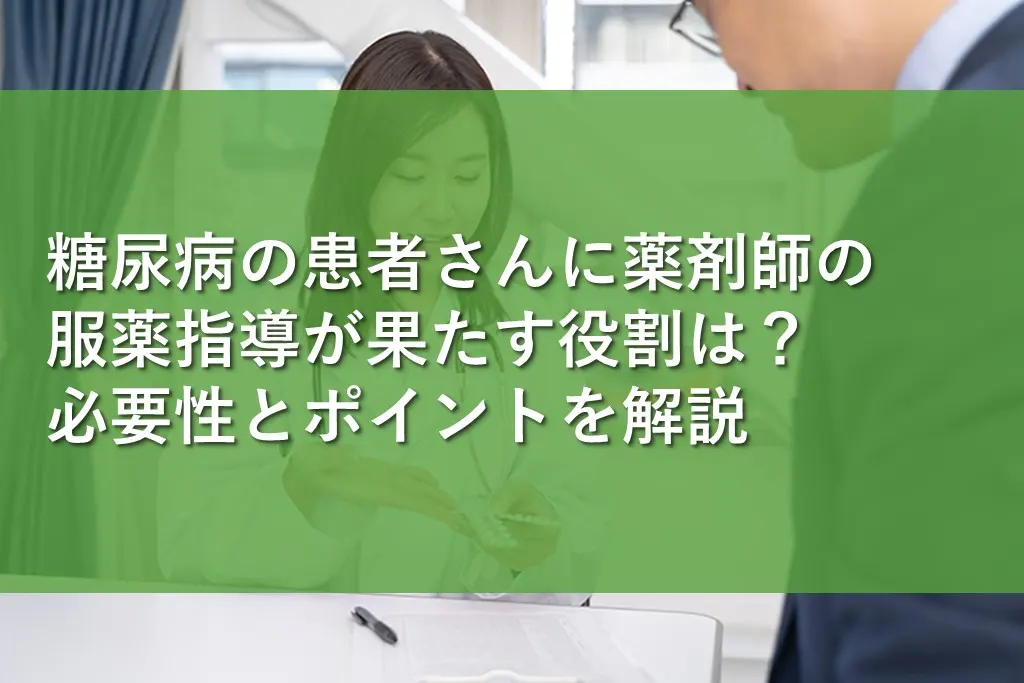
糖尿病の薬物療法に薬剤師の役割が大きいのをご存知でしょうか。糖尿病治療の大きな目的は、血糖値を正常に導いて、患者さんが健康な人と変わらない日常生活の質(QOL)を維持することです。
基本は食事療法と運動療法ですが、それだけでは不十分な場合、薬物療法が追加されます。
薬物療法は、ほとんどが長期にわたり、患者さんが薬について正しく理解できていなければ、飲み忘れや服用間違いなどを招きかねません。このとき重要な役割を果たすのが、薬剤師による服薬指導です。
本記事では、薬剤師が糖尿病患者へ服薬指導する必要性とともに、患者さんのQOL維持に貢献するための服薬指導のポイントを解説します。
目次
薬剤師による糖尿病の服薬指導の必要性

糖尿病は、予備軍を含めると国内に約2,000万人の患者さんがいると推定される生活習慣病の一つです。糖尿病患者さんに薬物療法を行う際に、薬剤師による服薬指導の果たす役割と必要性を解説します。
糖尿病患者の推移
糖尿病は、インスリンの作用不足により高血糖の状態が続く慢性疾患です。
高血糖が続くと微細な血管が傷つき、網膜症や腎症、神経障害などの合併症を引き起こすほか、より大きな血管に影響して動脈硬化や脳卒中、心臓病などの深刻な病気に発展する場合もあります。
日本の糖尿病患者数は増加傾向にありますが、治療薬の選択肢が増え、血糖コントロールの重要性についても認知が広まったこともあり、合併症の有病率は減ってきました。
薬物療法を含めた適切な治療を実施し生活習慣を見直せるかどうかが、糖尿病患者のQOL維持を左右します。
糖尿病治療薬は特に安全管理が必要な医薬品
糖尿病治療薬は、ハイリスク薬に指定されています。
特に腎機能・肝機能・心血管系の基礎疾患を持つ患者さんには、慎重な投与が求められます。
安全かつ効果的な薬物療法を実現するためには、薬の専門家である薬剤師の服薬指導が必要です。
患者さん一人ひとりの状態に合わせた服薬指導には、処方内容の確認や副作用のモニタリング、服薬状況の把握など、薬剤師のさまざまな働きが期待されています。
糖尿病治療薬は他の薬より服薬遵守率が低い
糖尿病治療薬の服薬遵守率は、他の疾患の薬と比べると高くないのが実情です。
その理由には、糖尿病が治療の終わりが見えない慢性疾患であることや、服薬に対する心理的ハードルが高くなりやすいこと、副作用が発生しやすく不安をもちやすいこと、服用する薬剤数が多くなりがちなことなどが挙げられます。
特に服用する薬剤数については、2型糖尿病患者の約半数は、ポリファーマシー(多剤併用)の状態にあり、1日5剤以上の服用が必要なケースも珍しくありません。
結果として、経口薬や注射を投与するタイミングがわからなくなるなど、服薬アドヒアランス(患者さんが自分の病気についてきちんと受け止め、積極的に治療に参加すること)が低下しがちです。調査によると、薬剤師が介入して服薬アドヒアランスが大幅に改善された事例も報告されています。
糖尿病の治療には、薬剤師による服薬指導は重要な意味を持つといえるでしょう。
糖尿病患者に薬剤師が服薬指導するときのポイント
糖尿病患者に対する服薬指導では、薬剤師には専門性を活かして情報を提供するだけでなく、患者さんに合わせた柔軟な対応が求められます。
ここでは糖尿病患者に服薬指導する際に気をつけたいポイントをまとめて紹介します。
身近な存在として対応する
薬剤師は、医療従事者のなかでも特に患者さん側の立場に近い存在として薬の飲み方をはじめとして、食事療法や運動療法の継続方法などにも、アドバイスが可能です。
そのためには、患者さんが気軽に相談できる雰囲気づくりを意識してみてください。
医師にはなかなか言い出せないことも、薬剤師になら話しやすいという患者さんもいます。
生活状況や体調の変化、薬の使用方法に関する疑問、治療への不安など、些細なことでも相談してもらえるよう、身近な医療者をめざしましょう。
丁寧に対応する
どれだけ仕事が立て込んでいても、服薬指導の場面では薬剤師は患者さん一人ひとりと向き合い、丁寧に対応する必要があります。
一方的に指導するのではなく、相手の話にしっかりと耳を傾けて、不安や疑問を話しやすい雰囲気をつくりましょう。
高齢の患者さんであれば大きな声でゆっくりとはきはき話す、子どもを連れた患者さんには絵本を手渡すなど、相手に寄り添った気配りも重要なポイントです。
患者さんとの信頼関係を築けば、服薬アドヒアランスを高めやすくなります。
指導の理由を説明する
糖尿病の患者さんは、服薬指導自体に抵抗感を抱いている場合もあります。
例えば残薬チェックをする場合に、残薬が多いと注意されるのではないかと不安になっていることがあります。血糖コントロールのためには、きちんと薬を飲む必要があるから服用状況を確認したい、飲めていないようなら一緒に飲める方法を考えたいと伝えれば、飲み忘れによる残薬を隠すことも少なくなるでしょう。
また、長期にわたって服用を続けている場合には、薬剤師による指導はもう必要ないと考えてしまう患者さんもいます。
患者さんに服薬指導を受け入れてもらうには、血糖コントロールのために一緒に頑張っていきたいこと、気になったことはなんでも気軽に相談してほしいと説明しましょう。
長期間同じ薬を服用していると服薬指導に飽きてしまう患者さんもいますから「この薬を飲むタイミングはいつでしょうか?」などクイズ形式にして患者さんに答えてもらうなど、楽しんで要点を確認できるよう、対応を工夫してみてください。
生活の様子を聞きながら指導する
薬による副作用や体調の異変にいち早く気付けるよう、服薬指導のなかで、患者さんの話を注意深く聞き取ることも服薬指導のポイントの一つです。
例えば、朝食を抜きがちな人は服薬を忘れたり、服用のタイミングにばらつきが出たりするケースがあります。
その場合、朝食なぜ抜いてしまうのかを患者さんに聞き、一緒に解決策を探りましょう。
食事による血糖値の上昇を不安に感じているようなら、食べ方のコツや食事量、メニューの選び方などをアドバイスできます。
服薬を習慣化するには、患者さんとの会話から生活状況を把握し、相手に合った服薬計画を立てることも大切です。
一包化を提案する
糖尿病患者は複数の薬を服用するケースも多く、薬の管理が負担になりがちです。
服薬指導のなかで、患者さんが薬をうまく管理できていないことがわかったら、一包化を提案してみるのも良いでしょう。
一包化すれば、薬がいっぺんに飲めるので飲み忘れを防ぎやすくなります。
ただし、患者さんの意向の確認・同意は欠かせません。
患者さんの変化も考慮する
糖尿病治療は長期に及ぶことがほとんどです。治療の間には患者さんの状態も徐々に変化していきます。
運動を始めたり食事療法に取り組んだりなど患者さんに良い変化があれば、「頑張っていますね」など、薬剤師から声をかけて前向きな姿勢を後押ししましょう。
長い治療になりますから、認知機能の低下が疑われることもあるかもしれません。気になる場合は、医師に情報共有を行い、適切な対応を検討しましょう。
患者さんが話す内容だけでなく、表情や振る舞い、話し方など、さまざまな要素から異変がないかを注意深く観察するのも薬剤師の役割です。
医療機関と連携する
患者さんは「薬による副作用が疑われる症状が出た」「錠剤が大きく服薬しにくい」などの悩みを抱えていても、医師には言いづらいかもしれません。
上述したとおり、薬剤師は患者さんにとって身近な医療者であり、医師には相談できないことでも打ち明けやすい存在になれます。
患者さんが悩みを聞かせてくれたら、必要に応じて医療機関にフィードバックして、必要な情報を共有しておきましょう。必要なら、より良い薬物療法の提案もできます。
また、薬剤師とのあいだに信頼関係が築けていれば気軽に相談ができ、患者さんも不安なく治療を受け入れやすくなるでしょうし、自己判断で服薬を中止するリスクも減らせるでしょう。
その際に、医療機関と密に連携を取っていれば、より良い治療をめざしやすくなります。
生活面を含めた長期的視点のフォロー
糖尿病は生涯付き合っていく病気であり、治療期間も長くなります。
薬剤師が糖尿病の患者さんにできることは、服薬指導だけではありません。
食事療法や運動療法など、先の見えにくい治療を頑張っている患者さんの不安の受け皿としてサポートするのも大切な役割です。
患者さんのQOL維持につなげるためには、服薬状況の確認、副作用のモニタリングに加え、生活面での進捗を確認して前向きな声かけをするなど、長期的な視点でのフォローが重要になってきます。
患者さんが自分らしい生活と治療を両立できるよう、寄り添い続ける姿勢を大切にしましょう。
糖尿病の服薬指導は患者さんのQOLも左右する大切な業務
糖尿病患者さんへ実施する服薬指導は、患者さんのQOL維持に大きく関わる業務です。
薬物療法を効果的に実施するためには、薬の専門家である薬剤師による適切な服薬指導は欠かせません。
正しい服用方法を一方的に指導するのではなく、患者さんの話に耳を傾け、生活の様子を聞き取りながら、無理なく服薬を習慣化できるようアドバイスを行いましょう。
一人ひとりに合わせた服薬指導を実施し、信頼関係を構築できれば、患者さんから治療に対する正直な気持ちや不安を話してくれるかもしれません。
このとき薬剤師は、必要があれば状況を医師にフィードバックし、より良い薬物療法を提案するなど、医療機関と連携を取る積極性も求められます。
薬剤師の専門性を活かした服薬指導で、糖尿病患者のQOL維持につなげていきましょう。







