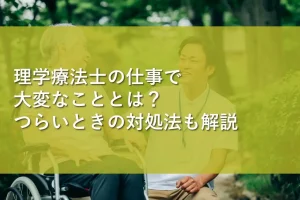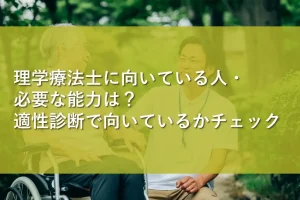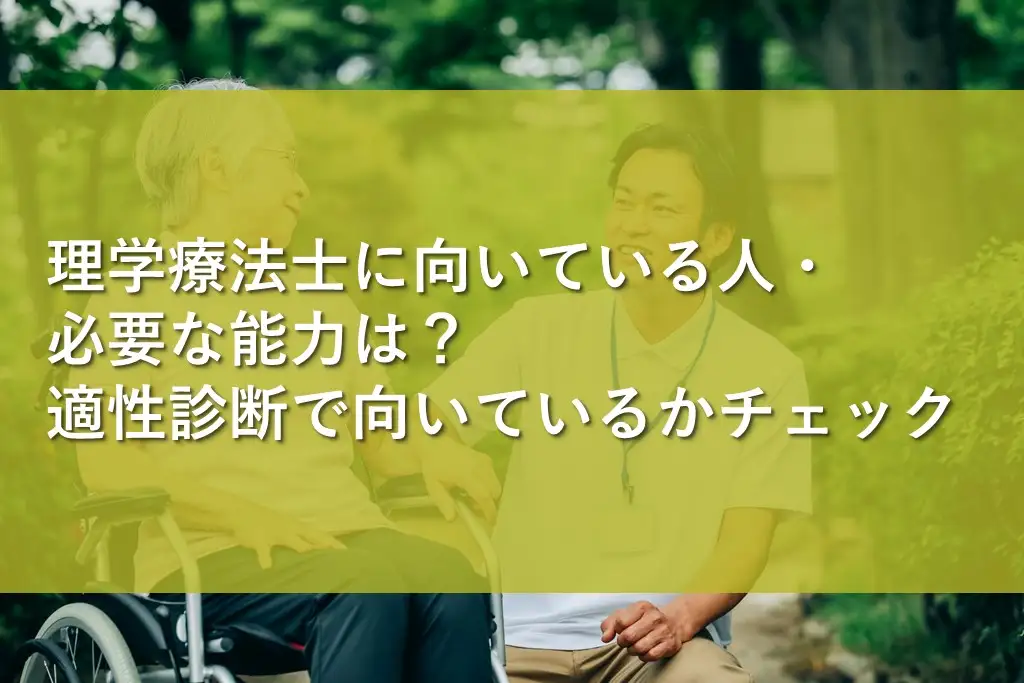
理学療法士という仕事に憧れがあるけれど、自分に向いているのか気になる人もいるでしょう。
身体に障害や不自由がある人をリハビリを通してサポートする理学療法士の仕事には、向き不向きがあることも事実です。
今回は理学療法士に向いている人や必要な能力を詳しく解説します。
最後に適性検査も用意しているので、自分が向いているか簡単に診断してみましょう。
ご自身が理学療法士に向いているかを考える参考にしてください。
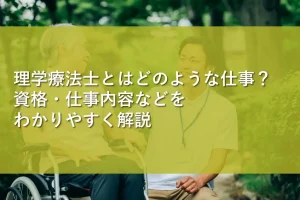
目次
理学療法士に向いている人とは?必要な能力8つ

理学療法士はリハビリを専門的に行いますが、それに対応できる専門技術と合わせて特定の能力も同時に必要になります。
ここでは長く働いている理学療法士が持っているスキルを8つ紹介します。
現在その能力がなくても、今後身につけていく努力ができるかどうかの判断材料にしてみてください。
職場や患者さんの関係者と良好な関係を築く力
理学療法士が働く現場には、さまざまな人間関係があります。
職場での人間関係では、同僚や他職種と関わる機会があります。
予期せぬことも起こる医療現場では、良好な人間関係を築くことが円滑に仕事をする鍵ともいえます。
良好な関係を築けていないと、コミュニケーションミスが起こり、業務が滞ってしまったり、素早い処置ができない場合があります。
また、患者さんやそのご家族との関係も重要です。
患者さんやご家族に信頼してもらい、良好な関係を築けると、リハビリも意欲的に取り組んでもらえます。
トラブルなどに対応できる臨機応変力
理学療法士には状況の変化をすぐにキャッチし、それに合わせて臨機応変な対応をすることが求められます。
リハビリを受けに来る患者さんは、体調や容体が安定している人だけではありません。
病院では、急変リスクが高い患者さんがリハビリを受けることもあります。
また、「具合が悪い」と自分から訴えてくれる患者さんばかりではありません。
そのため、言葉に頼らず一人ひとりの状態を把握し、判断できる知識と経験が必要です。
新人のうちは対応できなくて当たり前でも、日々の経験のなかで、勉強したり先輩を頼りながら自分のものにしていき、徐々に対応できるようになるよう努力を続ける必要があります。
ゆっくり進む改善に向き合う忍耐力
理学療法の現場では、思うような結果がすぐに出せないこともありますが、忍耐強く患者さんと向き合い続けていくことが求められます。
リハビリの多くの場合は、すぐに改善することは少なく、数ヵ月から数年かけてリハビリを続けることもあります。
また患者さんの体調はもちろん、精神面の不調でリハビリが進まなくなることもあります。
「すぐに結果を出したい」と思う方は、歯痒い気持ちになってしまうかもしれません。
理学療法士はリハビリが進まないからと自分や患者さんを責めるのではなく、根気強く取り組むことが大切と考え、計画改善を繰り返す必要があります。
忍耐強く続けることで、症状が改善される過程に立ち会えたり、患者さんの喜ぶ姿をみることができ、やりがいにもつながるでしょう。
理学療法士として継続して学ぶ意欲
理学療法士は、一度国家資格を取得すると、期限や更新はなく一生物の資格となります。
しかし、学校を卒業して資格を取得したら勉強が終わるわけではありません。
現場で出会う事例や、日々進歩する医療を知識として積んでいくためには、継続して学ぶことが重要です。
現場でわからないことがあれば、そのままにせず参考書などで調べたり、先輩に助言をもらったりしながら解決するよう努めます。
「患者さんへより良いリハビリを提供したい」という気持ちを持ち続け、現場での経験だけでなく、講習や勉強会にも参加して知識を増やすことも大切です。
理学療法士には、継続して学ぶ意欲も欠かせないのです。
細かい変化に気付ける観察力
理学療法士には、リハビリ中も常に患者さんを観察し、変化に気付ける観察力が必要です。
「臨機応変力」でも説明しましたが、リハビリを行うのは状態が安定している人ばかりでなく、急変リスクが高い人もいます。
観察力を持ち、ちょっとした変化も見逃さず早期対応することで、状態の悪化を免れることもあるでしょう。
観察力は元々備わった才能ではなく、経験や知識を積み重ねることで身についてくるものです。
最初は変化に対応できず向いていないと思うこともあるかもしれませんが、自信を失わず勉強を続けることが大切です。
リハビリ中以外にも、日常での患者さんの身体の使い方や、生活動作の観察も重要です。
患者さんならではの家事や趣味、運動などの生活習慣をリハビリに取り入れることで、患者さんのモチベーションを保つことにもつながります。
広い視野で観察していくことが大事です。
患者さんの困りごとを聞き出すコミュニケーション能力
理学療法士として働くうえで、切っても切り離せないことがコミュニケーションです。
患者さんはもちろん、そのご家族とのコミュニケーションも発生します。
リハビリは患者さんと適宜コミュニケーションを取りながら進めていきます。
そこでのコミュニケーションは、自分が教えたい内容や、励ましの言葉を伝えるだけではありません。
患者さんが伝えたいことを言いやすい環境を作り、双方向での意思疎通を行うことが重要です。
発言しやすい雰囲気作りはもちろんですが、なにより信頼関係を築くことがスムーズなコミュニケーションにつながります。
短い時間のなかで信頼を置いてもらえるよう、理学療法士は患者さんに寄り添いながらリハビリを実施します。
ご家族とも密にコミュニケーションを取り、対象者とご家族の双方の意見を取り入れながらリハビリを計画していく必要もあります。
業務も勉強もこなせるだけの体力
理学療法士には知識や経験がもちろん大事ですが、それと同等に体力も必要な仕事です。
リハビリは、対象者ができないことを少しずつできるようにしていく作業です。
できるようになるためには挑戦を続ける必要があり、転倒などのなんらかのリスクをともなうことも考えられます。
万が一、患者さんが転倒しても支えるためには、瞬発力や支えられるだけの体力が必要になります。
体力に自信がない人は、鍛えるなどの努力が不可欠です。
また理学療法士は勉強を続ける必要があるため、仕事のあとや休日に、振り返りや研修に参加することもあります。
仕事後や休日に疲れてぐったりしてしまうような人は、勉強したくてもできずに悔しい思いをしてしまうかもしれません。
疲れていても勉強できるように、日頃から生活習慣を整えて、勉強を生活習慣に取り入れるような工夫も必要です。
ストレスを発散できる力
理学療法士は人との交流が多い仕事のため、ストレスを受けることも多々あります。
ストレスは、自分を刺激し成長できる要因の一つともなるため、一概に悪いものというわけでもありません。
ストレスとうまく付き合っていくことが、充実して仕事を続けていく秘訣になります。
感じているストレスが辛すぎる場合は改善することも重要ですが、一時的に感じる軽いストレスであれば、上手に発散できる方法を見つけておくことも大切です。
ストレス発散方法は、さまざまなものがありますが、たくさん寝たり、身体を動かしたり、マッサージでリラックスしたりなど、自分に合った方法を探しておくと良いでしょう。
理学療法士に向いているか知りたい!表で適性診断
理学療法士に向いているか、簡単に確認できる適性診断を用意しました。
下表には、理学療法士に必要と思われる10個の項目が並んでいます。
その項目1つずつに、過去の経験や自分の性格から「あると思う」「わからない」「ない」で答えてみてください。
| あると思う(具体的なエピソードもある) | わからない | ない(具体的なエピソードも思い浮かばない) | ||
| 1 | 細かい変化によく気付くと言われる | |||
| 2 | 人と会話することが好き | |||
| 3 | ポジティブで物事を前向きにとらえられる | |||
| 4 | コツコツと何かをすることが好き | |||
| 5 | 人が困っていたら助けたいと思う | |||
| 6 | 専門的分野に興味がある | |||
| 7 | 一度始めたことは最後まで根気よく続ける | |||
| 8 | 体力がある | |||
| 9 | 身体機能に興味がある | |||
| 10 | 医療に興味がある |
「あると思う」が多いほど理学療法士に適性があります。
「ない」や「わからない」が多い人でも、なぜ「ない」と思ったかを考えて、絶対にできないわけでなければ、努力次第で改善していくこともできるでしょう。
理学療法士は日々の変化や成長を楽しめる人が向いている
理学療法士は、さまざまな病状や精神状態にある患者さんに対応します。
早く回復する人もいれば、ゆっくり時間をかけて回復していく人もいるでしょう。
変化する状況を見極めて臨機応変に対応し、忍耐力を持って継続できる人が、理学療法士には向いています。
理学療法士のさまざまな適性を紹介しましたが、なにより「患者さんをリハビリで救いたい、助けたい」と心から思えるかどうかが重要です。
その気持ちがあれば、日々の変化や回復していく患者さんの姿にやりがいを感じ、理学療法士を天職としていきいきと働けるでしょう。
今回は理学療法士が向いている人や必要な能力について解説しました。
自分に適性があるかを考えて、もし適性があり「やってみたい」と思った人は、ぜひ理学療法士をめざしてください。