
管理栄養士の試験勉強は、働きながらでも可能です。
しかし、勉強方法を工夫しなければ非効率で仕事と勉強の両立が難しく、合格も遠のいてしまうでしょう。
本記事では、管理栄養士の試験概要や難易度を踏まえて、働きながら効率よく合格に近づける勉強方法を解説します。
出題内容を網羅するためには、試験1年前からの勉強計画も重要であるため、スケジュールの立て方の参考にしてください。
目次
管理栄養士の試験勉強は働きながらでもできる

管理栄養士の試験勉強は、働きながらでも可能です。
ただし、働きながら管理栄養士の試験勉強をする前に、次の2点を確認しておきましょう。
- 管理栄養士の受験資格を満たしているか確認
- 管理栄養士の試験内容や難易度
それぞれ詳しく解説します。
管理栄養士の受験資格を満たしているか確認
管理栄養士の国家試験を受験するには、まず下記の受験資格を満たす必要があります。
- 修業年限2年の栄養士養成施設を卒業し、栄養士免許を取得後、3年以上栄養指導に従事
- 修業年限3年の栄養士養成施設を卒業し、栄養士免許を取得後、2年以上栄養指導に従事
- 修業年限4年の栄養士養成施設を卒業し、栄養士免許を取得後、1年以上栄養指導に従事
- 修業年限4年の管理栄養士養成施設を卒業
栄養士免許を取得しており、就業年数や栄養指導の実務経験年数を満たしていれば、国家試験を受験できます。
受験資格を満たしているか確認しましょう。
管理栄養士の試験内容や難易度
管理栄養士の試験内容は下表の9科目と応用力試験で、出題数は200問と幅広く出題されます。
| 科目 | 問題数(問) |
| 社会・環境と健康 | 16 |
| 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 26 |
| 食べ物と健康 | 25 |
| 基礎栄養学 | 14 |
| 応用栄養学 | 16 |
| 栄養教育論 | 13 |
| 臨床栄養学 | 26 |
| 公衆栄養学 | 16 |
| 給食経営管理論 | 18 |
| 応用力試験 | 30 |
応用力試験は、栄養管理の実戦で求められる知識、思考、判断力などが評価される内容です。
合格基準は60%で、120問以上の正答が求められます。
実際の管理栄養士国家試験の全体の合格率は、令和5年で56.6%、令和4年で65.1%で、毎年60%前後です。
しかし、合格者の大半を新卒者が占めており、既卒者の合格率は25.9%とかなり低いため、働きながら合格することの難しさが伺えます。
幅広い試験科目を網羅して合格基準を達成するには、合格のポイントを押さえて効率よく勉強する必要があるでしょう。
働きながら管理栄養士をめざす勉強方法5つ

忙しい社会人でも働きながら管理栄養士をめざすには、次の5つの勉強方法を押さえて進めていくと良いでしょう。
- 勉強開始までにテキスト購入・科目の優先順位をつける
- ゴールまで逆算して勉強スケジュールを立てる
- 暗記よりも過去問を中心に勉強して内容を落とし込む
- 模擬試験を受ける
- モチベーションに頼らずコツコツ継続する
合格のために一つひとつ進めていきましょう。
1.勉強開始までにテキスト購入・科目の優先順位をつける
まずは管理栄養士の国家試験日程を把握し、試験日び1年前には勉強開始できるように、テキストを購入します。
幅広い科目から出題傾向やポイントを押さえるためには、準備を早めに行っておくのがおすすめです。
テキスト購入後は、試験の情報収集を行い、科目の優先順位をつけます。
本格的に勉強に取りかかる前に、テキストや過去問をさっと開いてみるだけでも、内容がイメージでき、自身の得意不得意を把握できます。
特に「人体の構造と機能および疾病の成り立ち」と「臨床栄養学」は、他の科目と比較しても問題数が多く配点が高いため、優先すると良いでしょう。
2.ゴールまで逆算して勉強スケジュールを立てる
試験科目がイメージできたら、ゴールまで逆算して勉強スケジュールを立てましょう。
働きながら幅広い内容の勉強を進めるのに、無計画では非効率に終わってしまう可能性があります。
スケジュールは、試験日までの年間スケジュールと、勉強時間を確保するための1日の行動スケジュールを立てるのがおすすめです。
試験日までのスケジュールを立てる
まずはテキストや過去問を効率よく進めるために、試験日までの年間スケジュールを立てます。
全科目を広く勉強する点と、暗記に時間を割くよりも過去問で傾向をつかみ、深い理解につなげるようにする点に注意して、スケジュールを立てましょう。
スケジュール例を紹介します。
| 取り組む月 | 勉強内容 |
| 3〜7月 | テキストを中心に全科目を勉強する テキストの進捗に合わせて過去問を解き、解説を読んで考えながら内容を理解する |
| 8〜11月 | 試験の傾向をつかんで内容を落とし込むために、繰り返し過去問を解く |
| 12〜1月 | 模試を受けて苦手科目を把握し、重点的に勉強する |
| 2月 | 本番を想定して過去問を解く 足りない科目を暗記する |
例えば、スケジュールの序盤で暗記学習をしても、繰り返し学習をしなければ忘れてしまいます。
限られた時間を有効活用するためにも、過去問から全体を把握して最終的に必要な部分のみ暗記するといった、年間の学習計画を立てておきましょう。
1日の勉強(行動)スケジュールを立てる
試験日までの年間スケジュールができたら、勉強時間を確保するための1日のスケジュールを立てます。
仕事がある日は特に、隙間時間も有効活用できるよう、先に勉強を予定として入れておくと良いでしょう。
仕事がある日のスケジュール例を紹介します。
| 流れ | 勉強時間 | 内容 |
| 出勤前 | 1時間 | 1時間前に起床してテキスト・過去問を解く |
| 出勤中 | 1時間 | テキストを読む・動画配信や教材を聞き流す・アプリで勉強する |
| 昼休憩 | 1時間 | 暗記・動画配信や教材を聞き流す・アプリで勉強する |
| 退勤中 | 1時間 | テキストを読む・動画配信や教材を聞き流す・アプリで勉強する |
| 帰宅後 | 2時間 | まとまった勉強時間はテキスト・過去問を解く 家事をしながら動画配信や教材を聞き流す |
上記のように、通勤中や家事時間も有効活用すると、まとまった勉強時間が取りにくい社会人でも1日6時間勉強できます。
もちろん、プライベートな時間も大切です。
息抜きもスケジュールに組み込み、勉強を継続しやすいように計画しましょう。
3.暗記よりも過去問を中心に勉強して内容を落とし込む
働きながら効率よく勉強するためには、暗記よりも過去問を中心に勉強し、内容を落とし込むと良いでしょう。
実際にテキストを見ると「暗記しなければ」と焦ってしまいがちですが、暗記に頼ると働きながらでは追いつくのが難しいほどの内容量です。
過去問を中心に勉強すると、問題を理解しながら覚えられ、出題傾向にも慣れていきます。
誤答や不明点は解説を中心に学べ、要点を押さえられるため、効率よく勉強できるでしょう。
膨大な量でも、理解しながら知識と知識を関連づけていくと、意識して暗記しなくとも頭に残りやすいでしょう。
4.模擬試験を受ける
テキストや過去問を進めたら、模擬試験を定期的に受験し、実力を試してみましょう。
模擬試験は、本番を想定した会場受験や、気軽に挑戦できる自宅受験があります。
会場での模擬試験の方が、他の受験者もいて試験さながらの空気感が味わえるため、良い刺激を受けられたり、緊張感に備えられたりするメリットも大きいでしょう。
模擬試験の受験申し込み期限は、あらかじめ調べておくのがおすすめです。
模擬試験で判明した苦手部分はしっかり解き直して、確実に身につけていきましょう。
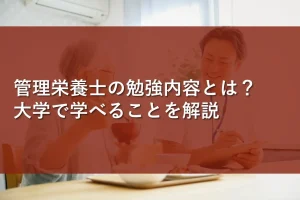
5.モチベーションに頼らずコツコツ継続する
1年間をかけて、働きながら勉強をするのはとても大変です。
最初はやる気があって勉強もはかどりますが、次第に疲れて継続できなくなる人もいるでしょう。
モチベーションに頼ると、疲れなどにより勉強できない日が生じてしまうため、モチベーションに頼らず勉強を習慣化させることが大切です。
集中して勉強するためにも、適度な息抜きをスケジュールに入れて、メリハリがある生活を送りましょう。
管理栄養士の予備校も検討すると働きながら対策可能

働きながら確実に国家資格取得をめざすなら、管理栄養士の予備校も検討すると良いでしょう。
前述したとおり、既卒者は新卒者よりも勉強時間を確保しづらい、勉強から離れている、仕事と勉強の両立が難しいなどの要因で、合格率が25.9%と低いです。
管理栄養士の国家試験は、1年に1度しかありません。
予備校での勉強は、より専門的な受験対策や、勉強相談・質問ができる講座もあるため、1年に1度の機会に備えられます。
また、通学するカリキュラムの予備校もあれば、オンライン受講できる予備校や通信講座もあるため、ライフスタイルに合わせて選ぶのがおすすめです。
予備校に通ったとしても、勉強と仕事の両立は自分次第のため、合格ビジョンを持ちながら積み重ねていきましょう。
管理栄養士の勉強方法を工夫して働きながら資格取得しよう
働きながら管理栄養士の国家試験合格をめざすのは、合格率も低くかなり難しいことです。とはいえ、勉強方法を工夫することで、合格に近づけます。
覚えないといけないことは山ほどありますが、勉強にあてられる時間は限られているため、すべてを暗記するのでは間に合いません。
優先科目に重点を置いたり、過去問で考えながら理解したりと、単純な暗記以外の方法で落とし込むと良いでしょう。
本記事で紹介した勉強方法を踏まえて、ぜひ取り組んでみてください。






