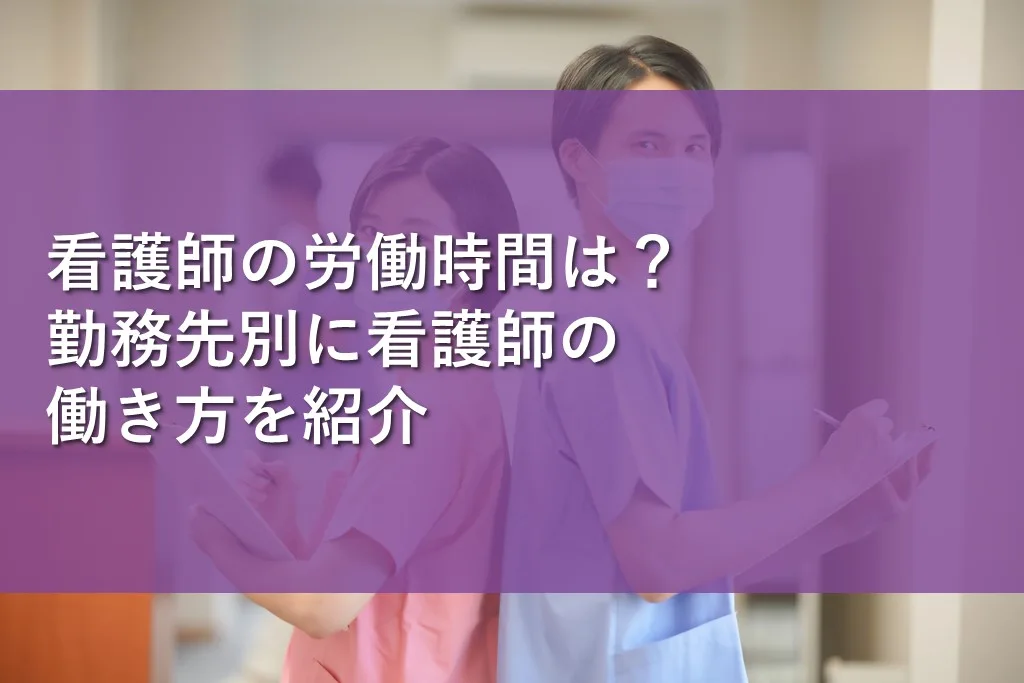
看護師が次の転職先や就職先を見つける際の重要な項目として、労働時間を挙げる方は多いのではないでしょうか?
同じ看護師であっても、どのような医療機関で働くかによって労働時間は異なってくるため、まずは勤務体制を確認することが重要です。
今回の記事では、勤務先別に看護師の労働時間や働き方を紹介していきます。
目次
看護師の労働時間と労働基準法
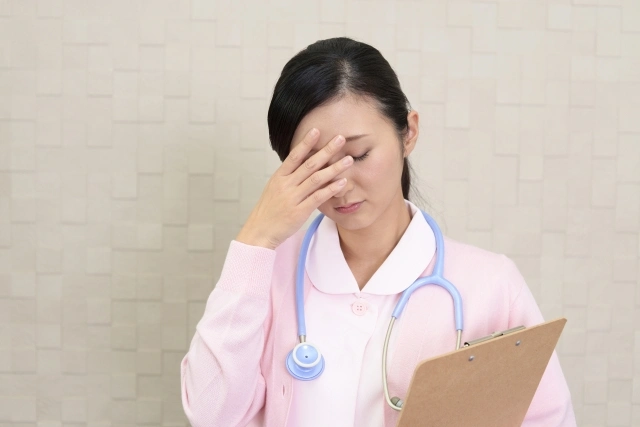
日本では労働者の労働条件を最低限度保障することを目的として、厚生労働省が労働基準法で以下のように定めています。
- 1日に8時間、1週間に40時間を超えて働いてはいけないこと
- 労働時間が6時間以上超える時は原則45分以上、8時間を超える時は原則1時間以上の休憩を取得すること
- 1週間に1日以上、4週間で4日以上の休日を取得すること
基本的には、このルールに則って勤務するよう雇用主が調整をしなければいけません。
しかし、看護師のように仕事の特性上、変則的に働かなければいけない業種もあるため、労働者を守りつつ、柔軟に働けるような体制を整える制度として変形労働制や36協定などがあります。
看護師が活躍する職場では、以下のような制度を活用してシフトを調整して勤務を組んでいるため、まずはこれらの制度を理解していきましょう。
変形労働時間制の採用
変形労働時間制は、法律的に認められた労働時間の制度の一つで、特定の期間内に働く時間数が固定されず、その期間内であれば自由に働く時間を調整できる制度です。
特定の期間は1ヵ月、1年、1週間のなかから設定できます。
例えば、1ヵ月単位の変形労働時間制を採用している病院の場合、1週間の労働時間が40時間を超えていたとしても、他の週で労働時間を調整し、1ヵ月間の1週間の平均労働時間が40時間以内であれば良いことになります。
看護師は、患者さんの健康状態に応じて24時間365日体制で働く必要があるため、変形労働時間制を導入することで、医療の需要に応じた柔軟な勤務体制を確保できるメリットがあるでしょう。
一方で、労働者である私たちは、残業時間がわかりにくくなるため、どの期間での変形労働時間制を採用しているのかを確認し、計算する必要があるでしょう。
36協定の締結
36協定とは、別名「時間外労働協定」とも言われており、労働者が法定労働時間を超える時間外労働を行う場合に、企業と労働組合が合意して締結する労使協定のことです。
36協定を締結することによって、企業側は、労働者に対して1日8時間・週40時間を超えた時間外労働や休日労働をさせることが可能になります。
そのため、この協定を締結した医療機関で働いている看護師は、勤務時間を超えても状況によって時間外労働ができる仕組みになっています。
しかし、36協定を締結したからといって、時間外労働を無制限にしても良いわけではありません。
2018年6月に労働基準法が改正され、原則月45時間、年360時間の時間外労働の上限が課され、この時間数を超えてしまうと、罰則がついてしまうこととなっています。
看護師の労働時間・勤務体制は勤務先により異なる

先述したようにさまざまな労働基準法の制度がありますが、実際の看護師の労働時間や勤務体制は勤務先によって異なります。
ここでは、典型的な看護師の働き方を勤務先別に紹介していきます。
また、この記事では、一般例を紹介していますので、実際の勤務時間は個々の就職先に確認しておきましょう。
【病院】所属部署に左右される
病院で働く看護師と聞くと、必然的に病棟で働いている看護師が思い浮かぶ人が多いかもしれません。
しかし、病院で働く看護師のなかには、主に外来勤務の看護師、オペ室勤務の看護師、病棟勤務の看護師の3パターンによって分かれており、それぞれ勤務形態が以下のように異なります。
- 病棟看護師:
24時間体制で患者さんの状態を見守る必要があるため、日勤・夜勤の2交代勤務、日勤・準夜勤・深夜勤の3交代勤務に分かれています。 - オペ室看護師:
手術は、緊急時を除いて土日・祝日は行われない病院が多いため、オペ室看護師は土日・祝日休みの日勤のみの勤務形態になっています。
また、オペ室看護師の特徴として、土日祝日などに緊急で手術が必要な状態になった時のために、オンコール体制を取っている病院があります。
月に数回のオンコール担当の日は、休みであっても病院からの呼び出しがあると、すぐに病院に駆けつけられるような体制でいないといけません。
- 外来看護師:
外来は、平日の日中のみであるため、外来看護師も基本的には日勤のみとなります。
ここからは病棟看護師に焦点を絞って働き方について紹介します。
2交代:病棟看護師は日勤・夜勤の2種類
2交替制を採用している病院で働く病棟看護師の勤務体制は、主に日勤と夜勤の2種類があります。
日勤は、8時〜17時の勤務で休憩が1時間、夜勤は16時〜9時で休憩が2〜3時間という勤務時間が主流です。
2交代の場合は、夜勤の勤務時間が長いことが特徴ですが、その分夜勤のあとの勤務は休みとなることが多く、次の勤務までの休息時間があるため疲れを取れるメリットがあります。
一方で、夜勤は日中よりも少ない看護師数で業務を回すことから患者さんの急変などが発生してしまうと忙しくて休憩時間を取れない可能性もあります。
3交代:病棟看護師は日勤・準夜勤・深夜勤の3種類
3交代制を採用している病院で働く病棟看護師の勤務体制は、主に日勤・準夜勤・深夜勤の3種類があります。
日勤は、8時〜17時の1時間休憩、準夜勤は16時〜24時半の1時間休憩、深夜勤は24時〜8時半の1時間休憩という勤務時間が主流です。
2交代制の場合と比較して、夜勤における労働時間が短いため、1回の勤務での体力的な負担は少ないメリットがあります。
一方で、さまざまな時間で出勤するため、生活パターンを整えることが難しいことや、準夜勤の次の日に日勤がきてしまうと帰宅後から次の出勤までの時間が短くなるなど、シフトパターンによっては、十分な休息が取れずに仕事を行わなければいけない状況も出てきます。
その他の勤務時間:早番・遅番・日長
勤務先の病棟によっては、先述した勤務体制以外に、早番・遅番・日長などのさらに変則的な勤務体制を取り入れている所もあります。
- 早番:
通常の日勤より早い時間(7時〜8時)に出勤し、その分早い時間(16時〜17時)に勤務が終了するシフト - 遅番:
通常の日勤よりも遅い時間(10時〜12時)に出勤し、その分遅い時間(19時〜21時)に勤務終了するシフト - 日長:
通常の日勤と同じ時間帯から勤務を開始するが、病棟が消灯するぐらい(21時)まで勤務を行う長い日勤のこと
このように、さまざまな勤務を取り入れて、それぞれの病院や病棟の特色にあった勤務体制を整えています。
【クリニック】日勤のみ
クリニックの場合は、夜間診療をしていないため、日勤の勤務が基本となっています。
また、日曜日などの休診日も固定の休みとなっているため、プライベートの時間が確保しやすい特徴があるでしょう。
一方で、同じクリニックでも夜間帯の透析を行っている透析クリニックなどの場合は、日勤以外にも遅番や日長、準夜勤などの勤務体制を取り入れている可能性があります。
【訪問看護】日勤が基本だがオンコール勤務もある
訪問看護ステーションの場合も、日勤の勤務が基本となっています。
しかし、訪問看護ステーションでは、患者さんの緊急時のために24時間対応できる体制を整えている事業者が約85%と大半を占めています。
このような体制を整えている訪問看護ステーションで働く看護師の場合は、オペ室看護師と同様に月に4〜8回程オンコール当番があるでしょう。
電話対応のみで解決する場合もありますが、状態によっては急遽出勤し、患者さんの家に訪問しなければいけないときもあります。
看護師の労働時間・勤務体制はよく確認してから勤務先を検討しよう
このように、看護師の労働時間は、働く勤務先によって変化します。
そのため、気になった職場の勤務体制は入職前に確認し、自分に合った働き方ができる勤務先を見つけることが大切です。より看護師として活躍できる勤務先を見つけてください。






