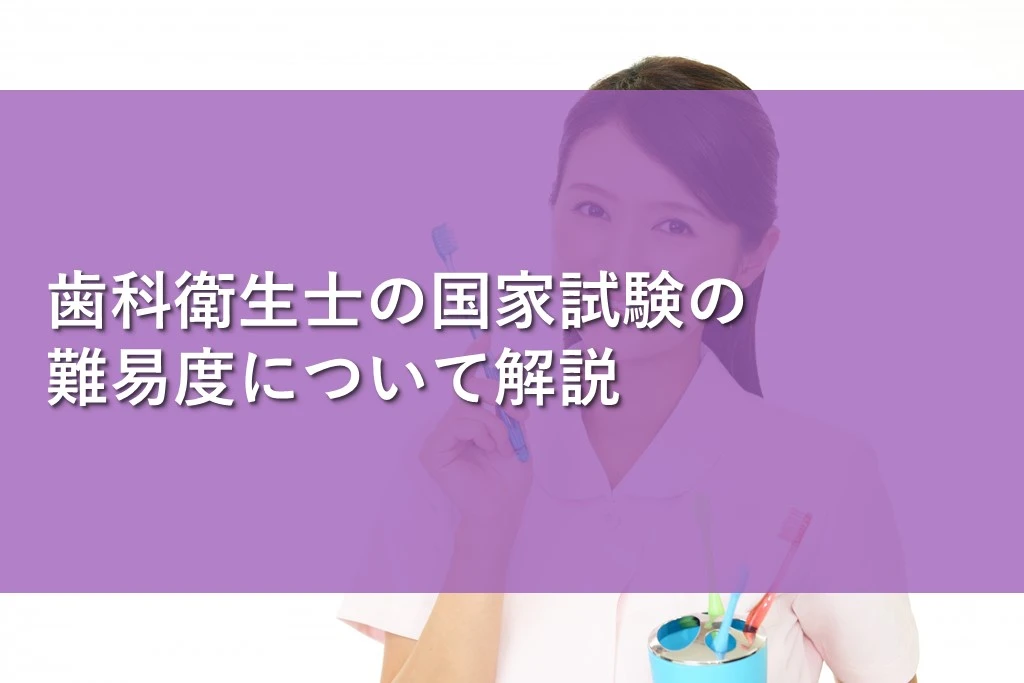
昨今、健康維持のために歯医者に通っている人や、歯列矯正のために歯医者を身近に感じている人は少なくないでしょう。
患者である私たちに寄り添ってくれる歯科衛生士に興味をもち、どうしたらなれるのか、試験は難しいのかなどと考えたこともあるのではないでしょうか。
ここでは、歯科衛生士になるための方法や国家試験の難易度について、わかりやすく解説していきます。
歯科衛生士をめざしている方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
歯科衛生士の難易度は?

歯科衛生士の国試合格率は、例年高い水準を保っています。
倍率によって合格率が左右される試験ではないため、歯科衛生士になる未来を得られるかどうかは、あくまで自分の努力次第です。
以下で詳しく解説します。
歯科衛生士の国試合格率は例年90%越え
歯科衛生士国家試験の合格率は、毎年90%を超えています。
厚生労働省の発表によると、令和5年に実施された第32回歯科衛生士国家試験の合格率は93%でした。
毎年6,000〜7,000人ほどの歯科衛生士が誕生しています。
また、歯科衛生士は年に1回の試験に合格しないとなれない職業ですが、資格を取得できれば、歯科医院だけではなく、歯科医療の製品を扱う企業なども就職先の選択肢の一つとなります。
需要は高く、求人も多くあるため、就職先に困ることは少ないでしょう。
歯科衛生士の資格は将来性がある国家資格といえます。
歯科衛生士の倍率は?
歯科衛生士の国家試験は、倍率により合格率が変動するシステムではありません。
選択回答式の全220問のうち、6割の132問に正答できれば合格となります。
周りに優秀な受験者がどんなに多くても、自分が目標点に達してさえいれば合格できるのです。
歯科衛生士の国家試験を取得するのは、高い合格率や倍率に関わらない点を見ると、簡単なように思えるかもしれません。
しかし、実際には歯科衛生士の国試受験には受験資格を得ることが必要で、それこそが資格の難易度を高めているといえるでしょう。
歯科衛生士国家試験を受験するための難易度は?
歯科衛生士の国試受験資格を得るためには、3年制以上の学校に通う必要があります。
その3年間のなかで座学や臨床実習を行いながら、歯科衛生士としての知識や技術を学びます。
仕事や子育てなどで時間に余裕がない方や、通学費用の準備が難しい方にとって、受験資格を得ることの難易度は高いといえるでしょう。
3年制以上の学校に通う必要がある
歯科衛生士国家試験の受験資格を得るためには、文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業するか、または都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業する必要があります。
以前は2年制以上の養成機関を修了すれば受験資格が手に入りましたが、平成22年4月1日までにすべての養成機関が3年制以上に変更されました。
歯科衛生士学校か歯科衛生士養成所のどちらかで3年以上のカリキュラムを修了し、単位を取得したうえで卒業をすることが国家試験受験の条件となります。
歯科衛生士の勉強内容
歯科衛生士養成機関では、カリキュラムがしっかりと組まれています。
3年制専門学校の一例として、1年生の間は歯科衛生士になるための基礎的な知識や、技術取得をめざした勉強を行います。
2年生の半ばから3年生の半ばにかけては臨床での実習を行い、3年生の後期からは国家試験に向けた勉強を含んだ総まとめを行うといった内容です。
歯科衛生士の国家試験には面接や小論文などはなく、筆記試験のみで判定されます。
学校でその対策を行う時間が設けられていることを考えると、国家試験対策は取りやすいといえます。
国家資格である歯科衛生士の難易度を理解し取得をめざそう
歯科衛生士の国家試験は合格率が高く、倍率に関わらず合格点に達することができれば資格を取得できます。
しかし、歯科衛生士の国試受験資格を得るためには、指定された養成学校や歯科衛生士専門学校に3年以上通ってカリキュラムを履修し、卒業する必要があります。
養成機関のカリキュラムでは、歯科衛生士になるための知識や技術を習得し、効率良く歯科衛生士になるための勉強を行うことができます。
国家試験の合格率が高いのは、それぞれが学業のなかで知識を身につけた結果ともいえるでしょう。






