
歯科衛生士が型取りを行う際には、歯科衛生士法に定められた業務範囲を意識しておくことが大切です。
もともと歯科医療には、歯科医師のみが行える絶対的歯科医療行為と、歯科衛生士が行っても良いとされる相対的歯科医療行為が存在します。
歯科衛生士の役割や業務範囲への理解が十分でないと、知らず知らずのうちに違法行為におよんでしまう恐れがあるため、注意しましょう。
本記事では、歯科衛生士が行える型取りの範囲と、違法行為に該当する業務を詳しく解説します。
目次
歯科衛生士の型取りは違法?

歯科医師の指示や監督がないまま、歯科衛生士が単独で型取りを行った場合、違法となる可能性があります。
その理由は、歯科衛生士法において次のように定められているためです。
歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすに当つては、主治の歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をすることは、さしつかえない。
つまり歯科衛生士は、医師の指示を受けた場合に、診療機械の使用や医薬品の授与などの診療補助が行えることになります。
したがって、歯科衛生士が歯科医師の指示を仰がずに単独で型取りを行うと、歯科衛生士法に抵触する恐れがあるのです。
ただし、歯科医師が歯科衛生士の能力で行える業務範囲を把握し、歯科衛生士に業務の遂行を許可した場合には、型取りに関する以下の行為をしても良いとされています。
- 対合印象
- 仮封
上記の業務を歯科衛生士が行ううえで知識が不足した場合には、あらためて歯科医師の指示を仰ぎ、患者さんに衛生上の危害が生じないように努めなければなりません。
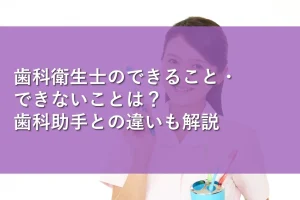
違法か合法か|歯科衛生士が行える型取りに関する業務
上述のとおり、歯科衛生士は歯科医師の指示・監督のもとで歯科診療の補助を行います。
歯科医療には絶対的歯科医療行為と相対的歯科医療行為があり、絶対的歯科医療行為は歯科医師のみが行える医療行為です。
例えば歯の切削や抜歯、レントゲン撮影などが、絶対的歯科医療行為に該当します。
一方、歯石の除去やホワイトニングなどの相対的歯科医療行為は、歯科医師の監督下で歯科衛生士が行っても良いとされる業務です。
ここからは、型取りのうち歯科衛生士が行うと違法になる業務と、携わっても問題のない業務を詳しく見てみましょう。
歯科衛生士が違法となる精密印象・咬合採得・詰め物の装着
歯科医療で行う型取りにおいて、絶対的歯科医行為に該当する業務は以下のとおりです。
- 精密印象
- 咬合採得
- 詰め物の装着
精密印象とは、補綴物を作る際に歯の形態に合わせて型取りを行うことで、大まかに印象採得を行う概形印象よりも緻密な業務です。
咬合採得は、患者さんに合った精度の高い補綴物を作るために、上下の歯の咬み合わせ位置を記録する業務を指します。
精密印象・咬合採得・詰め物の装着は、歯科医師のみが行える業務とみなされており、歯科衛生士が行うことはできません。
歯科衛生士が行える対合印象・仮封
型取りに関する業務で、歯科衛生士が行っても良い相対的歯科医療行為にあてはまる業務は、次のとおりです。
- 対合印象
- 仮封
対合印象とは、虫歯治療などで失った歯を補うために詰め物やかぶせ物を作る際、精密印象を行った歯列と上下で対になる歯の型を取ることです。
仮封は、型取りの際に治療部分を細菌から守ったり痛みを抑えたりするために、一時的に蓋をする業務を指します。
対合印象と仮封は、医師の指示や監督の下であれば、歯科衛生士が行っても違法にはなりません。
歯科衛生士の型取りは違法とならない範囲を理解しよう
歯科医療には、絶対的歯科医行為と相対的歯科医療行為が存在します。
このうち相対的歯科医療行為は、医師の指示や監督下であれば歯科衛生士が行っても問題のない業務です。
現状として、絶対的歯科医行為と相対的歯科医療行為に明確な線引きはありません。
とはいえ、歯科衛生士が歯科診療の補助を行う際には、従業員の能力や知識を十分理解した医師から指示を受けたうえで、患者さんに危害が生じないよう責任を持つ必要があります。
型取りに関する業務を安全に遂行するためにも、歯科衛生士である自分自身が携われる範囲をきちんと把握しておくようにしましょう。






