
「歯科医師国保の保障内容が知りたい」「国民健康保険と何が違うの?」と思っている方はいませんか。
国民健康保険や社会保険と違って、歯科医師国保は歯科医院に勤めている方やそのご家族に対象が限定されるため、詳しく知る機会は少ないかもしれません。
本記事では歯科医師国保の保障内容と、メリット・デメリットを紹介します。
国民健康保険や社会保険との違いも解説しますので、歯科医院への転職を検討する際などに参考にしてください。
目次
歯科医師国保とは?
歯科医師国保とは、歯科医業に従事している人とそのご家族が加入できる医療保険です。
歯科医師に限らず歯科技工士や歯科衛生士、歯科助手、受付など、歯科医院の従業員とそのご家族が加入対象です。
上記の条件に当てはまる被保険者が病気やケガをしたり、出産や死亡したりした場合に、国民健康保険法に基づいて運営が行われています。
歯科医師国保を運営する団体は、地域によって異なります。
特に「全国歯科医師国民健康保険組合」は、東京事務所と全国に20ヵ所ある支部で構成されており、歯科医師国保を運営する団体のなかでは規模が大きい団体です。
歯科医師国保の加入条件

「全国歯科医師国民健康保険組合」の加入条件は、以下のとおりです。
- 科医師会の会員
- 科医師会の会員である歯科医師のもとで働いている者
- 1、2に該当する者のご家族
住民票がある地域の指定や、同居家族の組合への加入など、条件は各保険組合によって異なります。
75歳以上になると「後期高齢者医療制度」へと移行するため、歯科医師国保の受給資格を失います。
しかし、加入している組合によっては、75歳以上になっても歯科医師国保の組合員資格を継続できる場合もあるでしょう。
組合員を継続することで、引き続き保険給付や保険事業の補助が受けられるケースもあります。
歯科医師国保の保障内容
歯科医師国保の保障内容は、法定給付と任意給付です。
法定給付は国民健康保険法で定められた給付であり、病気やケガをしたときの医療費の一部や被保険者の出産・死亡に際しての一時金を給付します。
任意給付は各組合が独自に規約を定めるもので、被保険者の病気やケガ・出産に際して手当金を支給します。
組合によっては、任意給付は支給されない場合もあるので注意が必要です。
法定給付
法定給付とは、国民健康保険法で内容を定められている給付を指します。
保険組合が必ず行うべき給付を「絶対的必要給付」といいます。
絶対的必要給付に該当する給付は、以下のとおりです。
| 給付の名称 | 給付の内容 |
|---|---|
| 療養の給付 | 病気やケガの診察・治療など |
| 入院時食事療養費の支給 | 入院時の食事療養にかかった費用を支給 |
| 入院時生活療養費の支給 | 入院時の生活療養にかかった費用を支給 |
| 保険外併用療養費の支給 | 保険適用外医療費の一部費用を支給 |
| 療養費の支給 | 療養の給付を受けるのが困難と認められたときに代わりとして支給 |
| 訪問看護療養費の支給 | 訪問看護にかかった費用を支給 |
| 移送費の支給 | 病気やケガで移動するのが著しく困難かつ緊急性が高い場合に支給 |
| 特別療養費の支給 | 保険料を滞納して資格証明書を交付された者に対し、療養の給付の代わりとして支給 |
| 高額療養費の支給 | 療養にかかった費用が著しく高額な場合に自己負担金の一部を支給 |
| 高額介護合算療養費の支給 | 医療保険と介護保険の自己負担額を一部支給 |
絶対的必要給付に対して、特別な理由があるときは支給しなくても良い給付を「相対的必要給付」といいます。
相対的必要給付は「出産育児一時金」と「葬祭費」の2つです。
| 給付の名称 | 給付の内容 |
|---|---|
| 出産育児一時金の支給 | 被保険者の出産にともない一時金を支給 |
| 葬祭費の支給 | 被保険者が死亡にともなう一時金もしくは葬儀の執行に必要なものを支給 |
任意給付
任意給付とは、各組合が独自の規約に則って給付するものです。
歯科医師国保の場合、各都道府県の団体によって給付の有無や金額が異なるため、職場がある地域の組合を確認しましょう。
任意給付にあたる給付には、「傷病手当金」と「出産手当金」の2つがあります。
傷病手当金は、被保険者が病気やケガにより仕事に就くことができず、報酬を得られない場合に、最大1年6ヵ月支給されるものです。
傷病手当金を受給するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 業務外で発生した病気やケガの療養のため休業すること
- 仕事に就けないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業期間中に給与の支払いがないこと
出産手当金の目的は、産休中の女性の出産や生活を支えることです。
歯科医師健保の組合員になって1年経過した日の翌日から、産前6週間と産後8週間休業した場合において、1日につき1,500円、最大90日間支給されます。
歯科医師国保と国民健康保険・社会保険の違い
国民健康保険は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入していないすべての人が加入する医療保険です。
社会保険の健康保険は、企業に雇用される正社員やパート・アルバイトが加入する医療保険を指します。
国民健康保険と歯科医師国保の違いは、「厚生年金に加入できるかどうか」です。
国民健康保険に加入する人は国民年金の対象となり、厚生年金への加入は不可能です。
一方で、歯科医師国保の加入者の場合、厚生年金に加入するかどうかは事業所ごとの判断に委ねられています。
社会保険の健康保険と歯科医師国保の違いは、「労使折半の有無」です。
社会保険の保険料は、雇う側と雇われる側がそれぞれ半分ずつ保険料を負担する「労使折半」が強制的に適用されます。
しかし、歯科医師国保は労使折半が義務化されていないため、労働者が保険料を全額負担するケースもあるでしょう。
歯科医師国保のメリット
歯科医師国保のメリットは、以下の2点です。
- 保険料が一律である
- 福利厚生が充実している
保険料が一律である
歯科医師国保の保険料は、所得などに左右されず一律であることが多いです。
そのため、所得などによって保険料が変わる国民健康保険と比較して、保険料の負担が少なく済む場合があります。
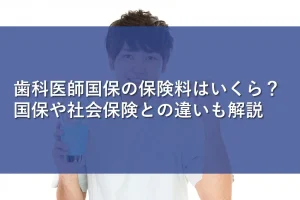
福利厚生が充実している
歯科医師国保では、被保険者の病気やケガに関する給付だけでなく「保健事業」という福利厚生もあります。
内容は組合ごと異なりますが、予防接種や健康診断、人間ドックといった健康維持や疾病予防を目的としたものが対象で、一部補助を受けられます。
保険事業の内容が気になる方は、勤務先が所属している組合のホームページをご覧ください。
歯科医師国保のデメリット
歯科医師国保のデメリットは、以下の2点です。
- 4人までしか加入できない
- 扶養がない
5人以上雇用している歯科医院や法人化している歯科医院は、社会保険の一種である「協会けんぽ」と厚生年金へ加入しなければなりません。
また、歯科医師国保には扶養の仕組みがないため、世帯人数が増えると保険料の負担が増えるでしょう。
4人までしか加入できない
歯科医師国保は、従業員が4人以下の施設に勤務していなければ加入は不可能です。
従業員が5人以上所属している歯科医院や法人化している歯科医院では、日本年金機構の健康保険(協会けんぽ)と厚生年金への加入が義務付けられているからです。
ただし、全国歯科医師国民健康保険組合や一部の歯科医師国保組合に属している場合は、協会けんぽの適用除外を受けられるため、歯科医師国保と厚生年金に加入できるケースがあります。
適用除外の手続きをせずにいると協会けんぽに強制適用されるため、手続きを忘れないように注意しましょう。
扶養がない
歯科医師国保には「扶養」の概念が存在しないため、同一世帯に属するご家族も一人ひとり保険に加入し、保険料を支払う必要があります。
つまり、世帯の人数が増えるほど保険料が高くなる仕組みになっています。
社会保険には扶養の概念が存在するため、扶養に入ったご家族に保険料の支払い義務はありません。
もし現時点で社会保険に加入していて扶養家族がいる場合、歯科医師国保に加入している歯科医院に転職すると、保険料の負担が増える可能性があるのでご注意ください。
歯科医師国保の保障内容・メリットを押さえよう
歯科医師国保は、歯科医師会に属する歯科医師や歯科医院で働く従業員とご家族が加入できる医療保険です。
歯科医師国保の保障内容は、国民健康保険法で定められた法定給付に加え、組合によっては任意給付である「傷病手当金」と「出産手当金」が支給される場合があります。
歯科医師国保のメリットは「保険料が一律である」点と「福利厚生が充実している」点です。
保険料が一律であれば、所得が上がっても保険料が上がらないため、保険料の負担が軽くなるケースがあるでしょう。
歯科医師国保は法定給付や任意給付の他にも「保険事業」により、健康診断や人間ドックなどの補助を受けることもできます。
ただし、歯科医師国保に加入できる事業所の規模には制限があり、また扶養がなく、世帯人数分の保険料を支払わなければならない点には注意が必要です。






