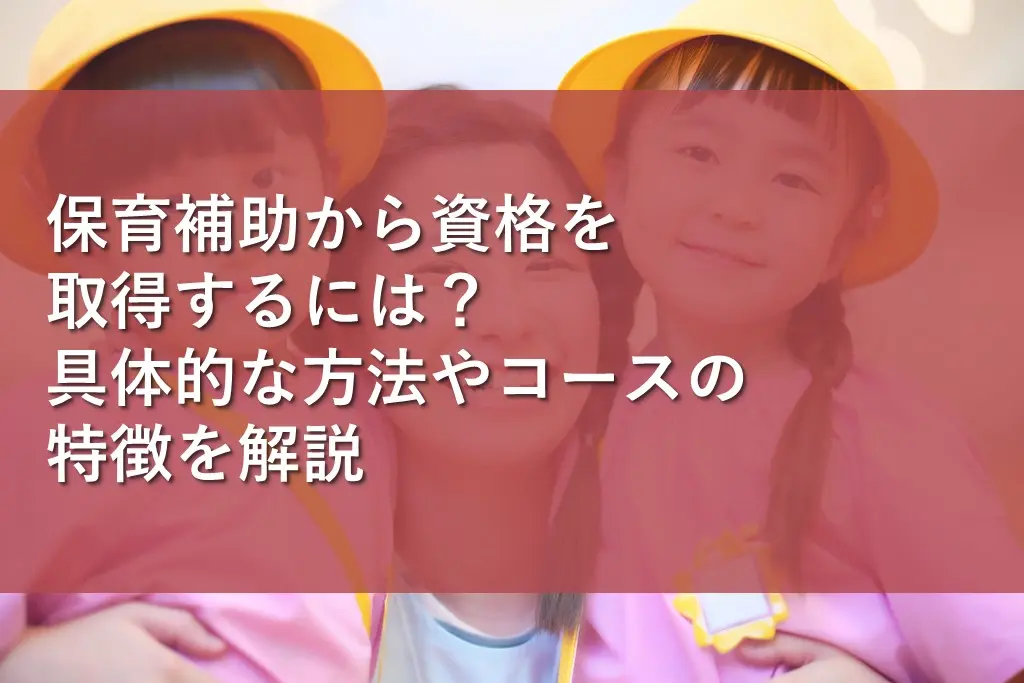
保育補助の仕事をしながら、さらなるキャリアアップをめざして資格を取りたいと考える方も多いでしょう。
保育補助自体は無資格でもできますが、より子どもと密接に関わる仕事をしたいのであれば、資格を取得することでその夢が叶うかもしれません。
本記事では、保育補助として働きながら具体的に何の資格を取得できるのか、どのような手段を踏めば良いのかを解説します。
保育分野の知識やスキル向上をめざしている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
保育補助から保育士資格を取得する方法

保育補助の経験を活かして取得できる資格に、保育士資格があります。
保育士資格を取得するルートとして、以下の4つが挙げられるでしょう。
なお、保育補助の仕事の内容については、こちらの記事をご参照ください。
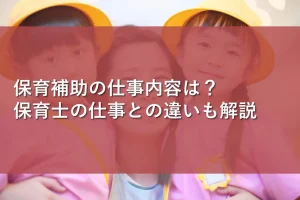
保育系の専門学校・短大・大学を卒業する
保育士資格取得までのルートとして一般的なのは、保育系の専門学校や短大・大学を卒業することです。
厚生労働大臣が「指定保育士養成施設」に指定した短大や大学、専門学校に入学し、必要科目を履修することで保育士資格を取得できます。
学費が発生するうえ、少なくとも2年の在学年数がかかる点に注意しましょう。
その一方で、保育士試験をスキップできるため受験勉強などは不要です。
子育てや保育補助の仕事をしながら在学するのはなかなかハードですが、時間をかけて保育について学びたい方や、確実に資格を取得したい方には適しているといえます。
なお、夜間学部を設けた学校もあるため、日中は保育補助の仕事を続けられる場合もあるでしょう。
通信やスクールに通って保育士試験に合格する
時間があまり取れない方や仕事を休めない方は、通信やスクールを活用して保育士試験に合格するという方法もあります。
専門学校や短大よりも必要費用を抑えられ、半年~2年程度の短期間で資格取得をめざすことが可能です。
このため、働きながら保育士資格を取りたい方に向いているといえます。
保育士養成学校に通う場合と大きく異なるのは、年2回(前期・後期)開催される保育士試験に合格しなければならない点です。
試験は例年、以下のように実施されています。
| 前期 | 後期 |
| 1月 受験申請手続き 4月 筆記試験 7月 実技試験 8月 合格通知 |
7月 受験申請手続き 10月 筆記試験 12月 実技試験 1月 合格通知 |
独学の受験も可能ですが、合格率が20%前後と低く、一から勉強資料や商材を集めるのも大変であることから、通信やスクールを活用したほうがベターです。
実務訓練を積んで保育士試験に合格する
保育士試験の受験要件は、短期大学卒業程度とされています。
しかし、中学が最終学歴の場合も、児童福祉施設にて実務経験を積むことで保育士試験を受けることが可能です。
最終学歴が高校の場合も、平成3年4月1日以降の卒業かつ保育科ではない方は児童福祉施設での実務経験が必須になります。
どの保育所や施設でも良いわけではなく、児童福祉法第7条に基づく児童福祉施設である必要があるため、あらかじめ確認しましょう。
実際に働くことで保育士の仕事がイメージできるほか、現場で役立つスキルが身につき、モチベーション向上や維持につながるかもしれません。
もちろん実務経験を積んだ先の目的には保育士試験の合格があるため、受験勉強も同時に行えると良いでしょう。
保育補助の資格取得を支援する保育園もある
保育施設によっては、無資格の保育補助職員に対して資格取得の援助を行っていることがあります。
交通費や資料代を負担してくれる施設や、勉強時間を勤務時間としてカウントする施設も増えてきました。
指定保育士養成施設で学ぶ場合、資格取得後に国が定めている訓練費用の最大70%の学費を返還してもらえます。
保育士に限らず、国や自治体による資格取得支援制度は多々あるため、事前にチェックしてみましょう。
保育補助として安定した給料を得ながら資格取得をめざしたい方に適したルートです。
なお求人情報には支援制度のことを記載していない保育園もあるため、興味がある園が見つかったら問い合わせてみてください。
保育補助から取得できる子育て支援員とは?
保育補助から取得できる資格は、保育士だけではありません。
国が定めた、子育て支援員という資格を取得することも可能です。
子育て支援員の詳細と資格の取得方法を、以下で詳しく解説します。
国が定めた子どもに関わる仕事に関する資格
子育て支援員とは、保育人材不足の解消を目的に2015年にスタートした、「子ども・子育て支援新制度」によって設置された新しい資格です。
保育士のような国家資格ではなく、地方自治体が主体となる民間資格ですが、地域の子育て支援に対し今後の活躍が期待されています。
保育士のように担任を持つことはないものの、保育士の仕事をカバーしながら子どもと関われてキャリアアップにつながる仕事です。
子育て支援員の資格取得には研修が必要
子育て支援員になるには、子育て支援員研修の受講が必要になります。
その研修内容は、各事業に共通する基本研修と、専門的内容を学ぶ専門研修の2部です。
なお、実施する場所によって都道府県・市町村など研修の実施主体が異なります。
自治体によって受講費用にも差があるため、お住まいの地域ではどうなっているのか、ホームページなどで確認しておきましょう。
保育士よりも資格の取得がしやすいと思われがちですが、勉強内容の範囲は広く、積極的に学ぶ姿勢が必要です。
また、選択するコースによっては保育事業への従事経験などが受講要件となっている場合もあります。
保育補助から子育て支援員の資格を取るための研修内容は?

保育補助から子育て支援員をめざすには研修を受ける必要がありますが、上記でも触れたとおり研修内容には基本研修と専門研修の2種類があります。
それぞれの概要を確認していきましょう。
基本研修
基本研修の目的は、子育て支援の基盤を作るために担うべき役割への理解や、子どもへの関わり方を学ぶことです。
子育て支援に関する基礎的な知識と原理、技術、倫理を修得するために、8科目に分けられた内容を合計8時間で学んでいきます。
子育て支援に関わるうえで大切な基礎知識を盛り込んだ内容になっており、この研修を受けることで子育て支援員としての自覚を身につけられるでしょう。
また、次に紹介する専門研修の前提を学べる研修領域でもあるため、集中して取り組む必要があります。
専門研修
専門研修では、子育て支援に関する各事業の具体的な取り組みを学ぶことが可能です。
研修内容は働く場所によって細分化されているものの、大まかには4つのコースに分けられます。
- 地域保育コース
- 地域子育て支援コース
- 放課後児童コース
- 社会的養護コース
自分の希望するコースはどれに当てはまるか、以下でチェックしてみましょう。
地域保育コース
地域保育コースは、基本研修と併せて受講することで、家庭的保育事業(保育ママなど)の研修と同等以上の学びを得られるコースになっています。
共通項目に加え、「地域型保育」「一時預かり事業」「ファミリー・サポート・センター」の3つの選択科目を受講することが可能です。
共通項目では乳幼児の発達や心理、安全確保など、保育するにあたっての基本的な知識と理念を学びます。
選択科目の概要は以下のとおりです。
| 選択科目名 | 時間数 | 研修内容 |
| 地域型保育 | 6科目6~6.5時間+2日以上 | 保育施設での保育従事者、あるいは家庭的保育事業の補助者をめざすコース |
| 一時預かり事業 | 6科目6~6.5時間+2日以上 | 一時預かり事業へ従事するためのコース |
| ファミリー・サポート・センター | 4科目6.5時間 | ファミリー・サポート・センター提供会員をめざせるコース |
自分のキャリアプランに合わせたコースを選びましょう。
地域子育て支援コース
地域子育て支援コースは、対象となる事業の種類が多くあるため、3つの研修カリキュラムに分けられています。
利用者支援事業の基本型と特定型、そして地域子育て支援拠点事業それぞれの違いは以下のとおりです。
| カリキュラム名 | 時間数 | 研修内容 |
| 利用者支援事業(基本型) | 9科目24時間 | 直接保育を行うのではなく、相談の支援や社会福祉を主とした内容 |
| 利用者支援事業(特定型) | 5科目5.5時間 | 基本型との共通部分に加えて、保育資源の把握などに関する内容 |
| 地域子育て支援拠点事業 | 6科目6時間 | 利用者に寄り添った地域の子育て支援について学ぶ内容 |
利用者支援事業(基本型)では、直接保育を行いません。
その代わり、子育て支援に関する情報収集・提供、地域連携に軸を据えた内容になっています。
一方、保育に特化した事業を学んでいくのが利用者支援事業(特定型)です。
保育コンシェルジュとして相談に乗り、子育て支援のニーズを把握するための研修を行います。
放課後児童コース
放課後児童コースは、放課後の児童クラブや子どもへの理解を深める研修になっています。
研修時間は6科目9時間です。
放課後児童支援の補助員であろうと業務全般を担えるよう、これまでの保育の価値観に囚われず、新たな子どもとの接し方・子育て環境について理解する内容になっています。
このため放課後児童コースでは、保護者が日中自宅にいないときに子どもを預かる、放課後児童クラブの支援者としての研修を行うことになるでしょう。
科目構成としては、子どもの育成支援や安心・安全な子どもへの対応などが挙げられます。
社会的養護コース
社会的養護コースは、社会的養護の基本的知識を持った人材の育成を目的としたコースです。
そのため社会的養護に関する基本的な理念や知識、技術を習得する内容で構成されています。
社会的養護における補助的な支援者として活躍するため、虐待を受けた子どもなどへの理解や支援技術の学習が主な科目構成となるでしょう。
乳児院や児童養護施設の補助的職員として働くことをめざしている方に適しています。
研修時間は9科目11時間の研修です。
保育補助から子育て支援員の資格を取得するための条件は?
子育て支援員の資格を取得するにあたって、受講資格の制限はありません。
保育業務に関わるうえで重要視される楽器の演奏能力も必須ではないことが特徴です。
以下で詳しく解説していきます。
子育て支援員の研修受講資格に制限はない
子育て支援員の資格を取得するための研修は、子育て経験や保育業務への従事経験がなくても受講できます。
「保育に興味がある」「子どもと関わる仕事がしたい」という方なら原則誰でも研修を受けられ、修了すれば子育て支援員を名乗ることが可能です。
子育て支援員研修修了後、実施自治体より証明書が交付されれば、全国で子育て支援員として通用します。
ただし、研修のなかには一部保育士の経験を積まないと受けられないものもあるため、各自治体のホームページを確認してみましょう。
ピアノなどの楽器を弾く能力は問われない
保育補助から子育て支援員になるための受講資格に、ピアノなどの楽器の演奏能力は問われていません。
しかし、資格取得後は子どもとより深く関わることから、保育士と同等の仕事をする可能性も見越して自主的に学んでおくと良いでしょう。
プロレベルまで上達させる必要はなく、曲のレパートリーも季節の歌や行事の歌などが弾けるようになれば十分です。
子育て支援員へのチャレンジをきっかけに、初級の練習曲からピアノに触れてみてはいかがでしょうか。
保育補助から有資格者へのキャリアアップも視野に入れよう
保育補助からめざせる資格には、保育士と子育て支援員の2種類があります。
保育士として活躍したい場合、大学や専門学校、短大に通い卒業するほか、通信やスクールを利用したり、実務経験を積んだりしたうえで保育士試験に合格しましょう。
子育て支援員は、国が定めた基本研修と専門研修を受けることで資格を取得できます。
基本研修では子どもとの関わりの基礎知識や技術、専門研修では4つのコースに分けて専門性に特化した学びを得ることが可能です。
保育補助の経験を活かしながら、自分のライフスタイルやキャリア形成を考慮し、有資格者への挑戦も視野に入れてみましょう。






