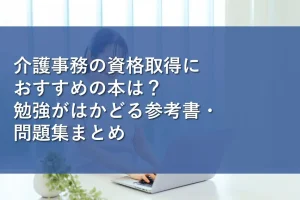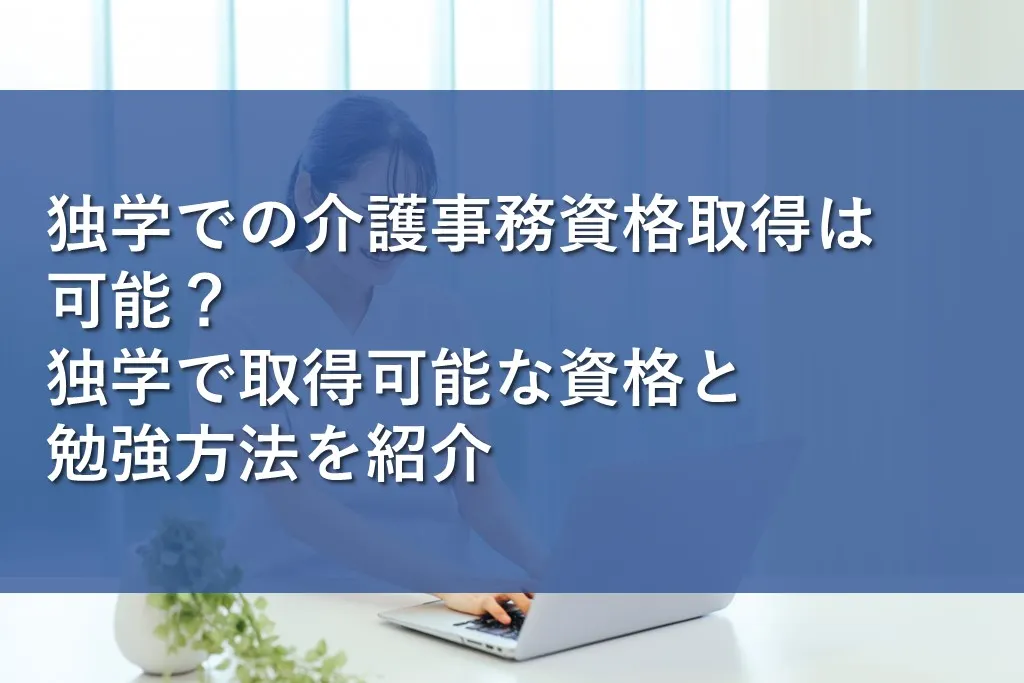
「介護事務の資格って独学で取得できるの?」
「すき間時間だけの勉強で介護事務の資格をめざせるの?」
これから介護事務の資格をめざすとなると、上記のような不安にとらわれるはずです。
独学で取得できる介護事務資格の種類や勉強の進め方などがわかれば、着実に合格へ近づけるのではないでしょうか。
今回は独学で取得できる介護事務のおすすめ資格や試験内容、学習の方法などを紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。
目次
独学で取得できる介護事務の資格3つ
介護事務の資格は複数あり、出題範囲や難易度、受験資格はさまざまです。
なかには指定の教育機関を終了していなければ受験できない資格もあります。
もしも独学で資格の取得をめざすなら、受験資格が設けられておらず誰でも受験可能な資格がおすすめです。
下記に独学で取得しやすい3つの介護事務資格を紹介します。
| 名称 | 受験料 | 試験頻度 | 試験形式 | 備考 |
| 介護事務管理士 | 5,500円(税込) | 月に1回 | 【学科】 マークシート形式:10問(共通問題7問・選択問題3問) 【実技】 レセプト点検問題:2問(全6問中2問を選択) |
毎月第四土曜日の翌日(日曜日)に試験を実施。 資料や電卓の使用が可能。 |
| 介護事務認定実務者 | 5,500円(税込) | 月に1回 | 学科】 マークシート形式:20 【実技】 マークシート形式:2問 |
毎月第四日曜日に試験を実施。 試験に参考書やノート、電卓を持ち込んでも良い。 |
| ケアクラーク | 6,900円(税込) | 年に3回 | 【学科】 マークシート形式:25問 【実技】 介護報酬請求事務・介護給付費明細書作成:2問 |
5月・9月・1月に試験を実施。審査領域には事務業務に加え、心理学やコミュニケーション学、介護技術なども含まれる。 |
介護事務管理士
介護事務管理士は専門的な知識・スキルをもとに介護報酬の請求を行う介護事務のスペシャリストです。
資格を取得すれば、ヘルパーステーションやデイサービス、グループホームなどさまざまな介護施設の事務員として勤務が可能。
また、介護施設以外にも損害保険会社やクリニック、介護系のシステム会社などで介護事務の知識を活かした業務に携われます。
介護事務管理士の資格は合格率が70%くらいと比較的高めなので、しっかりと試験対策すれば独学でも十分に合格をめざせると考えて良いでしょう。
試験概要・申し込みについてはJSMA技能認定振興協会ホームページをご参照ください。
試験内容
介護事務管理士の試験内容を下記にまとめます。
- 試験内容:学科でのマークシート10問(共通問題7問と選択問題3問)と実技でのレセプト点検問題2問(6問中から選択)
- 試験費用:5,500円(税込)
- 受験資格:受験資格はなく、誰でも受験が可能
- 受験場所:在宅
出題範囲
学科試験は、介護保険制度や介護報酬の請求などを問う法規の問題と、介護請求事務に必要とされる知識を問う問題です。
介護請求事務の問題では、介護給付費を算出し、介護給付費明細書を作成する能力と専門用語の知識が問われます。
一方、実技試験では居宅や施設、地域密着型のサービスそれぞれの介護給付費明細書を作成する問題が出題されます。
介護事務認定実務者
介護事務認定実務者は、全国医療福祉教育協会が運営する介護事務の資格です。
資格試験は毎週第四日曜日に実施されています。
受験場所は基本的に在宅ですが、認定機関の講座受講者であれば希望に応じて会場での受験を選択できます。
試験では参考書やノートなどを持ち込み閲覧できるため、試験対策で膨大な暗記は必要ありません。
また、合格率は60%から80%程度あり難易度は比較的低めであるため、独学でめざしやすい資格といえるでしょう。
介護事務認定実務者の試験概要は、全国医療福祉教育協会ホームページでご確認ください。
試験内容
介護事務認定実務者の試験内容を下記にまとめます。
- 試験内容:学科(20問)・実技(2問)ともにマークシート形式の出題
- 試験費用:5,500円(税込)
- 受験資格:受験資格はなく、誰でも受験が可能
- 受験場所:在宅(認定機関の講座を受講している場合、会場受験も選択が可能)
出題範囲
学科では介護保険制度や介護給付、介護報酬の算定に関する知識が問われます。
また介護保険制度と深い関係のある医療制度や医療保険の知識も問われるため、身につけた知識を関連づけながら学習を進めると良いでしょう。
実技では居宅サービス・施設サービスの介護給付費明細書を実際に作成します。
ケアクラーク
ケアクラークは介護事務のスキル・知識を証明するための資格として、介護保険制度が施行される前の平成12年に創設されました。
上記2資格と同様、受験資格は設けられておらず誰でも受験が可能ですが、試験回数は年3回(5月・9月・1月)に限られます。
また、試験は他の介護事務資格に比べると出題範囲が広く、コミュニケーション学や心理学、介護技術なども問われることが特徴です。
しっかりと学習のスケジュールを組んで試験に挑むことをおすすめします。
ケアクラーク試験の詳細は、一般財団法人日本医療教育財団ホームページで知ることができます。
試験概要
ケアクラークの試験内容をまとめると以下のとおりです。
- 試験内容:学科25問(マークシート形式)・実技2問(介護レセプトの作成)
- 試験費用:6,900円(税込)
- 受験資格:受験資格はなく、誰でも受験が可能
- 受験場所:在宅
出題範囲
学科では介護保険制度・請求業務に加えて、コミュニケーション学や高齢者・障がい者の心理、介護技術や医学全般の知識も問われます。
学科の出題は他の介護事務資格に比べると広範囲です。
一方、実技試験は居宅サービス・施設サービスの介護給付費明細書を作成する点で前述の2資格と変わりません。
介護事務の資格を独学で勉強する際の勉強方法
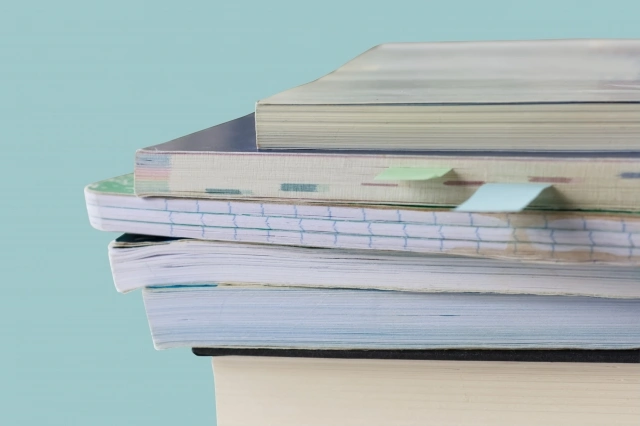
繰り返し学習は、介護事務資格の取得を独学でめざすうえで重要な学習方法です。
何度も同じ項目を読んだり解いたりすることで記憶が定着し、知識を順序立てて覚えたり他の項目と関連づけて理解したりしやすくなります。
実際、出題範囲のなかでも重要な用語や項目は解説量が多くなり、何度も繰り返し出てきます。
学習の反復によって、意図的にマーカーや付箋を使用しなくても重要な箇所を頭に入れることができるのです。
また、実技の試験対策でも、何度も同じ問題に取り組むことで解答までの手順・要領を身につけることが可能です。
たくさんの問題にチャレンジするのも良いのですが、まずはお手持ちの参考書や問題集に2回以上目を通してみましょう。
出題範囲を全体的に理解できたら、過去問を繰り返し解いてみることをおすすめします。
介護事務の資格を独学でめざすメリット・デメリット
介護事務資格を独学でめざすメリットとデメリットを解説します。
独学で資格の取得をめざす場合、メリットとデメリット両方をよく考慮したうえで検討しましょう。
介護事務の資格を独学でめざすメリット
介護事務の資格を独学でめざすメリットは、費用を抑えられることと、自分のペースで学習を進められることです。
費用を抑えられる
介護事務資格を独学でめざすメリットは、学習にかかる費用を抑えられる点にあります。
スクール・通信講座を受講して資格の取得をめざす場合、約3万円から約5万円の費用がかかります。
また、遠方のスクールに通う場合は交通費も見積もる必要があるでしょう。
一方、独学で学習を進める場合の費用は、参考書やテキストの購入にかかる数千円程度で済みます。
独学は、できる限り費用を抑えて資格を取得したい方におすすめの学習方法です。
自分のペースで勉強できる
ライフスタイルに合わせて学習を進められることも、資格を独学でめざすメリットです。
スクールでは決まった時間に授業を受け、提出期限のある課題を出されることがありますが、独学では好きな時間や場所で学習を進められます。
例えば、家事の合間や通勤中、お昼休みなどの空いた時間を活用して少しずつ問題に取り組むことが可能です。
また学習の進度も自分で決められるため、何度も出題範囲を反復して学びたい方は早いペースで問題を解き進めていくこともできます。
自分に合った学習方法で資格の取得をめざしたい場合、独学が適しているといえます。
介護事務の資格を独学でめざすデメリット
一方で、独学はモチベーション・学習効率の低下などのデメリットがあることも事実です。
効率の悪い勉強になりがち
独学でめざしやすい介護事務の資格ですが、基礎的な知識や実務経験のない状態で学習に取り組むと効率が悪くなってしまう恐れがあります。
試験で出題される介護保険の点数や要介護認定、サービスの種類などは複雑なため、机上の学習だけでは理解しづらく、誤った認識で学習を進めてしまうこともあるかもしれません。
もしも介護の知識がない状態で資格取得をめざすのであれば、的確な情報を持つ講師や一緒に学習する仲間のいる環境に身を置くのが無難でしょう。
モチベーションの維持や自己管理が難しい
介護事務の資格を独学でめざす場合に難しいことといえば、モチベーションの維持や学習の習慣付けです。
自分一人で学習スケジュールを立て、自分に合った参考書を選択し、地道に学習を継続するには、根気強さが必要です。
ときには自分の学習方法で本当に良いのか不安になったり、スケジュールどおりに理解が進まず勉強が億劫になってしまったりすることもあるでしょう。
独学での資格取得にはコスト面や手軽さにメリットがある反面、強い意志を持たねばならないことを十分に考慮しておく必要があります。
介護事務の資格を独学でめざす際の注意点
介護事務を独学で学ぶには、テキスト選びとスケジュールの立て方に注意が必要です。
以下ではそれぞれを具体的に解説します。
テキスト選び
介護事務を独学でめざすうえで重要となるのが自分に合ったテキストを選ぶことです。
最新の保険制度に対応したテキストを選ぶ
介護事務資格のテキストは、最新の情報に基づくものを選びましょう。
介護事務の学習で避けては通れない項目である介護保険制度は3年ごとに見直されています。
最近では2021年に制度の改正が行われ、次回の改正は2024年の予定です。
テキストを購入するタイミングによっては、市販のテキストでも改正後の内容が反映されていない場合もあります。
中古でテキストを購入すると、情報が最新ではないかもしれません。
介護事務のテキストを選ぶ際は、中身が最新であるか確認したうえで購入しましょう。
なお、現行の介護保険制度は厚生労働省が作成した「介護保険制度の概要」で知ることができます。
めざす資格に合ったテキストを選ぶ
介護事務の資格は複数あり、それぞれ出題内容・範囲に違いがあります。
したがって、テキストは自分が受験する資格で問われる分野を理解したうえで選ばなければなりません。
売れていてレビューで高評価がついているテキストでも、受験する資格の出題範囲が学べる内容でなければ意味がありません。
介護事務のテキストを選ぶには、めざす資格で問われることは何か、重点的に学ぶべきポイントは何かなどを整理しておくことをおすすめします。
余裕のある計画で勉強する
介護事務を独学で学ぶときは、余裕のあるスケジュールを組むことをおすすめします。
毎日の学習時間が長く、手を休める時間がないようなスケジュールだと、資格取得への準備に精神的な負担を感じてしまうでしょう。
独学を長続きさせるには、まずモチベーションの維持に心を配ります。
1時間から2時間程度の学習でもコツコツと半年ほど続ければ、十分に合格をめざせます。
早く資格を取得しようと焦るのではなく、ゆっくりと無理のない学習を進められるように計画を立てましょう。
独学でもOK!自分のペースで介護事務資格の取得をめざそう
ここまで独学でめざせる介護事務資格の種類やそれぞれの出題内容、独学のメリット・デメリットなどをお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。
介護事務の資格は受験資格が設けられていないものが多く、介護の知識がない状態でも独学で合格できます。
とはいえ、試験では専門的な知識を問われるため、余裕を持った学習スケジュールと適切なテキスト選びが重要です。
本記事が、これから介護事務の資格取得をめざす方々の効率良い学習の手助けとなれば幸いです。