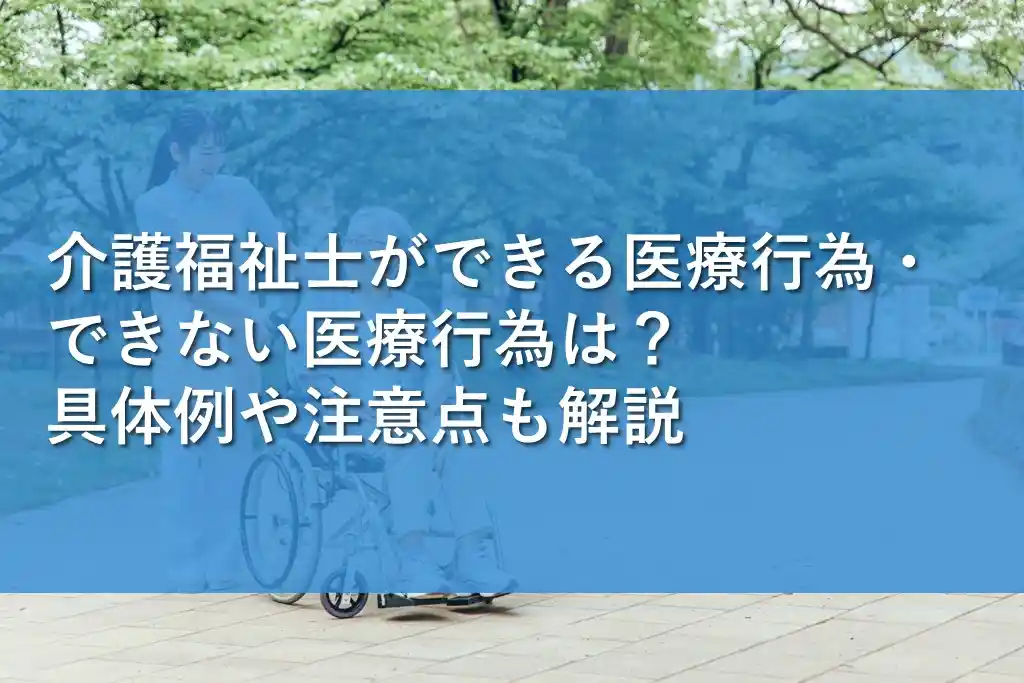
介護福祉士という職業に興味がある人はもちろん、すでに介護福祉士として勤務している人であっても、どこからが医療行為で、介護福祉士にできるのはどこまでなのかをはっきりさせておきたいと思うことがあるはずです。
また、一緒に働く看護師にとっては、どこまで介護福祉士に頼めるのかを知っておきたいという要望もあるでしょう。
そこで今回は、介護福祉士ができる行為とそうでない医療行為、また条件付きで実施できる医療行為の具体例を詳しく解説します。
目次
医療行為に当たらない、介護福祉士でもできること

はじめに、医療行為には該当せず介護福祉士でもできることを解説します。
爪切り
爪切りは、爪やその周囲の皮膚に異常がなく、糖尿病などの疾患にともなう専門的な管理が必要ない場合のみ、介護福祉士でも実施可能です。
座薬の挿入、内用薬の服薬介助
座薬の挿入をはじめ、点眼薬の投与や湿布薬の貼付、一包化された内用薬の服薬介助、鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助は介護福祉士でも行えますが、次のような条件があります。
- 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
- 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
- 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
引用元:医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
塗り薬の塗布は、褥瘡(床ずれ)の処置以外であれば可能です。
バイタルサイン測定
体温・血圧・動脈血酸素飽和度測定は、介護福祉士も実施できる行為です。
介護福祉士が実施しても医療行為に当たらないもの
続いて、介護福祉士が行っても医療行為に当たらないものはどういうものかを解説します。
- 口腔ケア(歯周病などがない場合のみ)
- ストマ装具のパウチに貯まった排泄物を捨てる(肌に接着したパウチの取り換えは禁止)
- 自己導尿の補助として、カテーテルの準備や体位の保持
- 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸液を用いた浣腸
”
これらは、利用者の病状が安定しているときに行う場合は医師法上の医行為(医療行為)に当たらないため、介護福祉士にも行えます。
ただし、利用者の病状が不安定なときなどには医療行為となることがあるため、注意が必要です。
判断に困ったら、看護職員や医師などに相談する必要があります。
研修を受けた介護福祉士のみが行える医療行為
研修を受けていれば、介護福祉士にもできる医療行為があります。
喀痰吸引と経管栄養です。
どちらも医療行為に該当しますが、同時に介護現場でのニーズが高い行為です。
それを受けて、2012年の社会福祉士及び介護福祉士法改正後は、研修を受けた介護福祉士であり、かつ利用者かご家族の同意が得られれば実施が認められるようになりました。
2016年1月以降に介護福祉士の資格を取得した場合は養成課程に研修が組み込まれていますが、それ以前の資格取得者は必要な行為ごとの実地研修を受ける必要があります。
喀痰吸引
喀痰吸引とは、専用のカテーテルを用いて口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の痰を取り除く医療行為です。
日常的に必要とされる医療行為であるため、介護施設などにおいては介護福祉士が医師や看護師との連携のもと、安全に実施されることが期待されています。
経管栄養
経管栄養は、自力での栄養摂取が難しい利用者に対して、体外からカテーテルを通して栄養や水分を投与する医療行為です。
ここでいう経管栄養とは、経鼻経管栄養、胃ろう、腸ろうを指します。
介護福祉士が行えない医療行為

ここからは、現在のわが国において介護福祉士による実施が認められていない医療行為の具体例を解説します。
褥瘡(床ずれ)の処置
褥瘡の処置は、患部の状態を観察し、アセスメントしてから適切な処置を行う必要があり、介護福祉士による処置は認められていません。
ただし、褥瘡のある利用者のオムツ交換をする際、汚物で汚染されたガーゼの交換は行えます。
インスリン注射
糖尿病の治療法であるインスリン注射は介護現場で必要とする利用者が多い処置ではありますが、注射は体に直接針を刺す行為であり、介護福祉士による実施は認められていません。
ただし、利用者本人が注射を行う場合の物品準備や体位保持介助であれば、介護福祉士でも行えます。
摘便
摘便は、便意のない人や自力での排便が困難な人に対して、肛門から指を入れて便をかき出す医療行為です。
実施方法を誤ると腸壁に傷をつけてしまい、最悪の場合は大量出血などにつながる可能性があるため、介護福祉士による実施は認められていません。
血糖測定
糖尿病がある人や高血糖のある人に対して行う血糖測定ですが、測定時に手指に小さな針を刺す必要があるため、介護福祉士は実施できません。
利用者が自分で実施できる場合は自分で、そうでない場合は看護職員等が行います。
酸素の取り扱い
介護福祉士による在宅酸素、医療用酸素の取り扱いは禁じられています。
カニューレやマスクの付け替え、酸素ボンベの交換も、手順を誤ると酸素投与が適切になされない可能性があり、危険なためです。
酸素に関わる業務は看護職員等が行います。
注射、点滴
注射や点滴は医療行為であり、介護福祉士による実施は認められていません。
介護福祉士が医療行為を覚える意味
介護福祉士にできる医療行為は限られていますが、それでも介護福祉士が医療行為を覚えることには意味があります。
介護福祉士は、介護施設に入所している利用者さんにとって最も身近な存在であるといっても過言ではありません。
介護福祉士が利用者を注意深く観察し、異常時にはすみやかに看護職員や医師に相談すれば、適切に対処できるケースがあるでしょう。
医療行為を覚えるといっても、医療行為の実施が目的なのではなく、利用者の健康状態や現状を知るため、また利用者の異常を早期発見するために重要なのです。
介護福祉士が医療行為を行う際の注意点
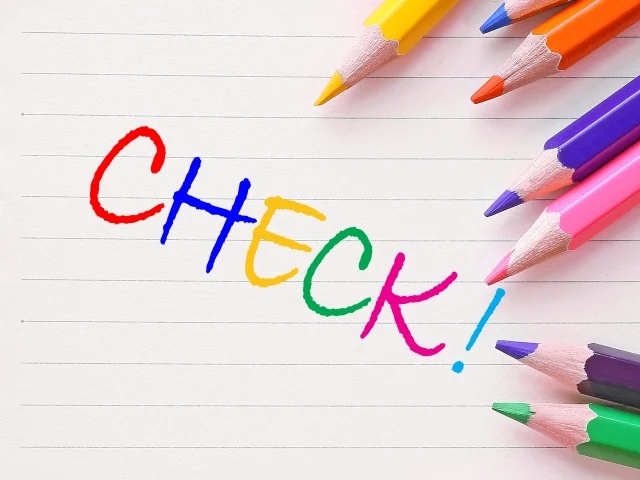
最後に、介護福祉士が医療行為を行う際の注意点を解説します。
他の職種との連携を大切にする
医療行為を行う際には、看護職員や医師など他の職種との連携を大切にしましょう。
医療行為を行う前後に利用者のことを注意深く観察し、異常があればすぐに看護職員もしくは医師に相談することが重要です。
許可されていない医療行為を求められたら、他者に相談する
介護福祉士として勤務していると、利用者さんやご家族から、介護福祉士では実施できない医療行為を求められることがあるかもしれません。
そのようなときには、介護福祉士では対応できないことを説明し、看護職員や医師などに相談しましょう。
また、施設や他の職員から医療行為を求められた場合にも、一部認められた医療行為以外は介護福祉士による実施が認められていない旨をしっかりと伝えましょう。
決して自己判断してはなりません。
看護職員または医師へ指示を仰ぐことを忘れないでください。
介護福祉士が行える医療行為を正しく理解しよう
今回は、介護福祉士にもできる医療行為と、できない医療行為の具体例を解説しました。
高齢化が進むなか、介護への需要は今後ますます高まっていくことでしょう。
医療依存度の高い利用者も増加していくかもしれません。
そのようななか、介護福祉士に求められるのは、介護福祉士として自分にできることとできないことを正しく理解することです。
積極的に多職種との連携を図りながら、安全に勤務していきましょう。






