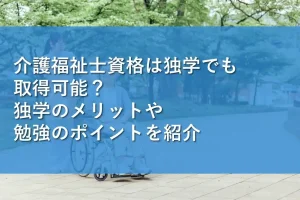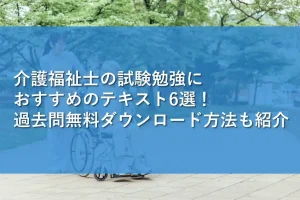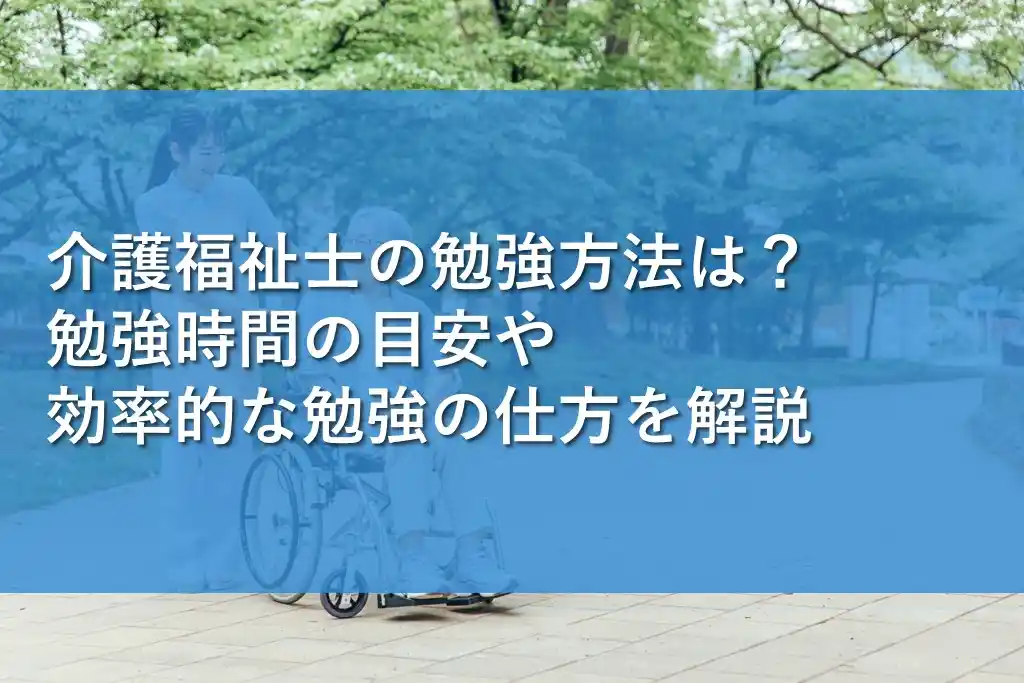
介護福祉士は、介護職員がめざす資格のなかで唯一の国家資格です。
合格率は例年70%程度と高めですが、出題範囲は幅広く、対策をしなくても受かるような簡単な試験ではありません。
そのため「仕事をしながら効率良く試験勉強を進めるにはどうすれば良いか」と悩む方もいるでしょう。
本記事では、介護福祉士国家試験合格のための勉強方法や、対策のポイントを解説しています。
やってはいけない勉強方法にも触れていますので、介護福祉士の勉強方法を知りたい方はぜひ最後までお読みください。
目次
介護福祉士の勉強方法や対策を決めるために押さえたい国家試験の傾向
試験に合格するには、自分に合う勉強方法を見つけ、効率良く勉強する必要があります。
勉強方法や対策を決めるために、まずは試験の傾向について理解を深めましょう。
介護福祉士国家試験の合格率は例年70%程度であり、他の国家試験のなかでも合格率が高い試験といえます。
筆記試験と実技試験がありますが、実技試験が免除される方が大半です。
筆記試験は4領域11科目群あり、5肢択一のマークシート式の1問1点で125点満点です。
合格基準値は総得点の60%程度を正答し、さらに11科目すべてで1点以上得点する必要があります。
介護福祉士国家試験の詳しい説明は、以下の記事をご参照ください。
介護福祉士の勉強方法は3つ
介護福祉士の勉強方法は、独学、通学、通信講座の3種類があります。
以下の表を参考に、それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の性格やライフスタイルに合わせた方法を選んでください。
| 勉強方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 独学 |
|
|
| 通学 |
|
|
| 通信講座 |
|
|
独学
独学は、勉強に必要な費用はテキスト代と試験にかかる手数料のみであり、学習スケジュールも自分で調整できます。
しかし、わからないことを相談する相手や、勉強仲間などが周囲にいないため、モチベーションの維持に苦労しがちです。
独学で試験合格をめざすコツについては、以下の記事で紹介しています。
通学
通学では、プロ講師の講座を受けながら、わからないことはいつでも質問できるため、効率良く勉強を進められます。
また、一緒に講義を受ける仲間との関わりもあり、モチベーションを保ちやすいでしょう。
ただし、講座の開講に合わせてスケジュールを調整する必要があり、3万~20万円程度の費用もかかります。
通信講座
通信講座では、パソコンやスマートフォンを利用し、自宅にいながらプロの講座を受けられます。
また、通学よりはスケジュールの融通もきくため、隙間時間などを利用した効率の良い勉強が可能です。
しかし、すぐに質問ができる環境がなく、周囲に仲間がいないため、独学と同じくモチベーションの維持に苦労することもあるでしょう。
費用面では通学よりは安価で済みますが、独学よりも多くかかります。
介護福祉士国家試験の合格に向けた勉強方法
介護福祉士の国家試験に向けて勉強する際は、以下の3段階のステップを踏むと良いでしょう。
- 過去問を解いてイメージをつかむ
- 問題を繰り返しといて知識を定着させる
- 弱点を把握し克服する
それぞれのステップについて解説していきます。
1.過去問を解いてイメージをつかむ
介護福祉士の勉強は、過去問を解くことから始めましょう。
間違えた問題についてはチェックして解説を読みつつ、まずは1周やり切ってみてください。
過去問を解くことで、試験のイメージや自分の得意・不得意を把握でき、その後の勉強で対策すべきポイントを明確にできます。
過去問を解く際には、スマートフォンの過去問アプリを利用してみても良いでしょう。
2.問題を繰り返し解いて知識を定着させる
大切なのは、インプットとアウトプットを繰り返すことです。
問題を解くことと、解説を読み理解することをバランス良く行ってください。
上述のとおり、試験の合格基準は約60%ですが、11分野のうち1分野でも0点があった場合は、総得点に関わらず不合格となります。
そのため、苦手な分野であっても、最低限の得点はできるように対策しておきましょう。
3.弱点を把握し克服する
過去問を2周、3周すると、何度も間違えている問題や苦手な分野がより明確になります。
苦手な分野のテキストや、何度も間違えている過去問の解説を読み込み、効率的なインプットとアウトプットを繰り返しましょう。
介護福祉士試験に合格するために必要な勉強時間
介護福祉士国家試験の合格に必要な勉強時間は勉強方法などによって個々で異なりますが、おおむね250時間程度といわれています。
筆記試験は例年1月下旬に実施されるため、勉強を始める時期から試験日までの残り日数を算出し、1日あたりの学習時間を算定しましょう。
以下の表は、勉強を始める時期ごとに、必要な1日あたりの学習時間をまとめたものです。
勉強を始める時期が5月初旬の場合、1日あたり1時間を学習に充てれば、試験日までに必要な勉強時間である250時間を達成できます。
| 勉強の開始時期※ | 1日あたりの学習時間の目安 | 250時間前後に到達する日数※ |
|---|---|---|
| 5月初旬~中旬 | 1時間 | 8ヵ月と10日 |
| 8月初旬 | 1.5時間 | 5ヵ月と16日 |
| 9月初旬~中旬 | 2時間 | 4ヵ月と10日 |
| 10月初旬~中旬 | 2.5時間 | 3ヵ月と10日 |
| 10月下旬~11月初旬 | 3時間 | 2ヵ月と23日 |
※1ヵ月を30日で計算
勉強において大切なのは継続です。
通勤時間や休憩時間、寝る前など隙間時間を有効活用して、着実に勉強を重ねていきましょう。
介護福祉士に絶対合格するには?対策ポイント紹介

ここでは、介護福祉士の国家試験で、合格率を引き上げるための対策ポイントを3つ紹介します。
得意な分野を伸ばす
得意分野で点数を稼ぐのは、合格率を上げるために有効です。
また、得意分野から関連付けることで、それ以外の分野も理解しやすくなります。
苦手分野で行き詰まった際には、得意分野の勉強から進めていくと良いでしょう。
ただし、前述のとおり、筆記試験では11分野のうち0点の分野が一つでもあると不合格となるため、苦手分野のことも常に意識しておく必要があります。
模擬試験を受ける
模擬試験は積極的に受けておきましょう。
模擬試験で本番さながらの緊張感を体験しておけば、実際の試験でも実力を出しやすくなります。
また、自身の実力や課題について、あらためて知るための機会にもなります。
生活の管理を怠らない
合格率を高めるためには、睡眠・食事などの生活習慣や体調管理も大切です。
特に介護職での実務経験を積みながら介護福祉士の資格取得をめざしている場合は、生活が不規則になり、睡眠不足に陥りやすくなります。
睡眠不足のときには無理に勉強せず、眠る時間をきちんと確保しましょう。
睡眠不足の状態では、勉強の効率が落ちたり、体調を崩して勉強できなくなったりなどのリスクも出てきます。
日々の生活のなかで適切に体調を管理し、万全のコンディションで日々勉強しましょう。
【やってはいけない】介護福祉士の勉強方法
ここでは、国家試験対策でやってはいけない勉強法を2つ紹介します。
すべて丸暗記するやり方
テキスト全体を丸暗記する方法は非効率です。
過去問を解き、国家試験の出題傾向を理解することで、暗記するポイントを限定するのが良いでしょう。
各分野で頻出される部分を押さえておくことで、0点の分野をなくすことにもつながります。
特に専門用語や法律の名称などは、出題頻度が高い傾向にあります。
過去問を最後に解くやり方
過去問を試験勉強の最後に解くのは、効率がよくありません。
過去問題集には、本試験での出題頻度が高い問題がまとめられています。
そのため、早い段階で過去問を解くことで、対策すべきポイントが明確になるのです。
効率的に学習するのであれば、最初に過去問を解く方法がおすすめです。
介護福祉士の国家試験に向けて効率良く勉強しよう
介護福祉士の国家試験に向けた勉強は、過去問を繰り返し解き、アウトプット・インプットをバランスよく行うことが重要です。
筆記試験の予定日から逆算して学習スケジュールを立て、効率的に勉強を進めていってください。