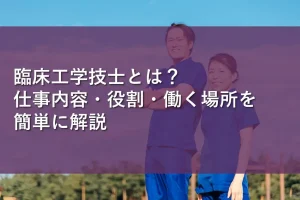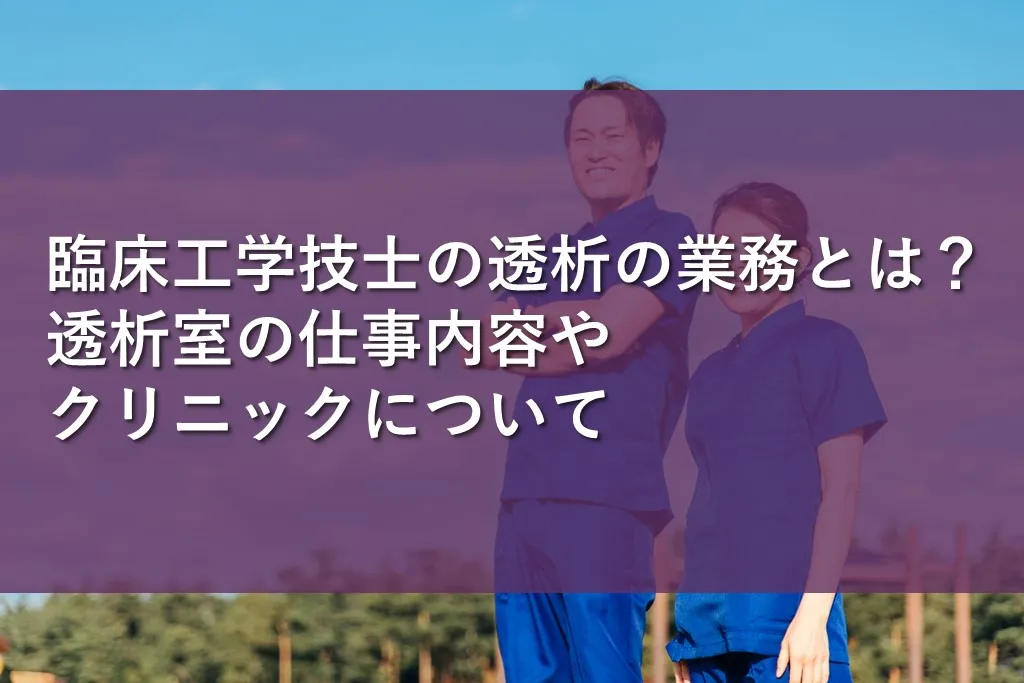
臨床工学技士をめざしている人のなかには、勤務先の業務に挙げられる透析について詳しく知りたい方もいるでしょう。
この記事では、臨床工学技士の透析業務、勤務する透析クリニックの詳細を1日の流れとともに説明します。
臨床工学技士への就職や転職を検討中の方はぜひ参考にしてください。
目次
臨床工学技士の透析室での仕事内容

臨床工学技士は透析室でどのような仕事を行っているのでしょうか。
ここでは、透析の業務内容と目的、役割を解説します。
また、透析に欠かせない穿刺についても詳しく説明します。
透析の業務内容
臨床工学技士が従事する透析業務とは、血液治療の穿刺や人工透析装置を使った血液浄化です。
血液浄化業務には、血液透析療法や血漿(けっしょう)交換療法、血液吸着法などが存在します。
では、透析室で働く臨床工学技士の1日のスケジュール例 を見てみましょう。
8:50 患者さんの状態や本日の流れを確認
9:00 午前中の透析開始
10:00 透析中の患者さんの観察
11:00 休憩(交代で1時間)
12:30 午前中の透析が終了
14:00 午後と翌日の透析準備
15:00 午後の透析開始
16:15 患者さんの情報を提供・引き継ぎ
17:00 退勤
人工透析装置の安全確認やメンテナンスを入念に行いながら、患者さんの治療にあたります。
それぞれの準備や回収、情報処理も主な業務です。
透析の目的
人工透析には血液透析と腹膜透析の2種類があります。
血液透析とは、血管に2本の針を刺して血液を体外に導き、人工腎臓を通じてきれいな血液にすることです。
悪化した腎臓の代わりに、体内の毒素や余分な水分を取り除きます。
腹膜透析とは、お腹のなかに透析液を一定期間入れておき、腹膜の血管を通じて体内の毒素や余分な水分を透析液に出すことです。
血液透析も腹膜透析も腎臓を根本的に治すのではなく、血液をきれいに保つための処置です。
つまり、人工透析とは腎臓の働きを人工的に補うのが目的といえます。
透析の役割
透析室での臨床工学技士の役割は、血液浄化業務における穿刺や人工透析装置の操作などです。
人工透析装置とは、人工透析に用いる薬剤作成装置と人工液供給装置、個人用監視装置の3つを指します。
臨床工学技士は、これら透析装置のメンテナンスや点検が主な業務です。
また、治療の準備として透析回路の組み立てを行い、さらに個人用監視装置と血液回路を操作し、透析を開始、その際に血管に穿刺をします。
透析の穿刺について
穿刺(せんし)とは、空の針を体に刺して内部の液体を吸い取る作業です。
患者さんの体から血液を透析回路へ取り出すためには、透析のたびに血管に針を指さなければなりません。
患者さんの血管には、事前に動脈と静脈を手術でつないでシャントという血管が作られており、そこに穿刺します。
シャントを作ることによって、充分な血液が確保できるようになるのです。
透析は週に3回行うのが基本で、1回につき2本穿刺します。
そのため、年間で最低でも300本以上使う計算になるでしょう。
回数が多いため、穿刺に失敗するとシャントに影響が出てしまいます。
シャントでは静脈の中を大量の動脈血が流れるため、人体は動脈血を抑えようとして瘤(こぶ)を作ることがあります。実際、その瘤は避けられません。
しかし、穿刺によってできる瘤はスタッフの注意により減らすことができます。
毎回同じ場所に穿刺を行うと、血管が狭くなるリスクが高まり、血管の壁が脆くなって瘤が形成されやすくなるのです。
瘤ができるとシャントを使える期間が短くなるため、臨床工学技士は注意する必要があります。
臨床工学技士が勤務する透析クリニックとは

臨床工学技士の勤務先の一つとして透析クリニックが挙げられます。
施設で行われる具体的な内容や、病院との違いを見ていきましょう。
透析クリニックとは
透析クリニックとは、基本的に血液浄化業務のなかでも血液透析業務のみを行うクリニックです。
仕事の種類が限られているため、トラブル対応以外は患者さんと接しながらゆっくりと時間が過ぎる 傾向があります。
患者さんとたくさんコミュニケーションが取れるので、信頼関係を築きやすいでしょう。
病院の透析とは何が違う?
病院は20床以上の入院用ベッドがある施設を指し、内科や外科など他の診療科があります。そのなかでも、大学病院はリスクの高い患者さんを中心に受け入れています。
一方、クリニックは入院用のベッドが20床未満の施設を指しますが、透析クリニックの多くは入院設備がありません。
また、臨床工学技士の業務内容も異なります。
病院の場合は血液浄化業務や機器管理業務、人工心肺業務、呼吸治療業務、手術業務を担いますが、透析クリニックでは血液浄化業務が主な作業です。
透析クリニックは透析に特化した施設であり、専門性を高めたい人に向いているでしょう。
どちらも個人ごとに役割がありチームで働いている
透析クリニックでも病院でも、臨床工学技士はさまざまな生命維持管理装置を操作するため、個人で重要な役割を担います。
しかし、臨床工学技士として働くには、チーム医療も大切だと理解しておく必要があるでしょう。
臨床工学技士は、多くの看護師や医師と関わりながら仕事をします。
看護師とは医療機器の操作についてアドバイスしたり、患者さんの情報を交換したり、お互いに協力しながら働きます。
また、医師との連携はとても重要で、手術室では高い技術と信頼関係が必要です。
透析に関するQ&A

ここでは、透析室がどのような場所なのか、臨床工学技士と看護師の透析業務の違い、透析の仕事におけるやりがいを紹介します。
臨床工学技士が勤務する透析室はどのような場所?
透析室は腎臓の働きが悪化して腎不全になった人が透析治療を行う場所です。
透析室で行われる業務は、機器管理や臨床業務、水質管理、透析情報管理であり、臨床工学技士は医師や看護師、薬剤師、栄養士といった専門家と連携して作業にあたります。
なかには、患者さんからアドバイスを求められたり相談を受けたりする場合もあります。
臨床工学技士の主な仕事は、穿刺や生命維持管理装置の点検および管理ですが、ただ自分の役割をこなすだけではなく、前述したようにスタッフ間との情報共有も大切です。
臨床工学技士と看護師の透析業務の違い
透析室で働く臨床工学技士と看護師の業務の違いを表にまとめてみました。
| 臨床工学技士 | 看護師 |
| ● 血液浄化療法業務 (人工透析装置の操作・管理、穿刺、患者さんの状態確認など) |
● 物品・透析の準備 ● バイタルチェック(体重・血圧測定など) ● 穿刺・抜針・止血 ● 患者さんの看護 ● 患者さんの健康管理や指導 |
看護師も臨床工学技士と同じように穿刺などの医療行為を行います。
しかし、装置の操作を行うのは臨床工学技士です。
看護師は、それにともなう幅広い業務を担う役割だといえるでしょう。
透析の仕事のやりがいとは?
透析の仕事がもたらすやりがいとしては、以下の3つが挙げられます。
- 患者さんとしっかり向き合えて、長く関われる
- 透析の専門的なスキルがつく
- キャリアアップできる
透析の患者さんは週に3回、毎回4〜5時間の治療を長期間にわたって続けます。
そのため、同じ患者さんとコミュニケーションを取る機会が多く、しっかり向き合えるのは魅力といえます。
透析の知識を活かして、アドバイスをしたり相談にのったり、患者さんが持つ不安をケアしていくうちに信頼関係を築けるケースもあるでしょう。
さらに、透析の仕事は専門的なスキルがつきやすく、キャリアアップにもつながりやすい特徴があります。
仕事に慣れてきたら、専門臨床工学技士や認定臨床工学技士 をめざして勉強するのもおすすめです。
透析は臨床工学技士の代表業務!スキルを身につけて質の高いサービス提供を
この記事では、病院の透析室やクリニックの仕事内容を詳しく説明しました。
臨床工学技士は透析業務に必要不可欠な存在です。
慢性腎疾患の治療が普及し、透析に関わる技術者の需要も増えています。
また、生命維持管理装置の高度化によって、安全管理や信頼性管理ができる臨床工学技士は、今後も重要視されると推測されます。
臨床工学技士は高度な専門職です。
医療の現場で専門的な知識や経験を得たい方には、向いている職種だといえるでしょう。