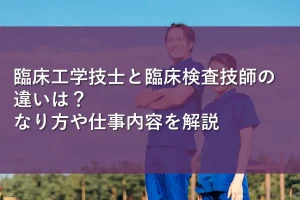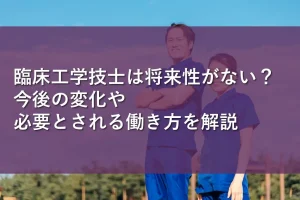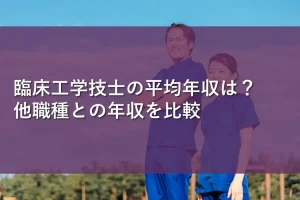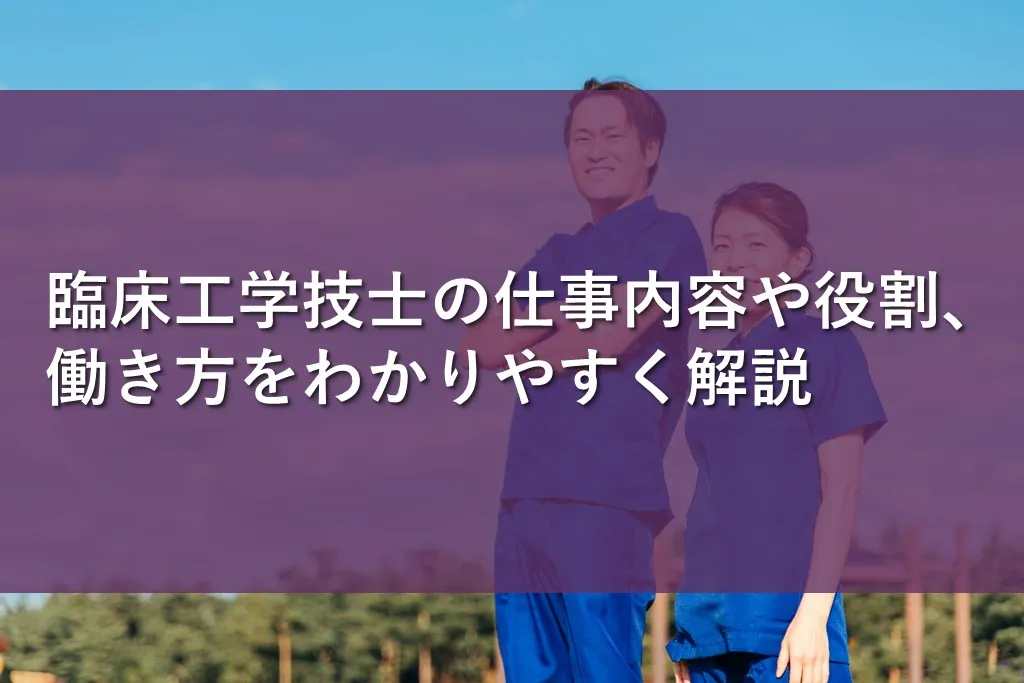
医療現場ではさまざまな職種の人が働いています。
医療の仕事に興味がある人のなかには、臨床工学技士の仕事が気になる人もいるでしょう。
臨床工学技士は、医療現場に欠かせない医療機器のプロです。
臨床工学技士の仕事に関心を持ちつつも、機械を扱った経験がなく、不安に思う方もいるかもしれません。
この記事では、臨床工学技士の仕事内容や役割、できること・できないことを紹介します。
また、仕事内容を詳しく説明するので、臨床工学技士の仕事が気になっている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
臨床工学技士とはどんな仕事?
臨床工学技士が何をする職業なのか、気になる人も多いでしょう。
ここではまず、以下の3つを紹介します。
- 臨床工学技士の役割
- 臨床工学技士ができること・できないこと
- 臨床検査技師との違い
では、それぞれをみていきましょう。
臨床工学技士の役割
臨床工学技士の役割は、医療機器の操作と保守・点検です。
医療の進歩にともなって医療機器が高度化しており、医師や看護師では操作が難しいケースもあります。
そこで活躍するのが臨床工学技士です。
臨床工学技師は扱いの難しい医療機器の操作を担い、医療チームの一員として安全でスムーズに治療が行えるようにサポートします。
臨床工学技士ができること・できないこと
臨床工学技士は、高度化する医療機器の適正な活用を担うために生まれた職業です。
さまざまな生命維持管理装置を適切に操作・管理し、手術時には人工心肺装置を操作するなどして医療を支えています。
クリニックや病院などでは、スタッフが連携して治療を行う必要があり、臨床工学技士も医療現場に欠かせません。
とはいえ、臨床工学技士にもできることとできないことがあります。
できることとできないことは以下のように分かれています。
| できること | できないこと |
| ● 生命維持装置の保守・管理・操作 ● 医療機器や補助循環装置、ペースメーカーの保守・管理・操作 ● 病院内で使用する医療機器の保守・点検・管理 |
直接身体に穿刺して行う採血や気管挿管など |
臨床検査技師との違い
臨床工学技士と似た名前の職種に臨床検査技師がありますが、実は両者の仕事は大きく異なります。
臨床工学技士の業務は、生命維持管理装置の操作や医療機器の保守および点検であり、臨床検査技師の業務は、診断や治療に必要な検査を行うことです。
臨床工学技士は、主に病院や診療所、医療機器メーカーで働きます。
臨床検査技師も同じように病院や診療所、医療機器メーカーで働きますが、製薬会社で働くケースもあるのが特徴です。
さらに、臨床工学技士として働いている人が3万人程度なのに対し、臨床検査技師は6万人以上となっており、就業人口にも差があります。
なお、臨床工学技士と臨床検査技師の違いについては、次の記事で詳しく紹介しています。
より多くの違いを知りたい方は、ぜひご覧ください。
臨床工学技士の具体的な仕事内容

臨床工学技士は、生命維持装置などの医療機器を操作するエキスパート(専門家)です。
医師や看護師などの医療チームにおいて医療機器の操作を担当し、いつでも安心して使えるように保守・点検を行うのがその役割です。
臨床工学技士がどのような仕事をし、どのような器具を扱うのか。具体的にみていきましょう。
呼吸治療業務
肺の機能が働かず呼吸不全になった患者さんには、人工呼吸器を装着します。
人工呼吸器は、病室をはじめ、手術室や集中治療室などでも使われている装置です。
呼吸治療業務とは、人工呼吸器が適切に稼働しているかを点検し、異常がないことを確認する仕事です。
人工呼吸器が肺の代行をしているため、不具合が起こらないように注意する必要があります。
そのため、メンテナンスや管理などもしっかりと行います。
人工心肺業務
心臓の手術を行う際には、心臓や肺の働きを体外で管理できるように、体外循環装置、いわゆる人工心肺を使用します。
その操作や管理をするのが人工心肺業務です。
人工心肺業務で使用する医療機器に誤作動があると、人命に関わる大きなトラブルにつながりかねません。
そのため、人工心肺業務には専門的な知識や適切な判断、操作方法が必要になります。
操作はもちろん、使用前の点検も臨床工学技士の業務です。
記録も担当するため、医師や看護師との連携も求められるでしょう。
血液浄化業務
血液浄化業務とは、機器を用いて血液中の老廃物や毒素を取り除き、水分量や電解質を調整する仕事です。
主な治療は、血液透析療法、血漿交換療法、血液吸着法などです。
一般的によく知られている人工透析も血液浄化業務の一つであり、臨床工学技士が人工透析装置の操作を行います。
血液浄化業務では透析室に勤務することが多く、透析中の装置や血圧の確認、回路の組み立て、穿刺、返血、抜針、止血なども担います。
臨床工学技士の透析の業務については、次の記事で詳しく紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
手術室業務
手術室では、手術の内容に合わせたさまざまな医療機器を使用します。
機器が正常に作動しなければトラブルになる恐れがあるため、臨床工学技士は使用前にしっかりと点検しなければなりません。
また、手術中は医療機器が正常に作動しているかを常にチェックし、トラブルが起こった際にはすぐに対応する必要があります。
医療機器の操作や管理において、臨床工学技士は重要な役割を担っているのです。
集中治療業務
集中治療室では急性期で症状が重篤な患者さんや、心臓や脳の手術を受けたばかりの患者さんが治療を受けます。
24時間体制で治療・管理を行っており、機器のトラブルは生命に関わります。
患者さんによって使用する機器が異なるため、臨床工学技士は使用する装置をしっかり把握しなければなりません。
臨床工学技士は24時間交代制で常駐し、機器の操作・保守・点検を行います。
心血管カテーテル業務
心血管カテーテル治療ではカテーテルという細い管を挿入し、冠動脈の狭窄や閉塞箇所を確認します。
バルーンを使って拡張するなど、カテーテルを用いた治療を行うこともあります。
実際に治療を行うのは医師ですが、臨床工学技士の役割は治療中の機器操作のサポートです。
また、動脈圧や心電図、動脈血酸素飽和度などから患者さんの状態をチェックすることもあります。
至急対応しなければならない場合は、体外式のペースメーカーや補助循環装置などの準備と操作も必要です。
高気圧酸素業務
高気圧酸素業務とは、通常より高い気圧のもと、高濃度の酸素を吸入する治療法での高気圧酸素治療装置の操作と管理を指します。
酸素不足の解消に効果がある高気圧酸素治療は、一酸化炭素中毒や急性末梢血管障害、感染症など、さまざまな疾患に用いられます。
臨床工学技士は、主に高気圧酸素治療装置の操作・保守・点検を行い、治療中の患者さんの状態が正常かを見守るのが役割です。
ペースメーカー/ICD業務
不整脈の患者さんには、ペースメーカーやICD(植え込み型除細動器)などの心臓植え込み型電気的デバイスを使用します。
埋め込み手術は医師が行いますが、臨床工学技士は手術に立ち会い、心臓デバイスの調整や確認を行います。
ペースメーカーに影響を与えないように事前に他の医療機器の調整をしておき、手術中も装置モニタリングを行うのが基本です。
また、患者さんのペースメーカー手帳に必要事項を記入し、手術後の定期的なメンテナンスなども担当します。
医療機器管理業務
病院にあるさまざまな医療機器は医療機器管理室にあり、院内での貸出や返却はそこで管理されているのが一般的です。
臨床工学技士は、それらの医療機器を正常かつ安全に使用できるように保守点検をします。
多く扱う医療機器は、生体情報モニタや人工呼吸器、輸液ポンプ、シリンジポンプなどです。
また、医療現場ではスタッフとの連携が重要なことから、臨床工学技士による説明会や講習会が開かれている病院もあります。
正しい使い方を広めることも、医療危機管理業務の仕事の一つといえるでしょう。
臨床工学技士の働き方は?
高度な医療機器を扱う専門職であり、雇用形態を問わず、医療機関から一定の需要があります。
2020年度の有効求人倍率は1.26倍 で、1倍を上回っています。
ここでは雇用形態によって働き方がどのように変わるのか解説します。
正社員・正職員
フルタイムで働く正職員・正社員の場合、基本的に一つの病院もしくは企業で働くことになります。
業務内容は働き先の病院や企業によって異なり、複数の業務を並行して行ったり、ローテーションで異なる業務を担当したりします。
毎月安定した収入が得られる点や福利厚生が充実している点はメリットです。
平均年収は607万円と高い水準です。
病院勤務の場合、夜勤や当直、突然の呼び出しに対応しなければならないのは大変な点といえるでしょう。
業務内容や勤務体系は勤務先によって異なります。
求人に応募する際はどのような働き方になるのか、事前によく確認しておきましょう。
パート・アルバイト・契約社員
臨床工学技士はパート・アルバイト・契約社員としての働き方もあります。
時間給で働くので、時間の融通が利きやすいのがメリットです。
小さな子供がいて育児をしながら働きたいという方におすすめです。
デメリットとしては時間給で収入が安定しにくかったり、場合によっては正社員と同じような福利厚生が 受けられなかったりする点が挙げられます。
必要性が高まる臨床工学技士をめざそう
今回は、臨床工学技士の仕事内容や分野、役割などについて詳しく紹介しました。
医療機器を操作する印象が強い臨床工学技士ですが、医療操作だけではなく、医療機器開発の支援など活躍の場は広がっています。
また、医療機器を操作するロボットの活用が進んでおり、その操作も求められています。
これらを踏まえると、臨床工学技士は今後もますます将来性がある仕事といえるでしょう。
今回の記事を参考にし、ぜひ臨床工学技士をめざしてください。
臨床工学技士の将来性については次の記事を参考にしてください。
なお、臨床工学技士の年収について詳しく知りたい方は、ぜひ次の記事をご覧ください。