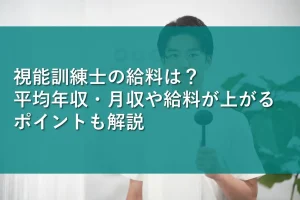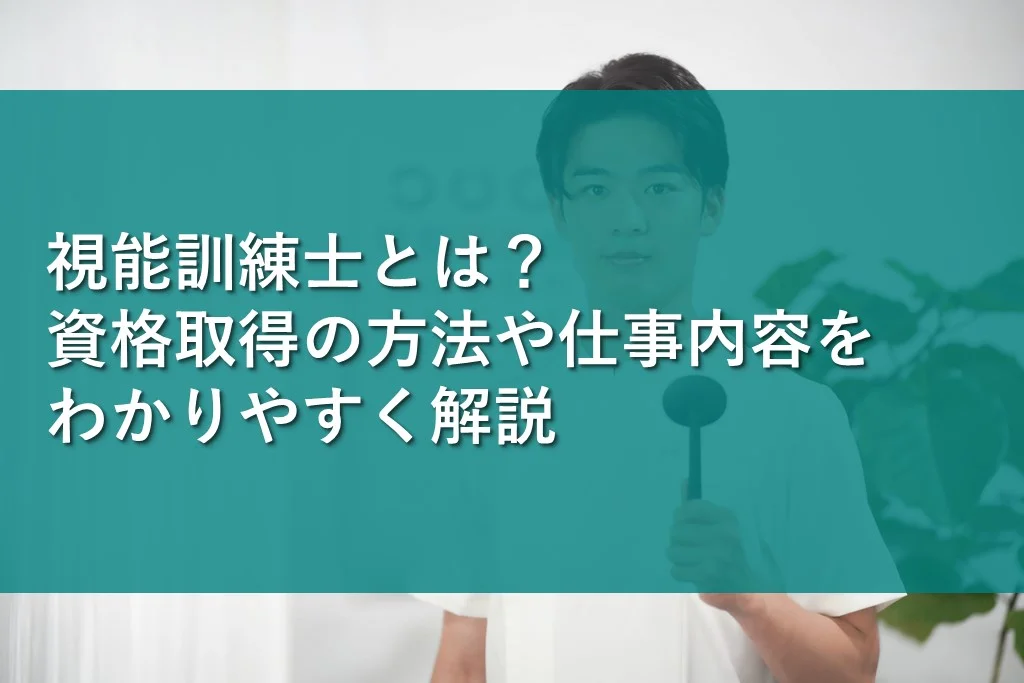
視能訓練士は視機能の専門家として、眼科分野で重要なポジションを担う仕事です。
今回は、視能訓練士の役割や仕事内容、資格取得の方法などを解説していきます。
目次
視能訓練士とは?

まず、視能訓練士がどのような仕事なのかを見ていきましょう。
役割や眼科医との違いといった視点から解説します。
視能訓練士の役割
視能訓練士とは、視力・視野の検査や矯正訓練を実施する視機能のスペシャリストです。
英語ではCertified Orthoptistといい、COと略されます。
日本では、小児の斜視や弱視を検査・矯正する国家資格として1971年に誕生しました。
医師の指示に基づき、視力や視野に問題のある人に対して、検査や回復に向けた矯正訓練をすることが視能訓練士の役割です。
視能訓練士が関わる対象者は、目に障がいがある人や眼科で治療を受けている人が中心となります。
ほかにも、集団検診では子どもから高齢者まで幅広い年代の人と関わる仕事です。
視能訓練士と眼科医の違い
眼科医と視能訓練士では、必要な免許が異なるだけでなく、仕事内容などできることにも違いがあります。
眼科医は、検査全般と診療や治療ができます。
一方で視能訓練士は、診療の補助、検査や矯正訓練が主な業務です。
手術などの外科的な治療は眼科医のみに認められ、視能訓練士はその補助業務の一部しかできません。
このことから視能訓練士は、眼の診療に関する一部の業務を眼科医から任されている専門職といえます。
視能訓練士の仕事内容
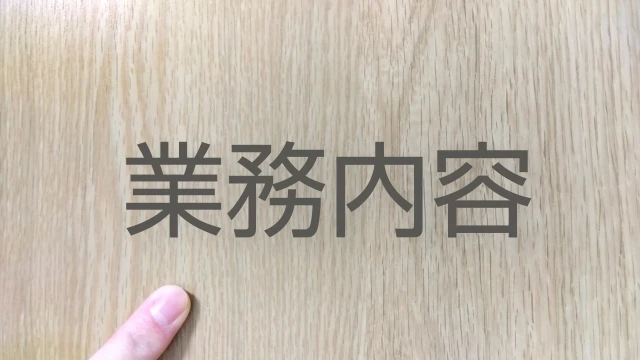
視能訓練士は、具体的にどのような仕事をするのでしょうか。
視能検査・リハビリ・視能矯正・視能健診の4点を詳しく見ていきます。
視能検査
視力、視野、角膜、眼底など眼に関する検査を実施します。
具体的には、視力検査、屈折検査、視野検査、コンタクトレンズ検査、眼鏡処方検査、眼の奥や組織の断層を撮影する画像検査などが主な検査内容です。
ほかにも、手術前検査などの一般検査から、精密な特殊検査まで幅広く担当します。
医師の診断や治療・手術に必要となるデータを提供し、医療をサポートすることが検査の目的です。
リハビリ
視力や視野を補うための工夫や、補助具の使い方を指導するなどのリハビリを実施します。
このようなリハビリをロービジョンケアといいます。
眼の疾患や外傷などで視機能が低下し、日常生活に支障をきたしているロービジョン者に対して、見えにくさを補う方法を用いて生活の質を改善する支援です。
学業や仕事など日常生活への影響を聞き取り、適した視覚補助具(拡大鏡、拡大読書器、遮光眼鏡など)を選定します。
そのうえで、使用訓練や歩行訓練、自立訓練などを実施することが主な仕事です。
また、身体障害者手帳の申請や、リハビリ施設との連携に関するアドバイスなど、広い分野で相談と支援を行います。
視能矯正
視覚が発達する年齢には限りがあるため、視能矯正の対象となるのは視能の発達段階にある子どもです。
両眼視機能・眼球運動・眼位検査といった視能検査をし、弱視や斜視の原因を取り除き、視力向上と正常な両眼視機能を獲得するための訓練を実施します。
例えば、弱視の原因を取り除くために眼鏡をかける、アイパッチで視力の良い目を隠し、視力の悪い目を鍛えるなどが視能矯正の内容です。
視能健診
保健センターなどで実施される3歳児健診、就学時健診、生活習慣病健診などで視能検査を実施します。
眼疾患の早期発見に貢献することが目的です。
子どもは弱視や斜視など視機能の問題があると、発達に影響が出るおそれがあります。
また、成人の場合は目の疾患が生活の質を左右するおそれがあるため、早期発見し適切な治療につなげることがポイントです。
視能訓練士の基本情報

ここでは、視能訓練士の勤務場所、給与、男女比など、基本的なデータを紹介していきます。
なお、給与などのデータは、日本視能訓練士協会の資料を参照しています。
参照:日本視能訓練士協会 視能訓練士実態調査報告書2020年
勤務場所
視能訓練士の主な勤務先は、眼科医院やクリニック、眼科のある総合病院などです。
なかでも眼科クリニックが最も多く、4割弱を占めています。
視能検査がメインの業務ですが、勤務先によっては矯正訓練やリハビリを中心に行う場合もあります。
また、最近ではレーシックの専門クリニックで活躍する人も出ていることが特徴です。
ほかにも、大学の研究機関で眼科領域を研究する人、視能訓練士の経験を活かして養成施設で教員となる人もいます。
給与
正職員に限定した場合の年間平均所得は423.9万円です。
ただし、非正規雇用者などを入れると変化し、300万円以上400万円未満が全体で最も多くなっています。
また、年齢や勤続年数に比例して給与が高くなる傾向があります。
そのため、年齢別では60~65歳未満が573.2万円、勤務年数別では30年以上35年未満が591.3万円で最も高い状況です。
男女比
2020年時点では、男性14.1%、女性85.7%と女性が大半を占める職種です。
ただし、男性の割合は年を追うごとに増えています。
2000年では男性6.3%、女性93.5%、2010年は男性10.8%、女性89.1%と変化しています。
今後もこの傾向が続き、男性の割合が増えていくでしょう。
視能訓練士になるには
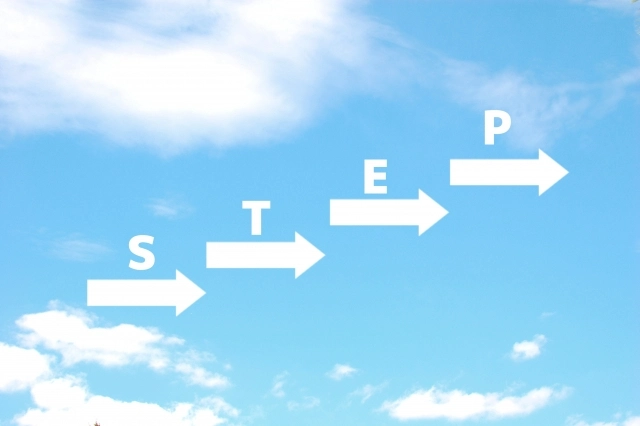
視能訓練士になるためにはどのようなステップを踏むのでしょうか。
国家資格の概要と資格取得までの流れを解説します。
国家資格が必要
視能訓練士になるためには、国家資格の取得が必須です。
資格の更新は不要のため、一度合格すれば生涯にわたって視能訓練士を名乗ることが可能です。
視能訓練士の国家試験は年1回、例年2月に実施されます。
厚生労働省によると、令和4年2月に実施された第52回国家試験での合格率は91.8%で、例年90%以上の合格率です。
なお、国家資格を受験するためには、受験資格を満たす必要があります。
受験要件と取得までの流れは次項で解説します。
視能訓練士国家試験の合格率については以下の記事をご参照ください。
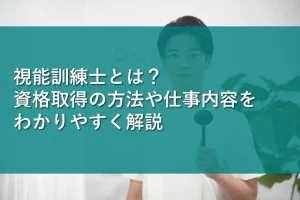
国家資格取得までの流れ
視能訓練士の国家試験は誰でも受験できるわけではありません。
以下のうちいずれかの受験要件を満たしていることが条件です。
- 視能訓練士養成校(3年)を卒業
高校卒業後に指定の養成校で3年以上学び、必要な知識と技術を修得します。
複数ある方法のうち、最短のルートです。 - 大学・短大を卒業後、視能訓練士養成校(1年)を卒業
一般大学・短大、看護師・保育士の養成機関で2年以上の修業、かつ指定の科目を履修したのち、指定の養成校で1年以上修業します。
なお、自分が過去に履修していた単位が該当するかは、養成校に確認しましょう。 - 海外の視能訓練士養成校を卒業
海外の養成校を卒業、または海外で視能訓練士に値する免許を保持し、厚生労働大臣の認定を受けていることが条件です。
具体的なステップとしては、12月~翌年1月に出願、2月に国家試験、3月に合格発表、その後に免許申請の流れになります。
視能訓練士の将来性

現在、全国的に視能訓練士の数は足りていません。
日本視能訓練士協会によると、眼科医1人に対して必要な視能訓練士の人数は2~3人です。
しかし、同協会による2020年の調査では、眼科医1人に対して視能訓練士が1人以上2人未満のケースが最も多い状況となっています。
現場で必要とされている数に対し、視能訓練士はまだまだ足りていないのが現状です。
それにくわえて、視能訓練士の社会的な需要は増加傾向にあります。
社会全体の高齢化や、日常生活でパソコンやスマートフォンを見る時間が増えていることにともなって、眼の健康への関心が向上しているためです。
近年では、病院やクリニックだけでなく、老人ホームのリハビリなどでの需要も増えており、視能訓練士の活躍の場は広がっていくことが見込まれます。
視能訓練士の将来性については以下の記事をご参照ください。
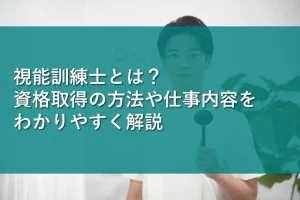
視能訓練士は視機能のスペシャリスト
視能訓練士は、視力や視野の検査・矯正訓練・視能健診・リハビリなどをする職種で、視機能に関する専門職です。
主な職場は眼科クリニックですが、社会の高齢化にともない、老人ホームなどにおける求人も増えてきています。
視能訓練士になるためには、国家資格の取得が必須です。
国家試験の受験には条件があるため、将来的に視能訓練士になることを考えている方は、事前に確認しておきましょう。