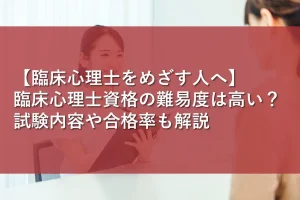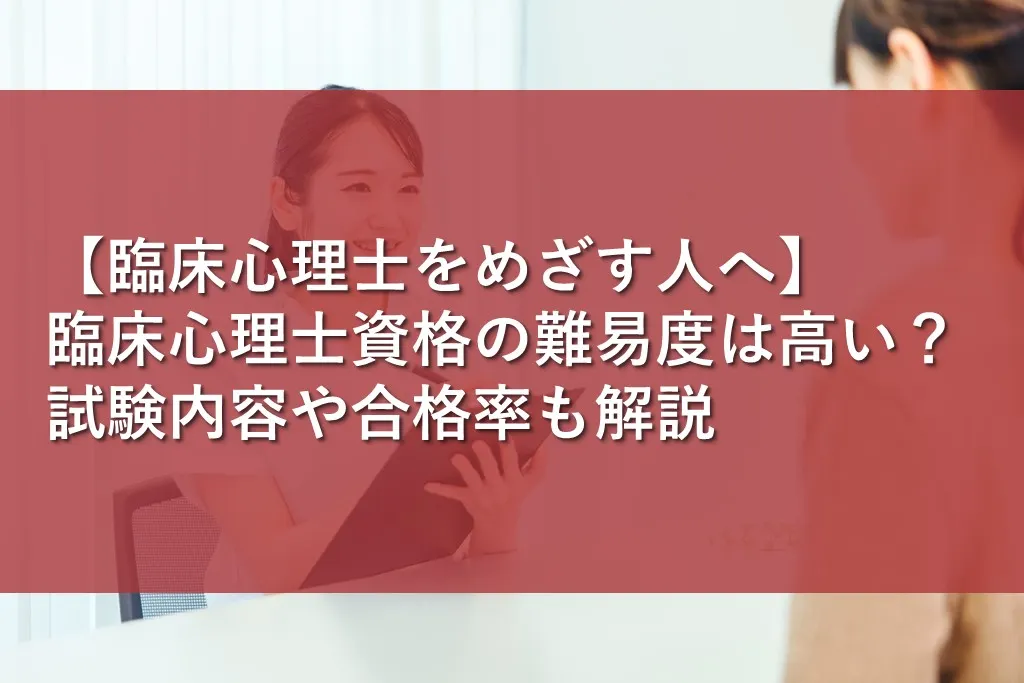
「臨床心理士の資格試験の難易度はどれくらい高いのか」
「いつから受験勉強を始めれば良いのか」
臨床心理士をめざすなか、このような疑問を抱く方もいるのではないでしょうか。
本記事では、臨床心理士資格の合格率や試験内容、対策方法などを紹介していきます。
目次
臨床心理士の資格難易度はそこまで高くない

ここでは、臨床心理士の合格率を公認心理師の合格率と比較して解説します。
臨床心理士資格の合格率は60~65%程度
臨床心理士資格の合格率は以下のように推移しています。
【臨床心理士資格の合格率】
| 合格率 | |
| 2018年 | 63.6% |
| 2019年 | 62.7% |
| 2020年 | 64.2% |
| 2021年 | 65.4% |
| 2022年 | 64.8% |
| 2023年 | 66.5% |
例年60~65%付近を推移しており、特別難易度の高い資格というわけではありません。
とはいえ、4割近い方が不合格になっていることを考えると、誰でも簡単に取得できるわけではなく、きちんと勉強しないと合格は難しいでしょう。
日本臨床心理士資格認定協会が基本モデルとしているルートでは、指定の大学・大学院の修了が必要です。
この指定の大学院への進学も、倍率の高いところでは5倍〜10倍になります。
公認心理師の合格率は50~70%程度
公認心理師は2017年より施行となった国家資格です。
2018~2022年のデータは、合格率に年度ごとのバラつきがあり、45~60%程度を推移していました。
その後、2023年、2024年は70%を超えており、近年の合格率だけで比較すると、臨床心理士よりも難易度が低めという見方もできます。
ただし、公認心理師は4年制大学で必要な科目の履修が受験資格の条件になるため、受験資格を満たすという点では、臨床心理士よりハードルが高いともいえます。
また、2017年にスタートしたばかりの資格のため、今後また合格率に変化が出る可能性もあるでしょう。
以下が過去7年間の公認心理師の合格率です。
【公認心理師の合格率】
| 合格率 | |
| 2018年 | 79.6% |
| 2019年 | 46.4% |
| 2020年 | 53.4% |
| 2021年 | 58.6% |
| 2022年 | 48.3% |
| 2023年 | 73.8% |
| 2024年 | 76.2% |
臨床心理士資格の試験は筆記試験と面接試験がある
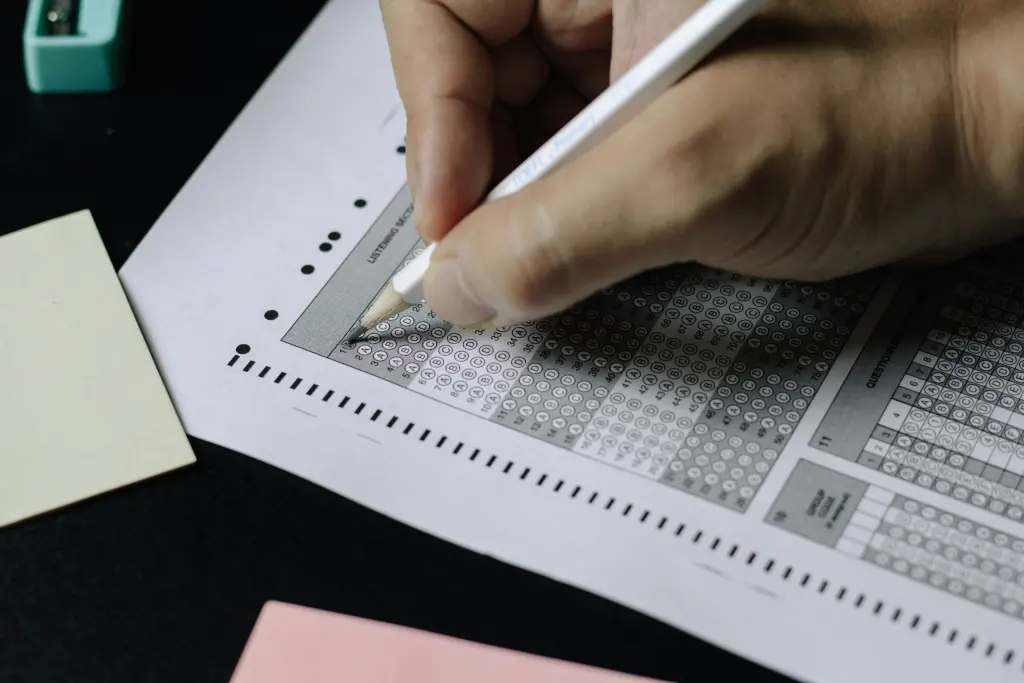
臨床心理士の資格試験は、筆記の1次試験と面接の2次試験から成り立っています。
それぞれどのような内容なのか解説します。
筆記試験は多肢選択方式試験と論文記述試験
1次試験は多肢選択方式試験と論文記述です。
多肢選択方式試験では、出題数100問がマークシート形式で出題されます(試験時間2時間半)。
出題内容は、心理学の専門基礎知識が中心です。
以下が出題される主な内容です。
- 心理学の基礎的設問
- 臨床心理士の基礎業務(臨床心理査定、臨床心理面接、臨床心理的地域援助、研究調査)
- 臨床心理士に関わる倫理・法律などの基礎知識
- 基本的な姿勢・態度に関わる設問
論文記述試験では、心理学に関わる1題のテーマを1時間半で1,001字以上1,200字以内の範囲で記載することが求められます。
論理的思考力の他に、決められた文字数や時間で内容をまとめられるかどうかも判断される試験になっています。
面接試験は二人の面接官による口述面接試験
1次試験の多肢選択方式試験に合格していれば、2次試験に進めます。
2次試験の口述面接試験では、2名の面接委員を相手に臨床心理面接技能力を問われます。
専門知識や技能の確認のみならず、臨床心理士としての基本的な姿勢や対人スキルなども評価対象です。
資格試験のなかでも、特に専門性の高い内容になっており、実際の現場を意識した場になっています。
日頃から実習や課外活動などの臨床実践で学びを備え、臨床心理士としての倫理観を持って心構えしておくことが大切です。
臨床心理士試験合格に必要な学習時間とは

臨床心理士の試験に合格するためには、どれくらいの学習時間が必要なのでしょうか。
臨床心理士と同じく心理職で、なおかつ合格率も60%前後の精神保健福祉士では、1日2時間程度の勉強を半年ほど続ければ合格ラインに達するといわれています。
また公認心理師の資格試験に合格するには、約400時間の勉強時間が必要ともいわれています。
他の心理職と比べても同等の360時間〜400時間の確保は必要であるといえるでしょう。
筆記試験と面接試験どちらの対策に重点をおくべき?
試験対策は、まず筆記試験(多肢選択方式試験・論文記述)を重視するのがおすすめです。
多肢選択方式試験に合格できなければ面接に進むこともできません。
また面接では、筆記試験の内容を理解していなければ答えられない質問もあります。
そのため、まずは筆記試験対策が必須といえるでしょう。
臨床心理士の筆記試験対策とは
筆記試験に向けた対策として、次のような勉強法が挙げられます。
- 大学、大学院の授業を有効活用する
- ノートにまとめる
- 過去問を活用する
- 暗記カードや一問一答アプリを利用する
- 対策動画を視聴する
- 有料講座を活用する
前述のとおり、臨床心理士の受験資格を得るには、指定の大学・大学院を修了しなければなりません。
これらの大学・大学院のカリキュラムは、臨床心理士にとって必要な知識や技術を学べるものになっていますから、まずは大学・大学院の講義をしっかりと受講することが、試験合格に向けた大前提となります。
ノートへのまとめや過去問の活用は王道ですが、解説付きの演習問題や一問一答形式など、無料でダウンロードできるアプリもあります。
インプットは自宅で、アウトプットはスキマ時間に、という使い分けも可能です。
動画では有料にはなりますが、専門校が配信している対策講座を受けるのも良いでしょう。
普段の講義や実習に取り組みつつ、基礎知識を定着させ、過去問やテキストを利用するなど、継続的な対策で合格をめざしましょう。
臨床心理士の資格はきちんと対策すれば合格をめざせる
臨床心理士の資格試験は合格率60~65%程度を推移しており、半分以上の方が合格していることを踏まえると、特別難易度が高い資格ではありません。
しかしながら、心理学の幅広い知識を問われ、臨床心理士としての自分の考えも記述しなければなりません。
そのため、対策をとらずに合格できるものでもないのです。
人によって必要な勉強時間は、生活スタイルや学習の進度によってさまざまですが、1日2〜3時間の確保と、筆記試験対策から始めるのがおすすめです。
試験は年に一回しかありません。
目先の数字にとらわれることなく、入念に対策を施しましょう。