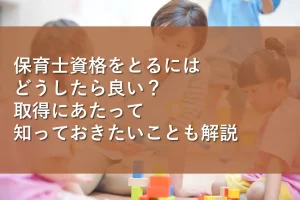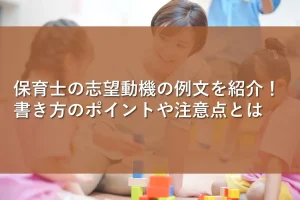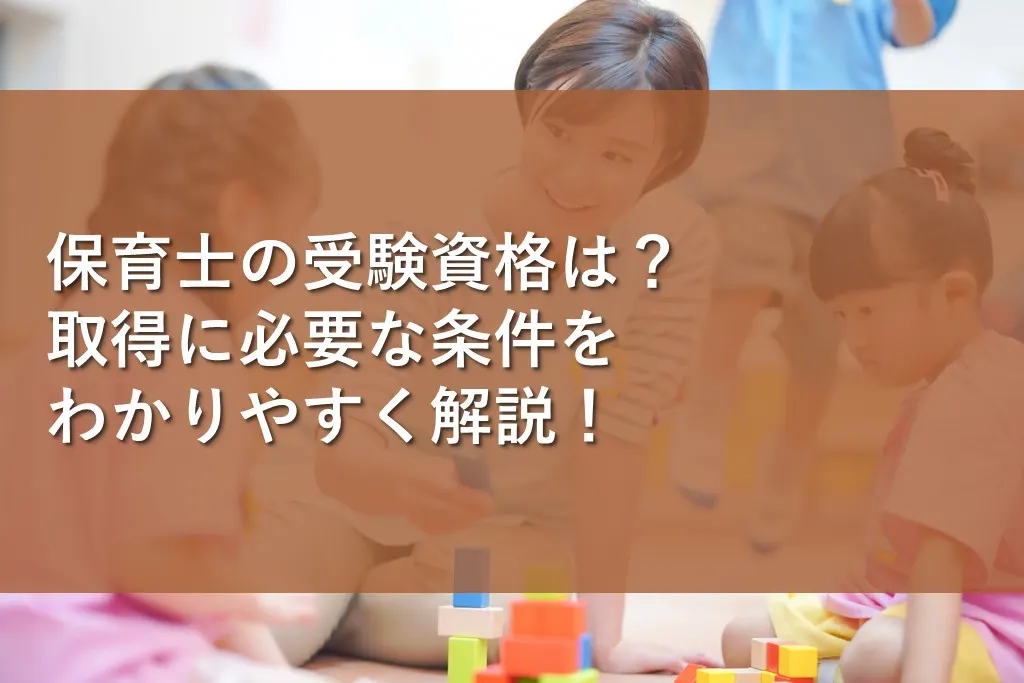
保育士になるためには、国家資格である保育士資格を取得する必要があります。
保育士資格の取得には、以下の2通りの方法があります。
- 高校卒業後、指定の保育士養成施設を卒業する
- 年2回実施される保育士試験を受験して合格する(最終学歴が中卒・高卒で受験の場合、実務経験2年以上必須)
指定の保育士養成施設を卒業する場合は、卒業と同時に保育士資格の取得が可能です。
そうでない場合は、受験資格を満たした上で保育士試験を受験し、合格することで、保育士資格を取得できます。
本記事では、保育士試験の受験資格について、学歴別、実務経験別に詳しく解説します。
保育士試験に合格して保育士になることをめざしている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
保育士試験の受験資格は最終学歴によって異なる

保育士試験は、最終学歴によって受験資格を満たすための条件が異なります。
学歴ごとの、受験資格を満たすための条件は以下のとおりです。
| 最終学歴 | 受験資格を満たすための条件 |
|---|---|
| 4年制大学 | 卒業:受験資格あり |
| 在学:2年以上在籍し、62単位取得済み(取得予定)の場合、受験資格あり | |
| 中退:2年以上在籍し、62単位取得済みの場合、受験資格あり | |
| 短期大学 | 卒業:受験資格あり |
| 在学:年度内に卒業見込みの場合、受験資格あり | |
| 専門学校 | 卒業:受験資格あり |
| 在学:年度内に卒業見込みの場合、受験資格あり | |
| 高等学校 | 平成3年3月31日以前に卒業:受験資格あり |
| 平成8年3月31日以前に保育科を卒業:受験資格あり |
上記の学歴に当てはまらない方は、実務経験によって受験資格を得ることができます。
4年制大学
4年制大学出身の方の保育士試験の受験条件は、大学に2年以上在籍し、かつ62単位以上取得していることです。
そのため、4年制大学を卒業した方は、全員が保育士試験の受験資格を持っているといえるでしょう。
なお、厚生労働大臣 指定の養成機関に該当する大学・短期大学・専門学校の場合は、前述のとおり卒業と同時に保育士資格を取得できるため、保育士試験を受験する必要はありません。
中退された方でも、中退までに2年以上在籍し、62単位以上を取得しているのであれば、受験資格があります。
大学に在学中の方は、上記の条件を満たしていなくても、大学に1年以上在籍しており、年度内に62単位の取得が見込まれる場合は、受験資格が与えられます。
短期大学
短期大学(短大)は、主に修業年限が2年間であるため、卒業が受験資格の条件となっています。
そのため、短大を卒業している方は、所属学部や学科に関係なく保育士の受験資格を持っています。
在学中の方は、年度内の卒業が見込まれている場合は受験資格が与えられますが、仮に年度内に卒業できなかった場合は、受験しても合格できません。
その他、医療系などの一部の3年制短大を中退された方は、受験資格の有無について保育士試験事務センターに問い合わせをしてみましょう。
専門学校
専門学校の場合は、まず以下の2点を確認しましょう。
- 学校教育法に基づいた専門学校であること
- 修業年限が2年以上であること
この2つの条件にあてはまる専門学校を卒業した場合は、保育士の受験資格を持っています。
条件に当てはまる専門学校に在学中の方も受験資格が与えられますが、仮に年度内に卒業ができなかった場合は、合格できませんので注意しましょう。
上記の2つの条件に当てはまらない専門学校を卒業、もしくは中退された方は、次にご説明する高等学校の受験資格を参照してください。
また、学校教育法に基づいた専門学校かどうか不明な場合は、直接学校に問い合わせをしましょう。
高等学校
最終学歴が高等学校卒業の方は、卒業した年月日や学科を確認してください。
卒業年月日が平成3年3月31日以前の方の場合、全員が受験資格を持っています。
また、平成3年4月1日以降に卒業した場合でも、保育科を卒業した方で、なおかつ卒業年月日が平成8年3月31日以前の方も受験資格を持っています。
それ以外の方は、後述する実務経験によって受験資格の有無が異なります。
高等学校が最終学歴の場合の保育士資格についてはこちらで詳しく説明しておりますので、ご覧ください。
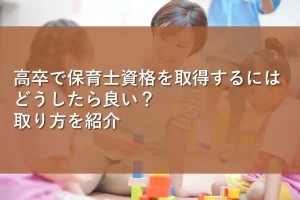
保育士試験の受験資格に必要な実務経験とは?
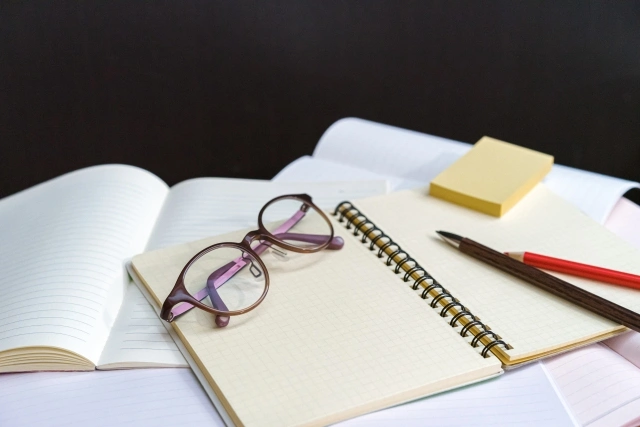
保育士試験の受験資格を満たす方法は、学歴だけではありません。
学歴で条件を満たさない場合であっても、保育関係の施設で実務経験を積み、児童福祉施設勤務証明書を提出することによって受験資格を得ることができます 。
ただし、必要な実務経験の条件や、実務経験として認められている施設は、学歴によって異なります。
確認していきましょう。
| 最終学歴 | |
|---|---|
| 高等学校卒業 | 児童福祉施設で2年以上2,880時間以上児童の保護に従事した経験がある場合、受験資格あり |
| 中学卒業 | 児童福祉施設で5年以上7,200時間以上児童の保護に従事した経験がある場合、受験資格あり |
高等学校卒業の場合
高校卒業が最終学歴で、学歴による受験資格を満たしていない方でも、実務経験として認められる施設で以下の3つの条件を満たした実務経験があれば、保育士試験の受験資格を持つことができます。
- 勤務期間が2年以上であること
- 総勤務時間数が2,880時間以上であること
- 児童の保護または援護に従事していること
これらの条件を一つでも満たしていない場合は、実務経験として認められない可能性があります。
詳しくは、保育士試験事務センターに電話で問い合わせをしてみましょう。
中学卒業の場合
最終学歴が中学卒業の方は、実務経験として認められる施設で以下の3つの条件を満たした実務経験がある場合、保育士の受験資格を持つことができます。
- 勤務期間が5年以上であること
- 総勤務時間数が7,200時間以上であること
- 児童の保護または援護に従事していること
また、勤務経験は他施設の経験と合算が可能 ですが、勤務期間が重複している場合は、勤務期間を合算することはできません。
これは高等学校の実務経験に関しても同様です。
実務経験に該当する施設
実務経験によって保育士試験の受験資格獲得をめざす場合、実務経験を積むために勤務する施設は、児童福祉法7条で定められた、実務経験に該当する施設でなければなりません。
実務経験に該当する施設は以下のとおりです。
- 保育所(利用定員20名以上)
- 保育所型認定こども園
- 幼保連携型認定こども園
- 児童厚生施設(児童館)
- 児童養護施設
- 助産施設
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 障害児入所施設
- 児童発達支援センター
- 児童心理治療施設
- 児童自立支援施設
- 児童家庭支援センター
自身の勤務先が、これらのなかに含まれているのか、必ず確認しておきましょう。
受験資格認定基準に該当する施設
児童福祉法第7条で定められていない施設での勤務であっても、必ず実務経験として認められないわけではありません。
受験資格認定基準に関する施設や事業での勤務の場合は、受験資格認定(知事認定)が下りることで、実務経験として認められる場合があります。
このような施設の一例として、以下のような施設があります。
- 認可外保育施設
- 幼稚園型認定こども園
- 幼稚園
- 学童クラブ・放課後児童クラブ・学童保育などの放課後児童健全育成事業
- 一時保護施設
- 放課後等デイサービス
- 院内保育
これらの施設の場合は、施設が受験資格認定基準を満たしているかどうかについて所属している都道府県に直接確認しましょう。
保育士試験の受験資格に関してよくある質問
ここからは、保育士の受験資格についてよくある質問についてご紹介していきます。
保育士試験の受験資格に年齢制限(上限)はある?
保育士試験の受験資格について、年齢の上限はありません。
前述した保育士試験の受験資格を持っている方であれば、誰でも受験が可能です。
通信制大学でも受験資格は得られる?
通信制大学であっても、「大学通信教育設置基準」を満たす通信教育の課程であれば、4年制大学の通学課程と同様に受験資格を持っています。
そのため、4年制大学の保育士試験の受験条件と同じ、以下の条件に当てはまれば受験資格を与えられます。
- 在学中の場合:2年以上在籍し、62単位取得済み(取得予定)
- 中退した場合:2年以上在籍し、62単位取得済み
※「大学通信教育設置基準 」は通信教育を開設するために定められている最低基準のため、通信制大学であればおおむね満たしている基準といえます。
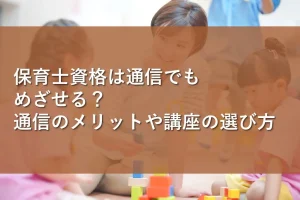
海外の学校を卒業した場合の保育士試験の受験資格は?
海外の学校を卒業した方は、以下の2つの書類を用意して「保育士試験事務センターの海外受験資格係宛」に郵送またはFAXで提出することで、受験資格の有無を確認できます。
- 受験資格事前確認依頼書
以下のURLから資料を印刷できます。
海外の学校を卒業した方の受験資格について|一般社団法人 全国保育士養成協議会 - 卒業(修了)時に取得した学位を証明する書類のコピー
英語以外の書類の場合、和訳も合わせて提出が必要です。
上記の資料が受理されたあと、おおむね2~3週間で、受験資格の有無の案内が電話で届きます。
保育士試験の受験資格を正しく理解しておこう
今回は、保育士試験の受験資格について学歴別、実務経験別にまとめていきました。
保育士試験の受験を考えている方は、まず受験資格をきちんと確認したうえで、試験対策を行っていきましょう。
保育士試験の概要については、こちらのページで詳しく解説しています。
試験の申し込み方法についても取り上げていますので、受験資格と併せて確認しておきましょう。