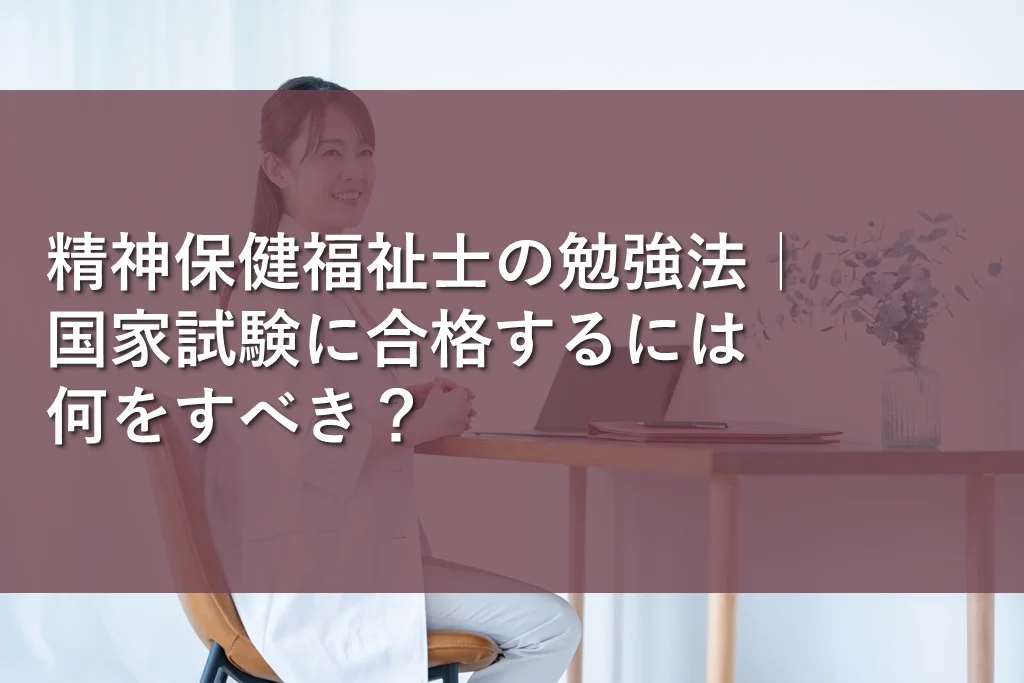
精神保健福祉士をめざす方は、まず国家試験を受けて合格することが必要です。
精神保健福祉士国家試験は1科目でも0点があると不合格になる ため、「合格できるか不安」と思う方もいるでしょう。
今回は、国家試験に合格するためにおすすめの勉強法を紹介します。
「どこから手をつけたら良いかわからない」という方も、この記事を読めば、自分に合った勉強法を見つけられるでしょう。
目次
精神保健福祉士の試験対策におすすめの勉強法

精神保健福祉士の試験対策には、以下の勉強法がおすすめです。
- 独学する
- 対策講座に参加する
- 模擬試験を受ける
ここからは、上記の勉強法のメリット・デメリットについて解説します。
独学する
独学の場合は、自分のペースで勉強を進められるのがメリットです。
一方で、自分で過去問やテキスト(参考書)を用意し、ペース配分にも気を付けながら勉強を進めなければなりません。
国家試験の合格には個人差はあれど、ある程度まとまった勉強時間が必要です。
また、勉強を始める時期が遅れると、その分1日に確保すべき勉強時間も長くなります。
過去問を解く
独学で勉強を進める場合、まずは過去問を解いて自分の苦手な科目を把握し、集中して取り組みましょう。
わからない制度や単語をピックアップし、テキストやインターネットで調べると理解を深められます。
過去問を解くことで国家試験の出題傾向を把握できます。
重要な問題は過去に繰り返し出題されているため、過去問を解いて出題傾向をつかみましょう。
また、過去問は出版社から出ている過去問集だけでなく、試験を実施する「社会福祉振興・試験センター」のホームページにも掲載されています。
過去問は少なくとも過去3年分を、試験本番までに3回以上は解いておきましょう。
テキスト(参考書)・アプリで学ぶ
過去問でわからないところは解説をよく読み、テキスト(参考書)で確認することをおすすめします。
文字を隠せる赤シートが付いていたり、図やイラストが多く描かれていたりなど、使いやすい特徴を持つテキストを選ぶと良いでしょう。
テキストを選ぶ際には、自分のレベルに合うものを選択することも大切です。
知識ゼロの状態から学び始めるのであれば、わかりやすい解説が記載された「教科書タイプ」のテキストが適切でしょう。
テキストの図表をみると、試験に必要な知識全体を把握できます。
また、忙しい社会人や学生は、勉強時間の確保が難しいかもしれません。
その場合、移動時間を利用してスマートフォンのアプリなどで勉強するのも一つの方法です。
模擬問題を解く
模擬問題とは、各出版社が作問したオリジナル問題です。
精神保健福祉分野では定期的に制度の見直しが行われ、試験問題の傾向も年ごとに変化します。
模擬問題集は近年の動向を踏まえて作成されているため、模擬問題を解くことで近年の注目ポイントを知り、応用力をつけることができるでしょう。
模擬問題は過去問をある程度解き終わり、「より高得点をめざしたい」と思っている方におすすめです。
書籍以外にインターネットやアプリにも掲載されているため、チェックしてみましょう。
対策講座に参加する
精神保健福祉士国家試験の対策講座は、養成スクールやテキストの出版社などが開催しています。
わからない点を講師に質問できるため、苦手分野を放置しない仕組みが魅力です。
また、国家試験では17科目が 出題されるため、独学の場合はどこから手をつけるべきか、わからなくなるかもしれません。
一方で、対策講座では講師による指導を受けられるので、自分で学習計画を立てずに済むでしょう。
しかし、対策講座は独学以上にコストがかかります。
特に精神保健福祉士国家試験は対策範囲が広いため、「受講料が想像より高かった」というケースも珍しくないでしょう。
最近ではリモートやeラーニングの対策講座も実施されており、会場への交通費や移動時間を削減したい方におすすめです。
模擬試験を受ける
模擬試験では、本番さながらの緊張感を肌で感じられます。
受験料は必要ですが、実際の試験に近い形での対策ができるでしょう。
たとえテキストをすべて暗記し、過去問を何度も繰り返し解いたとしても、試験本番の雰囲気にのまれて記憶が飛ぶこともありえます。
プレッシャーに飲まれることなく試験に挑むために、模擬試験で試験特有の雰囲気に慣れておきましょう。
「より本番に近い環境を経験しておきたい」と考えている方は、ぜひ模擬試験を受けてください。
精神保健福祉士になるには勉強法を工夫して計画的に対策しよう
精神保健福祉士国家試験に合格するには、計画的な試験対策が欠かせません。
独学では、過去問を中心に苦手分野を把握し、参考書を用いて知識を深めて、模擬問題で応用力を養います。
一方で、対策講座を利用すれば、コストはかかるものの専門の講師から直接指導を受けられます。
また、模擬試験を受けると、試験本番の雰囲気を事前に体験し、試験に対する緊張感を味わえるでしょう。
自分に合った勉強法を見つけ、ぜひ今日から実践してみてください。






